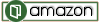2010-08-02
■水に溶けやすいカルシウム
イオン化カルシウム剤についてですが、口に入ったらすぐにイオン化するらしいのですが、どういうしくみで作られているのでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1280489044
ふむ。このあたりか。
「超濃縮活性(イオン)化カルシウム」ってなんかバズワードみたい〜。
でも特許番号が記載されている。これなら公開情報だろう。調べられそうだ。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110
出願「S59-147591」で検索。リスト。「特開昭61-028494」。
元々は水質改善剤か。
貝殻を2000℃以上で焼成する。
ってそれだけ?
化学式としては普通の生石灰と同一だけど、物性が違うらしく、きわめて水に溶けやすいのだそうだ。
とそこまではいいのだが、それがなぜ「超濃縮活性(イオン)化カルシウム」という名称になるのか? というあたりがちょっと可笑しいかも。
■おかしい
"あやしい"、"異常"という意味の時は「おかしい」。
"滑稽"という意味の時は「可笑しい」。
だな。自分の場合。
2010-08-09
■Gmailで2つのアカウントを使い分ける
Official Gmail Blog: Access two Gmail accounts at once in the same browser
なるほど、アカウント設定に"Multiple sign-in."があるな。
試してはいないけどメモ。
追記
試してみた。便利だ。
設定をOnにするのには,確認事項を4つほどチェックしないといけない。
- "現在のアカウント"がサービスの上部(モバイルの場合は下部)に出るよ。都度確認してね。
- 全部のサービスで有効なわけじゃないよ。有効じゃないサービスでは、現在のアカウントを変更するとそれにつられて変更されちゃうよ。
- defaultがついてるアカウントをセッションとして記憶するよ。
- GmailとCalendarのオフライン機能は無効になっちゃうよ。送付してないメールが消えちゃうからね。
すごく適当訳。
追記
すでに日本語でも使えるようになっているので迷うことはないだろう。
から。と書きたいところだけど、私のアカウント設定は英語で固定されているんですよ。なぜだろう? そんなわけで日本語での動作が分からないです。
追記
ログアウトしてから、最初にログインしたアカウントがdefault(既定)になるようだ。
アカウントのログインウィンドウが現れるのでもう一方の(defaultでない)アカウントでログインする
2010-08-21
2010-08-30
2010-08-31
■奇数か偶数か? の落とし穴
アクセス解析を見ていて、以前書いたエントリにリンクしていただいたようでそのリンク元からたどって、
を眺めてると各言語での具体的な実装とか、今まで知らなかったことが色々とあって面白い。
あるいは、奇数かどうかを判定するのに、
bool is_odd(int n) {
return n % 2 == 1;
}
と書くのは駄目だ(擬似コードです)ということとかも知らなかった。いや。見聞きしたことは多分あるのだろうが、知識として蓄えていなかった。
さてどこがどう駄目なのか?
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
答え
負数を渡すと判定に失敗するという可能性に気づいていない。
-1 % 2 は -1 になるから、
bool is_odd(int n) {
return n % 2 != 0;
}
が正しいとのこと。
引用元↓
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulo_operation#Common_pitfalls