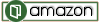2008-12-01
2008-12-02
2008-12-03
■I am legend
え? え? と思っている間にエンディング。
原作を読んでいるせいで、余計な勘ぐりをしてしまった。
いやもちろん、結末が違うということは知っていたけれども、まさかあれがカットされているとは。
孤独さをしっかりと描写しているので、いきなり話をする相手が出てきて軽く錯乱する主人公の気持ちが非常にいい感じで伝わってくる。
だからこそ原作の展開に行くと期待していたのだけど、残念。そうはならなかった。
この結末に向かうためには確かに邪魔な要素なので排除したのか、と見終わった後なら考えを巡らせられるけど、見ている最中はそんなこと思いもせず。
(原作との違いを判ってないとわけがわからない感想なのはいつものこと。なので遠慮しないで原作との違いを判ってないとわけがわからないように書いた)
リヴィングデッドの書き方は、もう完全にモードが変わってしまったなぁ。
凶暴、速い動き、大量の出現。もちろんCG。
まるでゲームのトレーラーを見ている感じで、正直言って、それ以外のシーンと比べてこの映画ならではの個性が全くない。
そこはマイナス点。
とはいえ「地球最後の男('64)*1」のリヴィングデッドも全然怖くないからな、とも思う。
旧作での描写は、怖いのはウィルス、あるいは知っている人が変貌してしまうという現象に対する感覚の方なんだよな。(恐怖という意味では、どちらかというとゾンビものよりもボティ・スナッチャーものの方に近いのかも)
だから原作や旧作では家族が××になるのに対して、こちらではあっさりと△△になっちゃう。
でもこれって損してるよなー。孤独感を強調したいなら原作や旧作の扱いの方がキツイものな。
逆に言うと、家族のエピソードを変更して、それでもなお孤独感を描写できたのはさすがと褒めるなのか。
で、やっぱりここまで演出が成功した要因としては「人がいないニューヨーク」抜きには語れないかと。
人がいない都市がどれだけ不自然で、空々しくて、不思議な感覚を与えてくれるかは、
の写真集で知っていることだけど。
「主人公独りしかいないニューヨーク」は圧巻。
ここまでやれるのは、さすがハリウッド、と言わざるを得ない。
まぁ、現代を舞台にするにあたっての変更はとても丁寧で説得力があるものだったし、かなり楽しめた。
関連物件
■ミラーズ・エッジ体験版
引用は今日時点の内容。
PS3版日本語体験版の配信を開始しました。10万ダウンロード限定での配信となります。
ニュース : ミラーズエッジ Mirror's Edge | エレクトロニック・アーツ
ダウンロード数に応じてSONYからお金を取られるんだろうなぁ……。
兎も角。
ミラーズ・エッジぱ一人称視点のゲームだけど、そのタイプのゲームに慣れてない、嫌いな人にプレイしてもらえる様に工夫してるなー、という感じがして好印象。
- 落下死するけどその直前からリプレイ。戦闘でのミスで致死した時も同様(これはデモだからかもしれないが)
- 次に向かうべきところが決まっている
- そこが赤く染まって視認できる
一人称視点のゲームは体験版とか色々やって絶対に買わん! というぐらい散々な結果だったけど──もちろん自分の腕の話──これは楽しい。
■MSX
その第一弾として、イー・モバイルの携帯端末「EM・ONEα」に、ゲームと読み物、開発環境を収録した CD-ROM 版の雑誌「MSX MAGAZINE 特別号 EM・ONEα で遊べる!作れる!ゲーム&BASIC」をバンドルし、アスキー・メディアワークスのキャンペーンサイトを通じて、限定1,000セット販売する。
イー・モバイルで Windows Mobile 6向けに MSX のゲームを提供開始 - japan.internet.com 携帯・ワイヤレス
余談
*1 見た時のエントリがないぞ?
2008-12-04
■新聞を読まないことに理由が要るだろうか
などと思った。
そんな合理的に理由つけて行動しているわけじゃないよなぁ。
私なら、
毎日新聞が本社ビル完成を一面記事にしているのを見て新聞を読む気が無くなった
と答えるだろう。
■例えばこんな書き方
for (i <- 1 to 50) (略)
と、
for {i <- 1 to 50} (略)
は同じ。
class Hoge extends Huga
と、
class Hoge <: Huga
は同じ。
Syntax上の「同じ」なので、実は挙動が違うかも。
これはメモであって、その辺りは後で調べる。
2008-12-09
■正規表現遣いは希少価値だ。ステータスだ
とか全然思ってないけど、秀丸のバックトラックあり正規表現での置換ですら、便利そうだねー、とか言われて、便利だから覚えればいいのに、と言っても笑って誤魔化されるなんて普通の光景すぎて笑って誤魔化すしかない。
キーマクロや正規表現、pythonやgawkとか使ってテキストファイルを処理してるところを見ては、「そんな便利なものがあるんだ」とか、「そんなことできるんだ」とか言うんだけど、そこから踏み出さない。
仕事は楽しようと考えてるみたいだけど、他に何も苦労せずに楽しようとしか考えてないんじゃないかと。勉強しろよ・・・
考え方の違い - 予定は未定Blog版
あはははー。
■ちひろテスト
昨日のうちに書いておきたかったんだけどな……。Windowsは(略)。
Senはどこかに解凍しておく。辞書も作る。
NetBeansでライブラリとしてjarを登録してしまう。この時、ApacheLoggingとの依存関係があるのだけどその辺どうしたらいいか分からない。後で。
とりあえず、今はScalaのプロジェクトのライブラリにApacheLoggingとSen(上で登録したものね)を追加。
実行時VMオプションに、-Dsen.home=C:\usr\loca\sen のように書いて、解凍したディレクトリを指定。
package scalaapplication1
import net.java.sen.{StringTagger, Token}
object NewClass {
def main(args: Array[String]) = {
var tagger :StringTagger = StringTagger.getInstance;
var s =
"毎日新聞が本社ビル完成を一面記事にしているのを見て"+
"新聞を読む気が無くなった";
var token = tagger.analyze(s);
//Javaなら Token[] token = tagger.analyze(s);
if (token != null) {
// var i :Token = new Token();
for(i <- token) {
println(i.toString() + "\t("
+ i.getBasicString() + ")" + "\t" + i.getPos()
+ "(" + i.start() + "," + i.end() + ","
+ i.length() + ")\t" + i.getReading() + "\t"
+ i.getPronunciation()
);
}
}
}
}
ま、こんな感じで。
参考にした、
では、var i :Token = new Token(); と書いていたけど、これはforで型推論してくれるはずなのでコメントにしたらやっぱり動いた。
■親クラスの引数付きコンストラクタ
class A(test: String) {}
class AA(test:String) extends A(test) {}
extends の右で親クラスのコンストラクタの呼び方を指定、と。
■ブロックは式で終わる必要があります
block must end in result expression, not in definition
が出たらセミコロン。
そのまま暗記。
……じゃ駄目かな。後で調べないとな。
2008-12-11
■カウンターナレッジって?
Amazonの紹介では「カウンターナレッジ(=ニセ情報)」と簡単に書いているけど、そんな単純な概念じゃないような。
ニセ知識そのものではなくて、その概念的な定義とか考察とかの方に興味がある。ということで。
■title要素にサイト名を入れない?
あれ。
TechCrunch も Lifehacher も、title要素にサイト名が入ってない。
昔はそうじゃなかったけど。
……TechCrunch 日本語版もだな。
それが「当たり前」になってるのかな?
2008-12-12
■ポン酢
醤油、酒、みりん、酢を1:1:1:1
小鍋で一煮立ちさせて冷ます
■狼と香辛料 VIII IX
この本にはちょっとしたいわくがありまして……。
ある日カミさんが、0:00ごろに帰ってきたのに3:00ごろに寝たという出来事があって、理由はというとこの本を読んでいたからだったのです。
その朝に次に読む本を棚から選んでいる*1時に言われたのが、
「あまり面白すぎるのは駄目」
という台詞。
もちろん、あまりに面白すぎると睡眠時間を削ってまで読んでしまうから、という理由なわけで。
その時は、なんて理不尽な、とか、次の日に読めばいいじゃないか、と思ったのですが……。
結局自分も下巻の半分を過ぎた辺りから止まらなくなってしまって。
(そうは言っても夕飯の支度とか風呂掃除とかはちゃんとやったわけですが)
まぁ、結局のところ同じ穴の狢と言うことなのでしょうか。
中身についてはあれこれ書かないでおきましょう。
次に読んだ時に、「その時にの自分」がどう感じるかすごく楽しみな小説です。その時には何か書くこともあるでしょうが……。
つまり、いつかもう一度読むことがあるという確信がそこにあるわけです。
はい。
■類は友を呼ぶ
の方が良かったか。
■今日のココロ日記
この文は自分が書いたっぽい雰囲気があるな。
トラックの荷台に乗りたい野望があることをquintiaさんに伝えるべきか否か。悩む。
prima materia-ココロのココロ: 12月12日のココロ日記(BlogPet)
*1 カミさんしか読まないコバルト文庫の本なども、刊行のチェックをしたり買ってきたりするのが私の方なので自然、そうなるのです。
2008-12-13
■俺の妹がこんなに可愛いわけがない 2
「このシーンでニヤニヤするのはエロオヤジだな」と思いながらニヤニヤしていた。
あとがきにもあるとおり、一作目はキャッチーなキャラクターだけで引っ張れたけど二作目となるとそうはいかないよね、その辺どうするのかな? と思っていた。
で答えはというと、ちゃんとストーリーを作ってきたな、という印象。
それそれのシーンでは相変わらずキャッチーなネタを散りばめてはいる。
でもちゃんと骨がある。伏線もある。キャラクターもしっかり作ってきている。
……方法論的には少女漫画──といっても20年ほど前のイメージになってしまうけど──のそれに近いな、と思った。
p94
「前々から気になってたんだが、おまえって、田村さんと付き合ってるわけ?」
「いいや。……見えるか?」
「見える。このクラスの誰に聞いても、同じ答えが返ってくるだろうな」
あぁ、なるほど。普通の高校生の視点っていうのは確かにそういうものかもしれない。
などと妙に納得したシチュエーションだった。
(意味不明)
■練り味噌
砂糖 大3
味噌 大3
みりん 大2
だし汁 大3
酒 大1
弱火にかけて練る
2008-12-14
■むこうぶち 23
最初原案をしていた安藤満氏が亡くなったのが12巻。
23巻まで出たので、亡くなる前と後とで、ちょうど話数的に半々になったのだなぁ。
時間が経つのは早い。
正直に言って、12巻以降は過去の遺産でどうにか凌いでいる(サブキャラクター的に)、という気がしないでもない。
でも──それでもなお、時として目を見張る様なエピソードが出てくるからまだやめられない。
青龍會と俺とでは
確かに雀風が違うが
俺は連中どうにか
生かしてやりてえと
思ってる…
上に立つ者の義務だからだ!それを甘く
考えている内は…
お前さんは全く
怖かないね
うっわ、安永さん格好いい。
2008-12-15
■Landreaall
面白い。圧倒されてしまった。
いやいや、エビアン・ワンダーを読んで、おがきちかのストーリーテリングの確かさは知っていたのだけど、こっちは巻数が進んでいたこともあって読むことを放棄してしまっていたのだな。
今考えるとなんという勿体ないことをしたもんだと呆れるばかりだが、残念ながら本の置き場所という物理的制約はいかんともしがたく買う本はある程度絞らないといけない──あるいは買った本を手放さないといけない──もので。
書評としては、すでにネットにあるものよりも良いものを書く自信は全くないし、自分だからこそ持てる視点を提示する自信もない。
なので。
この本を漫画喫茶で気軽に読めるようになりますように!!
たくさんの本屋を回って集めるなんことをしなくて済むようになりますように!!
2008-12-16
■数学セミナー 2009年1月号
予告が「折り紙の数理」だった(と思う)ので書店で探してとりあえず購入。
見ると「折り紙・折りたたみの数理」で、実際折り紙じゃなくて折りたたみの方がメインっぽい。
ミウラ折りの折り方が丁寧に説明されていたりして、あとで子どもに見せてあげようとか思った。
中ほどに「あなたが選ぶ数学書2008」の特集。
やはり「シンメトリーとモンスター(asin:4000054597)は読まねば、と改めて思う。
意外にも結城さんのインタビューがあった。結城さんのblogで告知されていただろうか? と思ったが見逃していたのだろうな。
ユークリッドの互除法と中国剰余定理がカットされている理由が語られていて面白い。
基本は、「何を説明するか」ではなく、「何を説明しないか」
from 「文書表現技術ガイドブック」(asin:4320005783)にも通じるな、と。
2008-12-18
■ぶっちゃけすぎじゃね?
こうしたなか、旧・道路公団OBやゼネコンOBの役員受け入れなどで受注維持に努めてきたものの、
大型倒産速報 | 帝国データバンク[TDB]
■回答できないや……
まず、中絶による身体的な影響を正しく把握することが必要。一般論ではなくて、彼女の状況についての話です。
仮に、中絶によってこれから子どもを授かることができなくなる、という事実があれば彼女の判断に大きな影響を与えるでしょう。ちゃんと診察を受けて、そのあたりを確認するべきです(可能性として、妊娠していない、という目が出ることもある……かも)。
まだ医者に行くには時期尚早のはずなので(月経予定日の1〜2週後ぐらいですね)、「今は決断できる時期じゃない。お医者さんの診察を受けるのが最初」と伝えるべきじゃないでしょうか?
4.の回答の2つめのリンク先( http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213133827 )のお母さんは立派だと思います。
それは「正しい判断をしたから」ではありません。
意見を汲んだ自分の娘に対して「アドバイスをした責任」をしっかりと果たしているからです。
このリンクは彼女にはまだ見せるべきではないかもしれません。でも彼女の母親と彼氏には見せてもいいんじゃないでしょうか?
彼女にアドバイスをするということ、彼女の選択に任せるということは、こういうことなんだと知ってほしいと思います(彼女の母親は何を当たり前のことを、と思うかもしれませんが)。
というわけで回答する気になれないのでした。
つーか彼の方に色々言ってやりたい。
2008-12-19
■機械どもの荒野(メタルダム) 読了
やや荒削り。
それが魅力になっているかというと微妙。
キャラクタもややステレオタイプっぽいとことがある。でもこっちは魅力的。
荒廃後の世界の物語には、やっぱり軽薄だが明るいキャラクタの、あっけらかんとした掛け合いが似合う。
機械文明の残滓にして、機械知能であるチャルもその掛け合いに関わってくる。
物語そのものを楽しむというよりは、世界に生きる人の掛け合いを楽しむ、その掛け合いの向こうに世界を見る、それを楽しむというタイプの小説のように思えた。
■精神科セカンドオピニオン
買って手元に届いているけど読んでいないので気になる本カテゴリ。(「気になる本」は読んでいないことを暗に示すために考え出したカテゴリ名だ)
値段は税込み2,520円。でも実物を見て大きさ・厚さ・製本などにちょっとびっくりした。想像していたよりもしっかりした作り。
これは読んでもらうために書かれた本だ。儲けるために書かれた本じゃない。
という印象に居住まいを正した次第。
あ、でも出版社はちゃんと儲けが出るように本を出さないといけないよ。
それを無視するような仕事はいけない。
追記
読んじゃった。
Amazonのレビューは☆5つ。全部のレビューが☆5つ。
かなり衝撃的な本だった。
絶対に憶えておくべきこと。
- 統合失調症につかわれる抗精神病薬(メジャートランキライザー)は、適応のない人(この薬を使うべきではない人、か)に使うと統合失調症と区別がつかない状況になる
- その場合、基本的に抗精神病薬の投与量が増やされて悪循環
これだけは心に留めて欲しい。
本の前半部分は、患者や家族の体験記である。
初診主治医での誤診により統合失調症とされ、抗精神病薬の処方から状況が悪化。原疾患(初発時の障害、疾患のこと)が無視されて抗精神病薬の増量と悪循環。
というケースがほとんどである(上で書いた通り)。
誤診パターンはいくつか示されており、それぞれの体験記の基本データにも付記されている。
肝心なのは、どのような誤診パターンであったかの選択は体験記を書いた本人がしていること。
つまりこの体験記を書いた人は、家族や自分がどのように診られ、投薬を受け、どうなったかをしっかりと学習しているということだ。
中には読んでいて涙がにじむようなものもあった。
しかし文章には感情的な発露は薄い(「怒りがこみ上げた」というような、直截でない表現はもちろん多々あるが)。
多くは、しっかりと状況を見つめ、適している投薬にたどり着いた、という内容であった。
しかし、投薬を調整するまでは神経をすり減らすような時間が続くことを私は知っている。ここに体験記を寄せている人に比べれば、何倍も何倍もマシだけど──あるいは比較してしまえば私のことなど苦労とも呼ぶに足りぬぐらいかもしれない。
この薬の組み合わせでこの量でいこう、とそう思える地点にたどり着くまでは大変なのだ。
中には、抗精神病薬5種類に睡眠薬2種類。副作用止めと称する抗パーキンソン病薬*1に下剤まで投薬されている人もいた。
それだけの薬を投与されたらまっとうな神経活動ができないだろう、と普通に思えるような滅茶苦茶ぶりだ。
減薬断薬のつらさは、想像を絶するだろう。
細かいことを書いていったらきりがないのでここまでにしよう。
後半は、「診断・処方を見直すためのサポート情報」となっている。
精神疾患(とその症状)についての基礎知識。薬物療法についての基礎知識。減薬断薬の基本。
ここまでが医師による。
セカンドオピニオン実現への道、ということでどうやってセカンドオピニオンを受けるか、治療に反映するかという話。
逆に言うとこれでページを使わなければならないほど、セカンドオピニオンを実現するのが難しいということだ。
残りはあとがきにあたる文章と、セカンドオピニオン実例集。
単純に言ってしまえば、医者の言うことを鵜呑みにするな、本に書いてあるような「薬は医者の言うとおりに飲みましょう。そうしないと大変なことになります」なんて嘘だ。
という本。
今すぐ読むべき、とは言わないがいざ精神科にかかった時、簡単に統合失調症と診断された時、主治医の診断や投薬が信頼できなくなった時(……では遅いか)に読むべき本。
あるいは、身の回りの人に読んでおいてもらうべき本。
*1 これに関してぱ全文引用するべきだと思う。p201より、"「副作用止め」とよばれ、精神科ではきわめて安易に使われるが、これほど副作用のきつい薬はないと言っても過言ではない。特に非定型抗精神病薬の服用に際して、いかにしてこれを使わずに済ませるかが、精神科薬物療法の最大の要点であろう。" つまりこの薬を安易に「副作用止め」として出された時は要注意だということだろう。
2008-12-20
2008-12-21
2008-12-22
■空白だけの言語
あーどこかで見たかも。
(BK1内容説明より)
8つの記号しかない言語や、空白だけで構成される言語など、奇妙な言語(Esoteric Language)があるのを知っていますか? このような言語を題材にプログラミング言語の作り方を詳しく解説します。
今買わないときっと入手できなくなるんだろうなぁ。
でも買うかなぁ。
ちょっと悩む。
■Javaにおいてstaticなメソッドがabstractであるはずがないからである
というGoogle検索からのrefererが。
あるはずがないよなぁ。
public class Main {
public static void main(String[] args) {
A a = new AA();
a.print();
}
}
public class A {
public static void print() {
System.out.println("A");
}
}
public class AA extends A {
public static void print() {
System.out.println("AA");
}
}
さて、Mainを実行した時の結果は? という質問に答えられるなら分かるはず。
答えは、A。
a.print(); で呼び出されるメソッドは実行時に動的に(dynamic)決まるわけではない。
コンパイル時点で、静的に(static)決まる。
実行時に変数が参照しているインスタンスじゃなくて、変数の型で決定されるわけだ。
つまり継承も多態もない。
なので、abstract な staticメソッドはありえない。
ところで、
public static void main(String[] args) {
A a = null;
a.print();
}
としても、全く問題なく実行できる。
インスタンスと関係なく、Aのstaicメソッドが呼び出されるので、これでもいいのだ。
2008-12-24
■デジカメに1000万画素はいらない
本の内容は「デジカメの使い方」とでも言えばいいか。
冒頭で「高画素化はデメリット」と言いきっているのは小気味いい。
大雑把に書いてみる。
サイズの多様性が無くなって、コンパクト機は同じ様な形になってしまっている。そうするとCCDの大きさ自体も変化がない。同じ大きさのCCDで高画素化すると1つの感光素子に入る光が弱くなる。ノイズも出やすくなり、色の階調も薄くなる。したがってそれをソフト的に補うことで解決する必要が生じる。元々階調が薄くなっているのを補うことになり、多彩な色が入っている風景写真などで、それらが均一化された様な画(え)になってしまう。
と、これはもちろん、同じ景色を古いデジカメと新しいデジカメで複数撮った写真と、複数ページに渡っている本文を「私が」要約してしまったものなので注意。
そんな枕で始まるが、その後に続くのは「今、もしこんな仕様のデジカメが出たら即買うだろう」という、著者の理想のデジカメの話。
つまり、今の技術力で数百万画素程度に立ち返って、デジカメのメリットを最大限に考えればこんな風になるだろう、ということ。
しかし、商品の企画開発の関係上、そのようなものが現れてくる可能性はほぼないとした上で、今のデジカメとのつきあい方の話となるわけだ。
ここはごく基本的な話から、tipsみたいなものも含まれるが、結局のところ、
とにかくバンバン撮れ
につきるのではないかと。(著者の意見でもあるし、私の意見でもある)
そのためには、常に持ち歩きなさい、気が向いたらすぐに撮りなさい、同じものを色んなモード、角度、距離で撮りなさい。
となる。
基本的な考えが私と同じだったのでつい買ってしまったが、「なるほどそうか」と思ったこともちらほらある。
私なんぞよりもたくさん撮っているし、基本的な知識もあるわけなので当たり前の話か。
全ページが、カラー印刷に使える紙になっているのでページ数は少なくてちょっとお値段高め。
本だけで見ると"割りに合う"かどうかはちょっと微妙だが、デジカメを数万円出して買っていることを併せて考えればいいかと。
デジカメの価値を高めるためのアイテムだと考えればよいと思う。
2008-12-25
2008-12-29
■DLNAサーバに日本語ファイル名は鬼門?
"UTF-8エンコードして送る"のがDLNAで求められる仕様みたいだけど、これができてない機器が多い? のか?
……機器がファイルをリストアップするまでのタイムラグが長いだけでしたー。
2008-12-30
■PHANTASY STAR 0
オンラインプレイ。
画面に対して自キャラが大きくて、他のキャラが何をしているのか把握しづらい。
うーん。