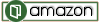2008-11-01
■定義せよ
(BK1 内容説明)
投資に「向いている・向いていない」時間がわかる金融占星術入り投資手帳。
「投資に向いている時間」「投資に向いていない時間」を定義せよ。
個々人に関係なく「投資に向いている時間」があるとしたら、それは単に「これから投資先の市場全体が上昇する時」なはずで、それは「投資市場全体が底をうっている時」以外にあるのか。
個人個人に区別した「投資に向いている時間」があるとしたら、その人のホロスコープを書かないと出てこないはずであって、だとしたらこの本は「投資手帳」じゃなくて「(かなりちゃんとした)占星術の本」でなくてはならない。
■1000spekers in Sendai
応募っ!
話せることがなにかあるかと考えた候補は、
- 素数ゼミとjava.util.HashXXX
- Knuth先生の浮動小数点表現での無誤差変換
- 文字集合(Character Set)・エンコーディング(Encoding)・字形(Glyph)
てな感じ。ある理由で「浮動小数点演算の無誤差変換と高精度計算のおはなし」に決めました。
本当ならディベロッパーズ・コミュニティに相応しいもっと地に足のついたような話題ができればいいのだけど、残念ながらシステム開発の前線から遠ざかって4年ほど、会社も辞めちゃった身としてはちょっと難しい。
だったら思いっきりロジカルではあっても、自分のフィールド──数学や情報工学──に近い話をしちゃえ、と。
今のコンピュータアーキテクチャには必ず潜在している話だし。
なにより、せっかくの機会に聞くだけなんてもったいない。
わざわざ時間を割いて会場に足を運ぶんだもの!
もっとバラエティに富んでいてもいい。もっともっと抽象的なところを話す人がいても面白い。現場に近い話も聞きたい。
発表なんていう「まとまった形」である必要もないんじゃないか。課題だけ投げかけて、まとめずに終わっちゃってもありかもね。それを肴にしてその後で話をしたりすればいいわけだし。
だからもっと話す人でてきてよ。
このまんま枠が埋まらなかったらつまんないよ。
いや本当、id:happy_ryo が、
東北ってこんなものなのかなみたいな思いをいだいて東京に行くというのはあかんと。
2008-11-01 - 仙台Rails社長2.0
そう思うよ。
追記
スライドです。
2008-11-03
■ひがやすを飲み会行ってきた
「ちょっと待て! ちがうだろ!?」
「あー、はいはい。第二回Seasar勉強会&ひがやすを飲み会に行ってきたよ。でもSeasar使ったことないし使う予定もないよ。何しろ無職だから」
「まるで飲み会だけ参加したみたいじゃないか」
「実際、前回のSeasar勉強会は飲み会だけ参加したんだけどな」
「それはIWDD遠征を予定していたのに、地震のせいで交通手段がなくなって、ぽっかり時間が空いたからだ」
「そうそう。そのせいで前回会えなかった id:happy_ryo 氏に、昨日やっと会えたんだよ。色々と話ができてよかったな」
「次は "1000speakers in Sendai" だな」
「あぁ、盛り上がって欲しいよな*1」
Slim3 についてはまた別に書きます。はい。
■人と会って話をする
家族以外の人と会って、1時間以上話をするっていうのも実は数ヶ月ぶりなわけで。
お昼ご飯を一緒にする。そのあとちょっと店を歩いて回る、ぐらいのことはあっても。
数時間椅子に座って話を聞く。
面と向かって話をする。
てなことは実は久しぶり。
ちょっと疲れたかな、という感じだけど、以前よりも苦ではない。
楽しい。
3つめの店で話をしたことを、カミさんに大雑把に話したら、似たようなことをだいぶ前に話をしたね、と。
はい、そうですね。
■富野さんの話から
だがCGを使って描き始めた時、みんな基本的にほとんど同じじゃない? 質感の違いを誰が突破してる?
「お前らの作品は所詮コピーだ」――富野由悠季さん、プロ論を語る (1/5) - ITmedia News
トゥーンシェーディングという技術は以前からあったけど、たとえその技術上ではあるけれど、「IDOL M@ASTER」ってのはその技術での質感の壁を突破した作品だと思っている。
ダンスがあって歌があって萌え的キャラ付けがある。大量のMAD作品に支えられている。というようなことはあるけど、基本的なところでは今までとは違った「質感」を評価してるんだけどね。
なんかこのまえふとした表紙に「きらりんレボリューション*2」のオープニングを見たんだけどトゥーンシェーディングの質感が「IDOL M@ASTER 以前」なのにびっくりした。まぁ、あれはプライズのカードゲーム画質にわざと落としてあるということなのかもしれない。
2008-11-04 第二回Seasar勉強会 行ってきた
■第二回Seasar勉強会 行ってきた
とはいっても昨日の「ひがやすを飲み会行ってきた」エントリで書いたとおり、Seasar使ったことないし、使う予定もない。無職・専業主夫ですから!
それでも勉強会行ったのは成分補給(鉄ちゃんには鉄分補給という言葉があっていいなぁ)ということもあるし、人とのつながりが欲しいということでもある。なんせ他人と1時間以上一緒にいるっていうこと自体久しぶりだし。
そんなわけで、Seasarはおいておく。
これからのプロダクトである Slim3 が面白い(interesting)。
武田ソフトさんのエントリを読んでみて、ここで自分のJavaレベルを書いておくのが吉だと思ったので書く。
- Java登場時に簡単なアニメーションとか書いて遊んだ
- Javaを使った最初の仕事は、1999〜2000年ごろ。ServletとJSPで縦断検索(Vertical search)のシステム
- スタート時点ではプレゼンテーション層もServletの予定だった
- 途中でTomcat3.x登場(Servlet2.2 JSP1.1)
- プレゼンテーション層をJSPに変更
- DBは無くファイルベース
- 当たり前だけどOSSなフレームワークなんてない時代
- 自分一人で全部やった
- 他の人が作ったもの保守とかエンハンスとかいくつか
- これもServlet,JSP,JDBCが生で使われていた
- その後はアプレット(Swingベースのアプリケーション)の製品開発
- DBアクセスはJDBCを生で叩く(私はあまり関与していない)
- GUIの方向性が一般的ではなかったので、独自コンポーネントがいっぱい。マルチスレッド駆使(ここが私)
ということで、実はWebアプリケーションとしてはServlet+JSPを直に使ったことしかない! のだ。
それは選択肢がない時代だからそうなったわけでその後に来たWeb全盛みたいな時期に、アプレットベースのシステムにどっぷり漬かっていたという変な話。
(ここで『なんでServlet+JSPで開発した経験のある人をWebじゃなくて、アプレットベースのプロジェクトに入れるの?』という向きもあろうが、アプレットの奥深くまで勉強をして開発できそうな人が私しかいない? みたいな、あるいは、初物は全部回しとけ、みたいな雰囲気が)
つまりSeasarどころか、他のどんなWebフレームワークも(PHP製のものなども含めて)使ったことがなく、それらとの比較ができない。
今年になって仕事とは全然別の場面で、Rail勉強会@東北に参加して(&参加するために)勉強したぐらい。
以上を踏まえて。
Slim3 というプロダクツの方向性を聞いて思ったのは、
「今、新しいWebフレームワークを作ろうと思ったら、こういう機能は当然持っているはず」
というものに絞りこんだイメージ。
ひがさんは「Seasar2 から機能を絞り込んだ」という表現をしていたと記憶しているのだけど、私はむしろ上で書いたような印象だった。(結果は同じなんだろうけど)
さらに、それに付け加えて、
「それらをゼロコンフィグ、あるいは"設定ファイルの記述は最低限で"やれますよ」
というのを前面に押し出した感じ。
Slim3 Transaction でのJTA実装の切り替えの話。
Servletコンテナが自前のものを持っている時はそれを、Tomcatの様にそういうものが無いときは Slim3 で実装したものを使いますよ。それをクラスを検索することで自動的にやりますよ。とか。
「それはやったぞ」と思った。Class.forName(クラス名)をしてみて、こういうクラスがあったらこういう環境のはずだからこっち、無かったらこっちを使う、みたいな Factory は書いたことがある。
URL←→ActionクラスとActionメソッド
というような対応も、最初の Servlet+JSP で作ったプロジェクトで似たようなことをやった。
もちろん自分でソースを書いて。
最初のころに銘々が「必要だから自分で書いていたもの」が一通りちゃんとそこにある、という感覚。
さらにその上で「必要としていないところでフレームワークに縛られることがない」んじゃないか、という予感。
「欲しいと思うもの」が最初にそこにあって、かつ「こうしたいんだけどフレームワークの仕様で無理です」という場面が少なさそうな、そんなフルスタックフレームワーク。
というか、それってフレームワークっていうのかな? メタ・フレームワークとか、フレームワーク of フレームワーク みたいな感じか。
まぁ、Webフレームワークを実地で使ったことが無い人間の想像ということで。
自重しないでトラックバックする。
2008-11-05
■iPhone 2.2 は脱獄済みらしい?
とLifehacker.comが報じている。
私、1.1.4 までじゃないと動かない iDic を愛用しているので、脱獄した1.1.4 なのだけどどうなるんだろう。
1.1.5 で「動かない」理由が分からないから(調べてないから)判断できないんだよな。
追記
元記事である開発者ブログを読んでみた。
「ファームウェア2.2β2は脱獄済みの状態を元に戻さない」ということの様。
脱獄してからインストールしたアプリを使用不能にしたりはしない、というだけで脱獄済み(と同じ様な状態)で提供されるわけではないだろう。
また、2.2β2の話であって、正式版はまた別なんじゃなかろうか。
(タイトルに?を付けておいて正解)
追記
検索でここに来た人は、
へどうぞ。
2008-11-06
■PS3 アドホックパーティー開始
でも遊ぶ相手が誰もいないもん……。
「アドホック・パーティー for PlayStation®Portable」βバージョンサービス 本日より開始 | プレイステーション® オフィシャルサイト
■Googleの*の振る舞いが変更になっているみたい
2年前には8万件ヒットしていた上の検索が、今は数千件程度。
結果を眺めてみると……、*にマッチするのは1つの形態素に限られる様な感じだなぁ。
ふむ。
では実験。
*を2つにしたら2つの形態素にヒットするかしらん?
お。合ってそうな感じがするぞ。
これ、一体いつからなのだろう?
2008-11-07
■毎日続けることがよいのです
数百って……。
一日に数百の記事を作ったポッと出のブログより、毎日毎日欠かさず更新していく方が、検索エンジンから、人からも好かれるのに。
などと思った。(検索エンジンから好かれる、というのは擬人的な表現だけど)
ブログ用に数百のオリジナルの記事(タイトル、本文を書いたHTML形式)を書いてきました。
そろそろ記事をブログに載せたいと思っているのですが、記事が多いため、1つずつ投稿するのが面倒で困っています。
http://q.hatena.ne.jp/1225933623
というわけで、くだらないことでもいいから、極力毎日更新しているわけなのだ。
2008-11-08
■いいかげん「合成=危ない」という印象操作をするような短絡的なタイトルはやめようよ
と脊髄反射的に思ったが。
(BK1 内容説明より)
洗濯用洗剤や台所用洗剤などに含まれている合成界面活性剤は、油汚れを落とす反面、人間の皮膚や粘膜を刺激し、河川や湖沼を汚染する。このような製品をひとつひとつ取り上げ、その成分を検証し、安全性や毒性を明らかにする。
という内容説明だけでくらくらする。
合成界面活性剤に限らず、界面活性剤なら「油汚れを落とす反面、人間の皮膚や粘膜を刺激し、河川や湖沼を汚染する」のは当たり前。
「合成」という言葉が要らない。
要らないにも関わらず付けているということは、キャッチーな効果を狙っているだけでは? と疑っちゃう。
2008-11-09
■ねこび……もとい NetBeans 特集ですってよ
買うか!
どーんとNetBeans関連の記事が並びます。
私も少しですがコラムを書かせていただきました、おまけ的に。
ねこび〜ん、かわいいよ、ねこび〜ん。
2008-11-06 - 人工無脳が作りたい
2008-11-10
■HOTEL
SFだな!
しかしなんという特装版。(印刷の版が特別、普通の製版じゃない、という意味)。
だからかお値段高め。
つまり、部数としてはすごいヒットにはなれないけれども、確実にこれだけの部数は売れる、という見込みがあっての判断だろう。
そしてここに、某ブログのレビューを見て買ってしまった者が一人。
……ヨハネの黙示録を指す場合は"Apocalypse"じゃなくてなんだっけ? "Revelation"、いや定冠詞を付けて"the Revelation"か。複数形の方は俗称なんだ。へー。
■Javaで指定範囲の乱数生成のlong版が欲しい、という話
ところで、Javaの乱数ではnextInt(int)というメソッドがあるので、intだと範囲指定して乱数を得ることができます。
けどもnextLong(long)というメソッドはないので、longだと範囲指定して乱数を得ることができません。
なにも考えなければ
nextLong() % n;などとすると範囲を抑えれるのですけど、乱数としてちゃんとなるためには、もう少し頭を使ったほうがいいような気がします。
2008-11-10 - きしだのはてな
n が 2^m の形になっているならば、[0, Long.MAX_VALUE) を均等に分割するので、剰余を取ればいいです。
それ以外の時は、均等に分割されないので、小さい方が多くでてきます。
簡単のために MAX_VALUE が15 だとしましょう。乱数が 0 から 15 の範囲ででてきます。
これを 0 〜 2 の範囲に絞りたくて 3 で剰余を取ってしまうと
- 0 (0, 3, 6, 9, 12, 15)
- 1 (1, 4, 7, 10, 13)
- 2 (2, 6, 8, 11, 14)
となって、0 が 1つ多く(15の分)出現します。
なので、15が出たらこれを棄てたいです。
ということで話を元に戻すと、「MAX_VALUE 以下で n の倍数のうち最大のもの」未満を採用して、それ以上なら棄てます。
で、実際 java.util.Random#nextInt(int)の実装は、
public int nextInt(int n) {
if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be positive");
if ((n & -n) == n) // i.e., n is a power of 2
return (int)((n * (long)next(31)) >> 31);
int bits, val;
do {
bits = next(31);
val = bits % n;
} while (bits - val + (n-1) < 0);
return val;
}
となっています。2のべき乗かどうかの判定や、上に書いた判定がちょっとだけトリッキーですが。
乱数で出てきた数(bits)から剰余(val)を引くと、bit 以下で最大の n の倍数が出ます。これに (n-1) を足して MAX_VALUE を超えて桁あふれ*1を起こすと負数になってしまう。
そうだったら値を棄てる。そうでなければ採用。
という具合になっています。
(追記) 注意! ここから先は大嘘です!! コメント参照のこと!!
……しかし。
しかしですね。
いざlong版をコードにしようとする段になると気がつくはずです。
nextLong(long) なるメソッドが欲しい時は、引数に指定するのは、Integer.MAX_VALUE より大きい値の場合なんですよね。
Javaでは言語仕様で、Integer と Long の MAX_VALUE は決められていて実装依存などないわけですから、
nextLong() して、n 以上の値がでてきたら棄てればいい
ってことになるじゃないですか。(Integer.MAX_VALUE より大きい場合、2倍しただけで Long.MAX_VALUE を超えてしまうのがほとんどだから)
public long nextLong(long n) {
if (n <= 0)
throw new IllegalArgumentException("n must be positive");
if (n <= Integer.MAX_VALUE)
return (long)nextInt((int)n);
long val;
do {
val = nextLong();
} while (val >= n);
return val;
}
これでおしまいだ! (注:コンパイル通してません)
なるほど、nextLong(long)が無いわけだ。と思いました。
これで大丈夫かどうかは、元々の乱数の質に依るのでこれだけでは評価できないです。
特定の乱数生成方法と相性が悪い、とかあるかもしれませんが、それは元々の乱数の質がよくないという意味でもありますし……。
■もう少しだけ
上で書いた nextLong(long) メソッドの中で、nextInt と nextLong の両方を使っている。
乱数生成の質が、nextInt の nextLong の両方で保証されてないといけないなぁ、と思った。
java.util.Random は実は long の大きさ(64bit長)を直接生成することはできない。nextLong() の実装は、int を2つ生成してビット結合するようになっている。
それだけではなく、
Random クラスによる nextLong メソッドの実装は、次と同等です。
public long nextLong() { return ((long)next(32) << 32) + next(32); }Random クラスは 48 ビットのみを含むシードを使用するため、このアルゴリズムは可能なすべての long 値の一部しか返しません
Random (Java Platform SE 6)
という但し書きが付いていたりする。
また、getDouble()なども、
[以前のバージョンの Java では、結果は次のように誤って計算されました。
return (((long)next(27) << 27) + next(27)) / (double)(1L << 54);これでもある程度等しく思われますが、実際には、浮動小数点数の丸めでのバイアスのために大きなばらつきが生じるので、有効数字の下位ビットが 0 になることが 1 になることの 3 倍ありました。この程度のばらつきは実際には問題になりませんが、完全性を求めて修正を試みています。]
Random (Java Platform SE 6)
浮動小数点数の丸めの処理などは、1000speakers in Sendaiのために、資料を読んでいてちょうどでてきた部分(話す内容とは直接関係ないけど)なので、なるほどそういうことも気をつけないといけないのかぁ。
とかもね。
*1 でいいんだっけ?
2008-11-11
■娘と話す「文化ってなに?」
AmazonやBK1だと
娘と話す文化ってなに?
書名にカギ括弧か何か欲しいところだけど、目録規則がそれを許さない!
のだろう。きっと。
(BK1 内容説明より)
「もうフランス国民なんていらないんじゃない?」「地球規模の文化は誕生すると思う?」 さまざまな文化が入り乱れるヨーロッパで暮らす父娘が、対話を通して、現代における「文化」のあり方を探る。
読んではみたいな。図書館に期待。
そろそろ、気になる本カテゴリの棚卸しでもするかな……。(図書館への入荷チェックとか)
■消費されるコンテンツ
韓国でハリウッド大手映画会社がDVD販売から撤退というニュース。
ワーナーホームビデオコリア、イ・ヒョンリョル代表は「今まで良質なビデオとDVDを最も手軽に、また最も安い価格で楽しめるように前防衛的な努力をしてきた。しかし変化に適応し、先行しなければ淘汰される。消費者の購買形態は、優れたデジタルインフラを基盤に大きく変化した。今後も良質のコンテンツが合法的に消費される、健全な市場を作るために努力する」と明らかにした。
innolife.net>>>韓国ニュース>>>ムービー>>>ワーナーブラザーズ韓国で一部事業撤収
訳文とはいえ、
今後も良質のコンテンツが合法的に消費される
という表現は気になる。気持ち悪い。
しかし、確かに、現状を正しく表現しているようでもある。
2008-11-12
■楽園の泉 読了
長かった。ずいぶんと時間がかかった。
読み終えて、(布製の)カバーを外して、本来のカバーに戻したとき、表紙を見て"あぁ"と思った。
小説では掴みそこねていたヴィジュアルイメージが、あった。
峻厳たる頂から立ち昇る「泉」。
これだけ有名な作品について今更あれこれ書こうとは思わないけど、FOUNTAINS という言葉のイメージの豊さ。
これをタイトルに使った感性の確かさに脱帽。
さて、ようやくこれで
が好き! って胸を張って言えるかな、と思った。
(しかし……この作品を本当に増刷しない気なのか。エンターブレイン)
■プログラミング……
あぁ、本当にブランクを心配した方がいいのかしらん。
ヘコむなぁ。
2008-11-13
2008-11-14
2008-11-16
■ケロロ軍曹を読んでいる
子どもがケロロたちの名前を一通り言える!
あまつさえ「そんなの当然」みたいな口ぶり。
お前絶対読んでないだろう? 的なノリで借りてきて読ませてあげる。
というのは明らかに欺瞞であるがツッコミ無用。
……このギャグやパロディは子どもには判らないだろ。
てゆーか世代的に親の方がツボすぎる。
2008-11-17
2008-11-18
2008-11-20
■オプションでしょ
子どもの友達が遊びにきた。
「ストーカーだよ! ストーカー」とやたらうるさい。
変な言葉がはやってるなぁ、と思いつつもじっくりと聴いていると、どうやらゲームで自分の後をつけてくるキャラのことをそう呼んでいる模様。
あー。
それはやっぱり「オプション」と呼ぶのが基本だろ。
などと思った。
2008-11-21
■タイトルが悪い
(BK1 内容説明より)
新婚時代のようなラブ2モードに戻りたい!自分のことは棚上げにして、日々蓄積する夫への不満を爆発させる妻たち。妻が冷静さを取り戻し、いたらなかった自分を認められれば、夫婦仲は劇的に改善できる!
うーん。内容説明とタイトルが合ってないぞ??
■サイコロジカル 読了
「説明しないことが、僕の説明」
「最後の防壁」
いいな。
戯言遣いの儚い抵抗ではあるけれど、でも。いいな。
説明してくれないおかげで、
いや本当に。
楽園の泉を読み終わってから10日間。
小説を読んでいるのが外出していた時ぐらいなわけで、実際使った時間という意味ではまぁまぁのペース。でも期間としては全然駄目だぁ。
2008-11-22
■図書館に自分の日記を置いていると想像してみて
図書館で利用者が勝手にしおりを挟んでいるようすを想像してください。
施設によっては利用者が数万人、あるいは数十万、数百万人もの人が利用して、
それぞれの利用者が勝手にしおり(ブックマーク)をすると、どのようなことになるでしょうか。きっと図書館はしおり(ブックマーク)であふれかえり、しおり(ブックマーク)に書かれた内容が
その図書館においてある利用物となってしまいます。これでは本来の図書館としての役割を果たすことは困難でしょう。
一般常識・礼儀とブログマナー - ☆女の徒然草☆ - Yahoo!ブログ
このメタファを拝借するならば。
図書館の棚に自分の日記を置いておいて「これは私の日記だから読まないでー」と大声で叫んでいる。
そんな感じでしょうか。
ついでに言うと。
Webって、まさにこのメタファで書かれた通りの原理で駆動している図書館だと、私は思う*1。
それは初期の手動登録型の検索サイトの時代から──Google の PageRankやソーシャル・ブックマークなど、新しい手法が出てきているとしても──ずっと変わっていない原理ではないかと。
■1000speakers@Sendai #1 より帰還
から帰還〜。
とりあえず日が変わらないうちに書いておくけどすぐに寝る。
ひとりだけ斜め上をいく異端な内容で話してきた。
なんか不思議だ、そういう世界もあるんだ、とちょっと思ってもらえればOK。
そんな感じで。
*1 ただしここで栞に喩えられるべきは"リンク"かもしれないが。
2008-11-23
■1000speakers@Sendai #1
資料アップ
「結構あがったけど『全然そうは見えなかった』って言われた」
と今日カミさんに言ったら、
「普段からちゃんとしゃべれてないからね〜」
だって。orz
1000人スピーカ プロジェクトの趣旨は「自分を晒そう」なわけだけど、そうは見えないプレゼン。
でも私の場合は「私はこういう話題が好きですよ! こういうのを読むとあぁ面白いなぁ、って思う人間なんですよ!」という趣向なのだ。
自分がやってきたことなんて普通すぎてネタにもならない、とか言って自重するよりもいいじゃないか。
と開き直って。
追記
ustを見てみると緊張しているのが(自分では)丸わかりで恥ずかしかった。
■日本語遣い
昨日のエントリでメタファという言葉を使ったけど、間違いなく誤用。
でもたまに「正しくキッチリ」した言葉ではなくて、わざとちょっと崩した言葉を使いたくなる。
「〜原理で駆動している図書館だ」なんかもそう。
■ホラー映画の世紀
「カリガリ博士」はともかく、「フリークス」をDVD収録ってのはよくやったなぁ、という感じだ。
まだ全然読んでいないけど、情報量よりは見やすさを優先した編集になっているな、と感じた。「ホラー映画クロニクル」とは対照的。
巻頭、センターがカラーページだけど、その他のページは基本2色なあたりも読みやすさを気づかってだと思う。
「ホラー映画クロニクル」について書いたエントリ。
追記
章立てはテーマ別。特に「歪んだ世界」の章に「恐怖の足跡」とか「エンゼル・ハート」とか入っているのが嬉しい。
以前友人*1が見たいと言っていた2002年公開の「プロフェシー」が紹介されていた。
確かに、これ、見てみたい。久々に連絡してみようか、とか思ったり。
*1 ホラー映画好き。この道の師匠??
2008-11-24
■プレゼンとか
10分枠で、7分話して3分質疑応答とかキツすぎる。
時間が短い方が、気持ち的にはハードル低いのだけど、実際プレゼンを構成しようとすると難しい。
この話については、
p11
学校の先生は説明のプロです.(略)
上手に説明できるかどうかは,先生の「授業スキル」の基本です.(略)そして,あるベテランの先生に伺うと,(略)
基本は、「何を説明するか」ではなく、「何を説明しないか」を考えるそうです。
を持ち出すに限る。
武田ソフト氏から褒められたのがすっごい嬉しかったぜ〜。
quintiaの難しい話を簡潔に伝えてくれる手腕はすばらしい。
庶民によるIT | ブログ.武田ソフト.jp
(これが言いたかったのか!)
(いや、実際今回この本にはちょっと助けられたんだよ。だから紹介)
2008-11-26
■分相応の学校に入れる
じゃ駄目かな?
あるいは、「子どもが通いたいと思えない学校を受験させない」とか。
子供の中学受験を考えています。
中学受験で合格したものの、燃え尽きてしまう生徒が数%いるそうです。
中学受験で燃え尽きないために - 教えて!goo
なんか妙な質問だなぁ……。
はてなじゃないけどhatenaカテゴリ。
2008-11-27
2008-11-29
■これは貴方の受像器の故障ではありません
アウターリミッツのDVDがゲオにあった。
ジェームズ・キャメロンの『ターミネーター』のストーリーは自分の作品の剽窃だとエリスンは裁判を起こした。キャメロンはエリスンの作品から着想を得たことを認め、エリスンの名前をクレジットに入れると共に謝罪広告を打った。
ハーラン・エリスンとは - はてなキーワード
のエピソードがあったので観ようと思う。
あ、ハーラン・エリスンは「世界の中心で愛を叫んだけもの」の作者ね。