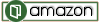2008-08-01
■del.icio.us が変わった
検索の日本語の単語区切りがまだまだ。
すっきりした印象なのに、より広いデスクトップが必要になったなぁ。
■格好良すぎる logo animation
World Science Festival というイベント用に作られたアニメーション。格好良すぎる。
音が出ます。Content-Type: video/quicktime です。
via
2008-08-02
■数学ガール 整数の《本当の姿》
フェルマーの最終定理の証明に関しては、最後の10章でのみ語られる。
フェルマーの最終定理は、その命題だけを見れば整数しか現れない。
けれどその証明には、今のところ楕円曲線という別の世界への橋を渡らなければ到達できないわけで。それが証明を解説するのが難しいところでもあり、あるいは証明までに長い時間を要した理由でもある。
今のところ、整数しか現れない命題に「初等的な証明はない(p335)」のだ。
では、この本はというと。
「数というものの《ほんとうの姿》(p25)」は何なのか? どこにあるのか? どこを通ればたどり着けるのか?
あるいは、それを追いかければどんな世界を垣間見ることが出来るのか? というのが大テーマ(だと勝手に思った)。
そのための道具立てが「フェルマーの最終定理」。
そこにたどり着くまでに見える世界は豊穣で、広い。理解するのは難しく、けれど想像することが楽しいほどに。
テトラちゃんが、群というキィワードを頼りに、想像の翼を広げて楕円曲線という世界を垣間見る瞬間があった。
その一行一行を、テトラちゃんの世界が広がる様を、ゆっくりと堪能した。
それは、私にとっては「感動した」と表現するのに値する時間──。
■統計的言語モデル
ぶっちゃけきしださん(id:nowokay)が薦めていたからという理由で買ったわけだけど、これはいい本だ!
音声認識システムというタイトルなのだけど、音声を扱わない自然言語処理、言語モデルを勉強したい人でも問題なくお薦めできる。
音声認識なのでフーリエ変換とかフォルマント(懐かしい!!)とか出てくるけど、音声関係ない人は無視していい。
NN法、パーセプトロン、SVM(サポートベクターマシン)にニューラルネットワーク、ベイズ推定から、システム評価法(分割学習とか効果確認法とか)にチューニングまで。
モデルとしてはHMM(隠れマルコフモデル)と学習のさせ方。
正規文法に文脈自由文法。
これだけの範囲を扱っていて、なお説明は読みやすい。
数式は出てくる。定式化が必要な部分ではちゃんと式を使って説明するのだけど(そうでなかったら評価はもっと低い)、その前後の説明や図表の使い方がうまい。
これは良い買い物だったと思う。
*1 これを書いている時点では、です。
2008-08-03
■押井守ファンならばトーキング・ヘッドを思い出すはず
押井「映画は観ただけでなく、語られることで映画として成立すると思っています。映画について誰と何を語るかで、真価が決まるのではないかと。今回はそれを特に感じています。大事な誰かと語っていただければ幸いです」
【レポート】押井守監督「映画は、語られることで完成する」 - アニメ映画『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』初日舞台挨拶 | ホビー | マイコミジャーナル
(「トーキング・ヘッド」より)
語られた映画とは実は常に映画の記憶のことでしかない
指し示すことはおろか引用すら出来ず
語ろうとする時には呈示することも不可能で
しかも他者との共時的体験すらない個的な経験
それが映画を観るという行為の実相だ
人は自分が観たものを言葉で表すことは出来ない
観るということと観たことを言葉で表すということの間には
結局は何の関係もないんだから
映画を観ること
観たこと
観た映画について語ること
そして映画を観ることについて語ること
これらの行為の間にはいかなる共通項も存在しないし
複数の人間の間に於いてはもちろん
同一の個人にとっても一本の映画が同じ体験として我々の前に立ち現われることは
テキストとしてのフィルムが単一の存在であるという幻想を前提としてしか……ありえない
押井さんもちょっと変わったな、と思った。
2008-08-04
■全てのデザイナーがダウンロードしておくべき30の必須PDFドキュメント
まぁ、全部英語なんだろうけど。
» 30 Essential PDF Documents Every Designer Should Download :: Positive Space Blog
こういう時の"essential"は訳しがたい。"必須"としてみたものの、"本質的な"というニュアンスを出すにはどんな日本語が相応しいか……。
■なんでWordPressはRSS1.0を捨てたんだろう
不思議。……いや全然経緯を調べてないけど。
2008-08-05
■ポリス・カーロフの"フランケンシュタインの怪物"
おっと、全然気がついてなかった。ちょっと欲しいな。
"フランケンシュタイン"じゃなくて、"Frankenstein's monster"だからね。フランケンシュタインは博士の名前だからね。
2008-08-06
2008-08-07
■七夕祭りのモチーフたち
仙台は七夕祭りの真っ最中。
通勤に邪魔だったりして生活している人たちには何かと不評な七夕飾り。
笹に短冊は全国共通として、仙台七夕祭りで見られる他のモチーフを揃えてみた。
吹き流し。これはとにかく目立つので──というか道路にこれでもかというほどあるので誰もが知っているだろう。


鶴。これもたくさん目にする。
でもそもそも「おめでたい」とされるものだから違和感を持たないかも。
上の写真の右端に写っているのが……、
「紙衣」と「巾着」。

「屑籠」と「投網」。
右側の赤いのが屑籠。右側の水色が投網。
投網の方は、特に仙台特有というわけではない。そうと意識していないかもしれないが七夕には飾っているはずである。
気をつけてみてみれば、至る所にこれらが飾られている。その由来について書かれた紙も、置いてあったりする。ぶっちゃけただ見るだけでは全くつまらない祭りなので、そういう捜し物をしながら歩くといい。
さて。
「籠」や「紙衣」の裏の意図は──、
で語られている(それが「ほんとう」かどうかはさておく)。
七夕にまつわる物語は、その頃には雨が降って川が増水して、牽牛と織女は会うことが出来ないという話である。
だから、「七夕にはよく雨が降る」というのはじつは「当然」なのだけど……。
今日は快晴で、とても暑い。
(追記)
七夕に牽牛と織女が会えないのは天の川が増水しているからであって、地上が晴れていようと雨が降っていようと関係がない。
地上で雨が降っていれば「会えない」と思うは現代の人間も同じ。
晴れて天の川が綺麗に見えた時には「あぁ、天の川が溢れている。今年も会えなかったのだなぁ」と昔の人は思ったわけ。
前出の本に書いてあるのだけど、和歌には「七夕に二人が会えない」という内容のものばかりだそうだ。
それも当たり前で、「七夕の時期には天の川が綺麗に見える」というのは「七夕の時期には天の川は氾濫している」わけで、「一年に一度、七夕の時だけ会っていい」という命令はとりもなおさず「二度と会ってはいけない」が真意である。
しかし現代の都会では天の川など氾濫しているようには見えない。、むしろ現代になって、ようやく二人は会えるようになったのかもしれない……。
2008-08-08
■ばいばい、アース 読了!
3冊に一月半もかかってるよ!
まぁ、3冊ほど寄り道してるけど。
面白い面白い!
とにかく1ページ、1段落、1行、いやいや一つ一つの言葉が驚くほどの情報量を持っていて(ダブルミーニングが当たり前!)時間がかかること。
世界も濃密。
未来世界を思わせる言葉遊びや仕掛けが満載なのでSFっぽくも見えるが、それらしいガジェットは終に登場せず。
あくまでも世界の理の記述にとどまる。そのおかげでハイ・ファンタジーとして成立させつつも、書かれていないことまで色々と想像させるという、読み手の想像力を試すかのような仕立て。
いやさ、こんだけの文章を目にしたら読み急ぐのは野暮ってもので、珍しくもじっくり読み込んでしまった。
さてさて、デビュー作の
も楽しみだけど、いつごろ読もうかな。
復刻版はこっち。
2008-08-09
2008-08-10
■帰省します
ネットのない世界へGo!
2008-08-16
■帰ってきました
無事に
■夜空
春に新しいカメラを買ったので夜空の写真を撮ってきた。マニュアル撮影のモードがあるから。
残念ながら綺麗な澄んだ空気ではなかったけれど、それでも全天に星が見えるぐらいの夜空。
ISO1600 F8.0 シャッタースピード60秒。北北東ぐらいの方角。
フレームの外、右側にある街灯からの光が入ってきている。
シャッタースピードが60秒が限界なのが残念。
60秒分のデータを蓄積して、あとから画像処理をかけるという機構の様でシャッタースピードを大きくするにはメモリが必要になるのだろう。
このクラスのカメラでそれ以上の露光をするのは、さすがに想定外というか期待のしすぎというものだろう。(60秒まで選べるだけでもすごいと思う)
花火モードもまぁまぁだけど、
何枚か撮ってみて、自分が撮りたいような写真が撮れたら、次はマニュアルモードで狙ってみた方がよさそうと思った。
しだれ柳をきれいに撮れたのがなくて残念……。
(ここに載せた写真は1560x1920で撮影したものを25%縮小したものです。ガンマなどはいじっていません)
2008-08-17
■親指シフト
設問の条件が甘いので無回答。
あなたご自身は、この動画での入力速度と比べて、より速く(156打鍵/分以上の速度で)打鍵操作をすることは出来ますか。また、より速く(121文字/分以上の速度で)文字入力を行うことは出来ますか。(択一)
http://q.hatena.ne.jp/1218558299
1回目の動画と一緒にタイプ。もちろん追いつけないし誤字も多い。
2回目、1回目で打った文を見ながらタイプ。最後の1行分だけ遅れた。
3回目。動画よりも速く打てた。
2008-08-18
■「引用」は無断で行うためのルールといっても過言ではない、という話
同感できる。
誤解を恐れずに言うなら,「引用」という行為は,"無断でできるからこそ意味がある"と言っても過言ではありません。
ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識:第3回 ユーザーにとっての福音? - 「引用」ルールの可能性とその限界|gihyo.jp … 技術評論社
著作者の氏名を表示しなかったり,他人の「著作物」を無断で改変して取り込んだりしたような場合には,適法な「引用」と認められない,あるいは,同一性保持権,氏名表示権といった著作者人格権侵害(広義の著作権侵害)となる
ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識:第3回 ユーザーにとっての福音? - 「引用」ルールの可能性とその限界|gihyo.jp … 技術評論社
ネットでは「著作者」が明でなく、「URL」だけでしか示せない場合があるとかいうのはどうなんだろう。
このエントリでの引用も、1つ目の引用と、2つ目と3つ目の引用はリンク先のURLが微妙に違っている。ページが違うせい。
パッと見では分からないだろう。でも同じ「著作物」へのリンクに見えるはずだし、リンクを辿って見る人を混乱させないためにも──引用元を誤解させないためにもその方がいいと思う。
私は「引用に関してはディープリンク当然!」派なのでいいのだけど、ここで「ディープリンク不許可」問題があるかと。
そのディープリンクに関しての話は意図的に回避しているように感じた。
実際にも,ある宗教団体を批判する目的で,その団体の名誉会長の写真(第三者によって改変されてインターネット上に出回っていたもの)を自分のホームページに掲載した行為が,「引用」にはあたらない,とされ,宗教団体側の損害賠償請求が認められた例(東京地裁平成19年4月12日判決)もありますので,注意が必要です。
ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識:第3回 ユーザーにとっての福音? - 「引用」ルールの可能性とその限界|gihyo.jp … 技術評論社
この判例は知らなかった。本当に注意が必要なんだなぁ。
■最高の夢オチ映画
計算しつくされた最高の夢オチ、というものを観た気がする。
見終わってから時間が経つほどに、構成の緻密さと伏線の絶妙さに震えが来る(本当にキーボードを叩いている指が震えている)。
何の映画かは movie カテゴリを表示してご想像ください。邦題だとしっかり(?)ネタバレしてるので分かるでしょう。
2008-08-19
■顔ちぇきが世界に紹介されている
……ちょ。結果が判らないだろ。純粋に技術的な紹介だけど、あのサービス、半分は(○○占いみたいな)遊びの領域のような。
Japan's Kao Chekki (Face Check) Proves That Vanity Apps Know No Boundaries | TechCrunch
顔ちぇきが、"Face Check"に訳されているな。
2008-08-20
■アオイシロ 1,2
なんとなく買ったものの手つかずでいたのを読んだ。
「牛の首」の話が出てくるのにびっくり。
やっぱり小松左京の短編は、都市伝説や伝承が先にあってそれを下敷きにしたのだろうか?
分からん。
分からないが、けれど小松左京の短編の切れ味の鋭さと"呪(しゅ)"の怖さに変わりはないのだ。
肝心の本編の方だけど、まだ続いていたので今のところ感想なし。とりあえず3巻が出たら買おう、と思うぐらいは面白かった。
2008-08-21
■クビシメロマンチスト 読了
「ふう」
──と言いながら本を閉じた。僕はそれに合わせて尋ねる。
「どうだった?」
「うん。なかなか面白い」
──ほう。
「君にとっての『面白い』の定義は?」
「2度読む価値がある、あるいは、もう一度読んでみようと思えること」
──即答。もっとも、それは今更訊かなくても、幾度となく問うてきたものだ。だったら、
「だったら、『なかなか面白い』の定義は?」
「……読んでいる間は楽しいし、作品としての評価は高いが、『いつかまたもう一度読んでみよう』とは思わなかったもの」
──そして、少し考えているような仕草をする。続きを促すようなことは、もちろんしない。
「あるいは、最初から、作品がそのように読まれることを前提として書かれているもの。あらかじめ『消費されること』が織り込まれている作品」
──消費される物語、というタームは借用だな。別の場所で目にしたことがある。
「その作品は、どうしてそう思った?」
「『史上最強の請負人』。物語の中の状況に一切関わりがないくせに、一通りの謎解きが終わった後に現れて、隠されていたことを洗いざらいにする存在。それゆえに、この本にはもう隠されたことはもうないのだと宣言するための機構の様に錯覚する。ある意味究極の安楽椅子探偵かも。だから、もう一度読もうと感じないのかな」
「それで評価は高いが『なかなか面白い』にとどまるわけか」
「いや、それは違う。『面白い』と『なかなか面白い』の間に優劣はない。どちらもクラスであり、タグ付けでしかない。一次元の『面白さ』なんていう尺度は、ないよ」
は明日にも届くだろう。そして、また同じ様に思うのだろう。
■フリーオ
とんでもない、というより「技術的欠陥」のような気がする。
なお、読者からのタレコミによると、サーバーにカードリーダーを取り付けることで、カードから読み出した情報を共有するという手法は「Card sharing」と呼ばれ、すでに海外では同様のことが広く行われているようです。
ついにあの「フリーオ」がB-CASカード不要に、とんでもない方法を採用 - GIGAZINE
■まつのべっ!! THE GIRL CALLS HIM, MATSUNOBE!
ドラマティック4コマ*1の大傑作だ!!
めずらしく紹介を書いちゃうぞ。
まつのべは主人公の名字で幼稚園の先生。
園児に先生のことをまつのべと呼び捨てにする子がいる。まつのべが幼稚園時代一緒だった女の子にそっくり。その子と同じ顔、口調、仕草でまつのべと呼び捨てにしてきたり、すごくしっかりしていたしてなかなか叱れない、叱っても効果がない。
で、その幼なじみは今は女優をやっている。それも押しも押されぬ有名女優。
小学生になったとたん引っ越していってしまって、長い間会っていないけれども──あるいはそれだからこそ、まつのべ! と呼ばれる度に彼女のことを思い出してしまって動揺するまつのべ。
ギリギリまで明かされないけど、でも見え見えな関係。まつのべと呼び捨てにするその子の母親こそが、幼なじみの女優なわけだ。
1巻は、そんな幼稚園が舞台。
まつのべの元カノの登場やらがあって、美少年アイドル大好きで1年先輩の先生がまつのべに惹かれていく。
そんな中、まつのべは幼なじみの大女優とばったり出会い、謎のおでん屋で時々会うことになる。
2巻は、幼稚園のシーンはぐっと少なくなって、まつのべと幼なじみと、先輩先生。(女優を目指して養成所に通っている)先輩先生の妹や、おでん屋のおっちゃん、元カノ。
もう、ラブコメらしい──少女漫画らしい? めまぐるしい展開の末に……。
連載から10年目の単行本化。
これは傑作。(少女漫画が苦手な人にはお勧めしないが)
2分冊で一度に発売。
本屋で見かけた僥倖に感謝。
*1 オビに書いてあった。ここでは、漫画の中で回を追ってストーリィが展開している形態の4コマ漫画のことを指して書いている。
2008-08-22
2008-08-23
■フリーランチの時代 読了
いつのまにか不老不死を手に入れてしまっていた、という話「千歳の坂も」。
でも私は未来で勝つつもりでいる
「私」が追いかける老女の台詞。
その意味がたちあがってくる時、「私」と同じく驚愕した。
傑作だ、と。
こうして、「第六大陸」を読まなきゃなぁ、という外堀が埋まりつつあるような……。
2008-08-24
■トゥインクル☆クロニクル 読了
本編より面白いじゃないか。と、似非歴史もの好き(似非がどこにかかっているかは明かではない)な私は思ったり。
ライトノベルの「外伝」としてはなかなか。筆者が好きなことを興に乗って書いている感じがしてよい。
2008-08-25
■古いページを更新してしまった
フィードを変更しない、のチェックをつけずに……。
*1 紙面構成が無いWebに対してコラム(縦欄)というのも変だが。
2008-08-27
■理性の限界 読了(?)
表面をなぞったのみ、という感じなので?をつけておいた。
架空のディスカッション形式で書かれているので、取っつきやすいと思ったのだけど、つい読み流してしまいがちという罠もあるかと。
タームを並べるだけでどんな本なのか分かるかなぁ、と思うので列挙してみる。
- コンドルセのパラドックス(投票についてのパラドックス)
- ボルダのパラドックス(投票についてのパラドックス)
- アローの不可能性定理*1(完全な民主的決定方式が存在しないことの証明)
- 囚人のジレンマ
- 繰り返し囚人のジレンマ
- しっぺ返し戦略
- ナッシュ均衡
- チキンゲーム
- ニュートンのプリンキピア
- ラプラスの悪魔
- 光速度不変の原理(ニュートン物理学での解決不能問題)
- 相対性理論
- 不確定性原理(位置と運動量の誤差の積に下限がある)
- ハイゼンベルクの不確定性原理
- EPRパラドックス(高速を越えた情報伝達)
- 二重スリット実験による干渉縞
- シュレーディンガーの猫
- 抜き打ちテストのパラドックス
- ゲーデルの不完全性定理
- 認知論理システム
- チューリングマシンの限界(ゲーデル・チューリングの不完全性定理、チャーチの定理、チューリングの定理)
二重スリット実験による干渉縞は驚きだった。でも前から知っていることを忘れていただけかもしれない。
追記
オビをふと見て気がついたのだけど筆者は「ゲーデルの哲学」と同じ人じゃないか。
で読んでいた。なんか納得。
■千の剣の舞う空に 読了
青春だね! ボーイミーツガールだ!
オンラインゲームで出会った女の子が実はクラスメイトだった、というキャッチーなシチュエーションが突出しているものの、基本的にはスタンダードなボーイミーツガールストーリー。
*1 本の中で出てくる表記はアロウ。ここではWikipediaの項目に合わせてアローとした。
2008-08-29
■俺の妹がこんなに可愛いわけがない 読了
あまりに設定がキャッチーだから、ちゃんと評価されるのか心配だが、しっかり書けているじゃないかと感じた。
ただ、このキャッチーな設定は物語の道中はすごく面白いのだけど締めの難しさはあるなぁ、と感じながら読んでいたらやっぱり終盤の展開はかなり苦しい。
それでもなんとかまとめて仕上げていて、最後の1行で納得、と。
さて。
どうでもいいが、某ギャルゲで「一人称が自分の名前」のキャラがカミさんと同じ名前だった時の苦行を思い出したよ。
■お金は銀行に預けるな
中身については、私が漠然と考えていることと重なっているものが多くて安心できた。
1つの本を鵜呑みにするんじゃなくて、いくつかの本や情報源から構築している知識を確認するという位置づけで読んでいるのでそんな感想になった。
初めて目にするもの、今までの認識とずれているものについては心に留めておいてあとでフォローする必要があるだろう。
ただ、カミさんはこういう本自体に拒否反応を示すので、話が平行線のままなんだよなぁ。
さて。
"住宅ローンは組むな"というのがあって、金融リテラシー的には全く正しいのだろう。
ただ、環境とか、間取りとか気に入っていて、特に間取りについてはここと似たようなコンセプトで設計されたマンションってのはお目にかかったことがないわけで、"住宅ローンは組む"というリスクを取ってここを買ったのは悪くはない選択だったと思っている。
その辺は自分の判断、ということで。
2008-08-30
■時砂の王 読了
さて次は何を読もうかと本棚の中の未読棚を眺めていて、これがあることに気がついた。つい先日読んだ「フリーランチの時代」の人の長編。
買ったっけ? と訝りながらも、これはタイミング的にも今読むべきだなと思って手に取った。
時間もので、分裂的平行世界もの。
「敵」との戦いに勝ち目が無いことがはっきりしてきたために、過去に遡っての殲滅線という手段を決意する人類。(ただし救えるのは別の時間線の世界なのだが)
過去へ過去へと遡り戦いを続ける部隊。
だがその戦いも実り少なく、最終決戦の時間線を設定し全線力をそこに集結しようというとき、そこから離脱して短い間隔での時間遡航を繰り返して連戦を決意する主人公。
A.D.248年の日本列島から話は始まる。章名にはStage448と銘打たれている。
で。
号泣した。
「ある日」は「唐突」にやってくる
「伏線」など張るひまもなく、
「説得力」のある破壊なんてあるものか。
とは、藤子・F・不二雄の短編「ある日…」の台詞であるが、その通り不意打ちをくらってしまった。
あー。泣いた泣いた。
細かな伏線などかあるわけではなくて、長編1つとそれに挟み込まれるような形の短編を読んだような感覚。(A.D.248年がメインになっていて、その間に、「敵」との遭遇(Stage001)から始まって、時間遡航しての戦いを段階的に挟んでいる構成)
そのためもあってか、楽しく一気に読めた。
そしてガツンと、やられたのだ。