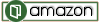2007-07-01
■一目でそれと判るデザイン
家の掃除をしていたらパトレイバー(98式AV)の食玩フィギュアゲーセンのプライズが出て来た。
子供が見て曰く、「これってパトカーでしょ?」。
偉大なデザインだなぁ。
視覚的効果まで考慮した
だったっけ。
2007-07-02
■ザ・ファシリテーター 2
前作(「ザ・ファシリテーター(森 時彦)」のこと)と比べると、2つの組織に2人のメインキャラクター、複数の視点・シチュエーションと、要素が増えたことで小説として面白くなったと思う。
逆に散漫になった感じもある。一本のストーリーに見えない。何かの決着が着いたかんじもしない。
別にストーリーを楽しむために読んでいるんじゃないのでそれでもオーケー。
色々なシチュエーションを詰め込んだ今作の方が面白いかな、と。
■21世紀に最ももらいたくないダサいレッテル
企業、従来型メディア、広告代理店は、SNS、ブログをマーケティングに利用するのに遅れただけではなく、ネット活用が下手な人達という、21世紀に最ももらいたくないダサいレッテルを貼られてしまいました。次はもう絶対に失敗しない、そして、われはネット最前線だとアピールしたいわけです。
ITmedia アンカーデスク:Second Lifeに3度目の正直をかける企業、従来型メディア、代理店
セカンドライフ関連の書籍がいっぱいでているけど、買い支えているのは本当のユーザじゃないのかも。とか思った。
2007-07-03
■「ブラウザ」って?
【レビュー】もはやブラウザいらずか - 「goo RSSリーダー」高機能版を試す (1) Feed未配信サイトのRSSを作成する | ネット | マイナビニュース
それがhttpクライアント&htmlユーザエージェントなわけだが。
まぁ、分かっていて書いているんだろうけど。
■最高幹部を狙ったメール攻撃が急増
全然関係ないが、入社時に"president"のアドレスが欲しいといった新入社員がいた、という話を思い出した。
自分の会社の CIO から『これを処理せよ』というメールが届いたら、疑問など持たないだろう。
単に"fromが自社のCIOのメール"なら警戒するだろうけど、転送で元メールが引用された状態で地の文にCIOのメッセージが入っていたら確かに警戒も薄れるかも。
一瞬、fromを最高幹部のものに偽装して、その会社の人間にばらまくという攻撃もありえるか? と考えた。
それと比べると記事にある攻撃法は、普段からCIOが処理を依頼しているスタッフに適切に行き渡るという点で優秀だな、と評価した。
攻撃方法を評価するのは大事。
参考
■涼宮ハルヒの憂鬱
今ごろ「涼宮ハルヒの憂鬱」なんである。
アニメの一巻を見たのが日曜日の夜。
ほう、と言いながら、まず小説を読もう、と思いたち買ってきたのが月曜日。
でさっき読み終えた、と。
結論。
「学校を出よう」の方が面白い。
以上。
……と終わるのも何なので。
アニメは三巻までは見るだろう。
2007-07-04
■対称性がバックアップとなる
てなことが
に書いてあったっけな。
回文はそれが回文だと分かっだ時点で(あるいは回文であるという情報と一緒に与えられた時点で)、約半分の容量に圧縮できるな。
CD-RやDVD-R。「容量、書き込み速度は半分になるけどキズに強くなります」みたいなライティングソフトやドライブが出たりしないものか。……これは単なる冗長性の話で対称性とは関係ないや。
2007-07-05
■学術用語としての重み
Non Restoring Division(引き放し法。筆者は、引きっ放し法と書くべきと思うのであるが、学術用語としては重みに欠けるためか、引き放し法という用語が用いられている)
【コラム】コンピュータアーキテクチャの話 (85) 引き過ぎを戻す必要があるのか? | エンタープライズ | マイコミジャーナル
軽く笑った。
それはともかく、面白そうな連載だな。今まで見過ごしていたのか……。
■時間管理はテクニックか
もうこういうパターンのタイトルはいいです。キャッチーなつもりでいるのかもしれないけど。
時間管理の超プロが究極の時間活用術を紹介し、仕事が速い人になるテクニックを伝授する。
ビーケーワン:通勤電車で新聞を読む人はなぜ仕事が遅いのか
時間管理ってテクニックだろうか。
こういう文脈での"テクニック"って、"tips"という意味に見えるのはなぜだろう?
"職人の技"みたいな意味の方が強い言葉だと思うのだけど。
■実験
WireSharkで80ポートを監視しつつ以下のコードを実行。
public static void main(String[] args) {
try {
URL url = new URL("http://10.50.180.33/");
URLConnection con = url.openConnection();
con.setDoOutput(true);
con.setDoInput(true);
con.setUseCaches(false);
con.setRequestProperty("Content-type", "application/octet-stream");
System.out.println("sleep");
Thread.currentThread().sleep(10000);
System.out.println("awake");
OutputStream outs = null;
outs = con.getOutputStream();
最初の通信(SYN,ACK)が監視されたのは、sleepの後、つまり getOutputStream() だった。
メモ。
2007-07-06
■ついうっかり
古いエントリを直した時にRSSを更新してしまったり。
■会社が変わらなければ社員の心の病は減らせない
会社が変わらなければ社員の心の病は減らせない
ビーケーワン:会社で心を病むということ
■鈴宮ハルヒの憂鬱
書くつもりはなかったのだけど、DVDを見ていて、テレビ放映時はこの話順じゃなかったのだな! と気がついたのでとりあえず。
原作からしてそうだけど、キョンのオフに圧倒的にうまい! と思うところは多い。
2007-07-07
■いい人
「いい人」になりきっていいことをする。そうやって「親切慣れ」していけば、素の自分でも気恥ずかしさや気後れを感じず、他人に対して自然に親切をできるようになりやすい。
まんぷく::日記 - 「いい人のふり」で親切を
よく人に道を聞かれたりする。
カメラのシャッターをお願いされたりもする。
東京に出張した時にそんな話をすると、
「えー、そういうのって全部無視する〜」
と言われた。
考えられん。まぁ私はいなかの人間だからな。
さておき。
道を聞きたい人っていうのは誰に尋ねるのか探しているはずなわけで、俺ってそんなに「いい人」に見える?
みたいな。
2007-07-08
■Foleoの気になるあの2つのボタン
マウスクリック用のボタン2つを犠牲にして、親指シフトにしてしまう人が出てくるんじゃないかと、やっぱり思ってしまう。
Linuxベースらしいし、すぐにHackして別のディストリビューションを入れようとする人は当然でてくるだろう。
2007-07-09
■川の流水量は?
昔、みそ汁一杯で生態系が狂う、みそ汁一杯分をきれいにするのにお風呂○杯分の水が必要だ、みたいな話を聞きましたが、結局あれはなんだったのでしょうか?正しかったのでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1183817651
回答にあったリンクを辿ってみて思うこと。
なんで河川の流水量を併記しない?
この話を聞いた時に当然疑問に思うことなわけだけど、それは自分で調べなきゃならない。それは不誠実というもの。
身近にある川を一つ、思い浮かべてみる。
その川を毎分どのぐらいの水が流れているのか、知っている人がどれほどいる?
2007-07-10
■冗談です。冗談
通りすがり 『メンバ変数の初期化も面倒ですが、委譲も面倒だと思いません?
そのまま委譲対象のメソッドを呼ぶだけなことも多いので、シンタックスシュガーがあると便利だと思うのですが。』確かに面倒ではあります。
新言語 Xtalを作る日記
でもコレ、よい記法が思いつかないんですよ。
誰かいい考えはありませんでしょうか。
そんなの多重継承をじっそ…… バキッ!!(-_-)=○()゜O゜)アウッ!
てなネタを思いついたのだけどさすがにコメントできません……。
■「あやしげなリンクをクリックしない」小中校生ユーザーの半数以上が留意
とはいっても、「どの様なリンクをあやしげと判断するか?」がリテラシであろうに……。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/07/10/16287.html
2007-07-11
■スペースキーは半角空白
FireFox使いが多い筈のはてなユーザーの有識者さんにお尋ねします
IEだとMS-IMEがONでもスペースキーでページ送りとか出来ますが、FireFoxだと半角モードでないとスペースキーでページ送り出来ませんよね?
そーゆーのを出来るようにして欲しいと言う要望を効果的に提出する提出先とその方法は?
http://q.hatena.ne.jp/1184094273
あぁ、そういうえばこの件もあってスペースキーは必ず半角空白になる様に設定してしまったのだけど、これがことのほか楽で気持ちがよい。
それまでは変な先入観で全角空白を入力できる余地を残しておいたのだけど、私自身にとってはIMEから入力できなくしてしまった方が(自分にとっての)良い選択肢なのだと初めて気がついたのであった。
どうしても必要なら、テキストエディタの半角→全角化機能を使うし、そこからコピーアンドペーストでいい。
2007-07-12
■あやしげなリンクって一体どういうものをいうのだろう?
要するにGoogleと見せかけてダイレクトにサイトへ飛ばそうとしたのですか???
http://q.hatena.ne.jp/1184171100#c94695
というコメントがついたので自分で解説。(IEではうまくいかなかっりしてちょっとトホホ)
このURLはれっきとした「www.hatena.ne.jpにリクエストしますよ」という表記です。
google は全然関係ないです。
というニュースを受けて以前、あやしげなリンクを判断するのは「人」の側なので「どのようなリンクをあやしげと判断するか」というリテラシが必要になるだろうな、というようなことを書きました。
というか、言下に「あやしげなリンクをクリックしないようにしましょう」ということに価値があるのか? とか思ったわけで。
で、非常にポピュラーな――ただし、だからこそ最近では使わなくなったような――記法で試してみました、と。
以下解説。(面倒くさいと思った人は読み飛ばしてください。)
質問にだしたこのURL、
IEではうまくいかないのだけどFirefoxでは警告が出ます。
このURLは、
- www.hatena.ne.jp という名前のサーバに
- www.google.co.jp というuser
- searchsourceid=mozclient&ie=utf-8&oe=utf-8&q=%A4%CF%A4%C6%A4%CA%A4%C8%A4%CF というpassword
でBASIC認証付きでリクエストしますよ、ということを意味する場合があります。
場合があります、というのはなにやら曖昧ですが、RFC(http://www.faqs.org/rfcs/rfc2396.html)を見てみると、
3.2.2. Server-based Naming Authority
(略)
<userinfo>@<host>:<port>
(略)
server = [ [ userinfo "@" ] hostport ]
The user information, if present, is followed by a commercial at-sign
"@".
userinfo = *( unreserved | escaped |
";" | ":" | "&" | "=" | "+" | "$" | "," )
Some URL schemes use the format "user:password" in the userinfo
field. This practice is NOT RECOMMENDED, because the passing of
authentication information in clear text (such as URI) has proven to
be a security risk in almost every case where it has been used.
とあって、ちゃんと決まっている記法ではなく、その様に使われる習慣(practice)がありますよ、というだけなのです。
ハッキリしているのは、「@から後ろ」がアクセス先(リクエスト先)のサーバだということです。
ただしその習慣は奨められない(NOT RECOMMENDED)とも書いてあるわけで、IEがこの記法を受けつけないのは……まぁしょうがないのかな???
Firefoxは、「そのサーバ(ここではwww.hatena.ne.jp)は別にBASIC認証なんか求めてないぞ。騙されてないか?」というような警告がでます。日本語のFirefoxを使ってないのでどう訳されているか知りませんが、こんなダイアログですね。

さて、本題。
このリンク↓。
「あやしげなリンクをクリックしない」と回答した小中校生ユーザーのどのぐらいが「あやしげなリンク」だと思うでしょうかね?
2007-07-13
■数学ガール
数学ってのは他の分野に比べて「理解し直す」という事象が起きやすい気がする。
「理解し直す」ってのはつまり理解していると思っていたことが、別の面から見たときに「こんな意味を持っていたのか!」と驚愕したりすること、かな?
数学ってのは「正解」がちゃんとある学問だと思われていたりするのだろうか。
一つの「正解」――例えば数列の極限とか――が確かに存在していても、そこに至る道は無数にある。
その道はどれも確かに正しいのだけど、自分が知っている道以外の道を辿って「正解」に行き着いた時。
おなじ「正解」が全然違う輝きを放つことがある。
ミルカさん、「僕」、テトラちゃん。
みんなが自分の道で歩いていくのが、とても眩しい。
特に、テトラちゃんの"三角関数の因数分解"。
全然関係ない話。
knuth先生の本
p142
2×π≡π+πを正当に証明できるけど、π+πを有限回の手順で計算できるとは限らないってことね。神様だけが計算を終えられるけど、人間にできるのは証明を終わらせることだけってこと。
に目眩がしたのは私。
■グロリアスドーン 3
庄司さんの本はどれもストーリーの構造が同じだな、と思ってしまいました。
これはいけません。
でもキャラが立っています。それはよいことです。
ティセの口調が移ってしまいました。
それは微妙です。微妙。
2007-07-14
■「ポリシー」に納得できないなら「属性」に言い換えてみよう!
日常的に使っている/使われているにも関わらず、「ポリシーって何?」と本気で聞かれると答えるのに困るわけで。
方針。政策。考え方。 規範。賢明。
検索したり辞書を手繰ったりしてみるとこんな感じ。
まぁ確かにそうなんだけど、しっくりこないなぁ。
と感じていた。
しかーし、偉大なる日本のOTAKUはこれに匹敵する概念をすでに作り出しているのだ。
「属性」
である。もしくは「属性萌え」か。
「なんでこのキャラなの?」
「俺は眼鏡属性萌えなんだよ!」
……そのキャラ*1について、バックグラウンドやディテールの説明なしに、これだけで「なぁ、そうなのね」と納得させてしまう――納得はしないが理解できてしまう何かを感じさせるではないか!
「なんでこんなウィルス対策ソフトに指定されているんですか? 選択の余地はないんですか?」
「そういうポリシーなんだよ!」
で納得できなくても、
「なんでこんなウィルス対策ソフトに指定されているんですか? 選択の余地はないんですか?」
「そういう属性なんだよ!」
ならどうか。
「会社の外に持っていくマシンにHDD暗号化ソフトを入れなさい、って言いますけどこんなもん入れてOS起動できなくなっりとか危なくないんですか?」
「それはポリシーだから従ってほしい」
ではなくて、
「会社の外に持っていくマシンにHDD暗号化ソフトを入れなさい、って言いますけどこんなもん入れてOS起動できなくなっりとか危なくないんですか?」
「それはそういう属性だから」
ならどうか。
冗談です。
*1 キャラ、キャラクターという言葉自体に属性が含まれてしまっているような気もするし、そもそも属性萌えという用語の使い方が間違っている気もひしひしとするのだけど、現役オタクじゃないのでご容赦を。……退役オタクって言葉はあるのだろうか?
2007-07-16
■ポケットモンスター
観てきた。子供とね。
ぶっちゃけサトシ達がいてもいなくても事件の顛末は変わらなかったんじゃないか? というぐらいストーリーに絡んでいなかったなぁ。
2007-07-17
■燃料を節約する29の方法、というタイトルだけど
えぇい! 29もあったら全部見られないっての! (なんせ英文だし)
と思ったけど、lifehacker が1つ抜き出して話をしている。
「スムースに運転できるだけで全然違う」ってとこか。
「車が増えること」「車を運転する機会が増えること」以上に、それによって「渋滞が起きること」が問題なのかな、と思い巡らした。
■空集合はφか0か
空集合の記号がφじゃなくて"斜線付きの0"で表記されていると、それが空集合だと認識するまでにタイムラグがあるなぁ。
■SFU の ls
普通のUNIXのシェルだと、ls は標準出力にリダイレクトされた時は、1行1ファイルになる。
Windowsにインストールして使うSFU(Service For Unix)の ls はそうなってない。
Helpを見て、-1 オプションを見つけた。
メモ。
2007-07-18
■タスクバー シャッフル
タスクバー上のアイコン――ってあれはなんと呼べばいいんだろう?――を入れ換えることができるソフト。
……らしい。
インストールなどはまだしていない。
via
追記
っていうかよく考えてみたら私は使わないなぁ。
参照。
■関数もまたオブジェクト
var a=2;
javascriptに関する質問です。 a=1; function hoge(){ var a=2; setTimeout(
setTimeout(function(){alert(a)},2000);
は、
function(){alert(2)}
という関数オブジェクトが渡されます。
(aは変数なので、呼ばれた時点で値が評価される)
が正しいとしたら、
<html>
<head>
<title>test</title>
<script type="text/javascript"><!--
var a=1;
setTimeout(function(){alert(a)},2000);
a++;
//--></script>
</head>
<body>only test</body></html>
とすると"2"と表示されることをどう説明する?
function(){alert(a)} が"無名の関数"のオブジェクトだというあたりが、理解を難しくしている原因だと思うけど……。
追記
私は 5. の回答者です。
setTimeout(hoge, 5000);
setTimeout(hoge, 1000);
setTimeout("alert(b)", 20000);
これでも実行結果同じなんですね。これは危険が危ない。
は当然で、1行目のhogeが"2回目に実行されるhoge"に、2行目のhogeが"1回目に実行されるhoge"になるというだけですから。(hugaも同じ)
"1行目のhoge"という表現を使っていないことにご注意を。
■Q.E.D. 27
「立証責任」を読んで理解した。
なぜこの漫画が好きなのか。面白いと思うのか。
ハードボイルドだからだ。
いやいや。ボギーみたいだとかそういうわけではなくて、
文芸用語としては、反道徳的・暴力的な内容を、批判を加えず、客観的で簡潔な描写で記述する手法・文体
ハードボイルド - Wikipedia
に近い意味として、あるいは、
の井上雅彦さん、朝松健さん、二階堂黎人さんの対談で朝松さんが言った
心理描写を完全に省いた、客観描写で綴っていくもの、それがハードボイルド。
の意味で。
とはいえ、燈馬君の心理描写が一切無かったというわけではないし、彼の代わりに可奈が一手に引き受けているのではあるが。
さておき。
それに思い至ればもう一つのミステリー漫画のお気に入り、NERVOUS BREAKDOWN もまた基本的に客観描写で、安堂君のオフなんてほとんど記憶にないなぁ、とか思ったりもする。
「全ての謎は解けた!」と主人公が叫ぶ時、読む側は――謎など一つも解っていなくても――彼に感情移入しているのかもしれない。
それを排した作品がお気に入りなのは、偶然ではないだろう。
きっと。
2007-07-19
■関数もまたオブジェクト 続き
javascriptに関する質問です。
http://q.hatena.ne.jp/1184576878
そうか。fugaを普通の関数の形式で書いたのが良くなかったか。
a=10;
function hoge(){
var a=1;
var huga = function(){alert(a)};
setTimeout(huga, 1000);
a++;
}
hoge();
これで"2"が表示される。
hogeの実行で作られた"無名の関数"のオブジェクト*1がfugaに代入される。
このオブジェクトはhogeの実行後も存在する。少なくともsetTimeoutによる遅延されて実行されるまでは。
fugaが参照している a もまたhogeの実行後も存在する。
この a は正確には hoge.a なわけだ。
そうか。
a=10;
function hoge(){
var a=1;
var huga = function(){alert(a)};
setTimeout(huga, 1000);
a++;
}
hoge1 = new hoge();
hoge2 = new hoge();
とすると、1回目のhogeと2回目のhogeの実行で、別々の a が確保されることがより判りやすくなるな(hoge1.a と hoge2.a だということがはっきり意識できる!)。
ちなみにこれだと"2"が2回出てくる。
■役に立つことだけが学習か
昨日、弾さんのこのページを見て、ケラケラ笑っていたのだけど。
ふと思う。その時間は無駄だったのか。
笑うこと、可笑しいと思うこと、その感性。そういうものは役に立たないことのか。
違うだろう。
なんてね。
*1 Javascriptはまともに使ったことが無いのでde factoな表現も公式な表現も知らない。
2007-07-20
■アート偏愛《フィリア》 異形コレクション
意外にも「音楽」が無いな、と思う(全く無いわけではない)。
強く印象に残っているものを掲載順に。
「ヴェネツィアの恋人」高野史緒
時間怪談。メビウスの帯。エンデの「鏡のなかの鏡」の一篇を彷彿とさせる(どこにしまっているんだっけ?)。
「デッサンが狂っている」飛鳥部勝則
すごい発想。
「オペラントの肖像」平山夢明
華氏451度(恥ずかしながら未読)、あるいはリベリオンの世界観。
短編ながらもしっかりと描き出される世界の状況。次第にあかされる主人公の心情。そして幕切れの一文。
緻密。
「輝風 戻る能はず」朝松健
オチが読めてしまう。
でも昔の雰囲気だー! と思い嬉しく読んだ。逆宇宙シリーズみたいな。
「新しい街」間瀬純子
一般公募からの採録とあって、さすが圧倒的。
しかも、これは何度も読めそうな――何度読んでも愉しめそうな予感。
■また出た画像ファイルの圧縮質問
画像ファイルを圧縮する方法を教えてください。ただし、機種は、WINDOWS XPで、お願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1184939756
おそらく一般的な「圧縮」ソフトを使ったけどさほどサイズが減らなかったための質問だと(勝手に)想像するのだけど、画像ファイルは大抵圧縮されているので一般的な圧縮ソフトではあまりファイルサイズは小さくならないので画像縮小などをキーワードに探すとよいです、という回答が集まるだろうか? と意地悪な注目をしていたりして。
2007-07-22
2007-07-23
■Advanced/W-ZERO3 [es]
Xscrawlは、円盤の傾きや動きを、抵抗値などで検出しているのではないかと思われる。指でなぞると、円盤が傾き、指の下は強く接触する。この接触状態の違いが、抵抗値などの変化として検出できるのではないだろうか。ATmega8Lには、A/Dコンバータが内蔵されており、こうした検出は不可能ではない。
しくみがわかったので、操作のコツもわかった。あまり軽くなぞってはダメなのだ。カーソル用のメンブレンスイッチ(クリック感がある)がオンにならない程度には、圧力をかけつつ、「なぞって」いく必要がある。設定(ユーティリティ)にある、感度の設定は、上記の圧力検出の閾値(しきいち)を設定するものだとおもわれる。
塩田紳二のPDAレポート
コンデンサ式じゃなくて(いわば)感圧式なのかー。
あ。試用できる実機が店頭に並んでいるのかしらん。
■待ち行列理論 の話
1時間あたり平均20人の客を通すことができるレジとレジ係があります。
そして1時間あたり平均20人の客がやってきます。
さて、レジに並んで待っている行列の長さの平均はどれくらいでしょうか?
とは、大学時代、待ち行列の授業の最初に出されたクイズである。
答えは「無限大」であった。
もう少し直感的に解りやすく言うなら、「(正の無限大に発散し)収束しない」だろう。括弧の中を意識から追い出してみるといい。
そんなわけでM/M/1の系の、平均待ち行列長の式自体は知っていた。
今回詳細を知りたくて――というか理解したくて本を買って読んだ。
本屋で探した時に、行列(Matrixの方)の棚の中に埋もれていたという悲しいことがあったけど別にどうでもいい。
このエントリの最初に書いた様な「掴み」的なものというか、まず最初に概念などを大雑把に説明して、それから詳細、みたいな構成の方がいいんじゃないか。
章立てなどもちょっと良くないかな。
少なくとも自習向きの本じゃなかったな、と残念に思うが、けれど「待ち行列」の本が見つからず選択の余地なしという状況だったのであきらめてもいる。
「実物を見る」ことにこだわらないで、Amazonで評価の高い本を買った方がよかったかしら。
とりあえず、必要だった部分の理解は得られたので読み進めるのは一休みする。
■ふたりごと自由帳
よい。
よい、としか形容できない。
面白い、とも違う。
ストーリーもない。
強烈なキャラクターもない。
圧倒的な世界観もない。
でも、よい。
机の上に花が一輪、で始まる四コマ。胸が痛くなった。
「ガクランコンビナート」が収録されることはないのでしょうか……。
2007-07-24
■タスクリストの情報
Windowsタスクマネージャーのプロセスの部分の一覧を保存したいのですが、検索の仕方がよくないのかググってもヒットしません(ŎдŎ) ログの取り方、というのでしょうか?保存の仕方を教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1185238741
コメント
tasklist コマンド。
えぇーっ!?
知らなかった……。
■メールアドレスにマッチする正規表現の話
って、この時点で「メールアドレス」が本当は何を指すのか曖昧かも。
http://www.tokix.net/txt/000228.html
http://www.tt.rim.or.jp/~canada/comp/cgi/tech/mailaddrmatch/
http://www.din.or.jp/~ohzaki/perl.htm#Mail
むむむむ。
hoge@example.com.
の最後のピリオドは、addr-spec としては正しくないのだなー、と改めて知りました。
終わり。
■"ファイルを指定して実行"の妙技
ふむふむ。
"." で C:\Documents and Settings\(User Name) になる。
なので、そこに頻繁にアクセスするフォルダへのショートカットを、簡単な名前で作っておく。
その簡単な名前を入力するだけでそこにアクセスできるようになる。
で、Windows+R 数文字入力 Enter の流れで ok。とそういうことか。
2007-07-25
■素案
草案と打とうとしてタイプミスで"そあん"を変換してしまったら、素案とでた。
へぇ、こんな言葉があるのか、と思っていたら、今日仕事で届いたメールにも。
……こう打とうとしたのか、それとも打ち間違いだろうか、などと思ったり。
■東大式絶対情報学
いや面白かった。途中でバーンと視界が開けて読む速度を変えたのであっというまに読み終わった。
速読で『現代用語の基礎知識』『IMIDAS』『知恵蔵』などを通読する、というのである。
p68
『知恵蔵』を通読する、という概念を持っていない人があります。
新しい概念を平易な言葉で紹介する。
項目ごとに別な分野を説明するから、あるところで意味を取れないとしてもその後に影響することはない。
確かに、速読の練習や習熟度を測るにはもってこいの本だろう。
そのちょっと前。
p60
実は、私が速読を習ったのは両親からでした。両親とも大正生まれで旧制時代の教育を受けています。(略)速読などの、基本的な知的反射神経のコツ、つまり「ノウハウ」は,旧制高等学校の学寮などで伝承されていたそうです。それだ一九四五年以後急速に途絶えたというのが実情のようです。
とある。
膨大な情報を選り分け、全体像を把握するには一冊の本に時間をかけていては駄目だ、というわけ。
なるほど、と思い速読みに切り替えた。私の場合速読というほどのものではなくて、黙読の数倍程度なので「速読み」である。
「ザ・ファシリテーター」(エントリ末に挙げる)でいうところの思考のフレームワークの活用の話。
記憶問題を出された時、正答が7±2の範囲にほとんどの人が収まるという統計があるそうだ。
したがってコミュニケーションにおいても相手のワーキングメモリ――つまりは海馬でまかなえる記憶容量だろう――を配慮するならばプレゼンテーションの1枚にいれる文の数、図表の数などなどもまた、7±2の範囲に収めるべきである。
プレゼンテーションに対する対応。まず褒め――けれど嘘は禁物――次に相手にとって役に立つ建設的な対案を発言する。
オリジナリティの三つの<根>。
などなど。
目から鱗が落ちる、というようなものではないが概ね納得できる内容を軽妙に読ませてくれる。
ただ、破壊的マインド・コントロールに関する
この書の本分ではないので、ま、いいか。
今なら、原稿の分量を調節して新書の形態で出版していたのではないか。
ハードカバーというだけでちょっと身構えてしまうんじゃないかと余計な心配をしたりして。
参考
いくつかの点で、これらと共通するものがあったように思う。
2007-07-26
■スプライトシュピーゲル II Seven Angels Coming
一体どれほどぶりだろうか。
一冊の本を、休憩もなく、ただ読みふけるなどというのは。
ただ消費されるだけではなく、没頭したいと思わせてくれる本に出会ったのは。
今手許にある他の3冊のシュピーゲル《物語》とともに、これから先幾度となく読み返すであろうことを想像しつつ。
今、最後の頁を捲り終える。
2007-07-27
2007-07-29
■闇電話
強く印象に残る作品は無かったなぁ。題材が難しいのかも。
『燃える電話』草上仁
タイトルで、紹介文で、怪奇大作戦を思い出してしまうのは悲しい性か。
違う意味だ、と解った瞬間が心地よかった。
逆に怪奇大作戦を知らない人の方が素直に捉えるだろう。
『十一台の携帯電話』
謎が謎として提示されないタイプのミステリ。
『ジャンヌからの電話』間瀬純子
一番のお気に入り。
多分、映画のエンゼル・ハート [DVD](ウィリアム・ヒョーツバーグ)あたりからの脳内補完あり。
追記
『よくある出来事』浅暮三分
これもよかった。美しい。「よくある」話が最後に、ゆっくりと、別の「尋常ならざる」話に変貌する様がよい。
2007-07-30
■電脳コイル 「大地、発毛ス」
親の方が受けていました。はい。
しかし、このストーリー(髭状のイリーガルがワーム様に人から人へ感染していく & 文明を築いていく)、
の一篇「ルクンドローム」を思い出す。「身体の資源」を元に体の中(?)で繁栄する何か。最後の「資源の枯渇した惑星」からの脱出など。
もちろんそれ以外にも、藤子・F・不二雄の短編にも似た話を見られるし、小説にだってちらほらある。
でも、不思議と真っ先に思い出したのは「ルクンドローム」だった。
文庫本↓
もあるけど、たとえ古本の入手になろうとも前の版の方がオススメ。
■パンドラの箱……
宮沢賢治を引き合いに出すと言うことは、著作権延長論の根拠の一つを、三田氏自らが否定してしまっている様に私には受け取れる。
memorandum - パンドラの箱を開けてしまった三田氏
内容は同意できるけど、タイトルは変な感じ。
パンドラの箱というからには災い(この場合は「都合が悪いこと」ぐらいの意か)が次から次へと出てくるぐらいじゃないといけないと思うのだけど、ここでは"1つの例"でしかないような。
2007-07-31
■言語のバージョン
ソフトウェアのサイクルが同期していくことに結局はなるのでないだろうか。
ソフトウェアパッケージのメジャーバージョンアップの時に、言語のバージョンも上げなければならない、ということ。
実装上の問題としては、J2SE 1.4.2には並列処理に対応したクラスが納められているjava.util.concurrentが用意されていない点が懸念されるところだ。
ここの意味(意図、か?)が判りませんでした。
■蘇る封印映像
これを読んでいるところをカミさんが見たら「あなたが好きそうな本」と評するだろうことは火を見るよりも明らかである。
それは兎も角。
本屋で見たときに、別に『封印』されていたわけじゃない作品もあるのに(契約が切れただけとか)と思った。
が、アイアンキングの項を読んだときに膝を打った。
結局のところ「再放送がされない」というマニア間の喧伝は、ただのデマなのである。
実際は『封印』されたわけでなくとも、観ることが事実上困難であるならば、それは観たい側にとっては『封印』されているのと変わりない。
この本は題名に反して『真に封印』された作品を扱っているわけじゃない。『事実上の封印』となっている作品、またかつてそうであった作品に、光をあてる本なのだろう。