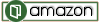2007-06-01
■Google Reader が変わったらしい
Firefoxで、Google ReaderのタブをCtrl+Wで閉じることができなくなった……。
不便。
■昨日までは同じ状況だったのに
今日は大丈夫……。
うーむ。
Windows版のFirefoxで、コンテキストメニュー(右クリックで出るメニュー)の内容が収まりきらない場合、▲や▼が出てスクロール出来るようになりますが、一度これが出てしまうと、その後コンテキストメニューが収まりきる量の場合でも ▲や▼が出たままになり、Firefoxを再起動するまで元に戻りません。
http://q.hatena.ne.jp/1180673180
多分これ↓だろう。
修正されてないなぁ。
2007-06-02
2007-06-03
■Zoho Notebook
なかなかすごい。
テキストは付箋紙のイメージ。
画像の貼り付けもできる。ファイルアップロードとURL指定。
HTML埋め込みができる。
URLを指定すると、そのページが埋め込める。
直線・フリーハンド曲線・基本図形を書ける。
2007-06-04
■Foleo
遅まきながら。
- 1.1kg は重すぎる
- 日本語対応ってだけじゃなくて親指シフトでで入力したいという欲求があるので当面絶望的か
- しかし、ポインティングデバイスにあるこのボタンを見るともしかして……?
- なんてね。タッチパネルになっていないってことは、このキーを(別の機能に割り当てて)殺すとひどい目に遭いそうだ。
There is no initial customer for (ultramobile PCs).
The best idea Jeff Hawkins ever had | Newsmakers | CNET News.com
この'initial customer'はどういう意味かしら?
いわゆる人柱?
2007-06-05
■ルービックキューブは26手以内で解ける
25手で解けない初期状態があるのかどうか触れられてないが、証明できなかったのか? という疑問あり。
2×2のルービックキューブを入手しているので、
の実習を実際に手を動かしてやってみようかなぁ、と思っていた。
……最近新しいのを本屋で見かけたな。
これか。
2007-06-06
■知識データが定型だとなにがよくないのか
まだ浅い。続きに期待。
例えば知識やノウハウが命題の形に表現できると考えます。この命題の形にブレークダウンされた知識のデータベースに対してパターマッチングを行って推論をするのが Prolog ですが、
は掴みとしてはいいな。
2007-06-07
■エレガントな回答はないだろうか
と思ってはいるのだけど。
どうプログラムを書けば良いか分からなくなったので質問させてください.
不等間隔のデータの中から,等間隔な部分を抜き出す方法?
例えば,「0 1 3 4 8 9 10 12 14 15」という不等間隔のデータから,等間隔な部分を抜き出すと,「0 4 8 12」,「1 8 15」,「3 9 15」,「4 9 14」,「8 9 10」,「8 12 14」,「9 12 15」がありますが,これをCとかFortranとかで書くとどう書けば良いのでしょう?具体的なソースを教えて頂けたらと思います.また,決まったやり方があるのでしたら教えて下さい.
http://q.hatena.ne.jp/1181059504
■PMBOKってAmazonで買えたんだ!!
ISBNの国番号が日本じゃない。
つまり和書じゃなくて洋書の扱いなんだな。
面倒な申し込みなしでさくっと買えるんだぁ。
(追記)
正確には「PMBOKガイド」です。
see also
■Frieve Editor 新しいエディター
ソフトウェアの自薦文に「新しい○○です」とあっても意外と凡庸だったりする。
「新しい!」というものに出会えるのはまれだ。
でも、これは久々に「新しい!」と思えた。
まだ荒削りで、こなれていないな、と感じる点もある。
ソフトウェアを立ち上げて最初どうしたらいいか判らない、というのもあるが、でもこれは「新しい」ことの裏返しかもしれない。
主な機能にある動画を見ていて、ほー、とうなった。
2007年に入ってバージョンアップがないけど、もっともっと成長して欲しい。
この先を見てみたい。
久々に、そんな風に思えるソフトウェアだった。
追記 (2008/01/07)
2007年後半に怒濤のアップデートがあったのね。
すごく見栄えがするようになった。それが使いやすさ、解りやすさに繋がっているところが心地よい。
2007-06-08
■やっぱりポリシーはコピペされるのだ(でも、なんで営利目的で警察サイトにリンクするのは駄目なの?)
リンク元ホームページの内容が法令や公序良俗に反する場合等には、リンクの削除をお願いすることがあります。
このサイトのご利用について − 山形県ホームページ
うわ。これは最悪だ。
警察のサイトが"法令に反しているホームページ"に対して"リンクの削除をお願いする"だけじゃ駄目だろう。
ここだけ読むと"法令に反しているホームページがあっても、自分のところにリンクされてなければいい"と意思表示しているみたいだよ、と。
さて本題。
茨城県警察ホームページへのリンクは、営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り原則として自由です。
茨城県警察ホームページの著作権及びリンクについて
リンクにつきましては、営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り、基本的に自由ですが、その対象を愛知県警察ホームページの最初のページとしてください。
愛知県警察|ホームページとリンクについて
当サイトへのリンクについては、営利を目的としたもの、公序良俗に反するもの及び岩手県警察の信用を害するおそれがあるものはお断りします。
岩手県警察ホームページのご利用について
リンクにつきましては、営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り基本的に自由ですが、リンクを希望される方は、ホームページ上のご意見ご要望メールでご連絡ください。
栃木県警察 TOCHIGI POLICE
ンクにつきましては、営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り基本的に自由ですが、リンクを希望される方は、ホームページ上のご意見ご要望メールでご連絡ください。
栃木県警察 TOCHIGI POLICE
営利を目的とせず、公序良俗に反しない限り原則として自由です。
岡山県警察ホームページ サイトポリシー
なお、営利目的や公序良俗に反する場合、山口県警察の信用を害する虞がある場合には、リンクをお断りすることがあります。
警務警察
なんで"営利目的"が駄目なの?
というか、"営利目的"なのは"リンクしているサイト"なのか"リンク"なのか。普通に考えれば前者だ。
でもこれらに書かれている文だけだと、"リンク"が"営利目的"なように読めてしまう。
謎。
2007-06-09
■石川智晶さん アンインストール
を見て、iTMSで売っている 石川智晶さんの曲を試聴しているところへ子どもがやってきて、一言。
「これ知ってる。ガンダムだ」
って、言われて、あぁ See-Saw のボーカルの人か! と気づかされたり。
……うちの子って一体。
■環境問題はなぜウソがまかり通るのか
私にとっては「何を今さら」感がある話題ではあるけれど、とりあえず購入。
p190
断火材の排斥では幼児とお年寄りが犠牲になり、DDTの禁止では南方の国の人がマラリアで苦しんで死んでいった。幼児、お年寄り、そして南国の子供達――。どの人も力が弱く、声も小さい。ダイオキシン報道によってセベソで中絶された幼い命の声はゼロである。
あと気になる小説(だと思う)。
2007-06-11
■スケーラブル
最近意識しているキーワード「スケーラビリティ」。スケーラビリティについて学びたい人が絶対に読むべき「この一冊」という本は存在するだろうか。もし存在するなら、それは何だろう。
結城浩のはてな日記
実は未読なんですが。
1章 はじめに
2章 ウェブアプリケーションのアーキテクチャ
3章 開発環境
4章 国際化とローカライゼーションとUnicode
5章 データの一貫性とセキュリティ
6章 電子メール
7章 リモートサービス
8章 ボトルネック
9章 ウェブアプリケーションのスケーリング
10章 統計、監視、報告
11章 API
という章立て。
目次を見て、スケーリングが後ろの方にあるという章立てに、ははぁなるほど、と思いました。
リソースが不足してるからマシンを足そう、というのがスケーリングではないという意志の現れ。
サプライヤが例えばサーバの広告に付けるような「ハードウェアの冗長性」なんていう売り文句は、スケーリングではないということ。
3章、4章が"開発環境","国際化とローカライゼーションとUnicode"とあってアプリケーション開発の領域の話になっています(5章もそうですが)。
ハードウェアを増強すれば、それだけでスケーリングになるかと言えばそんなことはない。
ハードウェアを増強することがスケーリングにつながるようなアプリケーションの構造。
帯域やリソースが不足した時に"何がどのように不足なのか?"ということを明らかに出来る環境。
リソースを増強する必要が出た時に、"何をどの様に増強すればどのようになるのか?"があらかじめ検討されているという状態。
そういう状態に組織・環境・アプリケーションを保つということ。
それがスケーラビリティなのかと、目次を眺めてみた瞬間に自分の中の概念がひっくり返ったので、購入。
でも読んでないんです。orz
追記
結城さんの言っている「スケーラビリティ」はまた別の(というか広い)話なんでしょうね。
「ある量」が100倍になった時に全体はどう変化するのか? それが1万倍になったら? 100万倍になったら?
量的変化がどういう質的変化をおこすのか? という意味かと思ったのですが。
WebやITシステムでは、「ある量」はページビューや転送量やユーザ数やトランザクション数ということになりますか。
2007/6/13 トラックバックした
■徒然なるままに「ひっそり書いてるんだから」考
人数が少ないうちにはうまいバランスがあり得るが、サイトのアクセス数が多くなって(あるいはそのサービス全体のユーザ数が多くなって)くると、母数が増えてくるために「うざい人」の人数は多くなるだろう(割合が変わらなくても)。
www.textfile.org - 「匿名性」と「ほめてほしい人だけ見て」の同居は難しいかも
読んでいて、検索における再現率と適合率のトレードオフに似ているなぁ、とか思った。
再現率は「検索クエリに適合するもののうち、実際に検索されたものの割合。適合率は、「実際に検索されたもののうち、検索クエリに適合するものの割合」。
「検索クエリに適合するもの」がアバウトで、検索システムの評価の難しいところ。
「○○は××だ」で検索した時に、「○○は××だというのは真っ赤な嘘」という趣旨の文書が引っかかった時にこれを「適合する」と言えるだろうか?
そんなの引っかかって当たり前だろ、と思う人はコンピュータシステム寄りの、論理的な思考の人なんだろうと思う。
「プリズナーNo.6 ネタバレ」で検索して「プリズナーNo.6 のネタバレなんて書こうとしても書けるものじゃない」っていうのが引っかかってきたり、実際プリズナーNo.6 のネタバレを書いたページなんて上位に出てこない。
それで「Google 使えねぇ」とか「検索語が悪かったか」と思う人こそあれ、「そうか無いのか」と素直に思う人はそうはいない様な気がする。
ところで、再現率と適合率はある検索クエリに対して出てくる数字で、検索クエリ全体に対してでてくるわけじゃない。だいたい検索クエリ「全体」って一体?何 という話だ。
だから、検索システムの評価は複数の検索クエリに対する平均の値を見ることになるのが現実。
これを先のモデルに当てはめようとするとどうなるだろう?
例えばある誰かと自分の感性が似ている――つまりは話が合うと感じることがある。
そうはいっても一から十までそっくり同じとはいかない*1。ある領域では自分は興味があるけど相手は全然興味がない、あるいはその反対ということもある。
さらにはある領域では真っ向意見が対立することもあるだろう。
「少数でもいい」から「とにかく自分に近い人」の集団を欲求するのは、検索で言えば「再現率は低くても良いから適合率を高く」ということか。
じゃあ逆は、「ある面でのみ自分に近い人」でいいから「多数の人」の集団を欲求するのは、「適合率は低くてもいいから再現率を高く」ということになるなぁ。
この場合「検索クエリ」は「自分はこう思ってますよ」という表明にあたるのか。
後者に属する人は blog とトラックバックと RSS で構成される粗い網を好んで使う。批判されたり否定されることも厭わない。
適合率が低いことを承知でシステムを使う。
同じblogであれやこれや、いろんな話題を書くとも予想される。
自分と「部分が似ている人」を的にしているから。
前者は招待とアクセス制限を好む。あるいは、メーリングリストで満足するかも。
適合率が低いことは我慢できない。
自分の中のごく一面だけを表にすると予想できる。
「私は○○が好き!」という話題だけを書いていれば、同じ様な人の集まりが形成される(はずだと思いこむ)。
「私は○○と□□と△△が好き」と書くのは、「○○と□□と△△が好きな人」が集まって欲しいからだろう。
「○○と□□は好きだが△△が大嫌いな人」は(検索のメタファでいう)ノイズになる。
あ、そっか。
Mixi なら、○○と□□と△△が別なコミュニティとして存在しているので、「○○が好きな人」「□□が好きな人」「△△が好きな人」と個別に話ができるんだ。
「○○と□□は好きだが△△が大嫌いな人」とは、○○のコミュニティと□□のコミュニティとで出会うかもしれないけど、そこでは△△の話題はまぁでないだろう。
Mixi の中では「○○と□□と△△が好きな人」とだけ相手をしているという錯覚を得ることができるんじゃないだろうか。
その錯覚を抱いたまま公開された blog の世界に来たときに、錯覚の方を信じたい人がネガティブな意見に非常に強い反応をしてしまうと。
(検索システムへのメタファはどうなった?)
(いや、書いている途中でどうでもよくなったのかも……)
■コン・ゲーム
オーシャンズ11、12、13シリーズや60セカンズ のように、泥棒や犯罪(殺人は除く)を鮮やかにやってのけるアメリカ映画を探しています。
http://q.hatena.ne.jp/1181477252
「鮮やかにやってのける」のあたりが微妙だけど、
に一票。
「微妙」と書いたのは、"鮮やかにやってのけ"たのが果たして作中の人物なのか、映画の監督・脚本なのかというあたり。
してやったり、コンゲーム小説、映画は? (1/2) - その他(エンターテインメント) - 教えて!goo
コン・ゲームの面白い映画を教えてください - その他(映画) - 教えて!goo
Fliers 映画用語辞典
あたりかね……。
■偽装請負
未読(斜め読み状態)だけど、読み終わったときに何も書かないだろうと予測できるので、今書いておく。
p16-17
偽装請負と呼ばれる雇用システムをひとことで言い表すなら、「必要がなくなれば、いつでも使い捨てることができる労働力」のことだ。企業にとって、これほど都合のよい「雇い方」はない。
(略)
偽装請負の実態は、労働者派遣そのものだ。しかし、請負契約を装っているので、労働者派遣法の制約は全て無視する。派遣労働者の場合、一定の年限が来れば、直接雇用の申し込み義務が発生するが、請負と偽っているので、申し込まない。つまり、同じ顔ぶれの労働者を何年も都合よく使うことになる。
Amazonのランキングもそこそこ。
本屋に行けば平積みもされている。
でも、今ひとつ話題になっていないような気が。
1章、2章でキヤノン、松下の事例。
3章で「日本最大の請負会社グループだった(p35)」クリスタルの経路。
4章で現場での危険性――自己が起きたときに企業がじこそのものを隠したりする傾向がある――ことを書いている。
5章は政府や企業の責任を考える、とある(この章は本当に未読)。
サブタイトルにも付いている通り「格差社会」というキィワードがしばしば出てくるが、この本が真に価値があると主張したいのなら、時事的なキィワードを入れるべきではなかったと思う。
*1 そっくり同じなら同じで、同族嫌悪に陥るような気がする。まぁこれは余談。
2007-06-12
■「打ち合わせします」言うなキャンペーン
タイトルの半分は冗談です。
人を集めるのに「○○の打ち合わせします」なんてメールするようではいけない。
他に解釈のしようがないほどに定例化しているのなら問題ないけど、そういう時はメールに「○○の打ち合わせします」なんていう文が並ぶことはないだろう。
○○について先行して決まっている何かがあって、その確認や意識合わせをするのか。
それとも○○について何か意志決定をする必要があって集まるのか。
その意志決定は招聘した人がやるのであって、そのための情報を収集の場なのか。それとも総意としての意志決定をする場なのか。
席に着いた時点で、全員が、どこに向かうのか判っていないと時間を無駄にするだけ。
その時になって初めて資料が配られた日には気が遠くなってしまう。
1. Set a firm agenda.
How to Run a Meeting Like Google
Mayer requests a meeting agenda ahead of time that outlines what the participants want to discuss and the best way of using the allotted time. Agendas need to have flexibility, of course, but Mayer finds that agendas act as tools that force individuals to think about what they want to accomplish in meetings.
「議題」というのはその打ち合わせで「話をする内容」ではなくて、その打ち合わせの「完了を判断する基準」なのだと、そう思う。
それが明らかにされないままに始まる打ち合わせは、最悪の時間になることうけあいである。
2007-06-13
■ルートの無限入れ子クイズ
ルートの無限入れ子クイズ
http://www.hyuki.com/d/200706.html#i20070613102030
\(2=\sqrt{2}\times\sqrt{2}\) だから……。
追記
ミルカさん「先生、この数式の値が《ある正の値に収束する》ことは仮定してもいいんですか?」
の台詞の意図が判ったので答えは簡単に分かるのだけど(収束することを仮定してよいなら2乗してもいいでしょ?)、漸化式から行こうとするとピンとこない。
2007-06-14
■Windows標準のダイアログボックスは Ctrl+C でメッセージをクリップボードにコピーできる!!
Apparently since Windows 2000, you've been able to copy the entire error message to your clipboard by hitting the universal copy shortcut, Ctrl-C (who knew?!).
Windows Tip: Copy error messages text to the clipboard - Lifehacker
本当ですか?
ダイアログボックス*1の文が Ctrl+C でコピーできるって??
さっそく確認。
Delphi で……
MessageBox(self.Handle, Pchar('マジですか?'),PChar('えええ'), 0)
というコードでWindowsのダイアログを開く。
--------------------------- えええ --------------------------- マジですか? --------------------------- OK ---------------------------
うわ、ホントだ。
じゃあ、
MessageBox(self.Handle, Pchar('マジですか?'),PChar('えええ'), MB_OKCANCEL)
とすると……?
--------------------------- えええ --------------------------- マジですか? --------------------------- OK キャンセル ---------------------------
おぉぉぉぉぉ!!
*1 タイトルで"Windows標準の"としたのは、WindowsAPIのMessageBoxを使ったもの限定だから。
2007-06-16
■驚異の数 π
数学セミナーの7月号が届きました。
特集は"数学ライブ2007"です。ぱらぱらめくってみただけで面白そう。
さしあたって、目に飛び込んできた"Sound of Science 驚異の数π"という記事を読んでみました(この"Sound of Science"というセンスがいいです)。
すごく調子のよい文です。
講演の原稿から採られたものなのでしょうか。
面白いです。
実際に聴いてみたくなります。
結びは、πが万能数――任意の有限数列を含む数――ではないかという可能性がでてきた、というものです。
びっくりです。
いえいえ。上記の話そのものにびっくりしたわけではありません。
ほんの15分ほど前。
"完全にランダム"な無限の長さの文字列の中には、どのような文章も入っている(もちろん文字種を考える必要はありますが)、てなことを考えていました。
俗に、「無限に生きることができる猿にタイプライターを渡して出鱈目にキーを叩せれば、いつかは、たまたま、シェイクスピアの作品ができる」と言われている話です。
それは厳密ではないなぁ。
「出鱈目」という表現ではよくない。
「完全に出鱈目」としてやる必要があるんだなぁ。
などと考えていたのです。
閑話休題。
記事の、最後の脚注にこんなことが書いてありました。
万能数について次のことが知られています.有理数は万能数ではない.超越数で万能数であるものが存在する.超越数で万能数でないものが存在する.そして,すべての代数的無理数は万能数だろうと予想されています.
最後の文に目を牽かれました。
なんとなく、超越数の方が万能数っぽくて、代数的無理数の方が万能数っぽくないような、そんな感じがしませんか?
数の世界は不思議なことだらけです。
講演の結びのスライド。
人はなぜ数を追い求めるのか
永遠、無限、神秘
とありました。
きれいです。
追記 2010/03/29
このあと、Webで検索などしてみましたが"万能数"という表現は一般的ではないようで、もしかすると、この時のスライドのために分かりやすく書き表しただけだったのではないか? とも思うようになりました。
数学的にポピュラーな概念(表現)は、以下の"正規数"なのではないでしょうか?(詳しい人のツッコミ求む)
■オンラインデータベース
……正確にはオンラインデータベースフロントエンド?
MS ACCESS みたいな。
"こいつぁスゲェや!"という感じのびっくりなサービスだけど、さてどんなデータを入れるかと考えると悩ましい。
ASINを使ってAmazonと連携〜、とかそういうスクリプトがあったら面白そうだ。
2007-06-17
■画像を小さくするのです
解凍は問題ありませんが、
圧縮がほとんど重さがかわっていないのです。
http://q.hatena.ne.jp/1182057707
……「解凍は問題ありません」が謎だなぁ。
兎も角。
JPEG圧縮された画像*1は確かにファイルサイズはさほど小さくならない。
小さくするべきなのは――言葉を変えると、小さくできるのは――画像のサイズ(画素数)なのだ。
という回答がつかない*2のはなぜ?
■時間がないので地の文がありません
誰かの名言で「文章は長文にするのは簡単だ。時間をかけて短くせよ」というのがあったような気がします。
誰が言った言葉か、そして正しい言葉を教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1182044129
それで、新聞のコラムで読んだと前置きした上で覚えている限りの文章を打ち込み、《時間がなかったので長文になりました》と結んだ。
(略)
――《パスカルだね》
(略)
きっと書き込みミスだと判断して、それを報せるメールを発信したのだ。まもなくそれに対する返信が届いた。
――パスカルはフランスの哲学・物理学者。彼が誰かへ宛てた手紙にそう記していると何かで読んだ覚えがある。「時間がなかったので長文になりました」とね。短い言葉で用件を伝えるには、それなりに時間が必要だからね。
2007-06-18
■魔地図 読了
《異形コレクション》の中でも、これは出色の出来かも。
印象に残る作品が多かった。
テーマがよかったのかな。
「大帝国の大いなる地図」(ダーヴィデ・マーナ)は、情報と物体のどちらが主か? という現代的なテーマを含有しているようにも読める。(prima materia - diary : データと現実のどちらが本当? あたりを参照)
「独白するユニバーサル横メルカトル」(平山夢明)。タイトルの通り、"地図の独白"という様式そのものがすでに独特だけど、地図の持つ"怪しい魔力"がストレートに書いてある。
「迷界図」(石神茉莉)はじわじわ怖くなるという面と同時に、最後にドーンと大きな衝撃で恐怖を与えるという面の両方を持っている希有な作品。
アンファン・テリブルと見ることもできる。
ホラー映画マニアの友人でさえ舌を巻く怖さを見せた18禁ゲーム*1「狂った果実」をふと思い出した。
「残された地図」(菊池秀行)は侵略もの。そして消失もの。
恐怖を感じるのは"残されてしまった"側だというのは、『ボディ・スナッチャー/恐怖の街 [DVD]*2』や『SF/ボディ・スナッチャー [DVD]』を見ると感じるところだけど、ここではもう一つひねってある。
「ひろがる」(坂本一馬)。うまい。圧倒的にうまい。
スタンダードなのに新鮮。
名人芸の域。
「わたしのまちのかわいいねこすぽっと」(多岐亡羊)。あえてジャンル分けするならアレだけど、この枚数でアレをやるか。
とはいえアレの中にはもっと枚数が少ない方が面白いだろうなぁと思ってしまったものも多いので、この作品が評価されたのはよいことなのだろう。
あぁ、代名詞ばかり。
2007-06-19
■私のマシンだけSubversionが重かったワケ
httpを使うレポジトリなのに、Google Desktop の除外URLに指定していなかったから。
なのだろうか?
■プロジェクトマネジメント・プロフェッショナルとPMP PMBOKとPMBOKガイド
まずは書名になっているプロジェクトマネジメント・プロフェッショナルの話。
ここを読もうと思った人ならば説明するまでもないかもしれないが、"プログラムプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル"はプロジェクトマネージャーの認定プログラムで、普通は頭文字でPMPと呼ばれている。
ここで書名をPMPとしなかったのは歴とした理由がある。
p13
開発研究職であっても営業職であっても、あるいは企業経営者であっても「プロジェクトの真の成功のために何をすべきか」という貢献に焦点をあわせ、その責任を果たす人を「プログラムプロジェクトマネジメント・プロフェッショナル」と呼ぶ。PMIの認定資格であるPMP(Project Management Professional)は、その必要条件の基準を提供するが、PMPの資格保持者がすべてプログラムプロジェクトマネジメント・プロフェッショナルとは言えない。
その意味で区別して使っている。
つまり、プロジェクトマネージャーではない人であっても、この本の対象読者として想定されている。
あるいは、むしろ、普段PMBOKに縁がない人ほど読むべきなのかもしれない。
さて、今、何気なくPMBOKと書いたけれども、この言葉もこの本での捉え方は通例のそれとちょっと違うかもしれない。
p129
PMBOKとPMBOKガイドは違う。PMBOKというのは、プロジェクトマネジメントの知識全体のことを指しており、この中にはいわゆる「暗黙知」のような概念も含まれる。PMBOKガイドは、その一部を「形式知」化したものである。
もうこの部分だけで、目から鱗が落ちる思いだった。
普段PMBOKと言う時は、PMBOKガイドのことを暗に指していたのではなかったか。PMBOKガイドをぺらぺらと捲った時に感じた「まさにガイドライン」という感覚・イメージは、ごく表面的な捉え方でしかなかった、と。
決断と判断。
マネジメントとコントロール。
リスクと前提条件。
論理と知覚。
スケジュールと時間。
問題とリスク。
様々な概念が、渦を巻き、"自分の中"へしまいこまれた。
さぁ、次は、"自分の行動"を通して、それらを外へ外へと"出す"番だ。
2007-06-20
■複数選択/単一選択のジレンマと、Gmail に見るUIの考察
あるリストボックス。
複数選択して、そして何かの処理をさせる機能が必要。(機能A)
だから、リストボックスを複数選択なスタイルにする必要がある。
そしてもう一つ。
一つだけ選択して、そして何かの処理をさせる機能も必要。それは一度に一つだけしか対象にしたくない。(機能B)
さてどういうUIにしよう?
リストボックスはモードを持たない
つまりリストボックスは複数選択のまま。
一つだけ選択されている状態の時だけ、機能Bの(ボタンなどの)UIが有効になる。
複数選択されている状態の時だけ、機能AのUIが有効になる。
欠点
初期状態で機能Aや機能Bが無効になっている。
それを有効にするのに選択しなければならないことに気づけるか。
リストボックスはモードを持たない の2
機能A,機能Bのボタンはいつも有効。
ボタンを押した時に、複数選択か単一選択かを判断して、条件を満たさないときは警告を出し、選択を促す。
取り合えずボタンを押してみることができる。
欠点
許されない(=してほしくない)選択条件の時に警告が出るのは、不必要にビックリさせるかもしれない。
リストボックスがモードを持つ
複数選択と単一選択のモードを切り替えるUIがある。
ラジオボタンかチェックボックスか、フリップ系のUI。
どちらの状態にあるかで、機能Aと機能BのUIの表示/非表示、あるいは、有効/無効が切り替わる。
欠点
結局、機能Aを使うには? 機能Bを使うには? という条件がパッと見て判らないのは変わらない。
今は昔の話
Dos以前の時代は、実はこのジレンマは、無かったと言ってもいい。
対象とする項目を選択してから、機能を選択するUIは主流ではなかった*1。
機能を選択してから、対象とする項目を選択する方が普通だった(と思う)。
Windowsの時代
リストボックスに単一選択のモードと、複数選択のモードがある。
正確には複数選択のモードにもう2種類あって、選択→Shiftを押しながら別の項目を選択でその間の全項目を選択、Ctrl+選択で一つずつピックアップ、Shift+キー押下で連続選択というのが一つのモード。
もう一つはCtrlもShiftも関係なく、クリックで選択/解除が切り替わる。
結局のところ、この"Windows標準"のコンポーネントが主流になる運命にあった。
Windwos API や Visual Basicで扱える"標準"の操作感が――善し悪しとは別の次元で――必要とされた。
(Macintosh も調べるべきなんだけどなぁ……と思いつつパス)
Gmail
項目をクリックすると、メールの詳細(つまりは本文)の表示になる。
一覧の各項目の左に、一つ一つチェックボックスがある。
直感的な操作として、クリックが選択/解除の切り替えとなる。
さて、あるチェックボックスを選択してみる。別の項目のチェックボックスをShiftキーを押しながらクリックしてみよう。
はい。
Windows標準の複数選択モードと同じく、二つの項目間の全ての項目が選択状態になる。(知ってました?)
解除も同じようにできる。
選択になるのか解除になるのか? Shiftキーを押しながらクリックする時に注意して見てみると、ちょっと複雑そうな規則が見て取れる。
けれど、実に直感的な感じ。(追記:Windowsの機能の方が法則は単純だが"そうなってほしかったんじゃないのに〜"という感じ。Gmailの方が法則は複雑だが"そうなってほしかった"様に選択できるなぁ、という印象を持った。)
実は、スターも同じ様に複数選択できたりして。
あと一歩
Gmailは項目をクリックすると即座に本文表示になった。
これを見直せばいい。
普通に項目の方をクリックした時に、選択された様に見えればいいのだ。
機能の方は、右クリックした時にコンテキストメニューがでる様なインタフェースでよいか。
そしてあと一歩。
選択: すべて選択, 選択を解除, 既読, 未読, スターあり, スターなし
というリンク(ラベル)が一覧の上にある。
"既読, 未読, スターあり, スターなし"のラベルは、アプリケーションに依るものなので、ここはアプリケーションごとに変更すればいいだろう。
さらにその上に、選択した項目に対する操作が並んでいる。
これはいいな。
複数選択してからの機能は、こんな風に一箇所に固まっていればいいんだな。
■リスクとは"危険性"や"脅威"のことではなくて"未来の不確定性"のことだ
アンチウイルスソフトって不要ですよね?
http://q.hatena.ne.jp/1182168711
を受けて。
"リスク"は"危険性"でも"脅威"でもない。
"未来の予測のしにくさ"、"未来の不確定性"のことである。
PMBOKガイドなんかではこれは非常に明確に示されている。
リスクにはプロジェクトに良い影響を与えるものと悪い影響を与えるものがある、と書いてある。
"ウィルスのリスク"とは"ウィルスに感染したときの脅威"ではない。
"今までの十年間でウィルスに感染したことがないから今日も大丈夫だろう"とは言えないこと、過去の観測が現在と未来を確定しない、確実性を増やさないということが"リスク"だ。
"今で家に鍵をかけたことがないけど一度も空き巣に入られたことがないから今日も大丈夫だろう"
"今まで車に鍵を置きっぱなしにしても車上荒らしにも盗難も遭ったことがないから今日も大丈夫だろう"
"今まで賞味期限を3日ぐらい過ぎた牛乳を飲んできたけどおなかをこわしたことがないから今回も大丈夫だろう"
3つめは、前の2つと(今回の質問と)は違っている。
"3日ぐらい過ぎた牛乳を飲んでも"大丈夫だった過去の経験が、確実性を高めていると判断してもよい(そう判断しない人もいるだろうけど)。
1つめと2つめは、一般には*2、大丈夫だった過去の経験から、確実性が高まっているという判断はできないだろう。
アンチウィルスを使っている理由は"ウィルスの脅威から守る"ためじゃない。
"ウィルスの脅威"というリスク(=不確実性)をコントロールできる手段が限られているから、だ。
現代のウィルスは「ネットワークを介する」という性質があるので、ネットワーク上の"ウィルスの脅威"は私にはコントロールできない。
自分のPC上の"ウィルスの脅威"のリスクは、質問者が主張する通り、ある程度までは自分でコントロールできる。
けれど、"それでも残る不確実性"を減らすためにアンチウィルスを入れている。
減るのは、"脅威"ではなくて"不確実性"だと、私はそう意識して行動している。
さて、先に、ネットワーク上の"ウィルスの脅威"は私にはコントロールできない、と書いたけど、この質問に反応してこんなエントリを書いているのは、多少なりともそれをコントロールしたい、リスクを減らしたいという、そんなささやかな欲求からだったりするわけだ。
■postscript
「また随分と堅っ苦しい文を書いたもんだな」
「ふむ。なんとかまとめられそうだと思ったから書き始めたんだけど、当初考えていたいくつかの要素は落っこちたな」
「そりゃ仕方がないだろ。ネタを100%使い切って書けるなんてそうあることじゃない。ところで、これはあれだろ? 相手が使っている言葉を再定義してしまうことで以前の議論を白紙にしてしまうっていうやり口だよな」
「もちろんそれもあるけどね。でもPMBOK云々のあたりは本当だし、"セキュリティはなぜやぶられたのか(ブルース・シュナイアー/井口 耕二)"にも『セキュリティのプロの世界では、「脅威」と「リスク」を区別して使う』って出てくる」
「『プロがリスクと言うときには、脅威の発生可能性と攻撃が成功したときの被害の重大さを考慮している』ともあるな」
「確率的にものを見る、という視点は同じだよ。またPMBOKを引くなら、『前提条件とは、計画を立てるにあたって、証拠や実証なしに真実、現実、あるいは確実であると考えられた』ものである」
「ふん?」
「あやふやで、確実でないもの、確率的にしか捉えられないものを、確率的に見ればそれはリスクだが、確定的に見たらそれは前提条件だと言っている。そして、リスク・マネジメントの中の、リスク識別には『前提条件が正しいことを確認すること』が含まれている」
「根拠はないが今までこうだったからこれからもそうだろう、というのが前提条件だ、と? リスク識別でそれが正しいことを確認する……いや、現状に照らし合わせると言った方がいいのかな? とにかく、それがただの思いこみ、間違いだと判った瞬間にリスクに変わる」
「それだけじゃないよ。今までは確かに正しかったことがある時点で変貌するということもありうる」
「……ていうか、今の世の中たいがいそんなじゃないか?」
「そうだね。『今までの常識は通用しない』なんて、ありきたりな言葉にしか見えないほどだし」
「確かにな。『考えてもみなかった』なんていう常套句もあるな。"セキュリティはなぜやぶられたのか(ブルース・シュナイアー/井口 耕二)"からも引いてみようか。『タイタニック号は沈まないと考えられていたから救命ボートは不要だとされた。エニグマという機械の暗号は解読不能だと考えられていたから、イギリスに解読されているなどドイツは思いもしなかった』てなところだ」
参考
2007-06-21
■富士通「LOOX U」開発者インタビュー
--先ほどオアシスポケットの話をしましたが、結果的には、当時、あれだけ小さいと思っていたオアシスポケットよりも小さいPCになりました。キーボードのサイズやレイアウトはどのように決めましたか?
本田雅一の「週刊モバイル通信」
「富士通社内でも、オアシスポケットというのは1つのベンチマークだったのですが、実際にオアシスポケットを持ってきて比べてみると、LOOX Uの方が小さいんですよ。
(略)
オアシスポケットよりも小さいのか……。なんか興味沸いてきた。
(オアシスポケットは確かにベンチマークになっていると、親指シフト使いである私も、そう思う)
■Google Toolbar for Firefox の update
検索語の補完が、ヒストリからのものだけじゃなくてサジェスチョンが効くようになった。
これはいいや。
2007-06-22
2007-06-23
■少数言語としての手話
地域差や性差、国際手話、手話の芸術、今後の存続までを幅広く解説。視覚言語の姿を明らかにする。
ビーケーワン:少数言語としての手話
男性言葉、女性言葉があるように、手話にも性差があったり、地域差つまり方言(?)があったりするのか。
図書館にリクエストしてみようかな。
■ザ・ファシリテーター
小説なんだけどbookカテゴリで。
ファシリテーションのマインドを説明――という表現はちょっと悪いなぁ、と思うのだけど――した小説。
面白いのは、ファシリテーションとは何か? ファシリテーターと何か? という説明が半分を過ぎたところで出てくること。
ファシリテーションの謂いを使うなら、"ストーリーの流れ"の上でのアイスブレイクやフォーミング(形成)、ストーミング(混乱・対立)、ノーミング(統一)が終わったあとにようやく出てくるのだ。
それよりも前、幹部達の合宿の場で、「ファシリテーターとは何か」と主人公が尋ねられるシーンがある。
言葉の意味は、よくわかったうえでの質問であることは明らかだった。棘がある。
(略)
「司会をすることですかな」
「ハイ、司会もしますし、記録係もさせていただきます。会議が効果的に進むことなら、何でもさせていただきます」
と主人公は
つまり、真実はそうではないということの、筆者の考えが表れている。その先にあるのだと。
ファシリテーターをそのように思っていた人ならば、読むべき本であろう。
また、「現実はこんなに簡単じゃない」とか思っても、それゆえに読むのをやめてもいけないだろう。
「かくあるべき」「かくありたい」姿を表出化させるのもまた、ファシリテーションの中の一つの大事なステップなのだから。
2007-06-24
■"読み逃げ歓迎"って"リンクフリーです"が"無断リンク禁止"派を生んだ(かもしれない)のと同じ情況を作り出すだけかも
mixiを検索すると"読み逃げ歓迎"、"読み逃げ推奨"とかいう言葉がちらほらあるけど、本当にそう思っているならわざわざ宣言することもないよね。
っていうか、"リンクフリーです"と宣言すること自体が、逆説的に"そもそもリンクはフリーじゃない"という認識を与えるのと同じ構造の再現では。
センテンスとしては、"読み逃げ禁止なんてナンセンス!"と書くことを推奨(これ自体"俺ルール"なわけだけどね)。
2007-06-25
■Until Death do us Part
このエピソードで5巻の最後まで引っ張るかー。
ちょっと長い気がする。
……主人公以外のキャラクターがドローンに手が出せない様子を描いてるからだな。そしてそれは自然だ。となるとしょうがないということか。
■Google Reader 不調?
なのかな。
■マインドマップは「描く」ものでしょう!
ふと思ったこと。
マインドマップ作成ツールについて
質問です。以下の要件を満たしたツールはありますか?
http://q.hatena.ne.jp/1182766419
「マインドマップ作成」ってとても違和感があるなぁ、と気がついた。
あ。私は違和感を感じる、と書く方が正しいか。
2007-06-26
■Buzan's iMindMap マインドマップはやっぱり描くもの
うーん、さすが唯一の "Official" Mind Mapping ツールだけあって素晴らしい出来栄え。
いちまんよんせんえん……。
欲しいな。
でも、もう一つ二つ欲しい(ないと困る)機能もあるし、タブレットが欲しくなったりするし、バージョンアップを少し待つか。
2007-06-27
■"Unicode対応"の弊害
どの範囲のコードポイントかが明になっていなかったり、Unicodeの機能(この言い方には抵抗があるのであとで調べておかないと)をどこまでサポートするかが明になっていなかったり。
そんなコード送られても困るよ! てなことがあったので……。
タイトルは"Unicode対応"で済ませちゃうと後でトラブルの元になる、という意味。
■可能無限? 可算無限?
「茂木センセ、それ、『可算無限(countable infinity)』のtypoでっか?」
404 Blog Not Found:無限は君が思っているほど大きいとは限らない
これを指摘している人が弾さん以外に見つからないのはなぜだ!?
ともかく。
本当に「可能無限という言葉」を可算無限と混同している可能性もありますな。
「可能無限という言葉」は、
にでてくるのだけど、その「言葉」のうさんくささは、
で指摘したし、また筆者の「可能無限に対する態度」のうさんくささは、
で指摘した。
■BLOOD ALONE 4
うわ。続いた。
現在二人が暮らしているビルは、ミサキが所有しているのかな? と思った。
彼女のお父さんのセーフハウスかな、と。
「力を持ってして」は「以てして」では? と思ったが、この「以て」はそもそも「持って」からの転だったのか(from 広辞苑, goo辞書)。
2007-06-28
■数学ガール
仙台ロフトのジュンク堂に入荷していた。
不安に思っていた通り、「プログラマの数学」の隣じゃなくて数学の棚にあった……。いや、間違ってはいないんだけど。
残りは1冊か2冊だったように思う。
(追記)
実は厚かましくも、出版社さんからいただいていたんですが結局自分で買ってるし……。一冊は職場に置いておこうかと。
それぐらい魅力的な本なのですよ。
2007-06-29
■セキュリティはなぜやぶられたのか やっと折り返し
手強い……。
結構長い期間読んでいるはずなのだけど、まだ半分。
原題(title)は"Beyond Fear"。subtitle は "Thinkings Sensibly about Security in an Uncertain World"。
ということで、この本、ITセキュリティの本ではない。
もちろんそれも範疇に入ってはいるが、もっと広くセキュリティを捉えている。
セキュリティは全てトレードオフであり、取捨選択である。
我々は日常的に、つねにその選択を行っている。
外出する時に家に鍵をかけるのもそうだ。鍵を持ち歩かなければならない、という不便をトレードオフとして選択している。
その取捨選択の基準として、リスクと脅威を分けて考えなければならない。
車上荒らし、車泥棒、カージャックのうち、脅威がもっとも高いのはカージャックである。何しろ命を落とす危険がある。
けれどそのリスク――脅威の発生可能性と被害の重大さを考慮したもの――は低く、車泥棒の方がカージャックよりもリスクは大きい。
問題なのは、リスクというのは主観的なものであり、直感的であることが多いということだ。
前者は、つまり立場によってリスクが異なるということだ。守らなければならないものが違うからだ。
後者は、多くは心理的なものだ。社会の複雑性、速報性が増したことも一因。センセーショナルに報じられる、けれど自分がよく知らない分野のリスクを、そうでないリスクよりも高く評価してしまう傾向がある。
セキュリティに完全はない。
システム(社会システムを含むことに注意)が目論見通りに機能すると期待することはできないからだ。
そして攻撃者は、システムを構築した者が思いもよらないところを狙う。
p74
数年前、知りあいが、ある企業のネットワークセキュリティセンターを見せてくれた。どんな侵入にも対処してみせると自信満々だったので、「爆弾をしかけたと電話で脅してからネットワークを攻撃してきたらどうなるのか」とたずねてみた。考えてもみなかったそうだ。
セキュリティと安全対策は違う。
攻撃者がいると仮定し、攻撃方法を想像するのがセキュリティだ。
セキュリティが最弱点問題になるのは必然である。
「鎖は一番弱い輪以上に強くなれない」
この問題をおさえる方法は、多層防御と区画化である。
前者は、城壁を二重三重にする、城壁と堀を組み合わせて使う、という感じ。
後者は、パスポートと財布を一緒にしない、お金を分散して持つ、という感じ。
それがないと、クラスブレークと呼ぶ被害が起きる。
一種の攻撃方法が、同種のシステム全てに対して――時として同時に――有効になるというものだ。
システムを変更するたびに最弱点が変化するのも問題になる。
p160
たとえば、「自動車泥棒が心配だから高い防犯装置をとりつけ、キーなしではエンジンがかからないようにしよう」と考えたとしよう。明暗のようにも見えるが、そのような防犯装置が普及しているロシアなどではカージャックが増えるという現象がおきている。(略)つまり、対策を講じた結果、最弱点がイグニッションスイッチから運転者に移動したのだ。
セキュリティシステムの評価として、剛性と靱性という概念を導入する。
これは、どの様な壊れ方をするか? ということを表現する。
剛性が高いと、一ヶ所がおかしくなっただけで全体が駄目になるのだ。
システムの中で、もっとも靱性が高い部分は人間だ。
臨機応変の対応や即断即決ができるのは、人間だけなのだ。
しかし一方で、セキュリティシステムの構成要素しては諸刃の剣でもある。
セキュリティシステムから人を排することはできない。誰かに信頼を託さなければならない部分が、必ず存在する。
信頼を託す人の長所を最大限に活かしつつ、信頼が乱用されないような策を講じなければならない。
これでようやくページの半分である。
さて原題が"Beyond Fear"であることから判る通り、9.11米同時多発テロはこの本の執筆の、大きな動機であったろう。
p3
同時多発テロは驚異的*1だった。テロに対する嫌悪感や恐怖心はいったん横において欲しい。嫌悪感や恐怖心を除いて考えてみることは有益である、いや、重要だといえるほどだ。
と本文が始まる。
セキュリティは、生活していて日常的に行っている行為の中にもあると知ること。
セキュリティというものを、専門家の手から一般人の手に移すこと。
一般人が、専門家の視点でセキュリティを考えること。
これがこの本のテーマなのだと思う(まだ最後まで読んでいないけど)。
「セキュリティはなぜやぶられたのか」という題名は、けれど過去に起こったことの検証としか読めない。
「セキュリティはなぜやぶられるのか」の方がまだマシだったかも。
p175
臨機応変なら新しい攻撃にもすばやく対応できることは、同時多発テロでも示された。ペンシルヴェニア州に墜落したユナイテッド航空九三便では、普通のハイジャックとは違うことを乗客が携帯電話で知り、計画を失敗させた。乗客がその場で脅威分析を行い、自分たちが直面している新手の攻撃に対する防御を編みだしたのだ。乗客自身が助かることはできなかったが、地上の数百人、数千人も一緒に死んだはずの攻撃を防ぐことには成功した。そして、どうやったらこの攻撃に対処できるかを世界に示したのだ。
を読んで昔Webで読んだニュースを思い出した。
弟を同時多発テロで亡くされた方が、出張の移動手段を飛行機から変更しようかと考えたが、"それは本当の意味でテロを成功させてしまうということ"だと気がつき止めた、というような内容だったと記憶している。
また読みたいと思ったが、さすがに見つからなかった。
で、残り半分はどのぐらいで読めるだろうか。
ここでいったん離れて、別の本を読もうか。
などと思ったので、自分の中の、情報と記憶の結び付きを強靱にするためにエントリを書く。
2007/8/17 読了
■テレキネシス 004 そして完結!
毎回映画をネタにしているわけだけど、この巻は有名な作品が多いなぁ(単に、自分が観たことがある、ということなだけかもしれない)。
「カサブランカ」の回が良かった。最後の2コマに、ジーンときた。「カサブランカ」を観た――一本の映画を観たという"経験"がこれほどに感情を涌きたたせてくれるなんて。
*1 ボールドは引用元では傍点。
2007-06-30
■Wii のペアレンタルロックってば入力するとき番号丸見えじゃん
ボタンを押したという視覚効果や効果音がない状態にしてほしい。
例え使いづらくとも。