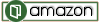2007-04-02
■ぽわそんだぶりる
せっかくの4/1にネット環境が無いところにいた……。
あーあ。
■サイトマップ
しかし、Watlington氏のクライアントたちは、そのインデックス作成サービスの適切な利用法が分かっていないという。以前あるクライアントが、インデックス作成の問題が発生した理由が知りたいと同氏に相談に来た。その人物は、40万ページもフィードしていた。
「検索エンジンスパムの解決法を公開する人はいない」--スパム関連イベントで研究者が発言 - CNET Japan
あぁ、そうか。Google Sitemap などで、サイト内の「全てのページ」を認識させる必要って無いんだな。
「検索経由で来てほしいページ」と「リンクをたくさんもらっているページ」を選択して登録した方がよいのか(後者はもちろん SEO の面で有利だからだ)。
google用のサイトマップジェネレータを探しています。
http://q.hatena.ne.jp/1174562414
なんかもウォッチリストに入れてたりしたけど、結局人手で編集する方がいいのかもしれないな……。
2007-04-03
■ひさしぶりにアイデア追加
医療・健康カテゴリでの質問時に「医師法第17条に抵触するような回答(具体的には「状況からの病名の特定」「薬の処方のアドバイス」)を求めてはいけない」という旨の警告を追加する
http://i.hatena.ne.jp/idea/14720
■いつから「占い」の意味が変わったのだろう?
どう考えても「占い」じゃなくて「性格判断」なんだけど……。
血液型性格判断もいつのまにか血液型占いになってるし、そのあたりの変遷の時期と、動物占いの流行と、どっちが先だったんだろう?
日本では動物占いや家電占いなどの、「面白さ」を優先した占いがありますが、海外ではこういった占いはあるのでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1175496846
■怪しいと感じないときが肝心
というか、そもそも、「フィッシングかな?怪しい!と感じたら、そのアドレスを注意深く確認してみましょう」じゃねーよ。怪しけりゃ確認するまでもないし、怪しいと感じないときに確認することが肝心だってのに、何言ってんの? お祭り見物気分で解説書くな。
高木浩光@自宅の日記 - 銀行のフィッシング解説がなかなか正しくならない
を読んで、まさにその通りだぁ、と思ったわけだけど、しばらく時間が経ってあれ待てよ? なんか既視感が……? となった。
そうそう。前に都道府県庁のサイトのリンクポリシーを類型化した時にも同じことを感じたのだった。
法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります
という文言だ。
これに関しては、あとから別のエントリでまとめを書いていて、
ここでまず1つ指摘したいのは「ホームページの内容が,法令や公序良俗に反する場合」という表現自体に、そのサイトが法令・公序良俗に反していることが一目見てわかるという暗黙の前提を持っているのではないかということだ。
prima materia diary - 法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります
甘い。
幼稚な1クリック詐欺のサイトならともかく、詐欺サイト(クレジットカード番号を盗もうとする目的で作られたサイトなど)が一見してそうと判る様に作るはずがない。
としたのだった。
なんでこんな文言が入っているんですか? どんなリスクを想定しているんですか? という問いに対して返ってくる答えはというと、
これは、法令や公序良俗に反するサイトにリンクが貼られたことにより、当該サイトと本サイトに関係があるような誤解を生じたり、信用・イメージの低下がご覧になった利用者に生じたりする可能性がある点から、注意喚起の意味で当該規定をサイトに明示しているものです。
なのだ*1。
「一見して公序良俗に反すると判るサイト」に都道府県庁のサイトへのリンクがあったってどうということはない。それで関係があるような誤解をする人がいるのか? と思う(本当にいたらそれはそれで問題だろうけど)。
本当に怖い/リスクがあるのは「(実際は悪質なサイトであるにも関わらず)一見して法令に反していると判らないサイト」だろうに。
今回の高木さんのエントリからのリンクに、
その運営者のことをまだよく知らない場合は、まずその運営者を信用してよいかを判断しなくてはなりません。残念ながら、信用できるかどうかを技術的に確認する方法はありません。通信販売サイトであれば「特定商取引に基づく表示」を探して読むか、「オンラインマーク制度」による認証を受けているかを確認するなどして、自分で判断するほかありません。
産総研 RCIS: 安全なWebサイト利用の鉄則
とある通り、サイト運営者のことがよく判らない段階で何を以て信頼性を判断しますか? という問いに対しては簡単で有効な答えはない。
だからこそ都道府県庁のサイトには、
法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります
なんて回りくどい上に効果が無いような言葉ではなくて、
他サイトから本サイトへのリンクがあったとしても、当該サイトと本サイトとの間に何の関係・関連があるとお考えにならないでください
とストレートに書いて欲しいのに。
■オンラインアルゴリズム ほか
今読んでいる
の第6章がオンラインアルゴリズムとなっている。
まず出てくるのがスキーレンタル問題。
p64
オンラインアルゴリズムの説明でよく使われるのが,スキーレンタル問題(Ski-Rental Problem)である.
とあるわりにGoogleから日本語で検索してみてもあまりよいページが出てこない。
むう。リンクで済ませようと思ったのに。
- スキーをレンタルするか(思いきって)買ってしまうかを決める問題
- レンタルは1回1万円、一式買うと10万円
- 将来に、何回スキーにいくか判らない
という問題。
もちろん肝心なのは3番目の制約で、スキーに何回行くか決定済みなら問題にならないわけだ。
これに対して、
- 必ずレンタル
- 思い切って買う
- 9回目まではレンタル、10回目で買う
という3つの回答を検討している。
ここで登場するのが「最適なオフラインアルゴリズム」。神様だ。
未来を決定済みのものとして扱うことができる存在がいれば、
- 1〜9回ならレンタル
- 10回以上なら買う
が最適であると判る。
そこで先に挙げた3つの戦略(戦術??)と神様を比較する。
- 必ずレンタル
- 1〜10回目までは神様と同じ
- 11回目以降は神様に対して\(\frac{n}{10}\) のコストがかかる
- n→∞で対神様比も無限大に発散
- 思い切って買う
- 1〜9回目までは対神様比\(\frac{10}{n}\)
- 10回目以降は神様と同じ
- 対神様比の最大は「1回しか行かない」時で10
- 9回目まではレンタル、10回目で買う
- 1〜9回目までは神様と同じ
- 10回目で対神様比1.9 (レンタル1万円/回×9回+購入10万円で計19万円)
- 11回目以降対神様比は\(\frac{19}{n}\) となり n が大きくなるにつれて小さくなる
それぞれの戦略の、最大の対神様比を考える。
すると3番目の「9回目まではレンタル、10回目で買う」の1.9がいちばん小さい。
さて。
オンラインアルゴリズムの範疇なのかどうか知らないのだけど、最近読んだ本(asin:4152087900 のはずだ)にこんな問題があった。
- 4回お見合いをする(4回目のお見合いで必ず ok する)
- 一度 ok したらそこでおしまい
- 一度断った人とはもう会えない(つまり、上と併せて「決定を覆せない」ということ)
- 相手に対して明確な順位づけができる
さてどのような戦略がありえるだろうか? というもの。
まだお見合いをしていない相手も含めて順位づけができるという「神様の視点」を持てるなら、必ず1番よい相手とのお見合いで ok できる。
過去の相手に対して順位づけはできるが、未来の相手が不明という状況でどのような戦略があるだろうか?
言わずもがなではあるけれど、例えば1回目で必ず ok する、と初めに決めてしまうと、1番〜4番の相手に対して等しく\(~\frac{1}{4}~\)
の確率となるわけだ。
紹介されていた戦略はというと、
- ある回数お見合いをして断る
- そのあと、過去にあったどの相手よりも順位が高い相手なら ok する
たったこれだけ。
例えば、「ある回数」を 2 にしてみよう。
お見合いの順番が 3241 になると仮定してみる('1'が1番よい相手)。
最初の2回は断る。3回目のお見合いでは上記の2番目の条件を満たさないので断る。4回目で1番よい相手に出会う。
1〜4の順列組み合わせと、ある回数を 2 にした時の結果は以下の通り。
1234→4 1243→3 1324→4
1342→2 1423→3 1432→2
2134→4 2143→3 2314→1
2341→1 2413→1 2431→1
3124→4 3142→2 3214→1
3241→1 3412→1 3421→1
4123→3 4132→2 4213→1
4231→1 4312→1 4321→1
24通りある順列組み合わせのうち、
1 12通り
2 4通り
3 4通り
4 4通り
となる。
半分の確率で、1番よい相手で ok できる。
気になった人は「ある回数」を 1 にした時のことを考えると面白いだろう*2。
話を戻す。
面白いな、と思ったのは、オンラインアルゴリズム自体は古くからあった問題らしいのだが、"神様の視点に立ったアルゴリズム=最適オフラインアルゴリズムとの比による評価"という評価手法の導入が1985年と比較的新しいこと(p78より)。
それに、アルゴリズムの評価が、計算量や空間量を基準にする"普通の"アルゴリズムと大きく違うことも新鮮だった。
(追記)
読了後のエントリはこちら。
あと、
が出てますよっ。
2007-04-04
■月の名前と英語
[Q1]
DateやCalendarの月の値が1月ずれてしまっているようです。なぜでしょうか?[A1]
Date#getMonth()やCalendar#get(MONTH)で返ってくる数を そのまま使用していませんか?
DateやCalendarは、月を0から始まる数で表します。
したがって1月は"0"、2月は"1"、12月は"11"、となります。
Date#setMonth()やCalendar#set(MONTH)で設定する数も同様の注意が必要です。月が0で始まることに対して日本人は違和感を感じますが、 英語圏では、月をJanuary,February,...など「名前」で表現するため、 月の始まりを0にするか1にするかは、日本ほど大きなこだわりは無いようです。
JavaFAQ: Date / Calendar
なんてことをふと思い出した。
Googleで検索してみよう。
■勝訴側は控訴できない
「勝訴したのに登録が移転させられてしまう」状況が起きると、「勝訴側は控訴できない」という現在の裁判制度では手も足もでなくなってしまうからだな。
だから、「どのような判決でドメイン名移転を行う/行わない」の基準が無いことには、裁判に臨む姿勢に困る、と。
私としても、「ドメイン訴訟で勝訴したのに、主文がJPRSのお眼鏡にかなわなかったために、ドメイン名の登録が移転させられてしまった」ということになると弁護過誤ともなりかねないので、「○○」という主文で判決が確定したらJPRSはドメイン名の登録移転を行わないこととしてくれるのですか?と確認しているのですが、「裁判所の判決が確定したらそれを見て判断する」の一点張りです。
benli: JPRSはなぜ自社の処理方針を明らかにできないのか。
■グロリアスドーン 2
「妙にオタクな幼なじみ」は面白いが、全体的には筆者の通常のレベルにとどまっているような気が。
巻末のテキストRadioいっそう磨きがかかって面白いのに……。
そういえば、カミさんは1巻を読んだ時点で、ドーンやダスクが時間帯を指す言葉だと判らなかったそうで。
ロメロの3部作を知っていればすぐにピンとくるんだよ、という話をしてみたり。
いやまぁ、フロム・ダスク・ティル・ドーンでもいいけど。
2007-04-05
■EM・ONE
なんか、すごく良さそう。
使ってみたーい(が、サービス圏外なのでどこにも売ってない)。
QWERTYキーボードとATOKによる日本語入力環境
ITmedia +D モバイル:“モバイルブロードバンド”は本当か?――「EM・ONE」の実力をチェック (3/3)
2007-04-06
■おすすめ新刊blog
おすすめ新刊と、出版関係のニュースがでるのでウォッチしている。
Role & roll がでるたびにおすすめ新刊に載ってくるけど……、これは単なる趣味なんでしょうか。
売れ筋の本なら、書店さんなど関係者にすすめる理由は判るけど、この本は??
■Googe Reader のキーボードショートカット
Firefoxの設定で、キーボード入力で即ページ内検索が始まる設定にしているので、g → a とか、 g → h とか使えないなぁと思っていたら g → Esc → a が有効じゃないか! と気がついた。
よしよし。
ちなみに ? を押すとヘルプが出るのです。
■NIGHT STRIKER
実機を見たことは2回だけ。どっちもメンテが悪くてゲームにならず(友人が先にプレイして判明)。
ということで初プレーイ。
格好いい!
サントラで耳になじんでいる曲が、本当にゲームのBGMに。
あぁ……。幸せ。
他のゲーム? えぇと、なんのことでしょう?
2007-04-07
■アルゴリズム・サイエンス 出口からの超入門
まずは、タイトルの勝利である。
『出口』からの『超』入門って? 入門書じゃないってこと?
このタイトルがなければ書店でこの本を手にしなかっただろう。
隣には「アルゴリズム・サイエンス:入口からの超入門 (アルゴリズム・サイエンスシリーズ 1―超入門編)(浅野 哲夫)」も置いてあったのだけど。
さて、本書の話に入る前に「データ構造とアルゴリズム」という本の話をしたい。
特定の本ではなくてそういうジャンルの本で、普通の本屋に売っているような範囲の本の話。
そういう本って「教科書的」だと思うのだ。
ちょっと言い直す。
そういう本は、教科書か事典的だと思うのだ。
前者はそのまんまの意味で、大学などの授業で教科書として使われる様な本だということ。データ構造やアルゴリズムについての理解を深めるための本。
後者は、つまり、名の通ったデータ構造やアルゴリズムについて、特定の言語で実装するとどうなるか? を列挙した本だということ。
で、両方の意味を併せて「教科書的」だと思う。
それはつまり「どんな本でも扱う内容は変わらない」。
クラスについて説明しないJavaの「教科書」なんてないだろう。
ポインタについて説明しないCの「教科書」なんてないだろう。
同じように、二分探索も連結リストもクイックソートも説明しない「データ構造とアルゴリズム」の本なんてないだろう。
そんな意味で、「データ構造とアルゴリズム」という本って「教科書的」だと思う。
さて、この本は、そういう「教科書的」なアルゴリズム本を離れて跳躍する。
なんせ「出口からの」本だから。
各章のタイトルを挙げる。
第1章 ウォームアップ,その1
第2章 ウォームアップ,その2
第3章 情報を漏らさない
第4章 通信量を減らそう
第5章 乱数を利用する
第6章 オンラインアルゴリズム
第7章 近似アルゴリズム
第8章 厳密アルゴリズム
第9章 幾何の計算
第10章 分散アルゴリズム
第11章 オークション
第12章 ウェブグラフ
第13章 利己的ルーティング
第14章 あとがきに代えて
いずれの章も概略、問題、必要になる基本定理の解説、アルゴリズム、検証もしくは証明、まとめ、出典そして練習問題。という感じ。
第3章は、秘密通信の話、なのだけど暗号の話じゃない。
ゼロ知識証明、電話でするジャンケン。
第4章も、圧縮の話じゃない。この本はアルゴリズムの本。
2点間の間で共有されていないデータを持っていて、その間で通信して中央値を求めるには? といった話題。
第5章はタイトルの通り。アルゴリズムを作ろうとすると難解な問題でも、でたらめにやれば大体うまくいく、という類のもの。
第7章も同じように、最善の解を求めることが現実的に難しい(現実的な――実用的な時間内で終わることが期待できない)問題の話。
アルゴリズムについて学んだなら、NP問題、NP完全問題、P≠NP予想といったところを思い浮かべるだろう。そのような記述は出てくるが細かい話までは踏み込まない。あくまでも問題とアルゴリズムを示す。
第8章は、逆に最善の解でなければ意味がないタイプの問題。
この本でためになる(と私が感じた)のは、検証。
ここでは数式がでてくる。まぁ、計算量を求めるためには当然。
それ自身もためになるが、そこでの発想、展開方法もまたためになる。
アルゴリズムの評価、特に計算量という意味では上限でおさえればいい。
理解はしているけど、実際に、滅多に目にすることがない(のは私の勉強不足だけど)アルゴリズムに対する検討はためになる。
第12章で Pagerank の話が出てくる。
Google のWeb検索で有名になった「あれ」だ。
ごく小さいページ群をモデルにして行列計算を行っている。その行列にどの様な条件が必要となるのか?
固有値や規約性から説明をし、条件を満たすための正規化などをしている。
面白かった。
逆に、この理屈をみると Google があれだけの規模のサイト群でこんな計算をしているのか、と嘆息である(とまぁこれは冗談。現実の実装はああではないはず)。
本来の読者層は、情報科学を専門とする人だと思う。
でも、「データ構造とアルゴリズム」という新刊が出てももう手にする必要を感じない人。そうはいっても情報科学が専門ではない、「現場」の SE やプログラマーの人。
そんな人も読む価値はあると思う。
さっきも書いた通り、直接役に立つかは別にして、アルゴリズムの評価や検討をするための、考え方を身につけるために。
(追記)
この本で興味を持ったオンラインアルゴリズムの巻が配本されました。
■Death note
後編が原作と違うのは当然として、前編の終盤もちゃんと原作から変えてくるのは圧倒的に正しい。
川井憲次の音楽がうまくマッチしてるなぁ。さんざんサントラで聴いていたからなぁ、画がつくとまた印象も変わるよなぁ。
面白かった。
素直に面白かった。
でも結末が……。ある意味意外だった。
ホントに意外だった。
原作よりも切ない話になっちゃったなぁ、なんか。
途中ででてきた月くんの統計(?)のシーン。
殺された人間を統計してプロファイルしたって?
3次元にプロットして?
それってどんな特徴量?
あぁいうシーンに説得力を与えるのは難しいよなぁ。
2007-04-08
■MASHUP++
本の内容以上に、ポップなデザイン(装丁)が気に入って買った、というのもある。
内容は……、どうなんだろ?
「ネットで調べた方がいい」と言ってしまっては身も蓋もないわけで、ここはやはり「本」というメディアでやるからには、本ならではの「読んで」「見て」楽しいというところを狙ったんじゃないかと。
こういうポップな装丁って「廃れやすい」という見方もできて、この先何年も通用する――再刷が期待できる――内容の本ではなかなかやれないんじゃないかと思う。
その点、「マッシュアップ」って題材は、Webやプログラミングの「今」を象徴していてポップな装丁とも雰囲気があっているし、数年後に同じ内容で刷り直すってこともありえないわけだし。
「企画」としては面白いと思うんだな。こういうの、嫌いじゃない。
そうはいいつつも、300ページ弱のうち、50ページぐらいをPlaggerに、30数ページを各種WebサービスのAPIリファレンスに割いていて、実用書として手元に置いておいてもいいかな、というぐらいのバランス感もあったりして。
読むのはこれからだけど、なんかまず最初に書いておきたくなった(多分読了の時には何も書かないだろうし)。
2007-04-09
■当選確実
結果が6対4だとする(候補者2名)。
最初の2票を考える。本当はここで組み合わせが出てくるのだけど、投票数が充分に大きいとすると独立な事象に近似してしまえる。
実際は負けている側が2票とる確率は0.4×0.4で16%。
実際に勝っている側が2票とる確率は0.6×0.6で36%。
同票になる確率は0.6×0.4+0.4×0.6で48%。
6対4という比を仮定しても、2票開票した時点での中間勝率(?)はすでに倍以上違う*1。
事前調査で十分な差が出ていたら、1000票も開ければほぼ判ってしまうわけだ。
都知事選なんて数100万票のオーダだから、1000票なんて0.1%未満。
*1 「負け側が多く票を取っている中間結果」の確率は、1票開いた時点で40%(自明)、3票開いた時点で35%、5票開いた時点31%というように低くなっていく。
2007-04-10
■ATOKで集合の記号
「ふくむ」と入力して変換→F4キー(辞書セット4変換。つまり記号辞書変換)を押すと∋,⊇,⊃しかでてこない。
逆向きは? 文字セットにないんだっけ? そんなはずはないよなぁ……。
としばし考える。
あ、そうか。
「ふくまれる」と入力して変換→F4キー。
よし、おっけー。
■コマンドシェルで年間カレンダー
うわ。面白い。
早速、debian君で実行。
cal -y | tr '\n' '|' | sed "s/^/ /;s/$/ /;s/ $(date +%e) / $(date +%e | sed 's/./#/g') /$(date +%m | sed s/^0//)" | tr '|' '\n'
結果は、
2007
1月 2月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 ## 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
うーん。5月10日がなぜおかしくなる?
追記
……えぇ、勘違いでしたとも。時計が狂ってたというただそれだけの話ですよ。orz
■Webサイトリニューアルは"衣替え"であってはならない
タイトルだけで内容を想像できなかった。
中身を見るとなるほど。
リニューアルは、ロゴやコーポレートカラーの変更など見た目の問題から操作性の向上など、その理由はさまざまですが、本質的なものはコンテンツのはずです。どうも、外見だけ変えて中のテキストは同じだったり、リニューアルしたものの、そのあと息切れして更新がなかったりと、努力の結果を享受することなくだんだん陳腐化して次のリニューアルとなるようなことが多いのではないかと疑ってしまいます。
衣替えであってはならないWebサイトのリニューアル - Allegro Barbaro [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
ここ(blog)もちまちま細かいところを変更していたりするけど、本質は変わらない。
トップページは大きく変えたりしているけど、内容が全然伴わなくて息切れしてしばらくそのまま、という感じ。
そしてもちろん、ここの方が、ちゃんとアクセスを集めるコンテンツになっている。
トップページどうしよう、何をしよう、何ができるかな? と考え続けて早一年……。
2007-04-12
■金融というギャンブル
家を買うのにそんなことを知らないでいいのだろうか?
いや確かに、ちゃんと判っているか? 他人に説明できるのか? とあらためて問われれば私もちょっと心許ないけど。
今、家のローンを払ってます。。。
3年前に家を購入し、ローンが始まったわけですが…
銀行から「固定金利期間終了のお知らせ」が届きました。
詳しい人、教えてください。
この先も固定金利を選択する場合、早めに手続きを!
との事ですが、変動金利・固定金利…何が違うの?
デメリット、メリット教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1176340218
「ローンもない。投資信託だとか株なんてあやしげなギャンブルみたいなものには手を出さない」
って人もいるかと思うけど、実はそれも、
「お金の価値が下がらない」
という目に自分のお金を全額かけるというギャンブルと同じだ、と書いてあったのは、
だったか、
だったか。それとも別の本だっけ?
かな?
■フライの楕円曲線
フェルマーの定理の証明に関して、ゲルハルト・フライが提示した式(以下略)
http://q.hatena.ne.jp/1176290271
手元にあるフェルマーの最終定理の本では、フライの楕円曲線は\(y^2=x(x-a^n)(x+b^n)\)
となっている(もちろん、展開すれば質問の式と同等になる)。
楕円曲線なので、曲線上の点全体が加法群になっている。
楕円曲線にも判別式があり、3つの根をα、β、γとするとき判別式は、
\(D=\{(\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)\}^2\)
となる。
フライの楕円曲線の式の左辺=0の3根は、\(0,a^n,-b^n\)
なので、判別式が\((abc)^{2n}\)
となり、判別式が自然数の2n乗になる。
合同式\(x(x-a^n)(x+b^n)\equiv~0~(mod~~p)\)
の根を考えたとき、aとbが互いに素なので、三重根を持つことは無い。
「フェルマーの方程式に解があるとすれば、その解を使って作られた楕円曲線は三重根を持たず、判別式が自然数の2n乗となる」
裏を返せば、フェルマーの最終定理は「n≧3の時、三重根を持たず、判別式が自然数の2n乗となる様な有理楕円曲線は存在しない」と言い換えられる。
と続き、谷山=志村=ヴェイユ予想へと繋がる。
追記
……らしいがよく判らない。
「楕円曲線はモジュラーである」という概念を理解する必要がありそうだが、ここが一番難しそうである。
かつ、楕円曲線の判別式が意味を持ってくるのは、どうやらここみたいなのだ。
だから、楕円曲線の判別式が\(D=\{(\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)\}^2\)
だということが Web
を検索してもなかなかでてこないのだろう。
さらに追記
やっと見つけた。
の13ページにでてくる Δ(f)。これが多項式 f ("if f is a polynomial" とある)の判別式の定義である。
"楕円関数の判別式"で検索してもでてこないはずである。
検索すべきは"多項式の判別式"なのであった。
そうと分かれば検索してみれば……、
とまぁ、簡単に引っかかってくる。
フライの多項式の判別式は、
\(\{(a^n-0)(-b^n-0)(-b^n-a^n)\}^2~=\{(a^n)(b^n)(a^n+b^n)\}^2~=(a^n~b^n~c^n)^2=(abc)^2n\)
となるのは上で書いたとおり。
その下あたりに、
In particular, such a curve cannot possibly be what is called modular (never mind what that means).
と書いてある。
「その様な場合はモジュラーと呼ばれる曲線にはなれない」とあり、そしてカッコ書きで「モジュラーが何かは気にしなくていい」と続く。
実際「気にしなくていい」とある通り、谷山=志村=ヴェイユ予想(「有理数体上の楕円関数はすべてモジュラー楕円関数である」)から、1.で回答した通り、
「フェルマー予想が誤っているならば、フライの楕円曲線はモジュラーではない」
しかし、「全ての楕円曲線はモジュラーである」ので矛盾
ゆえに「フェルマー予想は正しい」
http://q.hatena.ne.jp/1176290271#a704936
となる。
結局、「モジュラーである」ということの意味と、多項式の判別式とモジュラーであるということにどんな関係があるのか? というその部分が一番難しいわけだ(ほんの50年前の数学の"最先端"なのだから!)。
多項式の判別式から式展開できたところで、それで何かが判るというわけではないのだと、そういうことなのではないかと。
2007-04-13
■ファンタジーっぽいけどSF
こんな感じで表向きはファンタジーっぽいのに裏ではSFっぽい作品を教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1176388963
思いつくままに。
……そういや、もしかして、これもそう?
■「特に意味はない」という意味
Lifehackerのエントリって、ほぼ必ず*1写真がついているなぁ。
とか。
魔鬼*2(モグアイ)なんて、関係はあるようで実は意味ないよ! という写真。
でも印象づけ(impression)、象徴(symbol, image)としては、なんか機能しているかもしれない。
文章もだらだら横に長く続かないので、横方向に視線を流さなくても冒頭部分――レジュメ――を認識できるというのもあるかもしれない。
もっとも「あの写真が貼ってあった記事なんだよ!」と思い出しても辿り着けないけど。
なんか、意味がないようで意味があるような、意味があるようで意味がないような……。
不思議。
新しめの人気サイトには、そんな特徴が見受けられるなぁ、と思ったもので。
■タスクマネージャになるemailアドレス
タイトルは、「タスクマネージャとしてのEmail」なんだけど、中身を読むと専用のmailアドレス(IMAP)を作り、そこに自分でメールする。
完了したものは消す。
という運用。
つまり。
普段使っているメールアドレスやメーラをタスクマネージャにするということではない。
タスクマネージャとして機能するメールアドレスを作ろうということ。
ならばエントリのタイトルは、
「Email address as a task manager」であるべきではないか?
とも思った。
「旧来の To do list ではもう仕事の管理なんてできない」という認識は、GTD とか いろんな Lifehack の下敷きとして存在すると思っているので、こういう"単純な To do list"をLifehacker が発信するというのは少し違和感がある。
カレンダーを意識したタスクマネージャにはならない(だろう)と、コメントで指摘されているしね……。
2007-04-15
■毎年桜を観に行ってたけど
子供の体調はよくないし、雨も降ってるし。
今年はなしかな。
■活字のない印刷屋
サブタイトルの通り、ITによって「活字」が消えたあとの印刷屋の話。
雑誌連載エッセイをまとめた本。
各論についてもう少し踏み込んでほしいな、というところで次の話題に移るのが残念。
このような"エッセイをまとめた本"に共通の欠点であって、この本の欠点ではない。
IT側にいる者としては「活字のない印刷屋」という題から、「活版の時代」から「DTP+デジタル出力の時代」の2極を想像してしまったのだけど、その間に「電算写植の時代」があったことを初めて知った。
1980年あたりから2003年まで「そこにあった」のに知らなかったわけだ(この終わりの年はこの本に依る)。
デジタル出力といっても、デジタルオンデマンド(これはつまり"すごいプリンタ"である)とオフセット印刷のデジタル製版の2つが別物だとか、まぁ知らないことだらけである。当たり前ではあるが。
そうは言っても、SEとしてIT業界側にいる身としては、その移り変わりの様は決して無関係ではないわけで。
ホストコンピュータからサーバクライアント方式への移り変わり。
パソコン通信からインターネットへの移り変わり。
そんな話題は馴染みのものだ。
エッセイなので、ここがためになる、とかそういう類の論評は無用であろう。
ITという括りでいうと、"提供する側"からの視点ではなくて"提供される"側からの視点の、それも個人レベルではなくて"会社"や"業界"の視点からのエッセイ自体珍しく*1、その点で興味深く読んだ。
この本、アルファベット頭文字略語がばんばんでてくるが、IT業界のものだけじゃなくて印刷業界のものもたくさん。
おかげでそのような言葉がでてくるたびに注釈を参照する自分に苦笑。
なるほど「(コンピュータの本って)訳が分からない略語ばかり出てくる」と言う人たちの気持ちがよく判った。
■ロボット工学三原則
ロボット三原則を、ロボットが守らなければならない、ロボットに教えておかなければならない規則という誤用はよく見ますが(つか、そう思ってましたよ、ハハハ)、陽電子頭脳とやらを使うと数学上の都合でロボットは三原則を破れないのだそうです。ですからむしろ物理的制約に近いですね。
Note - 晴
この文の冒頭だけ「ロボット工学三原則」じゃなくて「ロボット三原則」なのはわざとでしょうか。
だとしたら慧眼です。
「ロボット三原則」と憶えてしまった人ほど、この誤用をしやすいと、私は想像します。
しかし、「ロボット三原則」ははてなのキーワードになっていて、「ロボット工学三原則」の方はキーワードになっていないのか。
*1 私の無知かもしれない。
2007-04-16
■tactics 9
もう漫画喫茶に行く機会もめっきり減って、かつ、それでも行く機会のある漫画喫茶には置いてないときてる。
んじゃぁしょうがない、と思って買ったら……。
本編が、本編が2話しかないってどういうことじゃあ!
■クロサギ 13
これも似たような理由で買ったわけだが……。
さすがに巻も進んで詐欺関連の話は薄くなったような感じもするが、逆に各キャラクターの主張が強くなってきたな。
その辺のバランスには気を遣うところだろうけど。
まぁ、まだまだ面白いですな。
■世界樹の迷宮 近況
1stパーティがB16F到達。
カースメーカーが選択できるようになったので、早速冒険者を登録。2ndパーティに。
2ndパーティでプレイしてブシドーlv20を目指す(クエストのため)。
ちょっと前に1stと2ndでメディックを入れ替えたのだけど、これがなかなかよい。
1stパーティはメディックのレベルが若干低くても大丈夫(なぐらい慎重に進んでいる)。
2ndパーティはレベルに見合わない階層で戦っている(装備がよいのだ)ので、HPの少なさから簡単に戦闘不能になる。でもメディックのレベルがパーティ内で飛び抜けていて回復とリザレクションのコストが苦にならない。
2007-04-17
■犯罪不安社会
である。
読み終えてから時間が経つのだけど、どうもこの本について書く気になれないでいた。
まとめきれないと思えたからだ。
で、今回書くことに決めたのは何かというと、NEXT WISE とかいうフリーペーパーの書評。
を取りあげている。
ここに、
「日本の犯罪の4件に3件は未解決」「05年における日本人の生涯未婚率は男性15.6%、女性7.2%」など、やりきれない統計結果にはリアルな危機感を憶えてしまう。
とある。
読んだ瞬間に「『日本の犯罪』というところの母集団は何?」「生涯未婚率の定義は?」と反応した。
まぁ、この本を読めば書いてあるのかもしれないが、書評でこれは無いだろう。それが何であるのか説明しないまま、数字だけを表に出すことに強い拒否感を憶えた。(ちなみに上の質問の答えは「統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか? (光文社新書)(門倉 貴史)」にちゃんと書いてあった)
で、「犯罪不安社会」である。
「安全神話の崩壊」などと言われはじめて久しいが、「安全神話の崩壊」自体が神話だと主張するものだ。
筆者は2人。
2人がそれぞれ2つの方向から、都合4つの方向からアプローチする。
まずは統計という観点から。ここでは「統計に騙されない」、「統計の真の姿を知る」ことに費やされる。
上で引用した「日本の犯罪の4件に3件は未解決」なんてのもそうだ。
この結果を良しとせず、解決率=解決する割合を増やそうとするにはどうするか? 軽犯罪、自転車の窃盗とか、そういうところに人員を費やせば、数字は上げられるだろう。だが果たしてそれでいいのか? という見方。
あるいは、警察が事件を受理しなければ見かけ上の解決率は上がる。それでいいのか?
そして、事実、警察が事件を積極的に受理するようになった結果としての「解決率の低下」であると本書は主張する。
それ以外にも様々な統計を駆使する。といってもある主張をしたいがために多くの統計を持ち出すわけではない。
統計の母集団を説明する。項目としてカウントされるのはどんなケースか? をフローを用いて説明する。似た指標を出す複数の統計を並べ、どの統計がどんなバイアスがかかるのかを説明する。
統計を見ることを難しさを知っているし、そしてそれを伝えようとしているという姿勢が感じられた。
次に、メディアによる「凶悪犯罪の語られ方」という視点から。
言葉を変えようか。
凶悪犯罪なるものをメディアはどの様に語ってきたか。そしてその変遷を論じる。
酒鬼薔薇事件の時のことをこう語る。
p91
挑戦状の内容が公表されるとメディアはまたも推理ゲームに熱中した。いつものように、推理作家・犯罪学者・精神科医・心理学者などを動員して、さまざまに犯人像を描き出した。
……私自身はそういった番組や雑誌との縁は浅いが、確かにその通りだったように思う。
ここで、そのメディアの態度を「推理ゲーム」と断じているが、さてそのゲームが終わったときに、何が残ったのか。
p109
いつ少年たちに襲われるかもしれないという『白日の悪夢』に変容したのだ。
そして地域防犯活動、つまり「地域ぐるみで子供たちを守ろう!」の話へと移る。
でも、「守る」って、一体誰から?
という問いを投げかける。
それは、地域に住む「もしかしたら犯罪を犯すのではないか? という疑いがある者」なのだ。
けれども「その問い」は、地域防犯活動の中にあってかえりみられることはあるのだろうか?
過剰な地域防犯活動の行き着く先を、本書は予想する。そこに誇張は感じられない。
地域ぐるみで同じ目標に向かうことによる感動、達成感。それは快楽。
けれど、その原動力は、不安。それも具体的な形のない不安。
防犯活動が、その不安に形を与えるという皮肉。
p184
それは揃いのジャンパーに身を包み、「防犯」という腕章をつけた善意の住民たちの目に、異質な者として映る者たちでしかない。だが、そうした異質者たちが不審者として、今社会から排除されている。
そして最後が、刑務所の真実。
実際に刑務所に勤務した際にかいま見た姿。
受刑者はそこにいる。あふれるばかりに。
だが懲役刑の作業をまともにできる受刑者は、少なくなっているという。
社会にでても職につけない、その能力も、気力もない者ばかりだという不自然な状態。
統計から社会学、そして刑務所で実際に見た景色からまた統計へと移る。
様々の角度からの視点が、この一冊に詰まっている。
ありがちな、「ただ一人の想像だけで書かれた本」と一線を画するのは、そんな様々な角度からの視点だと、思う。
■Amazonからの腹立たしいお知らせ
が「現在好評発売中です。 ご注文は以下をクリック」というDM。
でも、Amazon で在庫に無いことを知っていた。
増刷して入荷したのかな? と思って確認してみると……まだ在庫ないじゃん!
腹立たしー!
……在庫が入ったけど売れちゃったとか?? まさかね。
2007-04-18
■Google Reader Gadget
お。Google Reader のガジェットが。
パーソナライズドホームに未読が入っていく。
……でもこれ、気が散ってしょうがない気がする。
関連
p16
集中できない原因は、外部からの割り込みだけではありません。私たちにも責任があるのです。すなわち、音楽をかける、背景画面が勝手に更新されるようにしておく、IRCチャットルームのウィンドウを開いている。IMクライアントを目につく場所に置いておく、といったことです。
■過去のエントリを直すか?
私は結構修正してますな。
エラッタは当然。助詞の間違いなんかも。
後は追記。追記。追記。
後からよりよい(この基準は微妙だ)エントリを書いたらそこへリンク。
そんな人は多いのか少ないのか。
少数派のような気はするんだけど。
2007-04-19
■Google Reader Shared Items
トップページに、Googe Reader で共有(Share)した項目を表示するスクリプトを貼り付けてみた。
ついでに昨年ぐらいのレイアウトに戻した。
このトップページが何のためにあるのか未だに定まらないままだな。
■物語の魔の物語
キィワードは「メタ」。
すごい。
面白いとか怖いじゃなくて、すごいと形容するしかないような作品が揃っている。
「エッシャーのだまし絵(トロンプ・ルイユ)のような」とい形容がこれほど嵌る物語(!?)もないだろう、「丸窓の女」が逸品。
一体、どこでどうなった? と、読後にたくさんの疑問符が頭の中を跳び回り、なにかどこか落ち着かない様な非現実感と離人症的な感覚に襲われる。
こういう、頭が真っ白になって、思考ができなくなる瞬間を「感動した」と形容したいのだけどなぁ、とか思う。
2007-04-20
■わけがわからない小難しい言葉からわけがわからない横文字へ
(商用アプリケーションというものの宿命として、こういう「普通の」ユーザーがわかりにくいところの実装って、社内でも説得しにくいところなんだよな)
lethevert is a programmer - はてな : 実体参照や文字参照
そういう説得しにくさを覆い隠すために「サニタイズ」という言葉が生まれた(使われるようになった)のかもなぁ。
とか思った。
「&や"は実体参照に変換してhtmlにしないと駄目なんですよ」
↓
「サニタイズしないと駄目なんですよ」
2007-04-21
■本というのはかなり優れている、というのはとても同意できる
元々、本というのはかなり優れている。
万来堂日記2nd - 電子出版が普及しない程度の市場規模
持ち歩きに便利。ページをめくるのも実にすばやく実行することができる。書き込んだり栞を挟んだり付箋を貼ったりすることで、自分にとっての要注目箇所を簡単に明示することができる。
ふむ。
そもそも本は、コンテンツであり同時にメディアでもある。
日常的に「本」と言ったときにそれがコンテンツであるかメディアであるかをあまり意識していない。
「本を電子化する」って謂いは、語義としてどうもおかしい(id:banraidouさんがそう書いているわけではないですよ。念のため)。
ところでじつは、電子出版は、密かに進みつつあるのだけどそこにお金の動きがない――つまり商売になってない様に見える――ために皆が目をそらしているだけではなかろうか?
2007-04-22
■ARIA
ARIAのアニメ、不思議だなぁ。特別面白いとか感動したいうわけではないけど、つい何度も観てしまう。BGVにしてしまう。
オープニング、ふと探してみたらiTMSにあった。
"Aria the Animation" Opening Theme - Undine - Single - 牧野由依
2007-04-23
■意図しないファイルからのアプリケーション起動
なるほど。
Windows では,拡張子関連付けの無いファイルを起動しようとすると,[ファイルを開くアプリケーションの選択]ダイアログが起動します.しかし わざわざこうしてアプリケーションを指定する人はいないのではないでしょうか?恐らく操作ミスが大半だと思われます.
Studio P/Rhythm
このうざったいダイアログを出さずに,ビープ音を鳴らしましょう
■1=0.9999…… ? ε-δ論法への階梯
0.9999…… と 1 との間に数があるかどうか? を考えよう。
もし、0.9999…… + p < 1
を満たすような正の実数 p があれば「0.9999…… と 1 との間」に数があることになり、0.9999....≠1 ということになると言っていいだろう。
10の-n乗(nは正の整数)を小数点表現する。
0.0……01 となる。(小数点と1の間に n-1個の0が続く)
 (k は nの間違い。orz)
(k は nの間違い。orz)
これを 0.9999……に足すと小数点以下n桁目で繰り上がりが起こる。

となり、1より大きくなる。
よって 0.9999…… + p を考えたとき、
正の実数 p がどれほど小さい値だとしても、 《\(p~>~10^{-n}\)
であり、かつ \(0.9999\cdots~+~10^{-n}~>~1\)
となるような \(n\)
》 が必ず存在する。
これはつまり、0.9999…… + p < 1 を満たすような正の実数 p が存在しないということを意味する。
したがって「0.9999…… と 1 との間」に数は存在しない。
これを高校以前に考えておくと、ε-δ論法の考え方を教わる時に少し楽になるような気がするのだけど、どうだろう?
『1=0.9999…… ?』はシリーズです。
2007-04-24
■洞察力の定義
「先輩、洞察力の定義って何ですか?」
洞察力の定義(いつもふと思い出すこと) | i d e a * i d e a
ある事柄に対して「理解している」とはどういうことか? という問いから出てくる定理でもあるような。
「理解している」の定義は、「知らない人にもある程度判る様に説明できること」としておこうか(曖昧だなぁ)。
この定義の比重は「ある程度判る様に」のところじゃなくて、「説明できる」の方にある。
それを理解していない人に説明できるということは、「それ以外の何か」から言葉を作れるということで、その時点で「それ以外の何か」との相対化や関連づけができているということだから。
■ゲイルズバーグの春を愛す など
ジャック・フィニイである。
実は読みたかった短編があったのだけど、これに収められているわけではない。
解説に書いてあるんじゃないかと思って手にしたのがこの本。
読んでみたら《時間怪談》がことのほか多かった。
それらが特に出来がよいと感じた。十八番なのだろうか? この時代のSFはほとんど読んだことは無いが、しかし、古びないものなのだなぁ。
《時間怪談》と言えば「異形ミュージアム〈1〉時間怪談傑作選―妖魔ヶ刻 (徳間文庫)(井上 雅彦)」もカバーをかけて読み始めるぞ! という体勢に入っているのだけど、1本目の安土萌の短編を読んですごい衝撃を受けてそのままだったりして。
さて、フィニイで読みたかった短編は目論見通りに、解説から
に収められていることが判ったのだけど、どこでその短編のことを知って読みたいと思ったのか、それが今は思い出せなくて少し「こわい」。
2007-04-25
■"SEO対策"が言葉の誤用を要請する
(以前も書いたことがあるはずだけどもう一度書く)
"SEO対策"じゃなくて"SEO"で十分じゃないか、とツッコミたくなる人はどのぐらいいるのだろう……? とか思うのだけど、それはおいておいて、
の結果を見ると、"SEO"じゃなくて"SEO対策"という言葉が広まった理由が推測できる。
- どこかで、誰かが、"SEO対策"という用法を使う
- すると、"SEO対策"で検索する人が現れ始める
- SEOを売り物にしている会社は当然SEOに長けているわけで、"SEO対策"という検索語が使われていることを補足する
- すると自社サイトでのキィワード選定において"SEO対策"が重要視されることになり、そこに"SEO対策"という表現が出てくる
- それを見た顧客が普通に"SEO対策"という言葉を使い始める
- "SEO対策"というキィワードはさらに重要になる
ということが発生したに違いない。
さて。
この様な事態が進むと、
- 明らかに誤用・濫用だが一部の人がある"言葉"を使い始める
- すると、その"言葉"で検索する人が増える
- 関係しているサイトはその"言葉"で検索されていることを補足する
- そのキィワードが重要視され、SEOの一環としてその"言葉"がサイトに現れる
- サイトを閲覧している人がその"言葉"を目にし、使い始める
- その"言葉"はさらに重要になる
という事象の発生が、今後も進むのではないか?
"Web2.0"なんて、まさにこんな感じじゃなかったっけ?
2007-04-26
2007-04-27
■妙なコメントの正体は
1月にリニューアルした仙台市図書館のWeb蔵書検索。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/licsxp-opac/WOpacTifSchCmpdDispAction.do
全角文字じゃないとエラーが出てくる(半角カナじゃないよ。半角英数字も駄目だったりする)のだけど、そのダイアログに謎のコメントが……。

これの正体はというと、Tab Mix Plusで Merge Window してエンコーディングをUTF-8にすると……。

このエラー、IEだとでなくて、Firefoxだとでてくるんだよなぁ。
仙台市図書館ホームページは、Internet Explorer5.5以降、及びFirefox1.5でご覧いただくことをおすすめします。
サイトポリシー|仙台市図書館
おすすめされてるのになぁ。
1月に指摘しているのになぁ。
■Googleが変わった
微妙に検索結果のレイアウトが変わったなぁ。
一番下に"絞り込み検索"があるけど、前からだっけ??
2007-04-29
2007-04-30
■件数少なすぎて……
「を」を「wo」と発音している友人がいて驚きました。
http://q.hatena.ne.jp/1177859194
興味あり。
では早速「地域」でクロス集計。
……これじゃ何も判らないよ。
もう少し早く気がついていれば乗っかったのになぁ。残念。