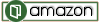2007-03-01
■リッツ・カールトン・ミスティーク
ざっと検索してみたら、「神話のような体験」だとか「神秘性」とか出てくるけど、「職人さんの持つ魔法の様な手」の様なニュアンスなんじゃないかと思ってる。
「ふわふわの泉 (ファミ通文庫)(野尻 抱介/御米椎)」のp152
それは老練な修理工の「これで大丈夫、前より丈夫になった」と同じ、技術者だけが持つ魔法の言葉だった。
てな感じ。
2007-03-02
■そんなサイトがあるなら
落ち着いている・洗練されている・見やすいと感じる『携帯サイト』のアドレスを、1回答につき2つ以上教えてください。
わりと堅めのサイトを見てみたいと思っています。
http://q.hatena.ne.jp/1172818840
「洗練」は『携帯サイト』の真逆だと思うけど*1とりあえずウォッチ。
■『1=0.9999…… ?』シリーズ 『n + 1 を n で割ったら、答えは 1あまり1 になる』
「1/3 は 0.3333……っていう循環小数になるだろ?
これに 3 をかけると、0.9999…… ってなって 1にならないじゃん!?」
「ん? それがどうかした?」
「どうかした? って、だって、おかしくね?」
「ふーん……、1÷3×3=1だから、0.9999……は1以外の何者でもないはずなんだけど、なんか納得できない、と」
「そうそう」
──
じゃあさ3進数で考えてみよう。10進数でいう1÷3は、3進数では1÷10で、0.1だ。
3進数での3は10だから、0.1×10=1だ。どこにも不思議はない。
そんなのは当たり前だって?
じゃ次だ。
10進数の0.5×2=1。これをやろう。この式自体はokだよな?
0.5は1÷2のことだから、3進数で書くと……(筆算をしている)……となって、0.1111…… という循環小数になる。
2は3進数でも2だ。
つまり、0.1111…… ×2=0.2222…… となるんだ。
で、さっき0.5×2=1だってことはちゃんと確認したよな?
だったら、この式の右辺は「1以外の何か」だとは言わないよね。
……まだ納得してないかな。
そうだなぁ……。
(n + 1)進数で、1/n を小数点表示すると必ず、0.1111…… という循環小数になる。
これは宿命だ。
なぜかというと、「(n + 1) を n で割ったら、答えは 1あまり1 になる」からだ。
いいかい。
今、当たり前すぎることを言った。
当たり前のことを当たり前だと捉えただろうから、もう一度言うよ。
──
「n + 1 を n で割ったら、答えは 1あまり1 になる」
それがさも秘密の呪文/真理の扉を開けるキィワード/人を魅了する悪魔の声/世界に潜む深奥なる秘境であるかのように、静かに、ゆっくりと、けれど確実に発音した。
──
1÷n を筆算することを考えてみよう。
1の位に1がある。当然 n での商は立たない。この時にどうするかというと、「左に0があると見なす」わけだ。
そうすると"10"を "n" で割ることになる。
(n + 1)進数でいう"10"は n + 1 に他ならない。これを n でわると、小数点以下第1位に商として1が立って、そして 1 が余る。
この余った 1 を n で割ろうとすると?
そう、さっきの手順の繰り返しになる。
だから、
0.1111……
という「永遠に終わらない手順」の繰り返しになるんだ。
10進数での1/9
3進数での1/2
これらは0.111…… としか書き表せない。
でも (n + 1)進数を n進数に、基数を1つずらすことで全て 0.1 ということになる。
表記の基数を変えているだけの話だから、この2つの表記は「同じ数を指し示す」と考えるのが妥当だ。
1と0.9999……も同じように、表現が違うだけであって、同じ数とみなすのが妥当だろう。
それが嫌なら、「数を表現する方法」としての「循環小数」という道具を、一切否定し絶対に使わない、とすることだね。
でもそれは不合理だ。
だって『数』そのものに問題があるわけじゃなくて、『数の表現方法』についてまわる問題なんだから──。
『1=0.9999…… ?』はシリーズです。
■ジャンルとはファセット分類
小説や音楽にとって、ジャンルとははてブのタグのようなものであると思う。
具体的に記述すると、こんな感じになる。
(略)万来堂日記2nd - ジャンルとは はてブのタグのようなもの
[ミステリ][日常][学園]
「秋の花」(北村薫)
あぁ、なるほど。
いいなぁ。
私なら、
[ミステリィ][日常][物語のない物語][涙が出た]
「秋の花」(北村薫)
てな感じかな。
「ミステリ」と「ミステリィ」をシソーラスとして見ると、共通する分類が2つ、という評価か。
蔵書データベースを作りたい欲求というのが年に1回ぐらい出てくるけど、これを読んでそれがきた。
うぅむ。
*1 全くのイメージ。だって携帯電話持ってないし。
2007-03-03
■沈黙のフライバイ
読了。
「SF……だよなぁ」
読み終わって、地下鉄から降りて、まず心に浮かんだのが上の言葉。
SF……、そう、間違いなく、SFだよな。
でも何かが、引っかかる。
Sense of wonder.
もう、SFにwonderはない、と最近どこかで読んだ。うん。確かに、これを読んでいてwonderを感じたりはしなかった。
でも、ワクワクするような高揚感はある。
うん。高揚感。それだ。
何かを作る。作りたいと思う。設計する。そこにある高揚感。
作り始める。苦労する。でも形ができあがり、もうすぐ完成する。そこにある高揚感。
《ここ》にあるのは、そんな気持ちだ。
登場人物は皆ワクワクしている。何かに高揚感を感じている。
そんな様子を読む。だから、こっちもワクワクする。……「だから」は間違いか。
読む側に、それにシンパシィを感じるものがある。だから、一緒にワクワクする。
p215
「できっこないですか?」
これが爆弾になった。
審査員たちは急に真顔になった。アイデアを評価するとき「できっこない」は禁句だった。
これも気持ちよい。アイデアを生み出すのは難しい。あるいは定式化した手順を作れない、と言い換えてもいい。
でもアイデアを殺すのは簡単だ。文字通りの殺し文句(アイデアキラー)がある。
「そんなのできっこない」
ただそう言えばいい。
でもこの本に出てくる人はみな、それを言わない。それを言わないことが先に進める道だと知っている。
これもまた心地よい。
ワクワクできる何かが提示される。それに対して「できっこない」と口にせずに真剣に検討をする登場人物たち。
その姿にも、「こうありたい」と願う気持ちとともにシンパシィを感じる――否、感じたいと思う心の動きが生まれるのだろう。
この本は、間違いなくSFだ。
Sense of wonder.ではない。でもそれでもなお「ワクワクできるものがまだ残っている」。それを夢見させてくれる。
それが、これからのSFが担う位置なのかも、しれない。
蛇足
そして、読み終わった時に感じるのは軽い喪失感。
何かができあがったとき――2000ピースのジグソウパズル? 精緻な模型? プログラミングをしていて「これで自分にとって必要な機能は完全に揃った」と感じた瞬間?――に感じるのにも似た軽い喪失感。
だから、読み終わった時に、何かぼうっとした、そんな感じを持った。
■ヤチマ
少々古い話題ですが。
話の流れと訳者後書きを読む限り、ヤチマのジェンダーは間違いなく女性です。女性ったら女性です。
Note - 雨のち晴
ということなら納得できます。
私も最後のシーンの手前で同じことを思ったからです。
が。
その次の瞬間、つまり最後のシーンで、あぁそういうことじゃないんだとも思ったのです。
「種の次の世代を残す」という事象に(聖母信仰に見られるような)女性原理を見てしまうのは、読んでいるこちら側がそうだからという理由からであって、ヤチマたち――ヤチマが筆頭に出てくるのは"孤児"だから――のメンタリティにはそういう原理はないんだろうな、と。
そこまで書くのが面倒だったわけですけどね。
■世界樹の迷宮 ゲームを探索する面白さ
今までちっとも書いてなかったけど、この1週間ちょっと、
で遊んでいる。
これはなんだろう? というのを「発見」する楽しさがあったり。
「CUSTOM」で未修得のスキルを選択すると、取得に必要な条件が表示される
まんぷく::日記 - 世界樹の迷宮・知ると得するこんなこと
とか、
一方、FOE接近メーターは自分の場合、なぜか説明なしでそういうものだと理解していた。
まんぷく::日記 - 世界樹の迷宮・知ると得するこんなこと
とか、
なお、コマンド選択時のAボタン押しっぱなしでは、直前のコマンドが再度入力されるようだ。
まんぷく::日記 - 晴れ
ですよ。
私はFOE接近メーターは、「あれ? これなんだろう?」と思って、もしかして場所に反応するレーダーだろうか? と思ってわざわざ戻ってみても再現しない。
説明書に……書いてない。
じゃあ、そのうち判るだろ、と思ってとりあえず放っておいて、果たしてそのちょっと後に気がついた。
そういう面白さがあるのですよ。
というか、いずれどのようなものであれゲームはそういう要素を持っているのだけど、そういう"気づき"がゲームを長く遊ばせる要素でもあるのではないか、と。
グランディアの攻撃方法が2種類あるとか、そういうことを理解してないと相手に攻撃されるばかりで自分の番が回ってこない/飛ばされるというイライラを味わう羽目になる。
でも、ある時点で、そうか! これはそういうシステムなのか! と気がつくと戦闘に対する認識ががらっと変わる。その変化は瞬間的で、かつ大きい。
そこから後のプレイ感覚を180°回転させるような、そんな体験をするとそのゲームに対する愛着とか評価とかが格段に上がる(あまりにショックが大きいと下がるけど)。
「世界樹の迷宮」は、「とにかくチュートリアルが豊富な最近のゲーム」らしくなくて、そういう楽しみを持っていると思う。
これから先にどんなことが待っているか、楽しみなのだ。
2007-03-05
■快適に仕事をする101の方法
「仕事」とは書いてないけど意訳するならこうかなぁ、と。
さすがに101個もあると……、半分ぐらいで力尽きた。
9. Stay visible – As a leader, you need to be visible in good times, as well as when there are problems to address.
見えるところにいなさい。
単純だけど、なかなかできてないんだよなぁ。上司とは、なかなか捕まらない人のことを言うんじゃないかというぐらい捕まりにくい。
17. Creative Solutions: A Japanese story – when a little girl kept wearing the wrong shoe on the wrong foot, her parents found a solution. There was half a smiley face on either shoe. The smiley face was complete only when she wore her shoes the correct way. Problem solved. It can be as simple as that if we use our creativity.
創造的な解法を。
Lifehackerにも引用された。
靴を逆に履く子供のために、靴にスマイリーマークを半分ずつ書いた。
スマイリーマークが正しくなるために、靴を正しく履くようになる。
という話。
18. When you pressure your team to deliver faster than is humanly possible, don’t be surprised to see a poor quality, bug-laden product.
殺人的なスケジュールをチームに押しつけると、ひどいクォリティの、バグをどっさり積んだ製品を見る羽目になるが、驚いてはいけない(=それが当然だ、ということだろう)。
■はてなブックマークの注目エントリーから外されてる
まただ。
注目エントリー、
http://b.hatena.ne.jp/entrylist?url=http%3A%2F%2Fmateria.jp%2F
に、
がいない。
http://b.hatena.ne.jp/bookmarklist?url=http%3A%2F%2Fmateria.jp%2F
と注目エントリーを比べると判る。
「あるロジック」でSPAMと判断されると、はてなブックマークの注目エントリーに入らなくなるのだな*1。
ここは日記形式で、ある日の分のtitle要素には先頭3パラグラフ分を連結して出しているという事情がある。
ブックマークへのエントリを自分で見つけたら、即自分でブックマークをしてタイトルの編集をする行為がSPAMに判断されるのだろうか?
次に注目エントリーに昇格するエントリが出てきたら、もう一回はてなに連絡してSPAM判定を解除してもらもう。
あ、こういうのを「はてブ八分」って言うのだろうか?
■今の小中学生って大変だよね
自分が前に書いたことだけど、眺めていて思いだした。
あと、「オープンなブログは危ない」というのは同意できる面もあるけど、クローズドな環境に慣れてしまうと「ローカルルールが外でも通用する」という取り違えを起こす危険性を考慮するべき。
prima materia diary - 小学生向けのネットマナーってやつが問題なのですよ!
まだインターネットという言葉が第一義としてWWWを意味しなかった時代の話。
大学内のネットで、「ある歌の歌詞を知りたい」と書いたらすかさず先輩(だったと思う)にたしなめられた。
「オープンな場に歌詞を載せることは許されない。ここはまだ大学内で閉じているからまだよかったが、外(そと)にその様なことを書いてはいけないと認識しなさい」
というもの。
外(そと)と言っているのは、NetNewsの世界。要は fj のこと。
とまぁ、今考えてみれば、そういうことを高校までの間に教えられないで育ったわけだ。私は。
でも今はインターネットが発達して、WWWがあたり前の世界になって、さらにblogやプロフか生まれ、情報発信の敷居が下がった。
だから自分と比べれば、ずっと早い時期に高いリテラシが必要になっているわけで、子供にしてみればそういう話をされるのは実に鬱陶しいのだろうな。
これはもう世界の枠組みの方がそう変化してしまったのだから、仕方がないというかなんというか。
もう何年かしたら、その辺で口やかましく言うだろうけど我慢しておくれ、などと心の中で呟く小学生低学年の子を持つ私だった。
■ηなのに夢のよう
ミステリというのは、その面白い部分のほとんど全てが「無駄」で「無意味」なのだな。
そういう部分を削ぎ落としてしまうと物語として成立しないから、別の話題を必要とする。
そういう方向に進むと、どんどん鋭くなる。
ミステリの形を成すための部分が鋭利な刃物の様に――装飾を施された儀式用の剣と、斬るという目的に徹した刀を想像するといい――なる。
代わりに小説の形を成すための部分が装飾として豪華になる。
そんな状況なのだろうか、と想像する。
*1 注:これは憶測ではない。
2007-03-06
■16歳のセアラが挑んだ世界最強の暗号 からのパズル
うぅむ。面白いじゃないか。全体の話は読了時に書くとして。
1章で出てきたパズルが面白い
p23 (引用にあたり適宜改行した)
保険外交員のパズル――保険会社の外交員が住宅地にある一軒の家のドアをノックした。
女の人が顔を出したとき、外交員は尋ねた。「あなたにはお子さんが何人おいでですか?」。
「三人です」と女の人が答えた。
「お子さんたちの年齢は?」ともう一度外交員がきいたとき、女の人はそのあつかましさに頭にきて、答えようとしなかった。
外交員は自分のぶしつけさを謝り、子どもたちの年齢の手がかりになるヒントがほしい、といいだした。
「三人の年齢をかけると36*1になります」と女の人がいった(子どもたちの年齢は正の整数とする)。
外交員はしばらく考えていたが、しばらくしてもうひとつヒントを求めた。
「三人の年齢を合計するとお隣の家の番地になります」。
それを聞いた外交員はすぐに塀を飛び越えて隣家の番地を確かめにいった。
そして、もう一度戻ってくると、最後にもう一つだけヒントがほしい、といった。
「わかりました」と女の人。
「いちばん年上の子はピアノを弾きます!」。
外交員はすぐに子どもたちの年齢を知った。さあ、あなたにはわかるだろうか?
うーん。秀逸。
p31。地球に巻いたロープのパズル。要約。
地球の赤道にロープがぐるりと巻き付けられているとしよう。
ロープは環状になっている。
その長いロープをいったん切って、そこに長さ1mのロープを付け足す。
ロープはちょうど1m分長くなっているから、もう一度環状になるようにすると地表とピッタリではない。
では全体が地表から高さが同じになるように浮かせてみよう。
さて、地表との隙間はどのぐらい?
答えは読了時に……。
(2007/3/10 追記)
解答!
でも引用しないで書いてみよう。
1つめの問題
全部かけると36。
とりあえず素因数分解すると、2,2,3,3。
36を3つの因数に分解する。素因数分解ではない。
自明な因数1を考慮することを忘れないように。
1,1,36
1,2,18
1,3,12
1,4,9
1,6,6
2,2,9
2,3,6
3,3,4
となる。
次のヒントは「三人の年齢を合計すると隣の家の番地になる」だった。
1,1,36 → 38
1,2,18 → 21
1,3,12 → 16
1,4,9 → 14
1,6,6 → 13
2,2,9 → 13
2,3,6 → 12
3,3,4 → 10
ここからがエレガントだ。
隣の家の番地は何番だったのかが判らない。
だけどここで3つ目のヒントを要求した。
つまり、隣の家の番地を見ても子どもの年齢が判らなかったのだ。
この条件を満たすのは……、
1,6,6 → 13
2,2,9 → 13
これだ!
そして3つめのヒント。「いちばん年上の子はピアノを弾きます!」
「いちばん年上の子*2」がいるのはどれ?
2,2,9 → 13
これ。もう一方は年上の子が2人いる!
よって、2才の子が2人、9才の子が1人、が答え。
2つめの問題
およそ16cm。
地球のぐるりに1mのロープを足すと地表から16cm浮き上がる、が答え。
円周の長さは半径をrとすると2πr。
地球の半径――最初にロープで作った輪の半径をr、1mロープを継ぎ足して作った輪の半径をr'とする。
2πr' = 2πr + 1
となる。
2π(r' - r) = 1
r' - r = 1 / 2π ≒ 0.16
《半径の差》はおよそ16cm。
読後に書いたエントリはこちら。
■犯罪不安社会
これも未読状態で取り上げちゃう。
昨日のエントリで「ηなのに夢のよう (講談社ノベルス)(森 博嗣)」の読了というのを書いた直後に、これを手にするあたりがなんとも……まがいいというか悪いというか。
ある意味、強くリンクしてる本だ。
事件そのものではなくて、周辺がそこに共通項を見いだそうとしている。
「騒いでいるのは中心ではなくその周辺」というような感じの台詞が「η」にもでてきたはず。
p90
人びとは娯楽のごときものとして事件を消費した。
という言葉は、まさにミステリ小説に対する読者のスタンスに他ならない。「η」は――あるいは犀川や瀬在丸たちは――そのような「ミステリ読者」をあざ笑うかのように「事件」を軽々と飛び越える。その様な「事件」は中心ではない、と看破する。
「犯罪不安社会」を読んでいて、これ一体どういうシンクロニシティか*3と、薄ら寒くなった。
2007-03-07
■県民所得
1人当たりの県民所得は、都道府県ごとの雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計を人口で割って算出する。製造業の拠点立地や稼働が好調だった福島、千葉、三重などで県民所得が増加する一方、公共事業の減少から、高知、岐阜などで減少した。
Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 県民所得の格差、3年連続拡大…東京は沖縄の2・3倍
本社が別の場所にある企業の企業所得は、一体どの様に割り振られるのだろうか? と疑問を持った。
と書いておこう。
■シンクロニシティ
動作や描写におけるシンクロニシティが、視覚にもたらす効果を研究している人っているのでしょうか。
専門家や研究機関などを教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1173255407
……シンクロニシティって、どういう意味で使っているのだろう?
で説明されているような意味しか知らないのだけど……。
ウォッチリストに入れる気もしないのでトラックバック。
2007-03-08
■(消費者である)私
「『通販 キャンペーン』と検索したのに、キャンペーンを実施していない通販サイトの広告文が露出したら、(消費者である)私はどう感じるだろうか?」
「Web サービスの会員登録フォームにメールアドレスだけでなく、住所や電話番号を入力しなければならないとしたら、(消費者である)私は会員登録をするだろうか?」
Japan.internet.com Webビジネス - 「消費者は変化している」の大きな見落とし
「私は」の前に「(消費者である)」が一々入っている。
この書き方、案外応用範囲が広いかもしれない。
「○○の視点に立って考えろ!」と言われることは多い。○○はこの例の様に"消費者"だったり、あるいは"お客様"だったり、"サービス利用者"だったり色々。
応用範囲が広い、と言ったのは、
「△△だとしたら○○は××するだろうか?」
という形式の疑問を、
「△△だとしたら(○○である)私は××するだろうか?」
という形式に置き換えてみつめ直す、ということ。
あまりに多用するとウンザリするかもしれないけど……。
■縦列駐車のコツ
元は
である。左右が逆になるが訳する時点で読み替えておく。
1.左折信号を点ける。駐める場所の前の車の横で停止。前後は同じぐらい、幅は腕一本分ぐらい空ける。
2.左肩ごしに後ろを見る。ゆっくりとバックを開始する。それからハンドルを左に切り始める。左後ろの角を目指す。
3.運転座席が「前の車の後ろのバンパー」と並んだら止まる。ハンドルを、中央位置*1から一回転右に回したところまで戻す。「左のフェンダー*2」が、「前の車の右後ろのフェンダー」の位置に来るまで、その角度でバックを続ける。(ここで、「自分の車の右後ろのバンパー」が「後ろの車の左前のバンパー」の線上にある)
4.素早く右にハンドルを切って、駐車位置でバックを終える。この時は右肩越しに見ながら、後ろの車を位置合わせに利用するようにして運転する。あるいはバックミラーを使う。
5.真っ直ぐにするのに、ハンドルは中央位置から左側に一回転しておく。(??? before pulling forward が訳せない……)
なんか合ってる気がしないんですけど。
ペーパードライバーだから判らん。
(じゃあ訳すなよ)
via
■スパイラルという言葉を見たらマッチポンプと置き換えてみよう
「スパイラル開発」は別ね。
格差社会スパイラル → 格差社会マッチポンプ
治安悪化のスパイラル → 治安悪化のマッチポンプ
という感じ。
2007-03-09
■コマンドプロンプトのコードページをUTF-8にする
subversionのWin32コマンドプロンプトなんかを使おうとする。
標準エラー出力にでてくる文字はUTF-8でencodingされていたりするわけで、どうも都合が悪い。
そこで、コマンドプロンプトのコードページを変更する。
十分信頼がおける(例えばMicrosoftサイトの「公式な」ページとか)情報は得られなかったが、検索してみると、
chcp 65001
とするといいらしいことが判った。
日本語を書いたファイルを UTF-8 で保存。
typeコマンドで確認すると、確かに中身を読むことができる。
追記
subversion の件は全然別の問題だった。
tortoiseSVN をインストールしている環境では、そちらの iconv モジュールを見に行ってしまうということだった。
(参考: http://www.clip.gr.jp/~imai/PukiImaiWiki/index.php?Subversion または、Google で APR_ICONV_PATH を検索)
追記
会社のマシンだと確かにUTF-8のファイルが読めた(読める様に表示できた)のに、家のマシンだとうまくいかない。
なんか、もう少し知っておかなければならない条件がありそう。
追記
フォントが関係していたみたい。
フォントをあらかじめMS ゴシックに変更しておく必要がある、ということか?
コードページを変更した後にフォントを設定しても無効のようだ。
ちなみに日本語の(=変更前の)コードページは932。
■工場由来の食品には命は宿っていない
日経新聞の広告で見た。こんなアオリだった。
工場由来の食品には命は宿っていない
これを見て思ったこと。
命が宿っている食品とは、天然由来のものである。まるで同義反復の様だが元のアオリ――工場由来の食品には命は宿っていない――の対偶なだけ。私の意見ではない。
進化の過程で他の生物の補食対象にならないような進化をしたものもある。
フグ、鰻の血、トリカブト、漆の表皮、etc...
命が宿っているもの。それがすなわち食べるのに相応しいと言えるか?
言えない。
フグの肝を、「命が宿っている」からといって食品とするのか。
鰻の血に含まれる毒は熱に弱い。だから焼くなどして食する。
それは宿している命を「殺す」ことに等しい。でもそうしないかぎり、食品として相応しいものにならない。
食品として相応しいかどうかの基準に、天然由来か工場由来かなんていう尺度を持ち込むなどナンセンス。
最初に挙げた本を読んだわけではないので、この本が「『工場由来の食品には命は宿っていない』から食品として相応しくない」と主張しているのかどうかは判らない。そこはご注意を。
でも多分そういう主張をしているのだろうなぁ、とも思ったけど。
■キーボード偏愛主義 Vista編
で書いたことがVistaで通用するか確認。ちなみにBusiness Edition。
クイックバー(クイック起動)を操作する
(XP) Windowsキー → Tab
(Vista, XP) Windowsキー → Esc → Tab
でフォーカスが移動
そのあとは左右カーソルでアプリケーションを選択して
- Enter, Space → 起動
- アプリケーションキー, Shift + F10 → コンテキストメニュー表示
Vista になって Windowsキーのあとの Esc が省略できなくなった。
なぜかというと、Windowsキーでスタートメニューを開いた状態で Tab キーを押すとスタートメニュー内部のフォーカス移動に変わったから
以下、同様のことが続く
タスクバーを操作する
(XP) Windowsキー → Tab → Tab
(Vista, XP) Windowsキー → Esc → Tab → Tab
でタスクバーにフォーカス移動(クイックバーがある時)
そのあとは左右カーソルでアプリケーションを選択して
- スペース, Enter → そのウィンドウにアクティブにする
- アプリケーションキー, Shift + F10 → コンテキストメニュー表示
タスクトレイを操作する
(XP) Windowsキー → Tab → Tab → Tab
(Vista, XP) Windowsキー → Esc → Tab → Tab → Tab
でタスクトレイにフォーカス移動。そのあとは左右カーソルでアプリケーションを選択して
- Enter → 左ダブルクリック扱い
- Space → 左シングルクリック扱い
- アプリケーションキー, Shift + F10 → コンテキストメニュー表示
デスクトップにフォーカスを移す
(XP) Windowsキー → Tab → Shift+Tab → Shift+Tab
(Vista, XP) Windowsキー → Esc → Shift+Tab
でデスクトップにフォーカス移動(クイックバーがある時)
カーソルで選択アイコンの移動
エクスプローラと同じく Ctrl + Space で選択で、Ctrl + カーソルで選択状態を変化させずにフォーカスを移動
- Enter → 起動
- アプリケーションキー, Shift + F10 → コンテキストメニュー表示
Windowsキー + D でもよい
ただ、Windowsキーが無いキーボードでもスタートメニューを開くのに Ctrl + Esc が代替えになることを知っていれば、このフォーカスの移し方は有効
マウス無し、Windows キー無し、クイック起動にデスクトップ表示のショートカット無し、という状況に陥ったときにこれを知らないとデスクトップの操作がなかなかできない
最大化,最小化
(Vista, XP) Alt + Space → X
(Vista, XP) Alt + Space → N
変化なし
シャットダウン系
(Vista) Windowsキー 右 右 右 U
(XP) Esc 連打 → Windowsキー → U → U
最後のストロークをS, R, H にするとそれぞれ、スリープ, 再起動, 休止状態、になる
ただし休止状態は使える様に設定していた場合のみ
(Win2000, XPで"ようこそ"画面なし) Windowsキー → U → 上矢印連打 → 下矢印 Enter
(Win9x系) Windowsキー → U → S
Meは知らない
これに慣れておくと、ディスプレイの故障などで画面が確認できない時でも困らない
この操作の前に Esc を連打しておくと高確率で安全にシャットダウンできる
ログオフ
(Vista) Windowsキー 右カーソル 右カーソル 右カーソル L
(XP) Windowsキー → L → L
ちなみにユーザー切り替えは最後のストロークを Vista なら W に、XP なら S に変える
ほとんど Windowsキー + L だろうし、滅多に使うものじゃないので覚えないけど
2007-03-10
■16歳のセアラガ挑んだ世界最強の暗号
読了。楽しんで読めた。
まず、残念ながら、ちょっとタイトルが悪い。
"挑んだ"が曖昧だし、語感も内容にそぐわない。
世界最強の暗号、とはRSA公開鍵暗号だ。知らなくても構わない。これまでの数十年に渡って暗号の中心的な存在であり続けた、偉大なものだということだけ分かればいい。
セアラは"RSA公開鍵暗号"に挑んだ。とはいってもそれの"抜け道"を探したとかそういうわけではない。
"RSA公開鍵暗号"に代わる暗号を考察し、まとめあげ、発表する。
そんな意味だ。
それが真に"RSA公開鍵暗号"と同じぐらい素晴らしいのかと問われれば、それを証明するには数十年に渡ってあらゆる検証をパスする必要がある、ということになる。
彼女は聡明にもそのことを――"世界最強の暗号に挑む"のがどういうことかを――正しく認識している。
読めば分かるのだが、タイトルからはどうもそのへんで誤解を生むような気がする。
また、この本は実は"数学"を楽しんだ少女の記録だ。
それもタイトルから判りづらい。
"暗号"が"数学"と密接な関係がある――というか現代では不可分であるということを知っている人ならいいが、そうでなければどうなるか。
そう。これは数学にまつわる本だ。数学の世界に飛び込んで、奮闘して、"RSAのR"と話をすることができた――そしてそのことに価値を見いだすことのできる――そんな少女の、数年にわたる日記。
各章のタイトルを挙げよう。
1 子ども時代
2 数学の旅
3 大事なのは残りもの
4 「法」の計算
5 一方通行
6 コンテスト
7 数学のあと、コンテストの余波(「数学のあと」に「アフター・マス」、余波に「アフターマス」のルビ)
3章、4章は数学そのものの話だ。興味のない人が読むにはつらいだろう。
ただ、「数学の理解」にはいくつかのステップがあることを知ってほしい。
この定理の証明は全く理解できない。けれど、それがどれほどに素晴らしいことを保証してくれるのか! それを考えるとワクワクする! というようなことがある。
この本で扱うのは、そのような数学だ。事実セアラは、学校の授業で言うなら行列すら勉強していない。そんなステップにいたぐらいだ(6章になって行列の理解を始めている)。
1章は彼女の生い立ちがざっと書かれているが、ここで退屈させるようなことはしない。いくつかの基本的な、あるいは本質に至る内容の、パズルを提示する。
それが楽しい(あ、もしかしてこの時点で読む人が篩い落とされるのだろうか?)。
で2つほど引用した。
第2章、第5章はコンテストへの参加を決意した彼女が、いきいきとして取り組む様を書く。
第6章でコンテストの結果が、そして、タイムズ、ロイターでニュースが発信されたことに端を発する狂乱の(?)日々が第7章で書かれる。
とにかく彼女の数学に対する姿勢が心地よい。
かくありたい。
能力や成果のことではない。
楽しいと思う知的好奇心。真摯な態度。自分が何を知っていて何を知らないかを知ること。
そういうことだ。
この本が書かれた時期は、今となってはちょっとした"過去の話"だ。
いくつかの記述は今ではもう古い(聡明な彼女は"現時点では"という但し書きを正しく使っている)。
数学への旅として読んでもいい。
ある少女の体験記として読んでもいい。
どちらにしても上等の本だ。
*1 今日時点での話。
2007-03-11
■ブランド
滞在時間なんてただの飾りです。スーツな人にはそれがわからんのです
404 Blog Not Found:Google AnalyticsのAnalysis、そして滞在時間のウソ
「Googleが提供しているのだから」という理由で信じてしまっている、という予測*1はどの程度当たっているだろうか。
*1 私の妄想ともいう。
2007-03-12
■集団痴
タイトルは語呂合わせなので気分を害されませぬ様に。
通例、"集団浅慮"という語が使われる様だ。
例えば。
複数人でおしゃべりしながら道を歩いている。
横断歩道。歩行者信号。
誰も赤信号だと気づかずに一歩踏み出してしまう。
車の流れに気がつき、慌てて戻る。
「他の誰かが信号を見ているだろう」という根拠の無い思いこみ。
「他の誰か」がいることによる思考停止。
例えば。
3〜4人で話をしている。
何か話を振ると、1〜2人が応じてくれる。
その時点で多数は、もしくは過半数。
話題に積極的に加わらない人も、まぁ、おとなしく聞いている。
ひとしきりその話題で盛り上がる。
そのうち別の話になる、もしくは取り残されている人に気を遣って別の話を振る。
ところが。
人数が多くなるとどうなるか。
少し"とんがった"話題を振って、他の1〜2人が応じてくれたとする。でも少数派。
残りの人を無視して、少ない人数で話を始めるか?
しない。
結果、当たり障りのない、大多数が加わることができる――けれども凡庸だったり内容が無かったりする――話題になる。
■集団知の逆を行く「他ユーザーの設定による回答拒否」というはてなの機能
集団知(Wisdom of Crowds)に関して書かれたごく初期のエントリを見る。
本書の主張は、ひとことでいえば、「適切な状況の下では、人々の集団は、その中で最も優れた個人よりも優れた判断を下すことができる」ということである。適切な条件とは、
H-Yamaguchi.net: The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business,Economies, Societies and Nations
(1) 意見の多様性
(2) 各メンバーの独立性
(3) 分散化
(4) 意見集約のための優れたシステム
であり、
はてなにて、このたび動き始めた*1「他ユーザーの設定による回答拒否」は(1)(2)(4)の点で逆をいく。
- 投票システムと見なした時に、投票できるのは「回避拒否」の票だけであるので意見の多様性はない。
- 他ユーザの回避拒否設定を、吟味なしに自分の質問に適用するのはメンバーの独立性とは反対の方向だろう。
- (分散化については原著を読んでいない私では、誤解をしそうなのでコメントしない)
- 自分を拒否している人が誰なのかが判らない。自分を拒否している人が、いったん拒否の票を投じたあとで自分のその後の回答、それ以外の回答見て票を取り下げるとは思えない。同じ人を拒否している人の間にもつながりがない。
から辿れるページをざっと見たが、こういう視点から書いているものが無かったので。
■トラックバックした先で文字化けしてる〜
知らないうちにRubyのiconvモジュールが入った(のではないかと思うが確認してない)のが影響しているか?
あとで調べなきゃ。
*1 今まで"動いてなかった"ことについてとやかくいうつもりは無いので、こんな表現。
2007-03-13
■桜
この友人に東京近郊の桜の名所に案内してあげたいのですが、どこがいいでしょうか?できれば、造られた人工的な風景でなく、日本の自然や里山や文化を感じてもらえる場所がいいです。
http://q.hatena.ne.jp/1173719160
基本的に株分けで増えるわけだから「人の手の入っていない」桜の名所なんてないんじゃないだろうか?
現時点でオープンになってないので、どんな回答が集まっているのか……。
■西松屋 効率主義・生産性の向上が「忙しくない店」を産む
今週号の日経ビジネス、西松屋の記事。
マタニティ用品、ベビー用品から子供服までをカバーする店。
面白く読んだ。
徹底した効率主義――"効率"を言い換えるなら"生産性"――が目指すのが、「忙しくない店」であり「パートさんにしっかりと働いてもらう」環境だという。
記事から
スーパーのレジ要員を考える。店が煩雑してくることを考えるとそれをさばくレジ要員が必要になる。
しかし、レジが混雑していない間は逆に仕事がなくて暇を作ってしまう。
店やレジが混雑する前は商品の入れ換えの必要なども少ないわけだ。
そして忙しくなるとレジに忙殺される。
その時に売り場に目を配る人が必要になり……という悪循環。
西松屋は「忙しくない店」を目指す。
レジが混んでくればどうしてもレジのヘルプは必要になるものの、しかしその間もパートに入っている人の半分は売り場の方に出ている。
店長の役割が明確に示されていて、それは「パートさんにしっかりと働いてもらう」のだそうだ。
前日のうちにパートさんの仕事の配分を30分単位で計画しておく。それが店長のmustの仕事。
パートさんには決められた役割というのはなく、一人で何役もこなす。30分単位でスケジュールが決められているというのは慌ただしいようにも思えるが、記事からはそのような雰囲気はない*1。
店長のスケジュール決定はまるでパズルの様だ、と書いてあった。そのスケジュールに「接客」という項目はない。
私の目から見て
実際、私は西松屋に行く機会が多いのだけど、確かに、同じ業種の店である赤ちゃん本舗とは、店から受ける印象が正反対だ。
西松屋は天井が高くて商品も高いところに並んでいる。
赤ちゃん本舗で高いところに商品があるのは、おむつとかチャイルドシートなどの"壁際"しかなく、他にはディスプレイだ。
西松屋はレジが2つしかない。それでも混んでいるときでさえせいぜい4〜5人だ。
赤ちゃん本舗はレジは4つ5つある。それでもずらっと10人程度全てのレジに並んでいることもある。もちろん空いている時は空いてるけど。
西松屋の服の売り場はすべてハンガーがけだ(これは今日記事を読んで気がついた)。
赤ちゃん本舗の服の売り場はハンガーもあれば、たたんで棚に並んでいるのもある(つまり、散らかったらたたむ手間がかかるわけだ)。
西松屋は店舗の構成がシンプルだ。入り口、横にレジ。店の手前から奥へずっと伸びている陳列棚が5列。棚に切れ目はなく、途中に通路もない。おそらくは同じフレームで、ハンガーかけや間仕切り、棚にする横板で商品のヴァリエーションに対応している。違う形の陳列が必要なものは、外周の壁に集まっている(例えば離乳食の様な小さい箱のもの)。
赤ちゃん本舗は店の中がゾーンで分かれている。棚に置かれたもあれば、円形のハンガーもある。布団のコーナーは大きな棚で、離乳食のコーナーには小さい棚だ。
西松屋にはポイントカードが無い。個人情報の登録が無い。ダイレクトメールも来ない。
赤ちゃん本舗はポイントカードが無いと買い物ができない。
ちょっとWebで検索
が見つかった。
姫路市にある本社から、レイアウト変更などの指示を全店舗にメールを写真付きで送れば、全国の店舗が瞬時にして模様替えを行う。
とあるが、記事ではさらに進んでいる手法を紹介していた。
あらかじめ決められたアングルで店舗内の写真をデジカメで撮る。
そして店側から電子メールで送らせて、一括でテンポの陳列などをチェックするのだそうだ。
そして、「陳列のプロ」が改善策を店に提案し、数日後に結果をまた電子メールで送らせる。
実際に足で見て回らせるよりも効率。
再び、記事から
この様な効率化重視の最たるものが、年商が3億を超えたら周辺に新店を出して客を分散させる、というもの。
そして思うこと
「効率重視」と言われると、「決まった時間にどれだけ仕事をこなせるか」が指標になり、時間単位の仕事がどんどん増えていくようなイメージがあった。
それが「間違い」だということに気づかされた。
「効率重視」というのは、つまり「自分がやるべき仕事」に集中できる環境を整えることなのだな。それが「忙しくない店を目指す」というのに繋がるんだ。
もちろん、残念ながら、西松屋に見ることができるのはルーティンワークということが前提にある「効率重視」だ。
日々刻々と状況が変化し、それに対応する仕事をしている人にとっては何をか言わんやって思うのだろうけど。
でも、例えば、
に「ルーチン」という章がある。ここでいうルーチンはこういうものだとされている。
一度だけ考え、何度も行動するための手段
「効率重視」
「パートさんにしっかりと働いてもらう」
「忙しくない店を目指す」
キィワードはこの3つだと、そう思った。
■Mind Mapping Tool
マインドマップを作成する上で便利なソフトウェアを探しています。
http://q.hatena.ne.jp/1173630834
が最強だと思うけど日本語書けない。
FreeMindで似非マインドマップを書くよりは、PaintShopProあたりを使った方がマシだと私は思う(今1,780円で買えるしね)。
テキスト検索できないのは難点か……。
■フォーカスが無くてもホイール
フォーカスがあるウィンドウではなくて、マウスカーソルがいる位置のウィンドウに対して、マウスホイールのメッセージをリダイレクトしてくれる。
便利。というか、昔使っていたマウスでは、デバイスドライバがやってくれた機能で、最近使えなくて不満だったものだ。
ところで、「マウスカーソルがいる位置のウィンドウ」と言った時のこのウィンドウは、広義のウィンドウである。
「タイトルバーがあってシステムメニューがあって最小化ボタンや最大化ボタンや閉じるボタンがついている」と普通に想像する「ウィンドウ」とはちょっと意味が違う。
このプログラムを起動して、エクスプローラを起動する(Windows+E)。2つのペインのどちらにもスクロールバーを出した状態にして実験。
左のペインにフォーカスがある状態で、マウスを右ペイン上に置いてホイールすると右ペインがスクロールする。
この2つは、WindowsAPIから見て「別のウィンドウ」だということ。そういう意味で広義のウィンドウと言った。
いやもうこれが使えるとなったら元に戻れないわ〜。
ソース公開あり。オープンソースにアラズ。
(追記)
今なら Ztop 1択。
■セクションのフッタを整理
セクションの下のフッタを出しているpluginを新しいものに変更。
追加アイコンを消して参照アイコンのみに。
MM/Memoを無くして、livedoorクリップを追加。
*1 まぁ、取材して書いているんだから、そういうマイナス面がもしあっても書かないだろうけど。
2007-03-14
■Webアプリケーションだけどローカル印刷したい
レンタルサーバーを使用したネットショップで、WEB管理ページに
商品登録を1品登録をすると、ローカルのパソコンから随時、
在庫管理用のバーコードが出力されるようなしたシステムは
無理なのでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1173834806
2番の回答に「ほう」と思った。
鵜呑みはできないし、悪用が怖いというのもあるが、検討に値すると思った(なのでメモ)。
2007-03-15
■法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります
承前
の続きっぽい。
都道府県庁のリンクについての原則・ポリシーを類型化してみたが、それとは別に、
リンク元のホームページの内容が、法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
という言葉が多いことを指摘した。
この文言はいったい何のためなのだろう……?
素朴な疑問
ナンセンス! ど断じることはたやすいが、まず疑問として形にしてみよう。
- 内容が「法令に反している」と判るサイトに対して、"リンクの削除をお願いします"という対応はおかしくないだろうか?
- 公序良俗に反するサイトからリンクされることに対して、"削除をお願い"するいうことはそこに何らかのリスクを考えているはずだ。それはどういうものだろうか?
- 実際にそのような"削除のお願い"というのは業務として行っているのだろうか? 書かれているものはただの飾り文句で、何もしていないということはないだろうか?
まぁ、こういう様な内容で過去いくつかのサイトに質問を繰り返していたりする。
その質問に対して得られる回答が──その組織の性質・規模に依らず──非常に類型的だな、と感じているのでそれについてまとめてみたいと思う。
危険な暗黙の前提
ここでまず1つ指摘したい──というか回答をいただいたところに再度指摘しているのは、とした方が正確か──のは「ホームページの内容が,法令や公序良俗に反する場合」という表現自体に、そのサイトが法令・公序良俗に反していることが一目見てわかるという暗黙の前提を持っているのではないかということだ。
甘い。
幼稚な1クリック詐欺のサイトならともかく、詐欺サイト(クレジットカード番号を盗もうとする目的で作られたサイトなど)が一見してそうと判る様に作るはずがない。
「その点についてどうお考えですか?」という文句で大抵再度質問するのだけれど、回答をもらったことは無い。
3つめの質問
3つ目の質問に対する回答の類型はいくつかある。
不適切なリンク設定があった場合に、利用者からお問い合わせをいただくことがあります。
この場合、明らかに不適切で誤解を招くようなリンクの場合は、サイト管理者にご説明し、削除するようお願いしています。
これはいいだろう。
機能しているといえなくもない。ただこのケースは非常にまれだ。
たいていはまた別の類型、
明らかに不適切で誤解を招くようなリンクの場合は、サイト管理者にご説明し、削除するようお願いすることがあるという姿勢を説明したものです。
というものだ。
……これは何の答えにもなっていない。会社でこんな説明したら怒られるぞ、きっと。
「なぜこのように書いたのか?」「私がその様に考えているからそう書いたのです」と答えているのも同然。
ひどいのになると「実際に削除をお願いしたことがありますか? ないとしたらこの言葉は機能していると言えるのですか?」という問いに、
リンクに関する姿勢・方針を表明しているもので、その機能は十分果たしていると考えます。
なんてのがある。
それは機能して当たり前。
自分たちの姿勢・方針を表明するという機能を果たしていない、なんてことがあってたまるか(あるとしたら「曖昧で誤解を受けかねない」表現の場合でそれでは、自分たちが削除をお願いすると表明しているところの「不適切で誤解を招くようなリンク」とレベルが一緒である)。
2つめの質問
この質問への答えの類型は非常にハッキリしている。
これは、法令や公序良俗に反するサイトにリンクが貼られたことにより、当該サイトと本サイトに関係があるような誤解を生じたり、信用・イメージの低下がご覧になった利用者に生じたりする可能性がある点から、注意喚起の意味で当該規定をサイトに明示しているものです。
……複数からの回答を適当につなぎ合わせてもそれっぽく見えるあたりが恐ろしいな。
それほどに類型化が強いということだ。
もう一つ、この回答の上に、
相互の了解無くして「リンク」できるという認識のない、インターネットへの理解が浅い初心者の方がいるため、
という様な言葉がつくケースもある。
この類型的回答に対する意見は簡単だ。
「ホームページの内容が、法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります」などと書く必要は無い。
「他サイトから本サイトへのリンクがあったとしても、そのリンクは本サイトが了承したものでない場合があります。当該サイトと本サイトとの間に何の関係・関連があるとお考えにならないでください」とそのまま書けば済むことをなぜ遠回しに書くのか。そもそも、「ホームページの内容が、法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります」と書くことで、利用者に「今ここにリンクがあるということは削除の依頼がなされなかったのだろう。だからきっと安全だ」という誤解を増やすだけではないか。
ということだ。
1つめの質問
この質問の意図はなかなか伝わらないことが多い。
私の書き方が悪い(というか意地悪?)なのだろう。
この質問はこういうことを意味していると、なぜか気がついてもらえない。
法令に反していると一見して判断できるサイトを見つけました。
そこに自分のサイトへリンクされていることが判明しました。
最初の対応として、
「リンクの削除をお願いします」
という連絡をするというのですか?
という意味なのだ。
「法令に反する*1場合などにはリンクの削除をお願いすることがあります」という言説は、「法令に反すると一見して判るサイトがあっても自分の所へのリンクを外してもらえればそれでいい」という態度を示してはいませんか?
ということでもある。
この指摘をした後に返事をもらった経験は皆無である……。
なんか結論めいたもの
こういうポリシーっていうのは、「こういうケースでこういう行動をします」ってことを書くものだろう。
他のサイトに書いてあるからってコピーしてくると、上の「1つめの質問」の項で指摘したように変な内容を取り込んでしまうことがある。
それだけならまぁ、まだいい。
「法令に反するサイトがあった時に、自分たちは『自分の所へのリンクを外してもらう』と依頼しますよ。それから先はしりません」という意味にとれますよ、と指摘しても何もしないってのは、自分の頭では何も考えていないんだな、とそう思うのだ。
たいてい、
実際はケースバイケースでの対応になるかと思います。
って回答が返ってくるわけで、それはつまり「ポリシーっていうのをなんだと思っているのさ?」ってことでもある。
だって、ケースバイケースになるなら、ポリシー(=原則)じゃないじゃん?
*1 ここでは「公序良俗に」を省いた方が、問題をよりクリアにする。
2007-03-16
■「素通り禁止」なんて3年越しの話題だよね
mixiの日記を読んでもレスを返さない、
いわゆる「読み逃げ」についてお伺いします。
http://q.hatena.ne.jp/1173981248
ま、はてなでアンケートをとったらこうなるだろうな。
とてもシンプルだったはずのhttp+htmlという、データ通信とコンテンツ記述のインフラが、完全にその当初の――および発展過程での設計の意図を超えて使われている、ということの一つのあらわれ。
「だいたい『読み逃げ』ってなんだよ」と(コメントにでてきているように)原理主義的に否定するのはたやすいが……。
「素通り禁止」なる概念を最初に見たのが2004年6月ごろ。
つまり「素通り禁止」を掲げる人は厳然として存在していて、それが正しいと――守らない人が常識的に間違いだと――思っている人も間違いなく、いる。
去年の9月にも、
こんなことを書いた。
なんでだろう?
「インターネットは怖いところだ、気を付けなさい」といつもいつも親や先生から言われる。
ついこの間も「携帯電話を持たせるときにはキャリアが提供しているコンテンツフィルタの登録をしましょう!」なんてプリントが回ってきたし。
図書館にいけば「怖いぞ!」と煽る本も山ほどある。図書館からざっと検索してると、
ITに殺される子どもたち
あなたは子どもをどう守りますか? 【情報社会の光と影-モラルとリテラシー】
ウェブ汚染社会
お母さんが安心して子どもにパソコンを使わせる本
親と子のインターネット&ケータイ安心教室
気をつけよう!ネット中毒
子どもと親と教師のためのサイバーリテラシー
なんて感じ。
で、Mixi のような半分閉鎖されたようなコミュニティに対して、現実以上に過大な「安心感」が生まれているのではないか?
自分の周りに近しい存在がいることが、マイミクシィという形で目に見えている。
それが「自分の周りにいる人はきっと自分と同じ考えをする自分に近い存在なのだ」という、盲目的で非現実的な過信を生むんじゃないか?
それが非現実的なのは、現実の友人関係を考えればすぐ判るはずなのに。
というかネットワークでの繋がりもまた現実の「人付き合い」だということを忘れてる?
インターネット(の中のMixiの様なスペース)は心地よくて自分に近しい――というのは大抵「自分に都合のいい」の誤認だろうけど――人たちが集まっていると思う人と、インターネットは怖いところだ、危険なところだと、盲目的にわめきちらす人と、さてどちらが現実を見失っているのだろう?
(追記)
「素通り禁止」ならこっちの方がよいか(ここにたどり着く前に目にしているはずだけど)。「3年越し」と書いたのはこのあたりから。
■なるほどこういう時にスクリプト言語なのか
Subversionのソースアーカイブの中に、toolsというフォルダがあってPythonスクリプトとかPerlスクリプトとか、Rubyなんかも入っていたりする。
例えばバックアップ用のスクリプト――最後にバックアップしたリビジョンより後の変更分を抜き出すなんていうもの――がPythonスクリプトだったり。
なんで? と思ったけど、後になって気がついた。
シェルによって違いが生じることがなくなるからだ。あるいは文字コードの問題なども回避できる。
なるほどねー。
2007-03-17
■初心者です
いや、初心者のする質問じゃないよ、それ……。
統計初心者です。重回帰分析をしたいと考えています。重回帰をする前に説明変数間に相関があるものを取り除きたいと思います。数値変数間および数値変数とカテゴリ変数(名義尺度の変数)間については、無相関検定(ピアソンの積率相関)をして判断しようかと考えていますが、カテゴリ変数間についてはどのように検定すればいういのでしょうか?調べたところ、相関比をみる、とか、分散分析をする等というのを見ました。分散分析をしようかとしましたが、その具体的なイメージがわかりませんでした。教えていただけるとありがたいです。
http://q.hatena.ne.jp/1174099101
2007-03-18
■ゲキレンジャー
初めて見た。
判りやすいなぁ。
メレの2面性が予想していたより可愛い。
■電王
最大の欠点は"子どもが主題歌を歌えない"。タイムレンジャーも近いものがあったけど。
2007-03-19
■科学とソフトウェア 永遠のβ版とリリース版
ちょっと引用が続くがご容赦を。
タイトルどおり、科学を永遠のβ版とみなすのだ。
404 Blog Not Found:科学=永遠のβ版
(略)
もっとも、実は科学の世界もソフトウェアの世界も、一つ小さからぬ共通の課題を抱えている。コーダーたちが「リリースエンジニアリング」と読んでいる問題である。
ソフトウェアとハックの喩えはなかなか良いものだと思いますが、非常に重要な違いがあることを忘れてはいけません。科学がソフトウェアと違うのは、「これがリリース版である」といった一方的な宣言が不可能である事です。
Skepticism is beautiful - 『404 Blog Not Found:科学=永遠のβ版』
「リリース版」宣言をした瞬間にそれは「ニセ科学」になってしまうのです。
「永遠のβ」であってもリリースエンジニアリングは必要だし、βX版(Xは数字、β1とかβ2とか)のことをリリース版と呼んでも差し支えないだろう。
nightly build と一線を画する意味での「リリース版」に違いはない。
後続のバージョンによって常に上書きされる可能性のあるリリース版、ってのはソフトウェアにもある。
厳密にはソフトウェアとは違うが、HTML3.0 なんてそうだ。
HTML4がでているけど、HTML2.0 や HTML3.2 は現在でも通用する(実際に使われるかは別の話だけど)バージョンだ。
HTML2.0 は後続のバージョンが出ても抹消されていないが、HTML3.0 は違う。
This document has been superceded.
HyperText Markup Language Specification Version 3.0
なのだ。HTML3.2 によって上書きされた、今はないことになっているバージョンだ。
例えばニュートン力学の「万有引力は質量に比例して距離の2乗に反比例する」ってのは、ソフトウェアの比喩で言うなら、
「すごく古いバージョンで限定された場面でしか使えないけど、使い所さえ間違わなければ充分役に立つし何より動作が軽い」
ってなところか。
いずれ上書きされてしまうバージョンかも知れないけど、まだ使える。
どっちみち比喩なんだし、「β版」と「リリース版」に区別を設けるとか、「リリース版」っていったらそれはもう変えられない/取り消せないバージョンのことじゃないか、とか言うことにあまり意味は無いだろう。
で、弾さんの「科学をハックする」という比喩だけど、これで頭に浮かんだのは、去年の「惑星の定義と冥王星」の話だった。
10年以上は前に知られていた(そういう意見が存在した)ことが、衆目に対して「リリース」されるまであんなにもごたごたしたわけだ。
それでいて面白いことに、「なんかよく分かんないけど科学者たちが会議を開いて突然そんなことを決めるのか!」というような反応を示した人が少なくなかったように思う。
やっぱり、ハックというのはそういうものをこよなく愛する一部の者の間でしか広まらなくて、結局「リリース」というフェーズが不可欠なんだろうな。
ハックとか、私家版パッチとか、そういうものがあったことを知らない人――知ろうとしない人にとっては「リリース」がイコール「真実になる瞬間」なのか。
だとしたら、まぁ、あんまり関わり合いたくはないわな。
■その"水"は重い?
ナノクラスターってなによ? -- 下の説明図が実にわかりやすいです。
檜山正幸のキマイラ飼育記 - 松岡農水相もなんだが、その“水”はなによ?!
この説明図を素直に見ると、「ナノの水」は「普通の水」よりも100倍比重が高いわけですな(この図が"断面"だと仮定すると1000倍)。
コップ一杯が10kgより重い!
そんなことしても何も変わらんって、基本的に水道水と同じだもん。
檜山正幸のキマイラ飼育記 - 松岡農水相もなんだが、その“水”はなによ?!
「水道水をそういう風にして飲む人はいない」ことがこの説明のトリックなのでは?
ならば、ここはやはり「水道水やミネラルウォーターを同じようにして飲むのと変わらん」かと。
■祝・数学ガール発刊披露!
結城浩の最新刊『数学ガール・ミルカさんとテトラちゃん』の紹介ビデオです。
結城浩のはてな日記
いきなり主題歌とか流れたり、ミルカさんやテトラちゃんがくるくる回りながら登場したらどうしよう、とか思った(嘘)。
いやめでたいめでたい。
これはかなり「画期的」な本になると思うので、すごく嬉しい。
2007-03-22
■文書フォーマット
メリット:初めての人でも書ける/読める
デメリット:「記述するべき事柄」から乖離したら役に立たない
後者の危険性を監視する必要があるということ。
■全数テスト以外の手法
http://www.jasst.jp/archives/jasst05w/pdf/S4-1.pdf
http://www.jasst.jp/archives/jasst05w/pdf/S4-2.pdf
http://www.jasst.jp/archives/jasst05w/pdf/S4-3.pdf
例えば、パラメータが4個あって、それぞれが {0,1,2} の3通りの値を持つとする。
全数テストをしようとすると\(3^4\)
のパターンとなる。
テストの「質*1」を落とさずにパターン数を減らそう、という話題。
S4-1.pdf が「直交表」「HAYST法」というものを、S4-2.pdf が「App-pair法」というものを説明している。S4-3.pdf が公開質問会。
基本的な考え方は、テストパターンの絞り込みを個人の know-how に依らないで行うもの、ということだろう。
先の例だと全数テストで\(3^4=81\)
パターンある。
現実的には、81回テストするのではなくてもっと減らしたい。その時に個人の know-how で"これとこれをやってこれはやらない"という判断でやると、
- どの程度ちゃんとしたテストなのか判らない
- 大事な組み合わせを抜かしていないかという不安
- ある機能について、ONの状態ばかりテストされていて、OFFの状態ではほんの少ししかテストされていない
なんていうバラツキがあったりする(あっても判らない。評価できない)。
そういう問題を排したテストパターンを作れますよ。と、そういうことだと認識した。
*1 こいつの定義が難しいわけだけどここでは直感的な解釈でスルーしておく。
2007-03-23
■顔とメールアドレスが一致しない
チームの元気度チェックなるものがあって、その中の1つの項目が「チームの中に顔とメールアドレスが一致しない人がいる」。
「顔」と「名前」じゃないんだなぁ。
■英語/中国語/ハングル版はWebじゃなくてpdfで
右上にある、Englishや中文、ハングルのリンクはhtmlページじゃなくてpdfだ。
なるほどそういう手もあるか。
図書館(のWebサイト)の場合、刻々と変わる情報を提供するのじゃなくて、利用の手引きを提供するというその一点に徹してもいいわけだ。
Webでの蔵書検索もあるけど、ここの部分で英語やハングルでの検索画面を用意するべきか? と問われれば「必ずしもそうじゃない」と思う。
図書館が管理している目録データは、蓄えている資料の2次データ――メタ・コンテンツ――だ。
その目録データは誰のためにあるのか?
図書館に行けば検索できる端末もあるし、Web検索も提供しているから勘違いしてしまうかもしれないが、目録データは司書のためにある。
利用者が検索によって目的の資料にたどり着けない時に、司書にはその利用者を適切にナビゲートするというミッションがある。
場合によっては、近隣の図書館や都道府県立の図書館に問い合わせして取り寄せる、ということだってする。
そうすると、資料自身は英語やハングルで書かれていようとも、その目録データは日本語での注釈が付随して然るべきだ。だって、司書のための情報なんだから。
そうすると、英語版検索画面です、ハングル版検索画面です、といって検索サービスをやろうとしても、目録データをそのまま出すことはできなくなる。
司書に必要な情報と利用者に必要な情報は確かに違う。
そこを意識して目録データを整備できるか? となると、難しいのだろうなぁ、と勝手に想像する(あくまで勝手な想像です)。
これからも今の状況のままでいいの? という問題提起がなされているかどうかも知らないけど。
でも、いっこうに更新されないままで日本語ページと乖離していく「英語ページ」を作ってしまうよりも、pdf という形式で情報を提供するという姿勢。
そうすることによって、ほぼ更新がないということがそれとわかるわけで、いっそ潔いなぁ、と思った。
■リアルタイム議事録
その方法は、リアルタイム議事録。Netmeetingなどを使って議事録ツールをシェアする。誰かが喋るたびに発言の概要を議事録として記録していく。
諸悪の根源は物理的:英語が苦手な人がいるミーティングの情報伝達効率を上げる方法
Googleライクなミーティングを、ってな記事で書いてあったなぁ。
A Google meeting features a lot of displays. On one wall, a projector displays the presentation, while right next to it, another projector shows the transcription of the meeting.
How to Run a Meeting Like Google
ここでは「リアルタイム議事録」という用語が創出された点に価値があるかと。
via
2007-03-24
■考えてみた 楽しかった
「完全な」乱数があるとする。
話を簡単にするために、0か1を生成する、としておこう。
そして「無限に長い」ともする。
さて、この「無限に長い0と1の列」の中には、0がn個続く部分列が「必ず」存在する。
nが100だろうと1000だろうと、10億だろうと、必ずそんな部分列が存在するわけだ。
……何で読んだんだっけ?
数学の本とかかな?
なぜそう言えるのか? は書いてなかった様な。
で、考えてみた。
分かった。
楽しかった。
2007-03-26
■しずるさんと無言と姫君たち
よーちゃんとしずるさんと、あの建物は一体?
ってーのがこのシリーズの「謎」なのだけど、けれどそれを本編中では追ってほしくないかも。
そういうのは他のシリーズを併読しているこちら側で受け止めて考えればいいことじゃないかな。
しずるさんには謎とも言えぬものをよーちゃんに説明してみせる安楽椅子探偵でさえあればいいし、よーちゃんもそのための情報提供者にして外部へと影響を与える者であればいい、と。
幕間にでてくるあの寸劇は、実はよーちゃんとしずるさんじゃないんでしょ。きっと。
2007-03-27
■なぜこの方程式は解けないか?
この題名だけから、ガロアを想像できる人はきっと数学が好きなんだろう。
ガロアの生前の不幸と、死後に認められることになるその業績から、今では「不滅の名」となっていることも、きっと知っているだろう。
……そうではない人向けには、サブタイトルの方がキャッチーな様に感じる。
読んでみて、想定している(であろう)読者層と、タイトルにギャップがあった。サブタイトルの方が、むしろ相応しかったのではないか?
ともあれ、筆者はガロアに大きな関心を寄せている。偏愛といってもいいぐらい。
9章あるうちの1章が、まるまるガロアの人生を詳細に浮かび上がらせることに使われている。
そして、その前の章で書かれるのはアーベル――ガロアに負けず劣らず不幸な人生を歩み、そして死後業績が認められた今一人の数学者――の人生。
アーベルからガロアへと連なる成果のうち、もっとも理解しやすいであろう命題が、タイトルになっている。
5次以上の方程式は一般に解法(解の公式)を持たない*1
というものである。
正確にはこれはアーベルが明らかにしたもので、ガロアが明らかにしたのはその一歩先、「解ける方程式はどのような形式でなければならないか?」ということ。
そこでは対称性――シンメトリーが大きな役割を果たしている。
それがサブタイトルになっている。
まず、シンメトリーが自然やパズル、絵画や音楽の中でどの様に見いだされるか、次に人間はどのようにシンメトリーを捉えるのかが書かれる。
その次に、数学における方程式の扱われ方、成果が書かれる。
2次方程式の解法――解の公式を憶えさせられた記憶を持っているだろう。
3次方程式、4次方程式までは解の公式が導き出される。
実はそこまででも幾人かの運命的な数学者のドラマがある。もっとも本書を通してみると、アーベルやガロアのいわば前座に見えてしまうのだが。
数学者たちの苦悩はそこから長くに渡り続いた。
そして綺羅星のごとくアーベルやガロアが数学史に登場する*2わけだが、実は方程式の解についてはそれよりもずっと昔に、ある1つの証明が与えられている。
n次の方程式はn個の解を持つ
である。
ちょっと整理すると、「n個の解を持つと言えるが、けれども解けるとは限らない」ということの証明をアーベルやガロアがやってのけたのだ。
そんな話で終わってしまったら、この本はここまで厚くはならない。
それにそもそも筆者がこうまでガロアに魅了されたとはとうてい思えない。
この本の主題は、その過程でガロアが見いだした「群」という概念の素晴らしさ、凄さを伝える、というものであろう。
そしてそれを伝えることで、ガロアがどれほどの非凡な才能を持っていたか、どれほどの「発想の飛躍」を成し遂げたのかを描き出したいのだろう。
事実「群」についての説明がなされたのち本書の内容は、科学・数学の恐ろしく広い範囲を跳び回る。
ユークリッドの「原論」から非ユークリッド幾何学へ。
ニュートンの「プリンキピア」に始まり、特殊相対性理論から一般相対性理論、量子論・クォークの説明からひも理論・超対称性へ。
生物学から心理学、音楽からカノンへ。
対称性というキィワードを武器に、それらの間を縦横無尽に駆け回り、なぎ払っていく。
あまりに話題を広く取りすぎていてその様は若干あざとい感もある。1つの原理からなる論が全てを説明してしまう、というイメージは一種似非科学的でもあり「ちょっと話広げすぎじゃないか?」とも感じる。
が、そうは言いつつも痛快で蠱惑的なことは否定できない。
夭折した悲劇の数学者が切り開いた、「群」という沃野。その広がりを楽しむもよし。
逆に、これほどの成果を成し遂げた数学者のその人生に、歴史の不可思議さを感じるもよし。
追記
書き忘れた。
この本は、アーベルやガロアによる証明の理解にはつながらない。
群に関しても、雰囲気に触れることはできるだろうが、そこまで。
数学史の本、といった雰囲気であって、数学の本じゃない。
「学習したい」人向けに書かれたものではないので、まぁ当然といえば当然。
追記 2012/05/01
ちゃんと数学的に学習したい人向けには、
をお奨めする。
発売前だけど断言してお奨めできる(なぜってレビュワーなので)。
1章を読んだ時点でこれはすごい本だと確信できた。
乞うご期待。
■ちゃんと
書評になっているか?
■Vista風タスクバーポップアップ
未使用。
Alt+Tab を Vista風にするツールもあったけど、XPだとやっぱり根本的に「もたつく」感じがしたのだよなぁ。
こちらについてはメリットをさほど感じないので試すつもりはないけど、一応メモ。
■凄いバカなプログラムを作ろう に参加
凄い&バカなプログラムを作ろう企画。
きしだのはてな - 凄いバカなプログラムを作ろう
に乗ってみた。要Java1.4以上。
方針は「データをソートしない」。
public class Untitled1 {
static String[] nullMessage;
static String[] emptyMessage;
static {
int maxOfHashCode =
Boolean.valueOf(Boolean.TRUE.hashCode()>Boolean.FALSE.hashCode()).hashCode();
nullMessage = new String[maxOfHashCode+1];
nullMessage[Boolean.TRUE.hashCode()] = "nullです";
emptyMessage = new String[maxOfHashCode+1];
emptyMessage[Boolean.TRUE.hashCode()] = "空です";
}
public static void main(String[] args) {
print(null);
print(new int[]{});
print(new int[]{5});
print(new int[]{3, 2});
print(new int[]{14, 13, 71, 2, 24, 19});
}
static void print(int[] inputs) {
String nullOrEmptyMessage;
boolean b =
(nullOrEmptyMessage = nullMessage[Boolean.valueOf(inputs==null).hashCode()])==null &&
(nullOrEmptyMessage = emptyMessage[Boolean.valueOf(inputs.length==0).hashCode()])==null &&
(nullOrEmptyMessage=print(inputs, Integer.MIN_VALUE))=="";
System.out.print(nullOrEmptyMessage);
System.out.println();
}
/*minimumと同じ数があったら標準出力に書き出す
その影で「minimumよりも大きくてかつ一番小さい数」を探す
「minimumよりも大きい数」がなければ再帰終了*/
static String print(int[] inputs, int minimum) {
int nextminimum=Integer.MAX_VALUE;
for (int i = 0; i<inputs.length; i++) {
boolean b =
(inputs[i]==minimum && _print("" + minimum + " ")) ||
(inputs[i]>minimum && inputs[i]<=nextminimum && (nextminimum=inputs[i])!=inputs[i]);
}
boolean ref = (minimum != nextminimum && print(inputs, nextminimum)!="");
return "";
}
/*Syste.out.printのラッパー。返り値がbooleanなだけ*/
static boolean _print(String s) {
System.out.print(s);
return false;
}
}
■バカな点を自分で解説。
冒頭のstaticな配列と初期化子。
"nullです"と"空です"というメッセージを出すためだけに配列を使う。
Boolean.valueOf(Boolean.TRUE.hashCode()>Boolean.FALSE.hashCode()).hashCode();
Boolean.valueOfの中身の Boolean.TRUE.hashCode()>Boolean.FALSE.hashCode() は、Boolean.TRUE と Boolean.FALSE の hasCode() を比較。Boolean.TRUE.hashCode()の方が大きければ true に、小さければ false になる。
それを Boolean.valueOf(boolean) に渡して hashCode() を取ると、Boolean.TRUE.hashCode() と Boolean.FALSE.hashCode() の大きい方になる。
Math.max(Boolean.TRUE.hashCode(), Boolean.FALSE.hashCode()) で済むんだけどあえてバカさを狙う。
nullMessage[Boolean.TRUE.hashCode()] = "nullです";
で nullMessage[Boolean.TRUE.hashCode()] のところだけ代入しておく。nullMessage[Boolean.FALSE.hashCode()] はnullのまま。
printメソッドの中身。
boolean の変数を用意して、&& と || を使って条件分岐。
inputs がnull, 空の時だけ、nullOrEmptyMessageに文字が入って、次の行で標準出力に書き出す。
配列に値が入っているときはnullOrEmptyMessageは空文字。print(int[], int)の返り値が必ず空文字だから。
配列に値が入っているときは print(int[], int) の中で、小さい方から順に標準出力に書き出すというバカさ。各行の末尾に要らない空白が入っているし。
再帰を使っているけど、最初と最後の呼び出しが必ず無駄になるというバカさも持っている。
で、最後に改行を出す、と。
追記
そうそう。
Boolean.valueOf(inputs==null).hashCode()
を
Boolean.valueOf(""+(inputs==null)).hashCode()
と書き直せば1.3以前でもOK。さすがに見づらいので止めたけど(にしても、なんでBoolean.valueOf(boolean)が無かったんだ??)。
2007-03-28
■映画名言集
メモ。
"Rosebud."
『市民ケーン』(41)
みたいに、それだけをみるとホントに名言か? みたいなものもあるので、"映画史に残る台詞"という見方をすればいいのか。
……"Rosebud."にはビックリさせられたな。オチ(大まかな意味)をあらかじめ知っている状態で見てもやっぱりビックリ。
トップページはこれ。なかなかの労作。
時間があった時に眺めてみよう。楽しめそうだ。
2007-03-29
■ロケットガール
……えぇ、一瞬宇宙飛行士を思い浮かべましたとも。
"October Sky"(映画。邦題は「遠い空の向こうに」。"October Sky"は"Rocket Boys"のアナグラムになっているのに、なんともつまらない邦題を付けたもんだ)ネタのニュースだったのか。
目標がどのへんにあったのか? ロケットの機構は? とかそういうことが知りたかったけどこのニュースじゃ判らないなぁ。
科学誌とかで取り上げないだろうか(だれかタレコミください)。
関連
どれも名作!
■サイダースファンクラブ ほか
完結。雑誌の切り抜きで全部持っているので改めて読むのも……。
加筆はあるみたいだけど。
ちゃんと話が進んでいるようで安心。
むむ。
予想以上に面白かった。爆笑ってのではなくて、そこはかとなく面白い(褒め言葉です。念のため)。
なんか肩の力が抜けていて、ゆるーい感じが good。
2007-03-30
■Dihydrogen Monoxide
『ジハイドロジェン・モノオキサイド』という物質があり
http://q.hatena.ne.jp/1175180286
あぁっ!
このネタではてなアンケートを採るというのは思いつかなかった!
「これはやられた」と思った。
ただし、「知っている人は手を出さない」というバイアスがかかるので(例えば、私は回答していない)、アンケートの結果だけを取りあげて「言葉の上っ面で簡単に騙されるよね」という結論を導き出すのは良くないだろう。
このネタはDHMOで検索するといい。
Wikipedia の説明は始めにネタバレしてるのでつまらないんだよなぁ
ところで、
人間が大量に摂取すると中毒を引き起こし死に至る。
とあるけど、これは正しい。
最近ニュースになった。
米紙ロサンゼルス・タイムズによると、郡検死官が死因と断定した「水中毒」は、過剰な水分摂取により血中のナトリウムが薄まることで起こる。脳が膨張し頭蓋骨(ずがいこつ)を圧迫、発作を引き起こし、時には死に至る。
子供のためにWiiを… 母、水飲み大会で「水中毒死」|米国|国際|Sankei WEB
■統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか?
- 「平均」に秘められた謎
- 通説を疑う
- 経済効果を疑う
- もう統計に騙されない――統計のクセ、バイアスを理解する――
- 公式統計に表れない地下経済
の5章から成る。
1〜3章で本の半分ぐらい。4章で全体の30%弱。残りが5章。
一般教養的な「軽い読み物」として読んでいられるのは3章まで。
4章では、どの統計にどんなクセがあるか? が詳細に語られている。
ここは本当に統計に日常的に関わっていて「統計を読む」というスキルが求められている人でないと、しっかりと読むモチベーションは出てこないのではないか?
1章と2章は、簡単に言ってしまえば「痛快」さを読み手に与えるために書かれたのではないか? と思ってしまう。
統計に関しての知識など無くても、読んでいて面白いということだ。
ここでは、入り口は広く、を意識したのだろう。
3章後半から4章は先に書いたとおり、いくつもの既存の統計を丹念に見ており、テンポよく読むにはつらい。
けれどオビにあるように「統計センスを身につける」には避けては通れない難解さだとは思う。
5章は「公式統計に表れない」ものがテーマだから、既存の統計の具体的な数値からは離れて読み物に戻ってくる。
実質よりも上にバイアスがかかる統計、下にバイアスがかかる統計、といったクセがあることを教えてくれる。
それ以外にも、実際の動きよりも遅れて結果に反映される統計や、実際の動きよりも先に(!)結果に反映される統計があることが興味深い。
「実際の動きよりも先に結果に反映される」と聞くとそんなことがあるのか? と思うかもしれないが、(統計ではないものの)身近なところにそんな性質を持つものがある。
株式市場だ。
株価は将来を先取りして変化することが経験的に知られている(「株の先見性」と呼ばれるらしい)。
これは考えてみると、案外に当たり前のことだ。常に業績につられて株価が変化するならば、株で損をする人がいなくなってしまう。何せ、これから株価がどう動くかが業績から推測できてしまうのだから。
現実はそうではないわけで、つまり株価は実際の業績などよりも先に動く指標だと言える。
詭弁めいた話の展開になってしまったが、統計には、上下にバイアスがかかるもの、時間に対して前後にバイアスがかかるものがあること。
どのような統計がどのような性質を持つのか。
統計の母集団は何なのか。どのようにしてデータが集められているのか*1。
統計を「読む」にあたって、そのあたりを頭の片隅に置いておくことはよいことだろう。
そのあたりを一冊で知ろう、という向きであれば読んで損はない。
ただ、3章まで楽しめればいいや、と思う人も少なくないと思う……。
「株の先見性」については、
を参照した。
■String.class で Classクラスのインスタンスを指す様になったのはいつから?
Javaで「String.class」という構文でクラスオブジェクトを取得できるようになったのはバージョンいくらからですか?
http://q.hatena.ne.jp/1175215756
あ、回答できないや。ハッキリと判らなかったからいいけどね。
The Java Language Specification, Second Edition
http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/syntax.doc.html
では見つけられたんだけどな。
IdentifierSuffix: [ ( ] BracketsOpt . class | Expression ]) Arguments . ( class | this | super Arguments | new InnerCreator )
First Edition では見つけられなかった……。
なんで First Edition に文法定義をまとめて書いてあるセクションが無いんだろうか? 見落としているだけ?
■判りやすくてかつ正しい404ページを作れないある理由
ロリポップにはこんなページ
があって、これを設定すると見事404ステータスが返ってこなくなる。(それどころか.htaccessを上書きをしてくれるし)
こういうサーバレンタル業者とか、どの程度あるんだろう……。
違います。そのURIにアクセスした時に、Status 404がきちんと返ってくることです。
404 Blog Not Found:誤った404エラーページをつくるただ1つの方法
誤った404エラーページをつくるただ1つの方法、それはStatus 404を返さないことなのです。
ところが、未だにエラーなのにStatus 200を返すURIがあふれています。
……って、すでにコメント入っているし。
*1 このへんが5章のテーマ。