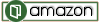2006-04-01
■エイプリルフール
ネタ準備してません。
■"100%植物由来成分"というオマジナイ
しかし"100%植物由来成分"というのも不思議な売り文句だと思う。
だいたい毒を持った植物なんていくらでも挙げられる。
トリカブト,ジギタリス,ベラドンナなんて有名所。煙草だって元は植物だし(というかタバコは植物名だ)ニコチンは"植物由来成分"だ。水仙なんかが毒草だという知っている人はどのぐらいいるのだろう?
それは本題ではなくて、"100%植物由来成分"という売り文句がどれほどアヤシゲなオマジナイなのか、そんな事例を見つけたのだ。
"100%植物由来洗浄成分"でかつ"ミルクプロテイン配合"なボディ・シャンプーっていったい……。
一瞬目を疑ってしまった。
追補
こんなページを見つけた。
2006-04-02
■ハチミツとクローバー 8
山田さんが野宮さんにさらわれた後の事務所での呑み会のシーン。「お赤飯の準備をはじめる姐さん達」のシークエンスがカットされていたけど、次の日にあゆのお父さんに手渡しているわけで、ということはちゃっかりお赤飯は作っていたのね〜。一回目に見たときには気がつかなかった。
竹本君がトンネルでトラックに追い抜かれるシーンが、下の子供(2才)に大受け。「キャハハハハハハ」とカン高い声で笑い転げてる。
なぜだ?
■惑星大怪獣ネガドン を見た
キッズステーションでうまい具合にやっていたので見た。
ほぼ最後のシーンで「第1宇宙速度」のランプが点滅するシーンは……。
別に要らないだろう。衛星になりたいわけじゃないし。
と、理性は言う。
おぉ、わざわざそんな計器を作ったんだ! 浪漫だなぁ。
と、特撮オタクの血が叫ぶ。
2006-04-03
■プルートウ
全部、発売直後に初刷りで買っているのだけど、今日まとめて読んだ。
今まで読まなかったのは、「地上最大のロボット」を読んでいないというのと、長丁場になりそうなのである程度情報量が高くなってから読もうかな、というカンが働いたのとの2つ。
この間「地上最大のロボット」を読んできたし、003 も買ってきたし、ということでまとめ読み。
で、思ったのはアトムへのオマージュというよりも、アシモフやハインラインなどの古典SFへの愛の方が強く感じられるなぁ、ということ。
あと、アトムが子供っぽくない。容姿とかの話ではなくて、「地上最大のロボット」での"僕も百万馬力の力があれば!"とかいったような子供っぽさのこと。
さて、続きも楽しみである。
2006-04-04
■新サーバー様 無断リンク禁止に対する教育委員会の無力さ
prima materia diary - 続々サーバー様 無断リンク禁止なのは学校・教育委員会の方なのだ
prima materia - diary : サーバー様そろそろまとめ
prima materia diary - 私がたどった路
の続き(はてなダイアリーで書いていた頃のエントリなので、正確にはちょっと違うが)。
あるいは、
からの続き。
仙台市民として、今年から子供を小学校に送り出す身として、人ごとではないのである。
なお、本webページへのリンクの問い合わせに関しましては、一切お断りいたしております。
仙台市立柳生中学校ウェブページ
なんて、何が言いたいのかすぐには判らないような文を平気でトップページに載せる様な学校にはうちの子供は通わせたくないのだ(いや、通うことになるわけではないけどね)。
"自由にリンクしてください。問い合わせは必要ありません"でいいじゃないか。
仙台市教育委員会に1月19日にメールした。内容を一部引用。
http://www2.sendai-c.ed.jp/~center/support/mail/info/rule1.htm
のURLにて「仙台市立学校におけるインターネットの利用に関する要領」という情報を公開し、これに則って運用されている様ですが、
--
第4条 学校長は,学校のホームページを開設する場合は,当該ホームページに第三者のリンクについては学校長への通知が必要である旨及び当該ホームページの複製につ
いては,学校長の承認が必要である旨明記しなければなれない。
2 学校長は,第三者より学校のホームページの複製の申出があった場合は,その使用
目的及び内容を検討し,教育の振興上の支障の無い場合に限りこれを認めるものとす る。
--
の部分について以下の様な疑問があります。どの様な判断からこのような要領が作られたのでしょうか?1.「第三者のリンクについては学校長への通知が必要である」とあるがこれはなぜか?
2.「当該ホームページに(略)明記しなければなれない」とあるが、明記しただけでは技術上全く抑止力は無い。それについてはどの様にお考えか?
それとも通知無しにリンクしているページを監視するなどの策を講じているのか?
3.http://www2.sendai-c.ed.jp/~center/school.htm
にあるような一覧のページが存在する以上、2.の様な制約に何の意味があるのか?
単純に上記の一覧ページのURLを提示し学校名を書いてしまえば、学校サイトに到達可能である。上記の様な一覧ページを公開している姿勢と、1.や2.のような姿勢の矛盾についてどの様に考えられているのか?
4.一部学校のサイトには「ただし,当該ウエブページが,教育目的性・非営利性・公益性を有しており,当該ウエブページにリンクを設置することにより,設置者や本校の児童,及び本校職員の個人情報が流出し,危害が及ぶ危険性がないと校長が認めた場合は,この限りではありません。」とあるが、「リンクの設置」と「児童,及び本校職員の個人情報が流出し,危害が及ぶ危険性」との間にどの様な関連があるのか?
リンクを設置しただけで「児童,及び本校職員の個人情報が流出し,危害が及ぶ危険性」が生じる可能性は、それはリンク先である学校にその様な危険性がある場合以外には考えられない。教育委員会ではこの様な基本的な部分でのチェックはしないのか?
5.ネットワーク上で http://slashdot.jp/article.pl?sid=05/10/30/0939232
の様な議論がされていることについて教育委員会の方では確認されていないのか?
6.平成10年から全く見直しされていないのか? この運用に則っていないかどうかのチェックはなぜされていないのか?
4.の様な明記をしていない学校もあるが、これはインターネットという世界を理解している先生がいらっしゃる学校であろうと思われる。その様な学校との間でこの要領について何も情報の交換など無かったのか?
そして、なんとなんと回答が返ってきた!
ちょっとびっくり。
北九州市教育委員会の方には、問い合わせフォームから同じ様な内容を出していたのに見事にスルーされてしまったという前例があるので返事があること自体、まだ少しは見込みはあると思っていいのか?
で、一部引用すると、
学校においては,学校と子どもたちを守るという
観点からこの要領を作成しており,お問い合わせの
「第4条」については,リンクを禁止するという
意味ではなく,教育的な配慮から,リンク元のホ
ームページの内容が,「法令や公序良俗に反する
場合などにはリンクの削除をお願いすることがあ
ります」から規定しておりますので,ご理解をいた
だきますようお願い申し上げます。
うーん。
だとしたら、各小中学校のサイトのトップページなどに「無断リンク禁止」とか「事前に校長の許可が必要」と書いてある実情と、運用規定の意図がずれているということになりはしないか?
と思うわけだ。
なので、
「教育的な配慮」という目的については理解しますが、
その手段として「リンクする際は校長の許可が必要です」と
サイトに載せる、という"手段"が完全に不適切です、と
申し上げているのです。1.技術的な不適切さ
無断でリンクをされたとしても、常時アクセス解析を適切に行い、
不審なアクセスが無いか監視していない限りは学校側がリンクに
気が付くことはできません。
(それとも実際に行っているのでしょうか? それならばいいのですが)
またリンクを中継する様なアプリケーションを間に入れることで
アクセス解析でリンク元を特定できないことが考えられます。2.法律的な不適切さ
「法令や公序良俗に反する場合などにはリンクの削除を
お願いする」とありますが、法令に反するのであればリンクの
削除ではなくてそのコンテンツの削除、サイトの閉鎖、
サイト管理者の検挙といった様な対策を求めなければ
なりません。その点についての記述が不適切です。公序良俗に反していても具体的に何らかの法令に反して
いなければ、リンクの削除を求めたところで、それに応じる
義務は相手側に発生しません。3.正しくないリテラシ
「無断でリンクしないでください、と書いておけばリンクは
されないだろう」というような、間違った認識あるいは常識を
児童生徒に与えかねません。4.著作権に関する間違ったリテラシ
著作権上、無断の複製などを行ってはいけません、といった
指導はあると思われますが、同時に著作権上「自由な言及・
紹介・参照が許される」という指導はないのでしょうか?
これはすなわち、Webを通じて公開したコンテンツは、第三者に、
言及(のための引用)・紹介・参照する権利が存在するという
ことです。
「リンクする際は校長の許可が必要です」と書くことは、それに
関する正しい知識から、児童生徒を遠ざけることになります。5.矛盾した対応
教育的配慮ということを考えるならば、
http://www2.sendai-c.ed.jp/~center/school.htm
の様なページが教育委員会の配下にあることは目的に
反していないでしょうか。
「法令や公序良俗に反するサイトからリンクされるリスク」を
想定するのであれば、容易に市内各学校のサイトのURLが
入手可能なこのページはそのリスクが大きくするだけだと
思います。6.リスクの想定
上記で勝手に書きましたが、「法令や公序良俗に反するサイト
からリンクされるリスク」をどの程度見積もっているのかが
判りません。
そのリスクが高いとするならば、学校がWebサイトを公開する
メリットと秤にかけなければならないはずです。
と返した*1。
このメールに対しては特に回答などは不要、新年度になっても何も変化が無ければまたサイトで言及するなりするかもしれない、とも付記しておいたので後は特に返事なし。
さて。
2006年1月20日時点で仙台市内の小中学校のサイトをチェックして、「無断リンク禁止」とか「事前に校長の許可が必要」とか書いてあったものをメモしておいた。
……で、4月3日時点で再度確認してみて、変化がないのは以下の通り。
新学期になっていくつかの学校は新年度になってリニューアルなどしているみたいなのに、この体たらく。ため息が出てしまうなぁ。今年度で何か良い変化があるとよいのだけど。
「無断リンク禁止」とか「事前に校長の許可が必要」といった文言を外したと思われる学校が5校ほどあったのは偶然なのか(それらの学校は以下のリンクには当然入っていないわけだが)。
立町小学校
南材木町小学校
荒町小学校
上杉山通小学校
連坊小路小学校
北六番丁小学校
中野小学校
東仙台小学校
小松島小学校
若林小学校
坪沼小学校
四郎丸小学校
旭丘小学校
遠見塚小学校
上野山小学校
福室小学校
北仙台小学校
鶴谷小学校
大和小学校
鶴谷東小学校
桜丘小学校
袋原小学校
古城小学校
西中田小学校
貝森小学校
幸町南小学校
広瀬小小学校
大沢小学校
秋保小学校
根白石小学校
黒松小学校
将監西小学校
将監小学校
泉ヶ丘小学校
長命ヶ丘小学校
鶴が丘小学校
南中山小学校
虹の丘小学校
館小学校
栗生小学校
北中山小学校
柳生小学校
西多賀小学校
上杉山中学校
五城中学校
五橋中学校
南小泉中学校
中田中学校
六郷中学校
七郷中学校
高砂中学校
岩切中学校
西多賀中学校
郡山中学校
中山中学校
山田中学校
桜丘中学校
中野中学校
袋原中学校
折立中学校
幸町中学校
広瀬中学校
吉成中学校
秋保中学校
七北田中学校
鶴が丘中学校
南光台中学校
南中山中学校
茂庭台中学校
高森中学校
南吉成中学校
松陵中学校
館中学校
広陵中学校
次。
じゃ教育委員会にサーバを納入したのはどこのベンダーだ?
そこのSEや営業はなんのアドバイスも無しか?
って話になるわけだが……。
broken link
broken link
broken link
broken link
broken link
broken link
broken link
入札の記録を漁るとでてくるのはこんなとこか。
- 富士通エフ・アイ・ピー(株)東北支社
- NECリース(株)東北支店
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
- テクノ・マインド(株)
- コムシス東北テクノ(株)
で、件名に「サーバ」という語が入ってくるのだけ見てみると、
- 富士通エフ・アイ・ピー(株)東北支社
- テクノ・マインド(株)
- コムシス東北テクノ(株)
の3つ。
富士通エフ・アイ・ピーは当然富士通の関連会社。テクノ・マインドがNECの関連会社で、コムシス東北テクノは日本コムシスの関連会社……だけどサイトのリンク集にNTTコミュニケーションズ株式会社が出てくるなぁ。
と、いうことで、富士通とNECとNTTコミュニケーションズがせめぎ合っていて、責任から「この運用規約おかしいのでは?」とか言ってくれる様な担当SE,営業はいないのだろうな。
さて、次の一手はどうするか……。
追記
長々と引用してしまったので書きたいことをすっとばしてしまったかな。
もしかして、「『リンクには許可が要ります』と書いておけば『悪意あるリンク』への抑止効果がある」と本気で教育委員会は考えているのでないか? という疑問と不安が残る、ということが書きたかったのだけど……。
■黄金比とフィボナッチ数列
実は、黄金比って結構昔から気になっていて・・・
U20プログラミングコンテストで成果を出したい d金魚による dKingyo Utility Toolkit 日記 - はてなに失望するトコロ・・・
という本があります。最後にはペンローズ充填からヒマワリの種子、パイナップルや巻き貝に表われる螺旋なんかに話が進みます。
「数学」が、「自然」や「世界」と無縁なものではないことを教えてくれます。
*1 私の考えだとこんな感じなのだけど、どこか変でしょうか?
2006-04-05
■例外を吐くコンストラクタって
このプログラムは"null"が出力されるのか、"not null"が出力されるのか?直感的には"null"になりそうだが、out of order書き込みの可能性を考えると、一概にそうとは言えないかもしれない。
lethevert is a programmer - Java : コンストラクタで例外
経験的にはnullだ。
早速実験。
public class ExceptionalObject {
public ExceptionalObject() {
throw new RuntimeException();
}
public int intValue() {
return 5;
}
}
public class Object1 {
public static void main(String[] args) {
Object obj = null;
try{
obj = new ExceptionalObject(); //例外発生
}catch(Exception e){}
if (obj == null) {
System.out.println("null");
}else{
System.out.println("not null");
}
}
}
結果は
null
次。
public class Object1 {
public static void main(String[] args) {
int i = 3;
int j = 0;
try{
j = (i++) + (new ExceptionalObject()).intValue();
}catch(Exception e){}
System.out.println("i="+i);
System.out.println("j="+j);
}
}
int の +演算子は左結合のはずだから、(i++)が先に評価される。
でも+演算子の右で例外発生。+演算子も=演算子も評価されないはず。
では(i++)はどうなるのか。これが(++i)なら4だろうと想像できるのだけど、さて?
結果。
i=4
j=0
i++によるインクリメントはちゃんと実行されている。
へー。そうなんだ……。
余談。
RuntimeExceptionではない例外を吐くコンストラクタ。
public class ExceptionalObject2 {
public ExceptionalObject2() throws java.io.IOException {
throw new java.io.IOException();
}
}
うわ。気持ち悪い*1。
public class Object2 {
ExceptionalObject2 obj = new ExceptionalObject2();
static ExceptionalObject2 staticobj = new ExceptionalObject2();
public Object2() {
}
}
とか書けません。
public class Object2 {
ExceptionalObject2 obj = null;
{
try {
obj = new ExceptionalObject2();
}
catch (java.io.IOException e) {}
}
static ExceptionalObject2 staticobj = null;
static {
try {
staticobj = new ExceptionalObject2();
}
catch (java.io.IOException x) {}
}
public Object2() {
}
}
と書かざるをえない。ダサダサ。
というかコンストラクタでRuntimeExceptionじゃない例外を吐く様なものを、クラスやインスタンスの初期化で書くのがまずい。
そんなことになったら、どっか設計がおかしいと思って見直すべし、だなぁ。
追記
public class Object1 {
public static void main(String[] args) {
int i = 3;
int j = 0;
try{
j = (i++) + (new ExceptionalObject()).intValue();
}catch(Exception e){
System.out.println("i="+i);
}
System.out.println("i="+i);
}
}
ってどうなるんだ? と思った。
i=4
i=4
だった。catchに入る前に i++ によるインクリメントされてるってことか。
■Palm TX買った!
英語デバイス初めて!
J-OS初めて!
ネットワークでHotSyncしたいのにマシン名が出てこない!
Linuxマシンの名前は出てくるのに?
初めてづくしだ〜。
ハードリセットだ〜。あはは〜。
*1 極端な形で書いたから気持ち悪いのであって、コンストラクタがIOExceptionなどをthrowするのは、java.ioパッケージなどでは当たり前の話。
2006-04-06
■検索語
「○○って検索語で来る人増えたなぁ。どっかで話題にでもなってるのかなぁ」なんて思うことがあったけど、よく考えたら「○○という単語で検索したときのページ順位が上がった」ということでしかないだなぁ、と思った。
それだけ。
2006-04-07
■私の見つけた宝物
読んだ。
そして、私は別の宝物を見つけた。いや、宝物へと続く道を見つけた、ぐらいか?
p4
「∞は無限大という数ですね」
「無限大は《数》じゃない。少なくとも普通は、数として扱わない。たとえば、実数に∞は含まれていない」
p16 の注釈
*2 数ではない∞が等式に表われている。このときの等号(=)の意味を考えよう。
なるほど、私の3/17の日記
にコメントをもらったのは、結城さんがこのお話を書いている途中だったからなのかな? と思った。
さて、p4 の「僕」の台詞が意味深だ。
少なくとも普通は、
とわざわざ制限したのは「僕」の知識に依るもの? だとしたら「僕」はかなりの数学好きなんだな、と思った。
「無限大」を「数」として取り扱う公理系が存在する。「そこ」では「無限大」も「数」の仲間だ。「そこ」は「無限大」という「数」が無限に存在する世界。「超現実数」という世界。
私の知識はそこまで。「そんなのもあるんだ」ぐらいしか知らなかった。
ところが、p27 「世界に素数がふたつだけなら」に入ったあたりで、私の頭の中は物語から離れはじめる。いや、過去に――去年の11月に――戻っていった。
p28
さて、2または3だけを素因数に持つ正の整数は、この和のどこかに必ず一度だけ現れるよね。
p29
「ふむ。素因数分解の一意性のことか。《すべての整数は素数の積で一意に書くことができる》ので、《世界に素数が2と3しかなかったら、5や7や10なんて整数はない》と言いたいんだね。(略)」
「全ての整数は素数の積で一意に書くことができる」
「素数は無限にある」
「素数の集合は可算無限集合である」
「『素数の集合』の部分集合の集合は、連続無限集合となる」
に繋がる!?
「『素数の集合』の部分集合の集合から有限の集合だけを取り出す。その元となる集合に含まれている素数の積を考える。それは自然数の集合になる」
そこまでは考えていた。
じゃ、余った無限集合の元は?
「『素数の集合』の部分集合の集合には無限集合が元として含まれる。それに含まれる素数の積を考える」
これは無限大に発散し、したがって自然数ではない。
と以前書いた。
「これ」を「無限大」という「数」だと捉えたら?
「超現実数」の世界では「無限大」という「数」は無限にある、という話は聞きかじりの知識として知っている。
もしかしたら、素数の集合に対して「無限大」という超現実数を導入したら、「無限大」という数は連続無限集合の濃度を持つ無限集合になるのではないだろうか?
ならば、実数の世界、\(\aleph\)
の濃度を持つ連続無限集合の世界に「無限小」「無限大」という超現実数を導入すると、その濃度は……一体?
さて、この道はどこに続くのか。
追記 2005.4.8
「無限大」という数は連続無限集合の濃度を持つ無限集合になるのではないだろうか?
と上に書いたがその補集合べき集合*1もまた「超現実数」であり……、「無限大」や「無限小」の濃度を考えることに意味はないことに気がついた。
「さて、この道はどこに続くのか」と締めたわけだけど、その道がどこに続くのかは知っている。
に、その答えはきっとある。
外出先で「テトラちゃんとハーモニック・ナンバー」を読んでいた最中に、「無限大」を「数」として捉えること、を思いついた瞬間、ぜひとも読みたくなって買ってきた。
著者に注目。「テトラちゃんとハーモニック・ナンバー」はLaTeXを使って書かれたものだけど、そのLaTeXはTeXから派生したヴァリエーション。この本の著者は、TeXの作者 Donald E. Knuth その人。
「テトラちゃんとハーモニック・ナンバー」の参考文献の[4]、『The Art of Computer Programming』もKnuth先生の著書。
結局、Knuth先生の後ろを追いかけているだけなのだな。
「至福の超現実数」を読んでみて目を剥いたのは下の文だった。
p142
2×π≡π+πを正当に証明できるけど、π+πを有限回の手順で計算できるとは限らないってことね。神様だけが計算を終えられるけど、人間にできるのは証明を終わらせることだけってこと。
理解するにはほど遠いのだけど、面白い本だ。
追記 2005.4.9
至福の超現実数を一読して、一日の時間が経った。あらすじらしきものをまとめられるぐらいには消化できたらしい。
ま、要するに、空集合φから出発して「数」という概念を厳密に定義しなおす、という小説だ。1や2といった日常的な数さえも自明ではないという所が出発点。
最初の日(第ゼロ日と表記されている)に0(らしきもの)が現れ、翌日には1(らしきもの)と-1(らしきもの)が現れる。その翌日には……、と続いていく。どんな自然数もいつかは姿を現わすのだろう。
それらの「数らしきもの」に推移律(x≦y かつ y≦z なら x≦z)が成立することを検証し、0(らしきもの)と1(らしきもの)の間が存在することを発見し……、やがて「数らしきもの」が本当に「日常的な数」の様な性質を持っているのか? ということを考えはじめる。「日常的な数」にある様々な性質が、「数らしきもの」でも成立することを証明していく。
そして、その果てに「実数」や「無限大」や「無限小」が姿を現わす。
で、ここにきて、
はおろか、
までもが、この小説と根っこのところで繋がっていることに気がついた。
11月から12月にかけて、「素数の集合のべき集合で自然数を表現する」とか「2のべき乗の集合のべき集合で自然数を表現する」とか、「自然数は有限の桁数で表現される」なんてことを考えていなかったら、今この本を読んでも(例え表面的なものであっても)理解が追いついたかどうか? 多分無理だったんじゃないか?
いやいや、11月から12月にかけてそんなことを考えていたからこそ、「テトラちゃんとハーモニック・ナンバー」を読んでいる途中で「無限大」や「無限小」にいたるモデルを想像することができたのだし、この本を読もうという決心ができたとも言える。
そう思うと、様々なことが「いいタイミング」で起こった結果として、この本に出会えたのかなぁ、などと考えるのであった。
追記
無限上昇螺旋階段付音楽室 は G.E.B. か、バッハの「音楽の捧げもの」の「螺旋カノン」を参考文献に書くべきだったのでは?
*1 「部分集合の集合」のこと。最初に書いた時に、誤って補集合と書いてしまっていた。
2006-04-08
■クイズです 5秒以内に答えてみてください
「ネクロノミコン」という書物は実在する。YesかNoか?
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
答えは「Yes」。元来は Cthulhu mythos に登場する架空の書物ではある。が、のちに何人かの作家がこれを著述するという仕事に挑戦している。それは確かに出版物、つまり書物として世に出ている。したがって答えは「Yes」。Amazon.co.jpでネクロノミコンや、Amazon.comでnecronomiconと検索すると何件か出てくる。
2006-04-09
■オーバーロードされた数学上の記法 再び
を読んで、\(2^{a}\) という数学上の記法が、3重4重にオーバーロードされているのが混乱を生んでいるのだろうか、とふと思ったので。
1.日常的文脈で。
\(2^{n}\) で、2をn個掛け合わせたもの。
つまり、
\(2^{n}~=~\underbrace{2~\times~2~\times~2~\times~...~\times~2}_{n}\)
ということ。
2.集合を扱っている時の普段の文脈で。
\(2^{A}\) でAのべき集合――部分集合の集合――のこと。
つまり、
\(A~=~\{1,~2,~3\}\) の時、
\(2^{A}~=~\{\phi,~\{1\},~\{2\},~\{3\},~\{1,~2\},~\{2,~3\},~\{1,~3\},~\{1,2,~3\}\}\)
ということ。
3.集合を扱っている時でかつ無限集合の濃度について語っている時で。
\(2^{A}\) でAの濃度を持つ集合のべき集合の濃度のこと。
例えば、
\(2^{\aleph_{0}}~=~\aleph\)
で、「可算無限集合のべき集合の濃度は連続無限集合の濃度に等しい」
ということ。
特に、2.と3.のオーバーロードがややこしい……のかなぁ? と思った次第。
■無限大の過大評価
まぁ、そうはいっても、という感じで、
に対する直接のコメントをば。
そもそも無限級数を考えるのに、「可算無限集合のべき集合」とか「可算無限集合」とかを持ち出す余地は無い。
だって、級数で取り扱う式――数列の各項を加算した式――は有限の項しか持たないのだから。
そのことを4ページ目でわざわざ「僕」が説明してくれている。
\(\sum_{k=1}^{\infty}~\frac{1}{k}\) と書くと、kを1から∞とまで変化させて\(\frac{1}{k}\) を足し合わせるみたいに読める。まぁ、そう考えても悪い訳ではないけれど、∞という数がどこかにあって、そこまで*1kを変化されるというのは正確な表現じゃない。
\(\sum_{k=1}^{\infty}~\frac{1}{k}~=~\lim_{n~\to~\infty}~\sum_{k=1}^{n}~\frac{1}{k}\)
ここで右辺を見る。出てくる式は「n個の項を持つ可算の式」だ。「n個の項」っていうのは――すごく当たり前の事だけど――「有限の項」だ。
\(\lim_{n~\to~\infty}\)
に惑わされてはいけない。nがどんなに大きくなっても「n個の項からなる可算の式」であることには変わりはない。いつか、どこかで、「無限の項からなる可算の式」になったりすることは、決してない。
だから、そもそも「無限集合」なんて概念が出てくる余地は、ない。
もひとつ。
\(~S_{2^{m}}~\geq~1~+~\frac{m}{2}\)
は、
\(~S_{1}~\geq~1~+~\frac{0}{2}\)
\(~S_{2}~>~1~+~\frac{1}{2}\)
\(~S_{4}~>~1~+~\frac{2}{2}\)
\(~S_{8}~>~1~+~\frac{3}{2}\)
を「一般化*2」した表現。
数列\(S_{n}\) の\(2^{m}\) 番目の項は\(1~+~\frac{m}{2}\) に等しいか大きい
と読めばいいのであって、ここでも無限集合だとかべき集合がでてくる余地は、ない。
*1 引用元では傍点による強調。あぁ、傍点使いたい!
*2 ミルカさんとコンボリューション 4章。
2006-04-10
■無限大の過大評価 再び
あぁ、今ごろになってROYGBさんが、「テトラちゃんとハーモニックナンバー」を読んでどう認識したのか、その思考がトレースできた(間違っていたらごめんなさい)。
p7で調和級数に対して \(S_{n}~=~\sum_{k=1}^{n}~\frac{1}{k}\)
という記法\(S_{n}\)
を定義した。もちろんこのnが取り得る値は自然数の範囲ということになる。
p14 で \(S_{n}\)
のうち、\(n~=~2^{m}\)
となる部分和だけを取り出して、その性質を考察した。
p15 で一般化して、
\(~S_{2^{m}}~\geq~1~+~\frac{m}{2}\)
とした。これは何かというと、
\(~S_{n}\) において、 \(n~=~2^{m}\) を満たす様な n と m について、\(~S_{n}~\geq~1~+~\frac{m}{2}\) を満たす
となるわけだ。
ところが、ROYGBさんは \(~S_{2^{m}}\)
という表記だけをみて勘違いしたわけだ。
これは、\(S_{a}\) という表記を、「自然数のべき集合」に対応する様に拡大するものだ
と。
ここから混乱を防ぐのに、\(S'\)
を、ROYGBさんが解釈したであろう意味で使うことにして書き直してみよう。
ROYGBさんは \(~S_{2^{m}}\)
という表記を見て、
\(~S'_{\phi}~=~?\)
\(~S'_{\{1\}}~=~S_{1}\)
\(~S'_{\{1,2\}}~=~S_{1}~+~S_{2}\)
:
:
\(~S'_{\{1,2,3,~...\}}~=~S_{1}~+~S_{2}~+~S_{3}~+~...\)
となるような \(S'_{a}\)
を頭に浮かべてしまったのではないだろうか?
ということ。
もちろん、「テトラちゃんとハーモニックナンバー」ではこの様な \(S'\)
が出てくる余地は無い。
その様な \(S'\)
を想像して、ROYGBさんのエントリを読んでみると……なんとなく言いたいことは伝わってくる。
\(S'_{a}\)
について考察してみよう。
\(S'_{a}\)
の a が取り得る値は「自然数のべき集合」の範囲だ。
「自然数のべき集合」の中には有限集合の元もあれば、無限集合の元も存在する。
a が「有限集合の元」の時のみ、\(S'_{a}\)
は値を持つ。
a が「無限集合の元」の時、\(S'_{a}\)
は値を持たず発散する。「僕」の言葉を借りれば「数として扱わない」ってことだ。
\(S'\)
は間違いなく、連続無限集合と1対1対応して考えるべき「もの*1」だ。
だけど\(S'_{a}\)
で、aを「無限集合の元」に限定すればそれは可算無限集合で、\(S'\)
も可算無限集合と1対1対応して考えることができる「もの」になる。
こんなところでどうでしょう?
■オイラーの定数
p34 にでてくる
文中で「僕」が研究してた《ずれ》
なんですけど、今なんとなく、
を読んでいたら出てきました。
p250
しかし,この数の正体はほとんど分かっておらず,無理数であろう,と予想されてはいるものの,それさえ未だ定かではない。
だそうで。
■入学式
子供の小学校の入学式だった。
子供達はみんなちゃんとおとなしく座っていて立派なのに対して、父兄席は(一斉に)ビデオカメラを持ち出したりひそひそ話をしたりで騒がしいこと。
……うーむ。
*1 適切な用語が思い浮かばない。
2006-04-11
■新機種プレスリリース
「FMV-DESKPOWERシリーズ」のラインナップを一新 : 富士通
「FMV-BIBLOシリーズ」のラインナップを一新 : 富士通
新機種発表のプレスリリースが火曜日っていうのは珍しいな。
Web上のプレスリリース更新よりも、週アスの記事の方を先に読んじゃった、ということになっちゃった。
週アスのサイトを見てみると……「今週のFocus」に載ったのは富士通だけで、こっちの
個人向けパソコン「VALUESTAR」「LaVie」新モデルを発売(2006年 4月11日): プレスリリース | NEC
NECの方の記事は載っていない。
と、いうことは、富士通が4月11日発表を先に決めて雑誌メディアにも事前に情報を出した。それで、後からNECもプレスリリース日を合わせてきた、という格好なのかな? と勝手に想像してみる。
■可能
ネットを見ていると、ときどき「可能無限」と「実無限」という用語を見かける。この用語が適切なものかどうかはさておき、無限をこうやって区別したい人は、3を「可能3」と「実3」に区別しないのかな、と思った
結城浩のはてな日記
結城さんの日記に興味があって読んでいるならば、そのほとんどの人は数学の公理系を受け入れているのではないかなぁ、と想像します。なので「可能3 って何?」みたいな。
「実10000」と「可能10000」ぐらいだと意図が掴みやすいかも。
「実10000」は「10×10×10×10 のこと」で、「可能10000」は「1*1から始めていって10000まで数え上げた時に初めてその『数』を10000と定義する」って感じ?
*1 公理に出てくるのは空集合φなので、0から、の方がいいのだろうか?
2006-04-12 可能無限, マウス オブ マッドネス
■マウス オブ マッドネス その1
映画"In the Mouth of Madness"(DVDは asin:B00005HYWP)のノベライズ。
朝松健氏だ!
ということで読んでみる。
p62
「しかし、ケインは、他の作家とどこか違っているな。なんだか自分の作品は、全て真実だと信じているみたいな……」
「SF作家のヴァン・ヴォークトも同じそうだったらしいぜ」
……事実なのだろうか? ヴァン・ヴォークトは「非(ナル)Aの世界 (創元SF文庫)(A.E.ヴァン・ヴォークト/中村 保男)*1」の作者ね。
p82
見馴れたものが、すべて消えてしまい、見たこともないもので世界が埋め尽くされたら? あなたは、どうする? 最後の一人は、きっと怖くて寂しいわよ
あれ? この映画*2もこのモチーフで解釈していいんだろうか?
マチスンの「地球最後の男」
とか、その換骨奪胎、藤子・F・不二雄の「流血鬼」
のテーマだな。
p102 トレントの台詞
「なぁ、リンダ。いい加減、現実を見つめようぜ。これはケインの小説世界じゃないし、おれたちは奴の創ったキャラクターじゃない」
いい台詞だ。にやり、としてしまう。
p103 リンダの台詞
「(略)パトリシア・ハーストが過激派に誘拐され、洗脳され、同志となってしまった事件――」
んー。
p51
このように、パティがターニャに変わった過程は、もはや一九五〇年代の「洗脳」とは異なるものであることが示唆される。
パティはパトリシアの愛称。ターニャは過激派に参加する様になってからの自称。
この事件がちょうど「洗脳」と「マインド・コントロール」の端境にあたり、また「マインド・コントロール」という社会心理学的テクニックについての研究の端緒でもある。
なので洗脳という言葉にはちょっと違和感を覚えた。
ちなみにハースト事件は1974〜5年。カルト・マインド・コントロールが洗脳とは違うものであるとして区別されはじめるのが1980年代後半。
今だと、
が入手しやすいのかな?(と、思ったら、マインド・コントロールとは何か(西田 公昭) も増刷されてるみたいね)
p133 トレントの台詞
「昔、ホラー映画にこういうのがあったな。『死ぬまでジェシカを怖がらせよう』……その伝でいけば、今回のタイトルは、こうだ。『死ぬまでジョン・トレントを怖がらせよう』……違うか?」
渋っ。
邦題は「呪われたジェシカ」。
題名が出てくるのがトレントの台詞の中なので、原題の「Let's Scare Jessica To Death」の訳になっているところが、細かいなぁ。
でもトレントが観ていそうな映画には思えないのだけどね。
で、小説を読み終わった後で、ビデオを借りてきて映画を観てみた。
これで4回目ぐらいかな?
朝松健氏の筆を以てしても、この映画の面白さにはちょっと敵わないかなぁ、と思った。
ただ、映画では中盤で特殊メイクやクリーチャーが出てくるあたりが、実は一番怖くない。そこまでの「現実が変わっていく」という暗示的な描写の方が面白く思えて、クリーチャーが出てきた途端「いかにもなホラー」っぽさを感じてしまう。そこを通り過ぎるとまた面白くなっていくのだけど。
で、小説版の方はその中盤が、面白さが厚みを増して書かれていて、上手いなぁと思う。
あとは、ぱらぱらと感じたこととかを書いていこう。
ホラー好きな読者/観客なら「名状しがたい」という形容詞を期待するだろう、と思ってしまう部分が、映画字幕ではそうなっていなかった。
朝松さんはその辺りは外さない。小説を読んでいるので「そこはやっぱり『名状しがたい』って訳すだろう?」というポイントがハッキリ判る(英語のヒアリング能力が前に観たときよりも向上している、という要因も少しはあるけど)。
その1で書いた、
p82
見馴れたものが、すべて消えてしまい、見たこともないもので世界が埋め尽くされたら? あなたは、どうする? 最後の一人は、きっと怖くて寂しいわよ
の台詞は、確かに映画にもあった。
あと、小説末尾の解説を読んで初めて知ったのだけど、この映画、エンドクレジットに主要な登場人物がでてこない。気がついていなかった。
他にも小説を読んで初めて知って、映画を観て「あぁ本当だ」と思った点は多数あった。それだけでも、読んで良かったかなぁと思った。
映画には先行する小説群(主に Cthulhu mythos もの)へのジョン・カーペンターのオマージュが満ち満ちている。
それでだろう。小説の方では、逆に先行するホラー映画群へのオマージュが多数挿入されている。
で、
p200-201
「モーテルのTVで流れているSF映画は」、およそまともな神経ならば耐えられないものだった。主演はゴリラの胴体に、骸骨の頭、そして宇宙人のヘルメットを被ったチープな怪物だ。そいつが半裸の女を抱えて、のたのたと歩いていた。
「……見たことがある。『ロボット・モンスター』って映画だ……」
って、あんた、見たことあるんかい!
「ロボット・モンスター」という映画については、
に詳しい。なんとこの映画の記事に2ページを割いている!
編集者からのオーダーは「なるべく詳しく、『ロボットモンスター Robot Monster』(53年・未)の物語を紹介してほしい」という大胆不敵なモノである。映画史上最低の誉れも高きこのデタラメな映画を堂々と解説できる機会はもう二度とないだろーなと思うと、ちょっと震える。
タイトルバックはアメコミ風のレイアウトとオドロ系BGMのミスマッチが素敵。作曲はなんと巨匠エルマー・バーンステイン!
と始まる。
そのぐらいマイナな、けれどカルトな映画。あ、そのシーンでそんな映画がかかっていたっていうのも、小説を読んでなきゃ気がつかなかった点だな。
その2に続く。
■可能 その2
うーん。現代数学の側に居ると「可能無限」の世界って……想像できないというか。
多分こんな話は1998年以降山ほどなされていると思うのだけど、まぁ書き記しておこうか(なんで1998年なのかは後述)。
自然数は確かに無限に存在し、1,2,3,,,, と数え上げていくことができる。しかし、「自然数の集合」という概念は「可能無限」の世界では取り扱うことはできない、らしい。
と、いうことは、日常的に使っている交換法則や分配法則や結合法則さえも「全ての自然数で」成立するかどうか? を証明することができない、はずだ。
それどころか、100 + 100 = 200 という様な計算さえ、200 まで数え上げなければそれが正しいかどうか確認できないということになる、だろう。
100 + 100 = 200 だと例として不十分か。123 + 234 = 357 という計算をするにしても、意識してはいなくても 123 + 234 = 100 + 20 + 3 + 200 + 30 +4 = (100 + 200) + (20 + 30) + (3 + 4) = (1 + 2) * 100 + (2 + 3) * 10 + (3 + 4) = 300 + 50 + 7 = 357 という様に、交換法則や分配法則や結合法則を使っている、と思う。
ということは、ここにでてくる一番大きい数、357 まで数えあげつつ、式の変形の途中で使っている諸法則が成立することを確認していって、初めて 123 + 234 = 357 が真であると確信できる、ということになるのではないか。
国家予算規模の数字を扱おうと思ったら、「可能無限」の世界に生きている人々は、どうするのだろうか?*3
1998年という年について語ろう。
この本が出版された年だ。
ちょっとした確認をしてみた。
これが、
All The Web で、1998年8月31日以前で"可能無限"を検索した結果。0件だ。
で、こちらが、
1998年9月1日以降で"可能無限"を検索した結果。
はい。見事に偏っている。
事実を示すのみにしておこうか。
ちょっと前にも引用したのだけど、
この本は、純粋に公理から出発して、「数」や「可算」や「加算」や「交換法則」や「分配法則」や「結合法則」を導き出すという小説。ということで「実無限」側に立っている本。
p142
2×π≡π+πを正当に証明できるけど、π+πを有限回の手順で計算できるとは限らないってことね。神様だけが計算を終えられるけど、人間にできるのは証明を終わらせることだけってこと。
これを読むと、「可能無限」の世界って、π+π=2π ですら人間の手では導き出すことができない世界だな、とそう思うわけで。
にコメントがついたぞ。ワクワク。
しかも可能無限を受け入れられる人 = 無限集合公理の不在を受け入れられる人、みたいだ。
私は、
を読んでおらず、Web上に散見される、メタ・コンテンツだけしか目にしていない、と立場を明確にした上で。
ZF公理系から無限集合の公理を取っ払ってしまうと、「自然数」の定義が無くなってしまう。ということは「全ての自然数」についての定理(=公理から導出できる命題)が全てチャラになってしまう。
前のエントリでも書いた様に、交換法則や分配法則や結合法則でさえも「全ての自然数」で成立すると言えなくなる。
無限集合が無くなると、自然数をn進数で一意に表現することもできなくなる。だって \(\{2^{0},~2^{1},~2^{2},~2^{3},~2^{4},~,,,\}\)
や、\(\{10^{0},~10^{1},~10^{2},~10^{3},~10^{4},~,,,\}\)
というような無限集合が考えられなくなるわけだから。
実無限は無限集合の公理でやっと存在が担保されるものですよね?
結城浩のはてな日記
3の存在にはそんな仮定がいらないから「可能3」って意味不明です.
とコメントがついているけど、そんなことはない。
3という自然数も「無限集合の公理」が無い世界では、公理から導出できないんだから。3 のZF公理系での定義は {φ, {φ}, {φ, {φ}}}。空集合の公理と無限集合の公理が無いと存在できないでしょ?
追記:あ、なるほど。対の公理があれば {φ, {φ}, {φ, {φ}}} まではいくのか〜。無限集合の公理がなくても「全ての自然数」に対する命題が言及可能なのかな? 勉強不足なので判断できないです。まぁ、少なくとも、この段落は読み飛ばしてもらっていいです。
追記の2:んー? やっぱり、対の公理では自然数を定義できない様な気がするんだが……。勉強不足だなぁ。
追記の3:追記の2は無かったということで。
この混乱が起こったのは、最初に挙げた本の著者が哲学者だ、ということにあるみたいだ。
ZF公理系から無限集合の公理を取り除いた上で、そこにどんな公理を付け足せば自然数や自然数が持つ性質――演算や比較の定義、その性質――を保持する新しい公理系を作れるか? が説明されていれば、まぁ納得できるのだろう。
けど、Webで検索してメタ・コンテンツを読む限りでは、どうもそうではないらしい。
最初に挙げた本のカスタマーレビューにも、
筆者が哲学者ゆえ、数学者は本書を足蹴にしているようだが、
という文が見られるけどそうじゃないんじゃないだろうか。
「実数という考えは無限集合の公理をよりどころとしているんだよ。無限集合の公理なんてアヤシゲなものを取り除いてしまうと実数なんて概念は霧散してしまう」と説明しているサイトは数々あれど、「無限集合の公理を取り除くと自然数の定義もあやふやになってしまうからこういう公理を付け足す必要がある」とは説明してくれない。だから数学者はこの本に価値を見いだすことができないんじゃないかな。
現代数学の公理系から「無限集合の公理」を取り除いて、替わりになる公理を提唱しないなら、数学は(おろか「算数」のレベルの定理群までも)全て瓦解する。でもそれは当たり前のこと。
ZF(C)公理系は数学者達が細心の注意を払って磨き上げてきた「玉*4」だもの。まぁ、もっとも、無矛盾性は証明できないわけで、もしらしたらとんでもないところから「矛盾を孕んでいる」なんていう疵が見つからないとは、誰も言えない。
余談
にこんな会話がでてくる。
「数学は自明である公理から始まり
そこから定理を導き出して命題を証明する
現代数学の公理は集合論だ
その前提となるものは何だ?」
「空集合φ つまりゼロが存在する」
この巻が出版されて初めて読んだ時は、この会話の意味を正しく捉えていなかったんだな、と今になって思う。
追記
可能無限に関しての私の結論は、
で書いた。
■自分の言語をGloriaと名付けようと思ったものの、家庭内での混乱をまねくのは明らかなのでやめた
ウケタ。コーヒーを飲んでいる時じゃなくてよかった。
私: 今日、Rubyがおかしくなっちゃってさあ。
Matzにっき(2006-04-06)
娘: え?
2006-04-13
■マウス オブ マッドネス その2
映画"In the Mouth of Madness"(DVDは asin:B00005HYWP)のノベライズ。
昨日の続き。
ノベライズより映画の方が面白いと思うのは何故だろうと考えていた。
映画版にこれほど惹かれる理由は、その高い自己言及性にあるのだと思う。
ということは、小説版は「映画のノベライズ」であってはならない。自己言及性が失われてしまう。「映画化の前に出版された大ベストセラー小説」という形である必要がある。
体裁だけでもそうなっているべきだ。
「朝松健の手によるノベライズ」じゃ駄目なんだ。「サター・ケーン著/朝松健訳 映画『マウス・オブ・マッドネス』の原作小説!」ぐらいのアオリでいいんだ。
あと、伊藤昭弘がベル☆スタア強盗団からワイルダネスへの流れで作った、2ページ目の「日本語版出版権独占」の表記。あれぐらいの体裁が良かったのでは?
体裁だけ整えてもしようがない、と言われればその通りだけど、ノベライズという体裁を取った瞬間にあの優れた自己言及性が失われる、というのも確か(だと思う)。
我孫子武丸氏が、
の後書きで「本当は『探偵小説』という小説か、『探偵映画』という映画であるべきだった」というようなことを書いていたと思う。
それが同様にあてはまるのではないかな。
■π進数
19:12 追記
途中の式――4 をπ進数で表現しようとした式――が思いっきり間違っています。が、最後の結論は間違ってないと思うので、とりあえずそのままにします。
ここでπ進数というのを考えて見ます。ある数がπ倍になったら桁が繰り上がるわけです。この表記を使うと、無理数であるπの表記が簡単になります。πをπ進数で表せば10です。これは2を二進数で表せば10になるのと同じです。
π進数などというものに必然性があるのかはともかく、こう考えると無理数でも確かに存在する数だというのが実感できるのではないでしょうか。Log of ROYGB - 10進数
SF的な発想をすれば、車輪生物がπ進数を使うということも考えられます。車輪生物が、自分の身長つまり直径に対して、1回転した長さ、直径×円周率を使って数というものを理解するわけです。
πは超越数なので、0を除く有理数が全て表現不可能なんですけど……。
とコメントをいれてはみたものの、怪しい……か?
有限の桁で表現不可能なのは確か。
でも、小数点以下無限の桁で表現可能か不可能か?
例えば 4 をπ進数で表現したい。記号 1 を使うとややこしいので I を使おう。例えば \(\pi^{4}~+~\pi^{2}\)
は I0I00 という表記になる、と。
4 が I.?????... という表記になるところまではすぐ判る。(19:12 追記 ここ、間違ってます。I?.????ですね)
\(\pi~+~a_{1}~\pi^{-1}~+~a_{2}~\pi^{-2}~+~a_{3}~\pi^{-3}~+~...~a_{n}~\pi^{-n}~+...~=~4\)
なる無限数列 \(a_{n}\)
が存在するか? ということか。
Windowsの電卓(関数電卓モード)を使ってちょっと計算してみるか。
4 -PI = 0.8584073464102067615373566167205 (1)
1 / PI = 0.31830988618379067153776752674503 (2)
I.I????だな。
(1) - (2) = 0.540097460226416089999589089975
……まだ 1/PI より大きいぞ。どうなってる?
そっか、各桁は [0〜π) の開区間を取るんだから当たり前なんだ。I と 0 だけじゃ表現できない。それぞれの桁に"[0〜π) の1つの実数"を表現することが求められるんだ。って、それじゃπ進数を考える意味が無くなっちゃうぞ。
あれ?
\(\pi~+~a_{1}~\pi^{-1}~+~a_{2}~\pi^{-2}~+~a_{3}~\pi^{-3}~+~...~a_{n}~\pi^{-n}~+...~=~4\)
の式に \(\pi^{0}\)
が出てこないのはなんでだ?(19:12 追記 式は間違ってます。でも、ここから下の論理は成立すると思います。)
……これは……つまり……乗算の単位元(10進数表現での"1")が、「π進数では有限桁表記できない」っていう事実を示しているのかな。
「10進数表現でいうところの"1"がπ進数では有限桁表記できない」のは分かってはいたけど、これじゃ困るな。
いや、発想を逆にしなきゃいけないのか?
「(自然数)進数の世界*1」でπが"超越数"であることの裏返しだ。
「π進数の世界」では、"乗算の単位元"が「(自然数)進数の世界」でいうところの"超越数"の扱いになるんだ!
……この辺にしとこう。考えたらキリが無さそうだ。
追記
本当に面倒くさくなって途中で書くのをやめてしまったのだけど、もしかして気がつかない人がいるかも、と思ったので追記。
ROYGBさんのエントリ中、
πをπ進数で表せば10です。
に登場する記号"1"や、私が
記号 1 を使うとややこしいので I を使おう。例えば \(\pi^{4}~+~\pi^{2}\) は I0I00 という表記になる、と。
として導入した記号"I"。
"これ"が"乗算の単位元"であり、"「π進数の世界」では有限の桁で表現できない(であろう)数"で、つまり"超越数"にあたる、そんな性質を持っている。
だから、「10進数ではπを正確に記述できないので"π"という記号を使って表現する」のと同様「π進数の世界では"乗算の単位元"を正確に記述することはできないので、"1"とか"I"という記号を使わないと表現できないんだ!」ということに気がついた、と、これはそういうエントリなのです。
追記 21:50
思いっきり間違えてたからこのエントリ自体「無かったこと」にした方がいいのかしらん?
とりあえず整理してみよう。
π進数が成り立たないということはすぐに判った。1桁(10進数の世界でいう"1の位")で、[0, π) の開区間を表現する必要がでてくるからだ。
次に思ったのはRYOGBさんが何の断わりもなく"1"という記号を使っているのが「まずい」と思った。普通に数として捉えると数直線で [0, π) の間にあるからだ。
零元として記号の"0"を使うのはまぁいいとして、"1という数"と"1"という記号を混同して使うのはよくない。
言い換える。乗算の単位元として"1"という記号を使うのはよくない。
ということで"I"という記号を導入した。
次にとりあえず、4 を表記しようとしたらどうなるか? と考えた。と、いっても、有限の桁では表記できるはずがない。でも無限に続く小数として捕らえることはできるんだろうか?
まず手作業で何桁か表現しようとした。
そこで単位元の捉え方が10進数の世界と異なるということが無意識に働いてしまったんだろう。思いっきり間違えてしまった。
で、思いっきり間違えた式を書いてしまったことで、逆に"単位元の捉え方が10進数の世界と異なる"というのがどういうことかに、強力に意識が向いてしまった。
\(\pi^{0}\)
が単位元にあたるはずなのに、この"数"は1桁目の [0, π) の開区間上に存在していている。
そしてπは超越数だ。n次の方程式の根としてπが表われることはない。だから最初の目論見ではもしも仮に――あくまで仮にだ――π進数を考えたとして有理数を表現できない、と思ったのだ。
ということは単位元でさえも、π進数では"超越数"的なことになるのでは? という方向に突っ走ってしまった。
まぁ、そういうことだ。
思いっきり間違えてはいるけれど、"楽しいから許す"という精神で残しておくので温かい目で見てやってください。
(楽しい……のか?)
(楽しいんだよ! 悪いか?)
追記
結城さんからコメントいただいた√2iを基数にするという話は、4/15にちょっとだけ考えてみました。
追記
を書きました。
■トマト銀行がNEC製勘定系の採用を白紙撤回
↓この話、日経コンピュータ誌の「動かないコンピュータ」で読んだ覚えがあるなぁ、と思った。ただそれだけ。
ところが、NECがBW21の開発にてこずったこともあり、第一号ユーザーである八千代銀行の稼働が2001年月から2003年5月にずれ込んだ。
トマト銀行がNEC製勘定系の採用を白紙撤回、日立製に切り替え:ITpro
*1 便宜上こう書いたけど当然1進数は存在しない。
2006-04-14
■こんなUIのRSSリーダ(アグリケータ)欲しい
ベイジアンフィルタなどの評価手法を使い、利用者の好み/ニーズに合致する記事は初期表示で全文を画面に展開。そうでない記事は見出しのみ表示
■Palm TX 買ったものの……
今使っているTG50、新しいPalmwareとか入れて楽しむ、なんてことをもうしなくなって久しい。使い方が完全に安定してしまったっていうこと。
TX買ってはみたものの触って楽しむ、という気分じゃなくて「環境移行しなければ」みたいなタスクの様な気分。おかけであまり触ってない。
とりあえず、ホームボタン(一番左のハードキー)に自由にアプリケーションが割り当てられない(!)ので、
の ButtonsEx は必須。
とメモしておこう。
■トゥインクル☆スターシップ 10
ストーリー、進んでるのか?
本当なら一章ぐらいの内容のハズなのにバロータとマユミのエピソードを増やしたくて一冊にしたみたいな感じ。
ディジーのお部屋、久しぶりに面白かった。っていうか2周目って一体。
■TeX記法のテスト
\(x^{n}~+~y^{n}~=~z^{n}\) において、n >= 3 でこれを満たす自然数x, y, z はない。
\(x^{n}~+~y^{n}~=~z^{n}\)
において、n >= 3 でこれを満たす自然数x, y, z はない。
2006-04-15
■笑いが止まらない
爆笑じゃなくて、くすくす笑いが止まらない〜。
子どもの勉強に付き合ってたら出てきた算数の問題集中の一問↓
2ちゃんねるベストヒット: さゆりさんの問題
「15年前の話です。さゆりさんは上野発の……
■rss.css置いた & umekomiblog
rdf表示用のCSSファイルを置いた。
右上タイトル横の「RSS」アイコンをクリックした時の表示が少しマシになった。
あとでmakerssプラグインをもう少しいじってみるつもり。
CSSファイルは、
から blog_rss.css をいただきました。多謝。
この umekomiblog ってのは php で書かれた、blog システムらしい。セットアップもすごく簡単な様だ。
画面構成もシンプルできれいだし、案外いい拾い物かも。
■2のべき乗の集合とフィボナッチ数の集合の共通点
「完全集合」という概念がある。
テクスト(後述)から引用しよう。
整数の集合が「完全」であるというのは,すべての正の整数を,その集合から有限個の数を1回だけ取って作った和で表せることです.
「正の整数」ってのは「自然数」に等しいな。このエントリでは「自然数」と書く。
例えば2のべき乗の集合。
\(\{2^{0},~2^{1},~2^{2},\cdots,~2^{n},\cdots\}\)
これは完全集合だ。ここから有限個選び、係数\(\sigma_{i}\)
が0または1として、「和で表せる」というのがどういことかというと、
\(\sum_{i=0}^{N}~\sigma_{i}~2^{i}\)
という形で全ての自然数を表現できる、ということ。
なんということはない。2進数表記に他ならない。
\(12~=~1~\times~2^{3}~+~1~\times~2^{2}~+~0~\times~2^{1}~+~0~\times~2^{0}\)
となるので、12を2進数で表記すると 1100 となる。
そしてフィボナッチ数の集合。フィボナッチ数については、
を読もう! ということで……。
気を取り直して、フィボナッチ数の集合(数列)は、{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ……} となるわけだが、最初の0と1は無用なので取っぱらう(あってもいいが意味はない)。
{1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …}という数列。
ここから有限個を選び、和を取る。係数\(\sigma_{i}\)
にご登場いただこう。
\(\sum_{i=0}^{N}~\sigma_{i}~F_{i}\)
これが全ての自然数を表現する。
2のべき乗の集合とちょっと異なるのは、ある自然数が一意に表現されるとは限らないということ。
例えば3を表現するのに、3 = 1×3 + 0×2 + 0×1 で 100 でもいいし、3 = 1×2 + 1×1 で 11 でもいい。
4 を表現することを考える。これは一意に表現される。4 = 1×3 + 0×2 + 1×1 で、101 という表現しか持たない。
ここで手を動かして、初めの数十個の自然数をフィボナッチ数の和で表現することをしてみるといいのだけど、パス。
4 の様に「一意に表現される数」にはある条件が存在する。それは……フィボナッチ数-1、という条件。
と、ここまでは、
の第8章の劣化コピー。
この本のタイトルに出てくる黄金比というのは\(\frac{1~+~\sqrt{5}}{2}\)
という無理数のこと。
この数の一般的な性質から、幾何学的な性質へ、そこからフィボナッチ数に入り、一般化されたフィボナッチ数列を考え、ルカ数(初項として 2, 1 を与えたフィボナッチ数列)が登場し、最適な間隔と計算アルゴリズムに関しての話で一旦コンピュータサイエンスに近づいて*1、ペンローズ充填という幾何学的な性質に舞い戻り、自然界に観察される性質――花の花弁や貝の模様に表われる対象性、ヒマワリの種の部分に見られる螺旋性――について論じられる、という実にアクロバティックな展開を見せてくれる本だ。
「ミルカさんとフィボナッチ数列」を読み終えている人は、フィボナッチ数の一般項に\(\sqrt{5}\)
がでてきて「僕」が「けげんな顔をする」場面を覚えているだろうか? フィボナッチ数と黄金比と無関係ではない、というか密接な関係があることがこの本で判る。
とはいっても、フィボナッチ数の集合が「完全」であることの証明なんかはスッパリと省かれているので*2、数学を本格的に勉強している人には物足りないだろう。かといって軽い読み物程度というわけでもない。
紹介終わり。
ここからは「私の問題」になる。
去年の11月〜12月にかけて考えていたこと。
集合 A を2のべき乗の集合とする。つまり、
\(A~=~\{~2^{n}~|~n~\in~N\}\) である。(\(N\) は自然数の集合、ただし0を含む)
簡単に書くと、\(\normalsize\displaystyle~A~=~\{1,~2,~4,~8,~16,~\cdots\}\) ということ。
Aのべき集合を考える。
\(\normalsize\displaystyle~\{\phi,~\{1\},~\{2\},~\{1,2\},~\{4\},~\{1,4\},~\{2,4\},~\{1,2,4\},~\{8\},~\cdots\}\)
という集合になる。
空集合はとりあえず無視するとして、その他の元について「その要素の和」を考えてみる。
実は先の記述は意図的な並び方で書いた。
要素の和をとると、\(\normalsize\displaystyle(1,~2,~3,~4,~5,~6,~7,~8,~\cdots)\) となる様に並べている。
つまり、元の「要素の和を取る」ことは、「2進数で自然数を表現する」ことに他ならない、ということだ。
ここまででおかしなことが起きている。
Aは可算無限集合である。
Aのべき集合は連続無限集合である。(カントールによる証明は割愛)
にもかかわらず、Aのべき集合の元について「要素の和を取る」ことで「自然数」と対応がとれている様に見える。これではAのべき集合が可算無限集合であるということになってしまうのではないか? という疑問がでてきた。
prima materia - diary : 集合とか無限とか極限とか
という問題(ここで ? となった人は引用元のエントリに行って全文読んで欲しい)。
今書いた、このエントリの冒頭の引用をもう一度見てみよう。
整数の集合が「完全」であるというのは,すべての正の整数を,その集合から有限個の数を1回だけ取って作った和で表せることです.
この、有限個の数を1回だけ取って、という表現。「あぁ、こう表現すれば良かったんだ」と今になると思う。
「Aのべき集合の元のうち、有限集合の元だけを集めた集合」
prima materia diary - 集合とか無限とか極限とか
なんて書いていて自分でもややこしいなぁ、と思っていたのが、ちょっとスッキリ。
■√2i 進数
結城さん(id:hyuki)からコメントしていただいた件。
Knuth先生のThe Art of Computer ProgrammingのVolume 2に√2i を基数にする話題が出てました。日本語版p.193。ご参考。
prima materia diary - π進数
そうか。2進数に展開するのと同様なのか。
2乗すると-2が表われ、4乗すると4が、6乗すると-8が、8乗すると16が表われる。
ん? 1はどうやって作る? ……(考えている)……0乗すればいいんだ(ってこの間も見逃していたなぁ)。
実質、-2 を基数にするわけだ。
1 = (-2)^0
2 = (-2) + 4
3 = 1+(-2)+4
4 = 4
5 = 1+4
6 = (-2)+(-8)+16
7 = 1+(-2)+(-8)+16
8 = (-8)+16
うん。小数点より左は問題無さそう。同じ理屈で小数点より右側も展開されるんだろうな、きっと。
追記 4/16
-2 じゃなくてわざわざ √2i を基数にしているのだから、その意図を考えると複素平面上の数が展開可能なのだろうなぁ、と感じてはいるけど、考えてない。あしからず。
*1 コンピュータサイエンスと書いたのは正確ではない。「オイラーの贈物―人類の至宝eiπ=-1を学ぶ ちくま学芸文庫 isbn:4-480-08675-7」 に依ればアルゴリズムとは「有限回の計算の後に目的を達する,あいまいさのない一連の手続き」のことだからだ。アルゴリズム=コンピュータサイエンスというのは短絡的な思考認識だ。
*2 このエントリで証明をしない――できない――のもそのため。どんな形の証明になるんだろうか……? 5分ぐらい考えたら分かった。
2006-04-16
2006-04-17
■BLEACH DS
「強い言葉」と言えば。
面白い、というか、格好いい。
Game Cube版にはがっかりしたけど(千本桜が本当に桜がしかもゆっくりと舞うのにはビックリ。視認できるような演出じゃ駄目じゃん!)、こいつは漫画での格好良さとゲームでの格好良さが別物であることをわきまえていて、漫画での描写に縛られることなくゲームでの格好良さを目指している様で、気持ちいい。
「神槍」なんかゲームの文脈で言えば「レーザー」だもんね。でも刀が「伸びる」よりも格好いいし、その格好良さがより「神槍」らしく感じるという、逆説的だけどそんな感覚。
■6万種と言われても
地球温暖化が現在のペースで進むと今世紀中に、希少動植物が集中して生息する地域で、そこにしかいない固有種の大量絶滅が起こる恐れが大きいとの研究を、カナダ・トロント大などの国際チームがまとめた。
Sankei Web 「ホットスポット」で6万種絶滅の恐れ 地球温暖化(04/15 18:34)
「大量絶滅」という言葉がちょっと引っかかった。
どういう意味で――どういう定義で「大量」なのか? がこの記事からだけでは判らない。
「強い言葉」で煽っている様に読めちゃうのだな。
昆虫なんかは既知で80万種みたい。未知のものだと300万とも500万とも言われてる(未知のものの推定なので、推定した人/組織によってブレがあるのは当然)。
植物種で25万〜26万種みたいで、このうち「約56000種」ってのは確かに「大量絶滅」の様に感じる。
2006-04-18
■家のサーバ
オークションで手に入れた富士通 LOOX T5/53。
Crusoe 搭載。ファンレス。
入れているOSはdebianだけど、i386バイナリ のCD(とかDVD)からのインストールなので X Window の設定以外は全然困らない。
LANアダプタとしてPCカードが必要だけど、玄箱よりもCPUパワーがあって、ファンがない分(?)省電力。そして静か。
オークションだと充分に安いし、実は玄箱よりも役に立っている。
■Keep It Simple, but
という話だな。
つまり、お互い自分の専門領域外で興味のないところはややこしくなくシンプルであってほしい、っていう意味になっちゃってるわけです。でも、自分の領域のこととなると、ディティールが見えているから、単にシンプルという言葉をかざして相手が押しつけてくるものは手抜きにしか感じられなくなる。
CNET Japan Blog - 江島健太郎 / Kenn's Clairvoyance:あらためて感じる、開発の進め方の難しさ
この後半の文に共感した。
内部的な細かいこと(ディティール)が見えている領域・知り尽くしてしまっている領域に対しては、シンプルに捉えられなくなる、というのはその通りだなぁ、と思う。
これに対するプログラミングでの――というかソースコードに近い領域での、と言った方がいいか――解答として、その手順を定式化・形式化しようという試みが「リファクタリング」なんだろうな、と感じた(=そう理解している)。
■メモリースティックDuoに録画してPSPで見る
Hagiwara Sys-Com 006.04.07 Easy Recorder for Memory Stick Duo『いーレコ2』の発売について
前者がMPEG-4 AVCで、後者がMPEG4 Simple Profile Level1, 3。
この映像フォーマットの違いに、価格比で2.5倍高い前者の価値があるのか?
……検索している……。
http://www.oki.com/jp/Home/JIS/Books/KENKAI/n200/pdf/200_R14.pdf
この辺か。
■ファイブスター物語 XII
読んだのは一週間前だけど。
アルルとかネイバーって、5話でMH(SR1とオージェ)を背負って、すっごい格好良く出てきたけどこの巻になると全然イメージが違うのね。
でもこれって、ジョーカー星団に住んでいる一般人の騎士に対するイメージがきっと「強い。格好いい」「でも怖い」なんだっていうことと、実際の騎士の生活との間には落差があるんだ、っていうことと同じなのかなぁ、と。
初登場でその人物のキャラクタが見えない内は「強そう。格好いい」ってイメージでいいんだけど、キャラクタをちゃんと書いていくと「そうじゃないんだ」ってことになるように自然になってるわけだ。
ファイブスター物語って新しい巻が出るとつい読み返したくなるのたけど、やっぱり読み返す度に新しい発見があるんだよなぁ。あ、この「やっぱり」は「今回もそうだった」って意味ね。
■やっちまった
古い日付のデータ更新で rdf を変更してしまった……。
2006-04-19
■自分の言葉
普段はどこかからかの引用や、自分の読んだものとかについて書いているわけだけど、たまには自分の言葉だけで書いてみようか。
まぁ、とは言っても、それは以前に目にした何かからの引用であるのだろうけど。
「言葉を紡ぐ」とはよく言ったもので、自分の言葉で書くっていうのは確かに自分の頭の中にある何か、を縒り合わせて糸にして巻き取っていくようなものだな。問題なのは糸車にかかっている綿の質と、紡ぐ技術。
紡ぐ技術ってのは訓練で向上させることもできるし、この日記なんてまさしくそのために存在しているといっても過言ではない(過言ではない、なんて口語では普通使わないよな)。いや、因果が逆か、訓練で習得・向上させることができるが、訓練無しには獲得できない能力を「技術」と呼ぶのか。
対象が人間である限りはそれでいいのだけど、人間ではないものに移った時、直感的な意味が逆転するのは面白いな。「科学技術」なんていうときの「技術」だ。ここでは、訓練無しには獲得できない能力を機械(ロボットだったり、人間を補助する道具だったり)に与えた時に使われる。
同じ「技術」だけど英語にすると、前者は technique で、後者は technology なわけだ。
……話を戻そうか(ここで、閑話休題、と書きたくなるのは私の癖か)。
「文章を書く」には「言葉を紡ぐ」以外にもう一つ必要な、大事な能力がある。
「言葉を紡ぐのを止める」こと。これが意外に難しい。あるいは「誰でも小説を書き始めることはできるが、書き終えられる人は少ない」とでも言おうか。
「小説が書ける人」っていうのは「書き始められる人」のことではなくて、「書き終えられる人」のことだ。
自分の本を書きたい、出したい、という人はゴマンといるけれど、それに本当に必要な能力は「書き終えられるか」だよね。
せどりがまたいで通る、新風舎とか文芸社とか、要するにお金を出せば本を出版できて――ここからが重要――ISBNが振られて全国の本屋で扱ってもらえる様にしてくれる会社。扱ってもらえる、ってのは流通ルートに載せられるって意味であって、本当に本屋さんが棚に置いてくれるかはまた別。
あ、さらにお金を出せば、棚においてくれる本屋さん、ってのもあるらしい。最近読んだ何かだな……。なんだっけ?
と、ここまできて、このエントリを「書き終える」ことができるかどうか不安になってきた。着地点が決まっていないで書き出すってのはなかなかに冒険だ。
でもたまには冒険の様なこともやってないと、鍛えられない。意図的に鍛えたい、っていう意思は、ある。それが何かに繋がればいいと思うのだけど。
ふむ。プログラミングにも近いものがあるかな。
プロトタイプで満足したり、ソース書いて終わり、っていうのはまだ「書き終えてない」ってことだな。
「プログラマ」っていうのは「書き始められる人」のことではなくて、「書き終えられる人」のことだ。
あ、いいなこれ。まさにその通りだ。
何かが作りたくて着手はするんだけど結局作れないまま終わる、っていうのは、とりあえず原稿用紙を買ってきて(っていうのはちょいとアナクロだけど)小説を書き始めるのはいいんだけど途中で止まっている、ってのと同じだな。
うっ。
今なんかこう最後の言葉がナイフのように……
by 真山くん from ハチミツとクローバー (6) (クイーンズコミックス―ヤングユー)(羽海野 チカ)
って感じ?
最後の最後で「自分の言葉」じゃないじゃん! ってとこで、お終い。
■またやった
2005年11月5日のエントリを更新して rdf を吐き出してしまった……。
リンク先の修正だけなんです。
■PHASE IV
レアなSF作品。ビデオのみでDVD化されてないとはいえ、値段にビビった。
これは海外版のビデオで発送も海外から。あちらでもDVD化されてないのか? それとも対日本市場価格?
こちら日本語字幕付き。
前にあっちで書いたことあったはずだな。
これだこれだ。
2006-04-20
■情報に溺れ、没し
最初は Firefox の Bookmark Toolbar に専用のフォルダを作っておいて、Open in Tabs で一気に展開してチェックしてた。
はてなRSS beta がでてきて、これに色々つっこんでまめにチェックするようになった(今は Bloglines)。
今度は feed のチェックも段々物足りなくなってくる。
「情報量」の定義からしても、当たり前のことなんだな。触れることが日常化していけばいくほど情報量は減っていく。情報量はデータの大きさではない、という話は前に、
prima materia - diary : iPod nano専用のドックはまだ?, lain, ビットとシャノンと情報量
で書いたっけ。
で、情報を求めて彷徨い歩く放浪者に成り下がってはいけない、と思う。
自分のブラウザのブックマークを開いて、どこか見ようかな、とか考えたりしてしまう。
はてなブックマークの注目エントリを眺めていたりとかすると、あっという間に時間が過ぎてゆく。
……でも手許には何も残らない。
■はてなアンテナの使いどころ
はてなRSSがでてからアンテナの使いどころは確かに狭くなった。
- たまにしか更新されないサイト。
- RSSをださないサイト。
- 連載記事みたいなものを追いかけたい時。
- 更新が無くてどうなっているのか心配だけど毎日見にいくほどではないサイト。
てなものか?
もしかして、はてなのスタッフはもう誰もアンテナを使っていなくて、みんなはてなRSSに移行してしまっているのかもしれないと思った。
まんぷく::日記 - はてなスタッフはもう、はてなアンテナを使ってない説
■IoってインクリメンタルGCなんだ
IoもLuaもインクリメンタルGCを実装しているのだし。
Matzにっき(2006-04-17)
へー。どれどれ?
ホントだ。
incremental collector, weak links
io - about
2006-04-21
■全ては渡辺淳一の所為
なんてタイトルを付けてみたりして(内輪ネタです)。
いや実は、ミルトンの失楽園を読んでいるところ。
なんでわざわざ「ミルトンの」って付けなきゃならないんじゃー、っていうのが「渡辺淳一の所為」なのだ。本当なら「失楽園 その1」っていうタイトルを付けるべきエントリ。
訳注が多いのだけどその中に「アエネーイス」という書が出てくる。気になって調べたのだけど、アエネアス(アエネーアース)というトロイア滅亡後の英雄の遍歴を書く叙事詩だそうで(「アエネーイス」は「アエネアスの物語」の意)。
これらの名前、浅学ゆえに関連付けて捉えていなかったけど、色々な所で聞き覚えがある。
加藤元治「ロケットマン」に出てくる情報機関True Eyesのトップ、最高意思決定者、アイエネス。
アニメ「キディ・グレイド」に出てくる惑星、アイネイアース。
あと、これは調べていく内に判ったのだけど、コナミのMSXシューティングゲーム沙羅曼蛇に出てくる惑星にアイエネスという名前がある。
あと、順番から言って、失楽園よりもダンテの「神曲」の方を先に読むべきなのかなぁ。
■ファミ通に親指シフトの記事あり
「桜井政博のゲームについて思うこと」
まず最初に思った身勝手なキモチは、「なんで富士通はサポートをやめてしまったんだ!」ということ。
いやいや、
はWinXPをサポートしているし、1年前ぐらい前(だったかな?)のモデルのBIBLOで親指シフトキーボードがオプションとして買えたはず(直販オンリー)。
親指シフト絡みで書いたエントリに、富士通内部ネットワークからのアクセスと思しきrefererが残っていたりしたし。
■I AM LEGEND (地球最後の男)
Night of the Living Dead に直接影響を与えた、偉大なる先駆、というべきか。
最初に「今」を描いて、その後に追憶で3年前に飛ぶというのは、キツいっす。
いや、でもこれ、面白い。最後の方は真剣に見入ってしまった。NOTLD*1も最後のシーンは似通っている。かなり不条理なのだけど(不条理劇というわけではなくて、主人公が不条理な目に遭う、という意味)、受ける印象はまるで違う。正直、ここまで出来がいいとは思って無かった。
映画原題は"THE LAST MAN ON EARTH"。邦題は"地球最後の男"。原作原題が"I AM LEGEND"で、原作邦訳は最初"吸血鬼"で後に"地球最後の男"。
小説は読んでいないけど、映画を見る限り"I AM LEGEND"に"吸血鬼"という組み合わせが一番よいかと。
余談。
吸血鬼のマイナな特徴に、
- 部屋の様な、「閉ざされた空間」には中に居る人間の呼びかけが無いと入ってこられない。
- 川や海の様な流れる水を(少なくとも直接は)渡れない。
ってのがあるけど、前者は「知能が極端に低下していて閂がかかっている扉を破れる様な道具が使えない」という形で描かれているなぁ。
後者の特徴は、さすがにない。
■雑感
謎のコメントだなぁ。
「分けわかりません」と言っているのが、回答に対してなのか、はてなダイアリーに対してなのかそれが判らない。
判ろうとしない、何が判らないかを伝えようとしない/伝えられない質問者には回答はつかないぞ、と。
はっきり言ってはてなのブログは最悪な感じじゃないですか、他のブログでは無料でそういった作業を自動変換しているのに。あとはてな用語みたいなので構成されていて分けわかりません。皆さんは何故はてなのブログを使用するのでしょうか
人力検索はてな - アフェリエイトをしたいのですが、はまぞうからアマゾンの商品をリンクすれば正常に貼り付けできるのですがアマゾンからハイライトをコピーして日記に貼り付けても...
■雑感2
とはいえ、質問するのって本当に難しい。
「こういう回答が来るだろうけど、それは私の望む回答ではない」っていうのが想定できる時、それを回避するように質問文に織り込むわけだけど、まず間違いなくその部分を華麗にスルーして読んでくれて、「こういう回答が来るだろう」という回答が付いたりするわけだ。
■はてなダイアリー
アマゾンからハイライトをコピーして日記に貼り付けても画像がリンクされません何故でしょうか
人力検索はてな - アフェリエイトをしたいのですが、はまぞうからアマゾンの商品をリンクすれば正常に貼り付けできるのですがアマゾンからハイライトをコピーして日記に貼り付けても画像がリ..
アマゾンが吐き出すhtmlはiframe要素が使われているが、はてなダイアリーでは利用できない様になっているから。
*1 DVD添付の解説にこう書いてある。一瞬、なんのことだか判らなかった。
2006-04-22
■授業参観
相変わらず、親の方がバタバタしているなぁ、と思ったのだけど、後から判ったのは「子供が2人以上小学校に通っている親御さんは時間差で両方に顔をださなければならない」ということ。
親が頻繁に出入りしなきゃいけないのも納得。
■おそるべし サマータイムマシン・ブルース
ちゃんと見たのが3回に、オーディオコメンタリで1回。そのあとも1日おきぐらいでBGVにしていたのに、今日だらだらと見ていたら、まだ新しい発見が2つもあった。
おそるべし(単に映画を見る姿勢が浅いだけだって?)。
■.hack//SIGN
たまたまCSでやってたから見てみたら、27話(Intermezzo,番外編)だった。ベアの「なんですと!?」が聞ける回。
来週は28話(Unison)をやるらしい。
を買わないと見られなかった話だな。
2006-04-23
■神をも畏れぬ所業 スパイラル
今、家にスパイラルの1〜5巻と15巻(最終巻)がある。
カミさんが5巻まで読んだ後に、「あと最終刊? 読もうかなぁ」って、なんですと!?
駄目駄目絶対駄目!
なんて怖ろしいことを考えるんだ!
で、読み返してみると、だ。
最終回の一回前、"彼女"が泣くのになぜ声を押し殺したのか。最後のページで歩君の顔がフレームアウトしていて、その次にロングショットになったのは何故か。
てなことが見えてきて面白い。
基本的に私は読み方が浅い。で、代わりに読むスピードは速い。
繰り返し読む。前後の関連づけが強化される。
というスタイル。
2006-04-24
■ISBN規格改定
来年以降、13桁になるんですね。
せどりの限界に挑戦!かぴぱら堂業務日誌 - ISBN規格改定
昨年5月の時点で発表されていたのか。知らなかった。
最終決定――制式採用が昨年5月のことで、改定の話自体は何年も前からあったんですよ。
broken link
ワークグループの"終了"が2005年
13桁になるというか、EANコード(日本だとJANコード)の方が、ISBNコードということで制式に扱われるようになるということです。
今でもISBNの記述の他にJANコードがバーコード印刷されていますよね。JANコードの頭3桁,"978"が bookland という仮想の国*1に割り当てられていて、そこにISBNをつっこんでいただけ*2だったんですね。
ワークグループで議論されている間は、ある本が他の言語で訳された時にISBNコードで判別できるようにするとか、改版の情報もISBNに入れようとかあったみたいだったんですが、どうなったのかなぁ……*3。
せどらーの人に。
ISBNがシールで隠れていて読めなくても、JANコードの番号が読めればISBN(のチェックデジットを除く部分)は判ります。先頭の978と、末尾のチェックデジットを省けばいいんです。ちなみに……ISBNの先頭4は日本に割り当てられた国番号。和書ならばISBNは4で始まり、JANコードは9784で始まる。ISBNの入力で先頭4とチェックデジットを省くことができる携帯チェッカを使っている人は、覚えておくべきです。
……というかこれは常識?*4
追記(2006/11/14)
2007年1月1日以降、書籍には現行の「"ISBN4"で始まる10桁コード(ハイフン付)」という文字が印刷されない。かわりに「"ISBN978-4"で始まる13桁コード(ハイフン付)」という文字が印刷されるようになる。要はJANコードに「"ISBN"という文字」と、「国記号(4のこと),出版者記号,書名記号,チェックディジットの境を区別をするためのハイフン」を付加して、新ISBNの表記とするということ。新旧ISBNで末尾のチェックディジットの計算方法が異なる。もちろん新ISBNのチェックディジットは、JAN/EANコードに準じた計算方法に他ならない。
現行、ISBNの文字("ISBN4-〜")の印刷はOCRでの可読なフォントが定められており、必ずその様なフォントを使用しなければならない。2007年1月1日以降はその制約はなくなり、「目視可能な11級以上」という条件で自由な書体で印刷できることになる。
バーコード印刷は現行と変化はない。ただし海外向けに印刷する場合はJANコードの2段目は印刷されない(調べてはいないが現行もそうなっていると思う)。
追記(2006/11/21)
出版者記号は、
このあたりをどうぞ。ちょっと古い資料だけど。
一次資料をどこから取ればいいのかは私は知らない。
追記(2006/12/12)
AmazonのASINは、ISBNと関連がないもの*5に変更される様だ。
ECSの機能としてISBN→ASINのマッチングが追加されるらしい。
https://affiliate.amazon.co.jp/gp/associates/network/help/t4/a5
(アソシエイトIDでのログインが必要)
この diary で使っているのも手直しが必要かなぁ。当面は、Amazonの商品画面でASINを確認すればいいのだけど。
追記(2007/1/30)
結局、今のところASINは旧ISBN等しいので一番簡単な解決方法にしてしまった。
2006-04-25
■H.264って
MPEG-4 AVC という標準化がされているのに、そう書かない理由はなんだろう?
MPEG-2 と並べて書くなら H.264 よりも MPEG-4 AVC の方が収まりが良さそうなのに。
参考・関連
H.264 - Wikipedia
prima materia diary - メモリースティックDuoに録画してPSPで見る
■こどものためのドラッグ大全
p56
「覚醒剤やめますか、それとも人間やめますか」というポスターはきわつけの洗脳ポスターだ。それに、この強烈なコピーのせいで、覚醒剤依存症から立ち直ろうとしているひとたちが、「非人間」扱いされることにより、かえって社会復帰を妨げられている、という皮肉な事態も起きている。
p57
「怖いぞ、怖ろしいぞ」とあまりに煽りすぎて、じっさいにちょっと手を出したひとが「なんだ、警察や世間でいわれているほど恐ろしくない」と思って油断し、次第に深みにはまり、だんだんとやめることが難しくなっていき、知らぬままに妄想に支配されて犯罪をおかす、という盲点や罠を見事に作り出している。
理論社YA新書*1には他にもいくつか気になる本がある。
極めつけはこの本だった。
とにかく、正確な情報を日常的に目にすることができない。
どんな種類の薬が、どんな作用があって、どのぐらいの依存性があるのか? とか。
合法/非合法だって時代と共に変わってくる(シャーロキアンなら知っていることだ)。
「アダルト・チルドレン」がアルコール依存症の家庭で育った子供に問題が発生する、という事例に対する用語だということをちゃんと認識している人はどのぐらいの割合なのだろうか?(この本の中ではアルコールや煙草もドラッグの1つとして扱われている)
「恐ろしいもの」といって遠ざけるのではなくて、正しい知識を身につけることも、身を守る手段のはずなのに……。
ということで読むために買ってきた。
同じ叢書で他に気になった本
*1 YAはヤングアダルト。ターゲットとする読者層が中学生,高校生あたりの本のこと。図書館,出版用語と思っていい。元は心理学用語だっけっか。大人(アダルト)として扱われる年代の最も若い(ヤング)層という意味だったと思う。
2006-04-26
■bee or wasp?
日曜日に仮面ライダーを見ていた。
ザビーのキャスト・オフの時のボイスが "change wasp" だった。
bee と wasp って何が違うんだろ?
と、呟いたら子供(小1)が wasp はスズメバチだよ、と教えてくれた。
へー、そうなんだ、と答えてはみたももの半信半疑。だけど正解である可能性は、高い。後で調べてみると、果たしてその通りだった。
さすが。
話変わって。子供の英語教材のDVDを一緒に見ていると、密かに私の方のヒアリング能力も少しだけ上がってるな、と思う。
■カンパニーマン
主人公はスパイになる。
別の人間として潜り込む。別の人間を装う。別の趣味、別の名前。
フラッシュバック。
強いコントラストの映像。謎の美女。
別の趣味、別の名前が、現(うつつ)に。元の名前、元の自分が虚(うつろ)に。
スパイは、そのままダブル・スパイに。
洗脳*1は無効になり、虚だった元の自分を取り戻す。だが虚構だったはずの別の人格の生活はそのまま。
そこから、幾度も立場が反転する。
印象的なのは、意図的な白と黒のハイコントラストの映像美。でも、嘘くさい。リアリティを追求していない。
主人公の記憶があてにならない。虚ろな立場に追い込まれていく。
だから、嘘くさい映像でもok。全ては曖昧! 曖昧! 曖昧!
ストーリィ的には特筆するようなことはないかと。最後まで見終わると、どっかで読んだような話だな、という印象。「あっ、と驚く」ではなくて「あぁ、なるほど」という感じ。
でも、退屈を感じさせないで展開する、という点では及第点。
■ライトノベル「超」入門 早まったかも……
新城カズマの名前だけで注文したが……、店頭で流し読みしてから考えてもよかったか。
読んでも読んでも面白くない、というか「入門」する必要なんてないんだよね、自分の場合。
でもあとがきの最後、ルイス・キャロルから引いてきたところは唸ってしまう。新城カズマの文はどこにどんな仕掛けがあるか判らんからなぁ。最後まで読むつもりはあるが……といったところか。
余談
なんでオビにジェスターズ・ギャラクシーの表紙イラストが? さらに言うと最新刊のイラストじゃないのはなぜ?
■「入門」といえば
何年か前に、地下鉄で目の前に座っていたおじさんが読んでいた雑誌にひときわ大きな文字で「田舎暮らし入門」ってあったなぁ……。
「入門」することか? と当時は思ったものだが。
■Amazonのマイページもたまには……
先のエントリを書くためにカンパニーマンをAmzonで検索したわけだ。
するとマイページに上がってきたのは、
わはははは。なかなかいいチョイスだ。
ふむ。漫画や小説だと、同じ作者のものを引っ張ってくる傾向があって楽しくないけど、映画だと結構いいクラスタが作られているかもしれない(監督-脚本-役者の組み合わせ数が多いから)。
*1 という言葉は使いたくないが……マインド・コントロールでもないし。マインド・アップデートとでもいうか。
2006-04-27
■「面白い」と「面白かった」
似ているが全然別な概念である。
少なくとも私はこれを使いわける。厳密には「面白い」にも2種類ある。
やっぱり映画を引き合いにだすのがちょうどいいか。
「面白い映画」というのは、少なくとも2回以上は観て、映像・脚本・演出について俯瞰で論じることができるようになって初めてできる評価。
「映画を観て面白かった」というのは、"映画を観ている間楽しめた"という評価。
――ややこしいのは、ちゃんと評価ができない状態で、メタコンテンツを観て「面白そうだ」というステートの時。この時にも「面白い」と使うことがありうる。「○○なあたりが面白い」とかつい書いてしまうことがある。気をつけよう。
前にも引用したことがあるけど。
押井守の映画「トーキングヘッド」から。
語られた映画とは実は常に映画の記憶のことでしかない
指し示すことはおろか引用すら出来ず
語ろうとする時には呈示することも不可能で
しかも他者との共時的体験すらない個的な経験
それが映画を観るという行為の実相だ
人は自分が観たものを言葉で表すことは出来ない
観るということと観たことを言葉で表すということの間には
結局は何の関係もないんだから
映画を観ること
観たこと
観た映画について語ること
そして映画を観ることについて語ること
これらの行為の間にはいかなる共通項も存在しないし
複数の人間の間に於いてはもちろん
同一の個人にとっても一本の映画が同じ体験として我々の前に立ち現われることは
テキストとしてのフィルムが単一の存在であるという幻想を前提としてしか……ありえない
■なるほど
結局、素人のロングテールに読んでもらうことを目指して書いてあるようだから、
ウェブ進化論 - わんこ日記 (2006-04-17)
半分ぐらいまでは読んだものの放っておいたのだけど、なるほど読んでいてどうもパッとしないなぁ、と感じたのはターゲット層とずれていたせいか。
自分が時代の最先端に追いついているとはお世辞でも思えないが、この本をあまり面白くないと思うぐらいの位置にはいるらしいぞ、と。
追記とトラックバック
エントリを書いた時点でトラックバックしなかったのには理由があった。
わんこさんが書かれた「素人のロングテール」の意味を図りかねていたからだ。
だって「Web進化論」の主なターゲット層は、ロングテールの側じゃなくて恐竜の"体"の側だ。本屋に行けば平積みされている本が"しっぽ"の側のはずがない。でも、これは単なる間違いとして指摘していいものかというと"そうではない"と、私の直感が引き留めていた。なので、その点は保留にして筆を置いた。
で、ここからはつらつらと考えていた結果。
これは"こちら側"と"あちら側"の対照性ではないか?
「Web進化論」で"あちら側"というフレーズが繰り返し使われる。モチーフといっていもいいかもしれない。
活字で出版された「Web進化論」から見るとネットワークは"あちら側"になる。ところが「『Web進化論』についてのネット上で記述」――つまり、「わんこ日記さんのエントリ」や「このエントリ」――からみるとネットワークは"こちら側"になってしまい、「『Web進化論』が流通しているところ」が"あちら側"になってしまうわけだ(以下もその様に読んでいただきたい)。
"あちら側"では「Web進化論」は、恐竜の胴体、もしかしたら頭部になる。しっぽは、まぁあらためていうことも無いだろうけど、全国の出版物の流通にはほとんどのぼらない書名も知られずに消えていく数多の出版物たちだ。
あるいは、読者という点から語ると、「『Web進化論』を一種の啓蒙書として読んでいる人達」が恐竜の胴体や頭部を「買い支えて」いるということになる。
では、「『Web進化論』を一種の啓蒙書として読んでいる人達」は"こちら側"では竜の胴体や頭部*1を「読み支えて」いる人たちになるか?
否。
と、ここまできて、わんこさんが、
素人のロングテール
と呼んだ理由に追いついたかな? と思った。
■ゲーム
なんか、今ひとつ。
夢オチならば道中どんな理不尽な展開であってもいいが、夢オチで無いならば様々なことに整合性をつけないといけない。
いや、そんなことはないか。面白さのために整合性を無視してもいいという局面はある。
でもパズラーやコンゲームでそれを許すと、作品の存在意義そのものが揺らぐことになるだろう。
ホラーっぽい短調でスローなオドロオドロしい曲と、ロックな曲を伴奏させた場面には感心した。
こういう作品を見ると「スパイラル」の歩君ってすごいよな、と思う。
■リアルな事実
という表現を見かけて、同義反復だ〜、と笑ってしまった(mixiなので引用はしない)。
でも後になって、違うか? と思い直した。
リアルな虚構。
フィクショナルな事実……いや、事実なフィクション?
ふむ。"ありそう"な表現だ。
あるいは、リアルという言葉をネットの対義語として捉えるとかもありか?
とか。
■何を書き込むのだろう?
とか書いてみたり。
掲示板への自動書き込みソフトでよいのがあったら教えてください。無料のがあったらそれが一番ですが…
人力検索はてな - 掲示板への自動書き込みソフトでよいのがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
*1 というのは例えば「梅田さんのコラムやブログ」を思い浮かべてほしい。
2006-04-28
■今週の いい電子
4ページ目で爆笑(註:家で読んだ)。
よめそうなオチだけど、よまないで読んで正解(註:"よむ"は囲碁や将棋の"読む")。
■PCハイジャックで資金移動
攻殻機動隊 S.A.C. で、トグサくんの奥さんが「株でもうけちゃった〜」とトグサくんに話をしたあと、誰もいない部屋でコンピュータが勝手に立ち上がってセラノゲノム社の株の買い注文を出していたのを思い出した。
で、それを見た時は、その注文でインサイダー取引、というか捜査上で入手した情報を元にした株取引、みたいなことで査問とか懲罰を食らってトグサくんが自由に動けなくなるとか、法廷に引っ張り出されて課長や少佐も動きを封じられる、とかいう展開を予想した。のだけど結局何も無かったなぁ。消化しきれなかった伏線なのか、その後の展開で"説明しきっているのだけど私が判っていない"だけか。
にそのシーンがあったか、削られていたか。思い出せん。
■郵貯のインターネットバンキング
パスワード入力が、ソフトウェアキーボードからできるようになってるぞ。
2006-04-29 インターネットにおけるルール&マナーの教育の構図
■それはそれ、これはこれ
内容の方はしっかりと笑わせていただきましたが。
たしかに、Winnyの話題で「違法行為を蔓延させた刑事責任は出版社にある」という指摘が出てくるときに真っ先に槍玉に挙がるのは「ネットランナー」であることが多いが、実際のところ同誌はそれほど悪質なものではなく、セキュリティ対策をキチンと啓蒙するなどの良い点もあるとの主張を耳にすることもあった。
高木浩光@自宅の日記 - 編集長が見て見てと言うので買ったネットランナー5月号の仰天内容
ここだけ読んで、あれ? と思った。
「セキュリティ対策をキチンと啓蒙するなどの良い点もある」というのと「違法行為を蔓延させた刑事責任」に繋がりがないぞ。
「違法行為を蔓延させた刑事責任」が本当にあるなら――まぁそれを判断するのは司法の仕事だけど――「セキュリティ対策をキチンと啓蒙」していたからといって罪が減免されるわけじゃないでしょう? ということ。
追記:トラックバックを2つ出してしまった。迂闊!
ついでの追記
あたりの記事も含めて考えると、"一般ユーザー"に「Wordには脆弱性があります」とか言うと「それで書いている途中で消えちゃったりするんだ」とか思われていそう。"一般ユーザー"からすると脆弱性≒虚弱性なのかも。
ところで……、"一般のインターネットユーザー"ってどういう母集団なんだろう。
■インターネットにおけるルール&マナーの教育の構図
学校・教育委員会の無断リンク禁止の、あるいは、「サーバー様」から続く話題。
"財団法人インターネット協会" のサイト。「インターネットにおけるルール&マナー 公式テキスト」というものを出している。
だけどこのサイト、どうしたものか……。
ウェブページで見ることができる、他の人が書いた絵や文章、他の人がとった写真なども、勝手に使ってはいけません。使いたいときは、それを作った人(著作権者)から許可をもらうことが必要です。
インターネットを利用するためのルールとマナー集(こどもばん)
からたどっていく「解説」。
だれか他の人が書いた文章や絵を、自分が作るウェブページや宿題のレポートなどに使いたいときには、その文章を書いた人やその絵をかいた人(=著作権者)から許可をもらわなければいけません。
解説
嘘を子供に教えようとしている。いや、教えさせようとしている、か?
(引用)
著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
このことを伝えていない。(余談。2項に依り、学校・教育委員会のサイトが無断転載禁止とした場合には従わないといけないのだろうか? と思ったりして)
自分で作ったウェブページの内容には責任をもちましょう。いい加減な内容のウェブページを作って公開してはいけません。
インターネットを利用するためのルールとマナー集(こどもばん)
自分のウェブページを公開するということは、世界中の人たちが、あなたの作ったウェブページを見るかもしれないということをわすれないようにしましょう。
解説
と書いておきながら、「自分のウェブページを公開するということは誰かがそれを報道、批評、研究などの目的で引用することがある」こと、それが「著作権の侵害ではない」ことを教えないのはなぜだ?
リンクをはる前に、リンクするときの条件や注意書きがあるかどうかを確かめましょう。よくわからなかったら先生や親などに相談しましょう。
インターネットを利用するためのルールとマナー集(こどもばん)
リンクに対する条件や注意書きが何も書かれていない場合や、「リンクを貼るときには連絡をください」と書かれている場合には、リンクを貼る前に、リンクを貼りたい(相手の)ページ、自分のページのURL、リンクの目的、公開は学校内かそれ以外か、などを記述して、リンクの許可を得るようにしてください。
教師・保護者の方へ
リンクに関する注意を無視して安易にリンクをはると、リンク先の相手に不快な思いをさせたり、トラブルを生じたりする可能性があります。
もう一度問う。
「自分で作ったウェブページの内容には責任をもちましょう」と子供に教えるのは何のためだ? 間違ったことや事実ではないことを書けば、誰かに批判されるだろう。リンクに対する条件や注意書きを盾にとって、そんな批判を封じ込めることなどできやしない。
「リンクに対する条件や注意書きが遵守されるべきものである」と、「リンクに関する注意を無視して安易にリンクをはる」のがよくないことだと、子供に信じさせてはいけない。
自分が書いたことがWWWを閲覧する多くの者の目に晒される可能性があることを、正しく伝えなければならない。「リンクしないでください」と書くのは意味のないことだと、教えなければならない。
あの日、あのコメント欄に*1、「此れでも駄目なら、サーバー様に相談しますので」と書いた人が、あのあとどういう思いでWebを見ていたのだろう? どうしてあの人はあんなことを書いてしまったのだろう? 先生に相談したりとかしたのだろうか? 後になってから「リンクしないでください」と書くのは意味のないことだと、そう知らされたら、どんな思いを持つのだろうか?
真に問題なのは市発行の「保護者の皆さまへ インターネットの有害情報から子供を守ろう!」なんて紙(というか学校から配られたプリント)で紹介されているのが、上記のような内容のサイトだということ。
正しくないリテラシを植えつけられようとしているのは、子供達だけじゃない! その保護者達もまた、その危険にされられているんだ!
さらにさらに恐ろしいことに、正しくないリテラシを植えつけようとしているのが無自覚な学校や教育委員会、総務省・経済産業省主管の財団法人だというこの構図!
2005年7月のこれ。
10月のこれ。
これらを経てもなお、仙台市や北九州市の学校・教育委員会に変化がないのがなぜか? 10月の slashdot.jp の記事なんか、"仙台市や北九州市"と名指しされていて、当の学校・教育委員会にとっては結構な恥だと思うのだけど?
仙台市や北九州市の学校・教育委員会は結局何の議論もしなかったのだろうか?(ちなみに、こんなことが話題になってますよ、という情報は両方の市教育委員会のサイトやメールアドレスに対してポスト済なのだ)
仙台市や北九州市在住の、保護者達は何もしなかったのだろうか?
その問いの答えを「保護者の皆さまへ インターネットの有害情報から子供を守ろう!」のプリントにみた思いがした。
子供達だけではなく、保護者達にも、同じ様なリテラシが育っているのではないのだろうか? という、それはとても嫌な予感。
最後に。エントリ中で何の断わりもなく"リテラシ"と書いているけれども、これは全て本来ならば"ネットワークリテラシ"や"Web リテラシ"、もしくは"情報リテラシ"とするべきところを、くどくなるので省略しているだけ。勘違いなきように。
*1 なんのことか判らない人は、ちょっと右に書いてある"サーバー様"のリンクをご覧あれ。
2006-04-30
■ハチミツとクローバー 9
一家揃って観てしまったよ。
はぐちゃんの絵画教室が省かれていたのは残念。予想済ではあったけど。
森田さんがカタヌキしているカットには笑った。
1話の冒頭の時点で着地点がここであることは判っていたわけで、黒田さんもその様に構成していったのだろうし、最終巻収録の3話はほぼ予想通りのエピソードが入り、予想通りのエピソードが削られていた。
そういう意味では、観る楽しみが一番少なかった巻ではある。
それよりも、ハチミツとクローバー2 はどこを着地点にするのだろう? という方が気になっていたりして。
■ガンダム展
せんだいメディアテークでやっている
を見てきた。とはいっても私はあまり乗り気では無かった。見にいきたいと言いだしたのはカミさんの方。
なにしろアート展なのだ。
見る側に「解釈する能力」が要求されるのだ。ガンダムに思い入れのない(というか、有名なエピソードは知識として知ってはいても、ストーリィの順番に沿って並べることさえできない)私に、その能力がないのは自分自身判っていた。
はい。面白くなかった。
ガンダムを知っていれば意味を見つけられるんだろうなぁ、と思って帰ってきた。
終わり。