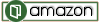2006-03-01 雑記
■Ever17 再プレイ〜
DCではなくてPS2版(Premium Edition)を購入しなおして。
今度はディティールを楽しむのだ。
■Amazon
本以外の商品についての、情報の表示直しました。
■届いた〜
しかし、THE MOVIE のサントラはこれで3枚目(1999 バージョンも含めて)だぞ……。
■はてなもどき
リクエストを全部はてなに丸投げしているのかな?
でもそれだとログイン処理はうまくいかないし……。あ、ログインパスワード盗むための偽装サイトなのかもなぁ。
なりすましはてな?
昼サイブログ2.0 - なりすましはてな?
2006-03-02
■デジタルデータはコピーを取るとオリジナルと同じものが得られるので「オリジナルという意義」は薄れる
っていうのは、SF小説や漫画で見なれた常套句だけど、この現実の今になってようやくこの常套句が真実味を帯びてきたのか。
の続き。
でもデジタルデータっていう言葉は違和感があるな。デジタルは離散量、アナログは連続量、だし。
紙媒体(ペーパーメディア)の対義語って何だろう?
メディアレスだろうか。いやもちろん、PCのメモリやHDD、プロキシのキャッシュに、サーバのログ、etc……といった何らかの媒体(メディア)の上でしかデータは存在しえない。でもデータの存在に媒体の種類を問わないのも確か。
あの「厳密に定義できないし何だかよく判らないがそんな感じ」で使われた*1「マルチメディア」という言葉の復権だろうか? とはいえ、過去に別の意味で使われた言葉を引っ張り出してしまうのも愚行。
さて?
■Optimus keyboard
のページに更新がかかったみたいだ。
End of 2006 の部分だろうか?
This spring のステートになっている商品の"Optimus Upravlator"って何だろう……。
■DS Lite
30台抽選に400人弱で1/13の確率。
外れたよ……。
■3月購入予定
3日
17日
Q.E.D.証明終了(23) (講談社コミックス月刊マガジン)(加藤 元浩)
21,22日
25日
30日
楽しみなのは、「魔女からの伝言」。
*1 「Web2.0」も同じ様な使われ方をされつつあると思う。O'REILLYの提唱した言葉からかけ離れて、という意味で、ね。
2006-03-03
■アンチウィルスとパーソナルファイアウォール
NortonInternetSecurityをやめて(というか更新時期が来たので)、NOD32 アンチウィルスとZoneAlarm(無償版)の組み合わせに。
NISは確認ダイアログが出るまで時間がかかりすぎる。自前で「安心してもいいソフト」のDBを持っていて照合しているせいだろう。きっと。
で、ZoneAlarmにした。このマシンにする前に英語版を使っていたのであまり不安はなかったのだけど……。
ハイバネーションから復帰後のHTTPアクセスがどうもおかしい。
pingは問題なく通るのでDNSの名前解決というわけではないのだけど、HTTPアクセスでもIP直打ちだとちゃんと通る。
ZoneAlarmのせいか、NOD32のせいか、はたまた組み合わせの問題か。
……んー。どうしようかなぁ。
■アンチウィルスの確認
ということで、アンチウィルスだけNorton先生に入れ替えて挙動の確認。
こういうこともあろうかと、期限切れになる前に環境整備をしているのさ〜。
アンチウィルス製品の動作確認は以下の様にするべし。
ウィルス駆除ツールが動作しているかどうかを確認するための「実際にはウィルスでは無いがウィルス駆除ツールが検出するべき」ファイルが規定されていたかと思います。
実際にはテキストエディタか何かで作成できるようなファイルだったと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1105936310
■で結局
NOD32のインターネットモニタの所為らしい。
http監視を止めるか、互換性を高くするサーバを記述するかすると大丈夫。
……みたい。
2006-03-04
■極限の読み方
n→∞の部分だけだと「nを無限大に飛ばして」に一票。
\(~\lim_{n\to\infty}~n^2~+~n\)
なら、「nの二乗プラスnの、nを無限大へ飛ばしたときの極限」もしくは「リミットnを無限大 の nの二乗プラスn」に1票ずつ。
\(~\lim_{n\to\infty}~n^2~+~n~=~\infty\)
なら、 (予想済でしょうが)「nの二乗プラスnの、nを無限大へ飛ばすと正の無限大に発散する」もしくは「リミットnを無限大 の nの二乗プラスn イコール 正の無限大」に1票ずつ。
lim n^2+n = lim n^2(1+1/n) = ∞
n→∞ n→∞
とまぁ基本的な式だが、最近気になることがある。
これ
n→∞
人によって呼び方が違う。
友人A… リミットnが無限大まで
友人B… リミットnを無限大に飛ばして …だったけな?
友人C… リミットnを無限大まで
Niblheim Niflheim - 頭の中が∞
こんな方もいます。
確かに、これはわかんない……。
2006-03-06
■ハチクロ 7 みたぞー
うぉ〜。レーベルが薔薇だ〜。芸細かっ。
Chapter 17
凧揚げのシーンがカットなのは予想通りだった。
カズさん。原作を読んだときは「ちょっと格好いい」というイメージだったけど、アニメの演出は自分とは違っていた。が、それもまたよし。
……こんなとこで「引き」かよ!
Chapter 18
で、アバンタイトル! で森田さん。
この回、うえだゆうじさんの一人舞台だ〜。
最近せんせいのお時間の工藤もうえださんだということに気がついた。
■桜の季節です
いや。パン屋とかケーキ屋とかお茶屋さんとかね。
桜あんデニッシュとか、さくらフロマージュとか、桜フレーバーの緑茶とか煎茶とかほうじ茶とか。
で、桜フレーバーの緑茶が今あるのだけど……失敗。お湯の温度低すぎた。
2006-03-07
■本日のティータイム
シナモンティー。
ハーブティーの部類に入るので長めに抽出しても苦くならない。むしろシナモンの香りが出てくるのでその方がよい。
■森博嗣vs西尾維新
対談にvsを使うのは好きじゃないけど、帯にそう書いてあるのだ。
西尾維新さんは森先生のファンだったのか。
というか、西尾維新さんの世代になると「森博嗣以前の世界」を知らないんだ! ということにビックリ。
まぁ、よくよく考えてみれば当たり前。
今のライトノベルの中心的読者が「ライトノベル命名以前」のヤングアダルトを知らないのと一緒。
自分の世代で言えば、「ロードス島以前」のファンタジーを知らないのと一緒。
もちろん上記は極論であって、例えば、私でさえ「指輪物語」はちゃんと一応読んでいるわけで。
この本、森博嗣先生の小説群のディティールにあたる、細かな仕掛けの解説があるので、何度も読み返した人でないと興を削ぐことになると思う。
■雑記
はてなRSSの代替をどうしようかな〜、とか考えてみたり。
■新機種が出たよ〜
んー。デザイン面ではもう新味を入れるつもりはないのかな。
Bluetooth搭載して携帯電話やPHSとの連携とか機能面でもまだ追加の余地はありそうなのに。
HDD増やしてコンテンツ充実路線はあまり面白みがないというか。
現行ユーザの乗り換えのみで、新規ユーザの獲得は期待でき無さそうな……。
■反変の継承と共変の継承
- BarはFooのスーパータイプであるべき。クラスの型と引数の型において、サブ/スーパ関係が反対方向になるので、これを反変規則と呼びます。
- BarはFooのサブタイプであるべき。クラスの型と引数の型において、サブ/スーパ関係が同じ方向になるので、これを共変規則と呼びます。
(略)
檜山正幸のキマイラ飼育記 - 牛が牧草を食うのが共変継承なのか?
今日は余裕がないから次回に。
次回に期待。
言語レベルで規定される様な例(言語)ってあるのかしらん。指摘通り、問題領域によってどちらが良いか? というのは変わると思うのでそんな規定をされたら困るような?
あ、でもJavaでは、throws節*1に限って言えば、反変規則が適用されていてコンパイラに文句言われるな。
*1 句?
2006-03-08
■PC購入
俺のところ、パソコンは持ち込み禁止だって総務が言うんだよ。
2ちゃんねるベストヒット: パソコンは持ち込み禁止
んで、部品は持ち込んでもいいのかって聞いたらいいよっていうんだよ
CPUもHDDもほかなんでも構わないっていうから一式バラで買って
自作したら、パソコンは持ち込み禁止だというんだよ。もう
この会社辞めよう
PCの購入が稟議書必要だったころ、まだ珍しかったベアボーンとHDDとメモリを別々に物品購入してPC組んだことがあったなぁ。
そのあと、社内備品がしっかりと管理され始めた時に、先輩と「これどうしましょう?」って会話をしたことが。
IPアドレスを振ってもらわないといけないので普通にリストに書いたけど……。
■セキュリティホール実証コードの扱い方
あぁ、なるほど。
セキュリティホールの実証コードをちゃんとした手続きを経ないで公開することは、犯罪と見なされる可能性があるのだな(法律の解釈上で、ね)。
「非常に残念なことだ。合意書への署名なしにマルウェアを配布することは違法になるからだ。一連の保護が必要だ」とMARAの声明文は続いている。
ウイルス対策企業とMARA、トロイの木馬「Crossover」のコード引き渡しで対立 - CNET Japan
■Javaだから高額 か 高額だからJava か
高橋氏はちゃんと認識しているが言葉の綾でそういう表現になってしまったか、インタビュアーか編集の段階でそういう表現になってしまったか、そのどちらかだと思うのだけど……。件の部分は地の文に書いてあって、「」で括られた高橋氏の発言の部分では無いからねぇ。
真相は果たして??
それは話が逆だろう。「10年持ちそうな」という言葉で比喩されるような、つまり、しっかりとした設計や構造のアプリケーションを作るときには、設計を事前に十分に吟味しておく必要があることから、「費用もそれなりに高額」となるところ、その際に使用言語として、Javaを使わない理由がない(またJavaが向いている)というのが本来の世間で言われていることの筋道だろう。「Javaだと高額になる」ではなかろう。
高木浩光@自宅の日記 - 「高橋メソッド」的突貫工事と、脆弱性を排除する構造設計は両立するか
■親指シフトっぽいタイプミス
ここに来ている人は、「ゲームにはまった子ども」に悩む保護者が多いわけで、講師批判ととられかねない発言をしてせ伝わらない。ぼくの発言は、やはり講師批判と取られかねないものだった。
リヴァイアさん、日々のわざ: 「あなたの方がおかしい」と森昭雄氏に言われるの巻(世田谷区のゲーム脳講演リポートその2)。追記あり
発言をしてせ伝わらない
お開きになってから、ぼくの周りに5、6人の人が集まってきて、「よく頑張った」的なことを言ってくれたことで、やや気持を取り直す。
リヴァイアさん、日々のわざ: 「あなたの方がおかしい」と森昭雄氏に言われるの巻(世田谷区のゲーム脳講演リポートその2)。追記あり
400人のうちの5、6人。
少ないけど、アウェイにしては、悪い数じゃない。
うん。「確かに悪い数じゃない」と思った。
■ハチ公神話
昼サイブログ2.0 - 工エエエエ(´Д`)エエエエ工昭和10(1935)年3月8日午前6時過ぎ、ハチはその幸うすい一生を終えました。享年13歳でした。
http://www.welcome-shibuya.co.jp/history/hachiko/
私が認識している「真実」はむしろこちらの方に近い。
こういう話の真贋は難しいですけどね。
2006-03-09
■ハッシュの脆弱化
非常によくまとまっているようだが、ハッシュそれ自体は(狭義の)暗号ではなくて*1、主要な暗号化方式の礎として重要な地位を担っている技術だということが伝わりにくいような?
それは前提の知識として判っている人だけ読んでね、ということなのか。
■タイトルだけで内容が判る
void GraphicWizardsLair( void ); // ファイルネームに.bakを追加するときは mv filename{,.bak} とすれば良いことを知った
覚えておこうっと。
■最近読んだ漫画
「よげんのしょ」の最後のページが世界の最後、って寸法?
そろそろ終わり時だと思うのだけど、これからどれだけ続くやら……。
珍しく、長い続き物だった。
stage.62 を読んで若干陳腐な落としどころだとも感じたが……
いまだこの世に正義が存ぜぬのなら、
おまえの魔法の杖で
これを生み出してはくれまいか!?
という黒淵の言葉でstage. 61 を締めくくっている効果もあって、それもまたよし、と思わされた。
stage. 62 の終わり方も余韻があっていいねぇ。
ヒロインのルルのキャラクタが掴みかねてちょっと消化不良気味。
もっとも吸血姫シリーズは、吸血姫側が狂言回しで人間側が主人公というパターンが多い*2から、これもそう読むべきなのか……。また読み返す機会にということで。
BLEACHもあるけどあれはまぁいいや。
2006-03-10
■差分ソフト
普段はDF*1を使っているけど、
これで紹介されているソフト差分がある部分でのスクロールの処理が面白い。
あと、Simple Pane Diff Layout が使い出があるかも。
ただ、ファイルを最初に2つ指定するUIはいただけない。
起動した後にファイルを2つドラッグ&ドロップするか、ファイルを1つずつ2回D&DすればOKというDFのUIは秀逸だと思う。
■OSAKAフォント入れて使ってみる
まだちょっと慣れない。
が、ちょっとした気分転換というか、雰囲気を変えてみるというか、楽しい感じ。
■奇麗なフォントを
差分ソフトのエントリは結城さんのサイトの、
からアクセスしてみつけたものだけど、たまたま私もフォント関連のサイトを探して見ていた(OSAKAフォントを入れたのはそのため)。
にあるフォントとか参考になった。あとIPAフォントもわりと奇麗(というか具体的に言うと、アンチエイリアスがかかって表示されるのがよい)。ビットマップ取り除いたバージョンもいいかも。
2006-03-11
■勧誘の電話
もう5年以上前になるけど会社にこの手の勧誘の電話がかかってきた。
こんな感じ。
電話「仕事上、コンピュータでWordやExcelなどお使いじゃないですか? 必須スキルになっていますよねぇ」
私「まぁ、そうですね」
電話「そのあたりの学習コースなどについてご案内さしあげているんですけど」
私「私、コンピュータのシステムエンジニアなのでそういうのは要りません」
おしまい。
電話に出たときの社名で判るだろボケ! と思った。
■フランケンシュタイン あるいは、現代のプロメテウス
読了。
面白かった。
でもこれ、現代日本に生きている私が読むと、"ホラー"とは言い難い。キリスト教のパラダイムの中でこそ"ホラー"・"恐怖譚"なのだろう。
巻末の解説(これが非常に詳細で読み応えがある)を読む限り、文学的にはゴシック小説、もしくはロマン主義の小説と見られているようだ。
とはいってもこの小説が書かれた経緯――「ディオダディの館の幽霊会議」は広く(?)知られている。すくなくとも、メアリ・シェリーにあってはやはりこれは恐怖譚だったのだろうと思う。
ディオダディの館の幽霊会議に関しては、
このあたりを。あ、映画の名前「ゴシック」だっけ。
さておき。
原作を読んでみるとケネス・ブラナーの映画「フランケンシュタイン」――というよりはロバート・デ・ニーロの"怪物"と書いた方が通りがいいかな?――はわりと原作に近かったのか? と思った。
ただ、映画を観たのも11年前(!)、しかもマスク [DVD]の併映だったからたまたまついでに見たのだからちょっとあやしい。
構成は凝っている。
海洋冒険家のロバートの手紙から始まる。北海を冒険中の彼が、その行く先をほぼ氷に閉ざされつつある、という状況下で一人の男を氷から拾い上げる。それが、ヴィクター・フランケンシュタイン。この物語の主人公(の一人)。
フランケンシュタインを介抱しつつも「なぜこんなところにいるのか?」という疑問を持つロバート。やがてフランケンシュタインから驚くべき話しを聞くことになる。
そして、フランケンシュタインの一人称による物語が始まる。
彼の生い立ちが語られ、パラケルススやアグリッパ、マグヌスへの一時の傾倒。そして大学への出発。自然科学、あるいは化学の英知との接触。
彼のみが辿りついた論理と、おぞましき実験。そして――生まれ出でたる"怪物"。
だが"怪物"は、自分の創造主とのほんの一瞬の邂逅ののち、姿をくらます。
フランケンシュタインは、自分の成したことに恐れをいだき、精神と肉体の平衡を失う。親友の看護もあり、復調した彼は故郷へと帰ることになる。けれどそれは安らぎの帰省ではない。弟ウィリアムの死の報せ。それが理由だった。
そして、その帰路で"怪物"を目撃する。
ウィリアムの死は事故ではなかった。容疑者がおり、裁判があり、刑が執行される。けれどヴィクターだけは知っていた――そうだと確信していた――ウィリアムの死は"怪物"の手によるものだと。それでは、ウィリアムの死の本当の犯人は? と自分に問わざるをえない。真の犯人は自分なのではないか!?
そして、"怪物"と再び邂逅する。
ここで小説は"怪物"の一人称に変わる。"怪物"が創造主ヴィクター・フランケンシュタインに語るのだ。
で、ここがこの小説の肝心な部分。
彼(と称するには理由がある。後述)の体験、心理。彼が何を得、何を失ったか? が肝だと思うのだ。
で、"怪物"は「自分のために女を創造してもらいたい」と――それはもちろん"アダム"に対する"イヴ"というアナロジー――フランケンシュタインに迫る。
そして小説はフランケンシュタインの一人称に戻る。
この後はストーリーはあまり書かない様にする。
色々なものを失った彼は"怪物"を追うことを決意する。旅を重ね、"怪物"の足取りを追い、あるいは"怪物"に導かれ、極寒の地へ進む。
そうして物語は、ロバートの手紙へと再び舞い戻る。
このロバートだけが、フランケンシュタインと"怪物"とを結びつけるただ一人の人物である点もまたこのストーリーの肝だろう。
"怪物"とフランケンシュタインの両方と邂逅する、唯一の人間なのだ。
解説にある通りのことを繰り返すようではあるが……。
ロバート,フランケンシュタイン,"怪物"の三者の共通項。ロバートとフランケンシュタインとの共通項。フランケンシュタインと"怪物"との共通項。
語り手を3人配置し、それらがきれいに「畳み込まれる」形を成しているところが、退屈さを感じさせないポイントだと思った。
果たして解説にその通りのことが書いてあったわけだけど。
後は余談。
まずは映画の話。
正直に告白すると、ピーター・カッシング & クリストファー・リーの映画はもちろん、実はボリス・カーロフの映画も観ていなかったりするのだな……。ボリス・カーロフが"怪物"を演じたものと、その続編、エルザ・ランチェスター*1が出てくるものは観てみたい。
解説が読み応えがあると書いたけれども、「フランケンシュタイン・コンプレックス」について、アシモフの
の序文から始め、カレル・チャペックの「R.U.R」、ウェルズの「モロー博士の島 (偕成社文庫)(H.G. ウェルズ/佐竹 美保/H.G. Wells/雨沢 泰)」、ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」、その映画「ブレード・ランナー」まで展開を見せてくれるのが面白かった。
「フランケンシュタイン」を読んで初めて、アシモフが「ロボットの時代」の序文になぜメアリ・シェリーの話を出してきたのか? と思いめぐらせることができる。そういったこともまた、"読む愉しみ"というやつだろう。
以下、印象に残った部分を適当に引用。
p123 フランケンシュタインの独白。
愉しみは全て死者への冒涜でした
ハチミツとクローバーのリカさんを思い出した。
p124 フランケンシュタインの許嫁、エリザベスの台詞
ああ、ヴィクター、偽りがこうももっともらしく見えてしまうのだったら、自分の幸福のたしかさを信じられる人などいるかしら?
んー。このフレーズ、既視感があるなぁ。なんだっけ……。
p156
森のナイチンゲール
このナイチンゲールは――意訳でもいいから――訳した方がよいのでは。鳥の名前だと判るかな?
p167
"怪物"が「失楽園*2」を読んでいるのが興味深い。
p280 フランケンシュタインの台詞
そんじょそこらの企画屋と自分を一緒にすることはできなかった。
この「企画屋」の意味がちょっと取れなかった。原文の単語が知りたかった。
さらに余談を続ける。
1994年の映画。ケネス・ブラナー監督・主演……じゃないのね。出演者の筆頭が"怪物"のロバート・デ・ニーロなんだ。まぁ、フランケンシュタインも"怪物"も、どちらも主人公だとは思うけどね。
なんでこの小説を読もうと思ったかというと、
の後書きがきっかけだった。
■ダス・リート・フォン・デア・エルデ
という言葉が頭に残って離れなかった。
クラシックか何か、音楽の題名だと思うけど、なんでドイツ語での記憶がこんなにしっかりとあるのだろう。
なんて思っていたら、思い出した!
の最終章の副題だった。
■PalmMagazine永久保存版
はう。予約できん。
追記:あ、出版年を1年勘違いしていただけだった。これから出る本じゃないのか。
追記の2:Amazonの書誌データがおかしいのかもしれない、とも思ったが確認できん……。
追記の3:Amazonに書誌データ修正情報を送信。
■カレル・チャペック
カレル・チャペックその人とはぜーんぜん関係ない話。
紅茶や紅茶用の小物、その他雑貨を扱っていて、その名前を「カレル・チャペック」という店があった。
……"ロボット"という言葉を初めて世に出した、「R.U.R」の作者の名前が、なぜこの"かわいらしい系小物類を扱う雑貨ショップ"に使われているのだろう? と不思議でいっそ店員に聞いてみようかとまで思っていたら、いつのまにか店の名前が変わっていたという意外な結末。
実際、どういう理由だったのだろう?
■トポロジーなゲーム?
面白い……かも? lv4になると頭がこんがらがってくる。
lv5はクリアできんかった。
via
追記
ハマる。
lv5 5:28
lv6 6:49
lv7 6:42
lv8 11:04
lv9 5:55
lv10 9:11
とりあえずの記録。
# kmt-t 『今、レベルをスキップしてレベル35を見てみましたが、すさまじいですね。本当にクリアできるのか。』
僻地のプログラマkmt-tの日記 - 明日また病院行く
lv35... ウチのマシンではマウスでつまんで移動するのがもっさりしていてやる気がおきない……。
2006-03-12
■戦隊シリーズ30作目
記念ということで、豪華CDセットが出るぐらいは予想(あるいは覚悟)していたのだけど……、
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 秘密戦隊ゴレンジャー(ささきいさお/堀江美都子/こおろぎ’73/コロムビアゆりかご会/ウィルビーズ/八手三郎/石ノ森章太郎/渡辺宙明/堀江美都子 ささきいさお)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> ジャッカー電撃隊(ささきいさお/こおろぎ’73/八手三郎/石ノ森章太郎/渡辺宙明)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> バトルフィーバーJ(MoJo/コロムビアゆりかご会/フィリングフリー/八手三郎/山川啓介/渡辺宙明)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 電子戦隊デンジマン(成田賢/小池一夫/渡辺宙明)
スーパー戦隊シリーズ30作記念主題歌コレクション 太陽戦隊サンバルカン(串田アキラ/こおろぎ’73/コロムビアゆりかご会/山川啓介/渡辺宙明)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 大戦隊ゴーグルV(ファイブ)(MoJo/こおろぎ’73/ザ・チャープス/小池一夫/渡辺宙明)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 科学戦隊ダイナマン(MoJo/こおろぎ’73/小池一夫/京建輔)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 超電子バイオマン(宮内タカユキ/康珍化/矢野立美)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 電撃戦隊チェンジマン(KAGE/さがらよしあき/矢野立美)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 超新星フラッシュマン(北原拓/園部和範/及川恒平/奥慶一)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 光戦隊マスクマン(影山ヒロノブ/売野雅勇/藤田大土)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 超獣戦隊ライブマン(嶋大輔/大津あきら/藤田大土)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 高速戦隊ターボレンジャー(佐藤健太/松本一起/米光亮)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 地球戦隊ファイブマン(鈴木けんじ/売野雅勇/山本健司/松下一也)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 鳥人戦隊ジェットマン(影山ヒロノブ/荒木とよひさ/つのごうじ/山本健司)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 恐竜戦隊ジュウレンジャー(佐藤健太/つのごうじ/そのべかずのり/山本健司/ピタゴラス 佐藤健太/ピタゴラス)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 五星戦隊ダイレンジャー(NEW JACK拓郎/八手三郎/山本健司)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 忍者戦隊カクレンジャー(トゥー・チー・チェン/ロブ/E-Cup’s/冬杜花代子/山本健司/ZIPANGU/西川啓介/大田幸子/山内喜美子)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 超力戦隊オーレンジャー(速水けんたろう/八手三郎/米光亮/まきのさぶろう)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 激走戦隊カーレンジャー(高山成孝/森雪之丞/小路隆/奥慶一)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 電磁戦隊メガレンジャー(風雅なおと/朝川ひろこ/八手三郎/藤林聖子/奥慶一/鷹虎/佐橋俊彦/朝川ひろこ 風雅なおと)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 星獣戦隊ギンガマン(希砂未竜/EVE/藤林聖子/亀山耕一郎/佐橋俊彦)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 救急戦隊ゴーゴーファイブ(石原慎一/高山成孝/桑原永江/藤林聖子/渡辺俊幸/佐橋俊彦/高山成孝 石原慎一)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 未来戦隊タイムレンジャー(佐々木久美/NAT’S/磯谷佳江/吉井省一/亀山耕一郎/NAT’S 佐々木久美)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 百獣戦隊ガオレンジャー(山形ユキオ/Salia/桑原永江/中川幸太郎/奥慶一/Salia 山形ユキオ)
<スーパー戦隊シリーズ 30作記念 主題歌コレクション> 忍風戦隊ハリケンジャー(高取ヒデアキ/影山ヒロノブ/及川眠子/池毅/籠島裕昌/影山ヒロノブ 高取ヒデアキ)
こ……これはさすがに……全部買うと27,300円ですか? みたいな。
さらにこれにアバレンからボウケンまでのCDを今から買うと結局合計いくら?
しかも、
【スーパー戦隊シリーズ30作記念 主題歌コレクション全巻購入キャンペーン】
「スーパー戦隊シリーズ30作記念 主題歌コレクション」全26タイトルを全巻購入すると、
ボウケンジャーまでの主題歌マキシシングル全30枚収納可能コレクションBOXがもらえる!
ですか?
戦隊15作*1のダイレンジャーの時にCD2枚組で出してくれたじゃないか〜。CD4枚組で1万円台でCD-BOXで出してくれてもいいのに……。
しかし……Amazonを「スーパー戦隊シリーズ 30作記念」で検索して資料を見ないで放映順に並べられる自分がちょっと嫌(ウソ)。
追記
出てます。
■書きたいネタはあるけれど
技術系の話を前のエントリの下に書く気にはなれないなぁ、というかまだまだまとまっていないのでまたそのうち。
■なんでニコリの社名が出ない?
おいおい。ニュースタイトルで「数独」というニコリの登録商標を使っておきながら、本文での紹介で社名を出さないというのはどうなの?
ふざけんな!
日本のパズル出版社が数独と名付け、
Yahoo!ニュース - 共同通信 - 東京の西尾さんら入賞 イタリアで「数独」選手権
*1 計算が合わないって? 本当はボウケンジャーはスーパー戦隊シリーズの28作目なのだ。その辺は大人の事情ってやつなんだろうなぁ。
2006-03-13
■nanoに貼っていた保護シールが剥がれた
& 折れてしまってもう貼れない。
アップルストアに行ったらこんなの
があった。
ドックに差せる様に下の蓋が外れる。それもドックに差した時にピッタリにはまる様に斜めにカットしてある。
買ってきた。
2006-03-14
■虚業
サンデープロジェクトでは、実業か虚業かとかいう無意味なテーマが話し合われ、その中で僕の本も紹介されたらしい。
My Life Between Silicon Valley and Japan - 虚業という言葉について
虚業。
嫌な言葉だなぁといつも思う。嫌な言葉のわりに、日本の製造業系、重厚長大系の企業幹部は、この言葉をとてもカジュアルに使う。自分たちがやっているのは「実業」だけど、君がやっているのは、たかが「虚業」だろう、というふうに人を見下すのである。
「虚業」という言葉をマスメディアで見るたびに思うのだけど、日本社会での最大の「虚業」は当の「マスメディア業界」なんじゃないか? と言いたくなる。
サンデープロジェクトを見ていたわけではないので、当の番組企画を名指しで批判するものではない、と前置きした上で。
サンデープロジェクトがそういう論調で進んだのかどうかは知らないのだけど、「モノをつくらない産業」が「虚業」だと言うなら、宝くじだって、プロスポーツ選手だって、政治家だって、「虚業」や「虚業家」だよなぁ。
で、「実業か虚業かとかいう無意味なテーマが話し合」った様子を番組にするなんて、それこそまさに「虚業」だとも思うのだ。
に、ある起業家のこんな言葉が書いてあったと思う(本は手放してしまったので正しく引用できません。あしからず)。
日本には「情報」にお金を出すという感覚がない。知っていそうな人に電話をかけて「ちょっと教えてくれる?」と軽く訊けばいいと思っている。だから、まず「情報」が商品であることを認識してもらうのが一番大変だった。
というような感じ。それを思い出した。
■やっとtDiaryのトラックバックの仕様が判ってきた
書き始める前にテストぐらいしておけよ。 > 自分
■メールが来たりて
CDが開く。
いや、ノートブックでは(怖くて)到底使えないけどね。
もう5年も前にあったソフトなんだ。全然知らなかった。
via
MOONGIFTについて - MOONGIFT|オープンソース・ソフトウェア紹介を軸としたITエンジニア、Webデザイナー向けブログ
AL-Mail や Becky! 用。
■暗号
現在最新の暗号通信でも、傍受して50年くらい保管しておけば余裕で読解できちゃうのかなって思う。
スラッシュドット ジャパン | エニグマ暗号文、64年ぶりに解読
解読不可能な完全系(unbreakable system)を成すためには、原文の長さ以上の鍵文を準備する必要がある。
適切な暗号系なら、鍵文よりも短い通信に関しては暗号文が解読の手がかりにならない。ここからは理解が怪しくなるが、要するに「ブルートフォース以外に手段がない」ということなんだろうと思う(違うかもしれない)。
鍵としての乱数列を用意して、かつ使用済の乱数列は再利用しない、という条件下では暗号系を完全系にすることができる。が、これは事実上――技術的にも経済的にも――無理な話。ちなみに「使用済の乱数列を再利用しない」というのは言い換えると「無限に長い乱数列を用意する」というのに等しい。これが難しいのは、コンピュータで生成できるのは擬似乱数であることも関係する。
通信の文長が鍵の長さを超えると、暗号系は脆弱になっていく。SSL/TLS通信でも、定期的に共通鍵を取り替えていく、という方法を採っている(はずだ)。一応書いておくと、公開鍵暗号方式を使っているのは通信相手の確認と共通鍵の交換で、それ以降の通信は共通鍵暗号方式だ。
基本的に暗号っていうのは「秘匿可能な期間を十分確保する」技術だと思っている。
だから「今使っている暗号はいずれ脆弱になる」というポリシーで行動することになるわけだ。
あたりを読んでみると、
原理的には、エニグマ暗号が正しく使われれば、解読は不可能ではないにしても、かなり困難である。
とある。続けて、
解読の手がかりの多くは、使用者の不注意に基づく。
と来るのだけど。
この本、暗号を解読したという事実の方が、逆に「秘匿しなければならない」情報になってしまうという様な話も読める。
暗号解読の成果という機密を保つために一つの市を見殺しにした、という様な話もあったらしい。
話は変わるが、2ちゃんねる語の様な隠語も立派な(?)「暗号」だ。「電車男」が出版された時、一読しただけでは意味が判らない部分が多々あって、読み終わってからカバーを外してみて脱力した経験がある。
「暗号を解読した」とあった時に「暗号文を平文に戻せた」という意味なのか、「暗号系が破られた」という意味なのか、あるいは「暗号鍵が判明した」という意味なのか、注意して読む必要はあるなぁと思った。
他の参考資料。
「絶対安心な暗号」なんてない(理想上にしか存在しない)という話。
2006-03-15
■UTF-9
最後の1行で納得。
今年のXデーに向けて"仕込み"をしている人は多かろう。
あー、昨日書いた暗号のエントリじゃないけど、こういう時の"Xデー"なんていうのも符牒、つまり秘密通信の一種、だなぁ。
■4コマ雑誌
を買った(といっても古本で安かったから)。
パラパラと捲ってみたら知らないネタがあった。
私はライフオリジナルを毎月買っているのだけど、この漫画はライフオリジナルとくらぶオリジナルに両方に掲載されていているから。
つまり半分は未読なはずで、そんなわけで買った。
小坂さんはガクランコンビナート以来のファン*1で、このハルコビヨリもかなり笑いながら読んだ。立ち読みなどは危険なので買って読むわけだ。
「掲載誌が2誌あってネタの半分は雑誌で読んでいない」というと思い出すのは、
まんがタイムオリジナルの掲載は、六鹿くんが(ほぼ)主人公の扱いではあるけれどニュートラルな視点でのエピソード。
で、まんがタイムスペシャルの掲載は、同じエピソードを別の登場人物の視点で――つまりは明確な物語の主格としての主人公を設定した状態で――全然違うストーリーとして描くという離れ業!
タイムオリジナルの連載で「天然の六鹿くん」という題で書かれた4コマ。その2コマ目,3コマ目,4コマ目が、タイムスペシャルの方の1コマ目,2コマ目,3コマ目に使われる。台詞と行動は同じ(なぜか服装が違うけど)。でもそこに六鹿くんのモノローグが入って4コマ目が入ってその題が「天然じゃない六鹿くん」。
なんて凝った構成! と感心しながら読んだ。
*1 まんがライフオリジナル秋月りす増刊号に2度(だと思う……)掲載。サークルコレクションの井上の高校時代の姿が見られる。が、すでに捨ててしまっている……。無念。
2006-03-17
■ウィルス?
コンピュータウィルスの定義は広い。
SQLインジェクションでDBのデータとして自己を複写し、そのデータがそのまま別のICタグに書き込まれると、その別のICタグも「同様の手段で自己を複写する」ICタグになってしまう……のだろう。
さて感染能力はあるわけで、現時点では実証実験にとどまっているわけだが、ここをついて利用者に不利益を与える同種のものがでてくる可能性は高い。
ここで「データをサニタイジングする必要がある」「データをサニタイジングすれば大丈夫」なんて言ってしまうと、それはすでに思考停止以外のなにものでもないのだろうなぁ。
植え付けたウイルスは、『SQLインジェクション』と呼ばれる手口で、無線タグ・システムのデータベースを改ざん。
Yahoo!ニュース - WIRED - 無線タグに入り込むウイルス、研究者が試作
■C.M.B. 読んだ
C.M.B.って東方の三賢者の頭文字だったのか!
気がつかなかった……(本誌では読んでいない)。
ヒロイン(と言えるのか?)の造形ががQ.E.D.と同じなのがちょっと気になる。
主題として、「謎を明かす」のではなくて「不思議を見せる」ことをもっと突き詰めた方が面白そう。
まぁ、1巻ということでとりあえず人物 & 基本設定紹介みたいなものだから、これからに期待。
さて、東方の三賢者(定冠詞が付いて the three magi)からちょっとネットで調べてみた。
Many references to the three magi can be found in various games and shows. For example, in the Neon Genesis Evangelion anime/manga series, a supercomputer (called "MAGI") is divided in three distinct parts, all of which are named after the Magi.
Magus - Wikipedia, the free encyclopedia
英語版の Wikipedia に出てくる例が、"Neon Genesis Evangelion"だ。
なんだかな〜。
■Q.E.D. 23 を読んだ。
いとこだったのかよ!
……それは兎も角。
ついに出てきたか。リーマン予想。
とはいっても、こいつは命題を理解することそのものが困難な代物(私は理解できない)。どういう風に扱われるかに興味があった。
やってくれました。「リーマン予想に魅入られた者」というテーマでくるとは……。ミステリィとしての仕掛けは、秘密通信。広義でいう暗号解読。
さらに燈馬君はMIT時代、リーマン予想をテーマにしていたことが明かされる。そういえば、「Q.E.D.―証明終了 9」収録のエピソード「凍てつく鉄槌」でゼータ関数に関する発表をしていたという描写があったことを思い出した。
かつて自分の手で閉ざしたその道を、また歩き始めるのか。
水原さんは燈馬の名を呼び、そして……何も言わない。
もう一つの話は、もうこれは読んでいて頭に浮かぶのはあれ。ミステリィの大御所クリスティの「オリエント急行の殺人」。
ということはそれがミスディレクションとして使われるだろうというのは、見当がつくわけで。ミステリィを読むときには「謎を解こう」という姿勢を棄てている私でも――私はきれいに騙されたくてミステリィを読んでいるので――そこまでは思いつく。
あとはどういう風に来るのか。と思ったら、直球のロジカルな謎解きでスッキリした。
さて、次は"もうひとつの QED"を読まないとね。
追記
四色問題の話がちょっとだけ出てくる。どんな白地図でも隣り合う地域同士を別の色で塗るためには四色で充分である、という命題。
買ってあるけどまだ読んでいない。やれやれ。
Q.E.D.の説明だけだとちょっと判らないと思うので補足……しようと思ったのだけどなんか簡潔に説明できないや。でも一応。
ケーニヒスベルクの橋の問題(http://www.hyuki.com/math/interview.html, あるいは前述のエピソード「凍てつく鉄槌」を参照)に見る様に、地図の問題はグラフ理論に還元可能だ。
あるグラフの集合を考える。それは次の性質を持つ。いかなるグラフを持ってきてもその「あるグラフの集合」のどれか一つがサブグラフとして含まれる。
そんなグラフの集合を不可避集合とする。
次。
ある不可避集合を考える。それは非常にうまい集合である。どんなグラフも(不可避集合の定義から)その「ある不可避集合」の要素をサブグラフとして持つ。かつ、そのサブグラフを取り除いたグラフが四色に塗り分け可能なら、元のグラフも四色に塗り分け可能である。そのような非常にうまい不可避集合があるのならば、四色問題は解決する(らしい。自明ではないが理解不足により割愛)。
ここにコンピュータを使った。その様な非常にうまい不可避集合をコンピュータを用いて求めた。
問題は、そこで作られたプログラムが本当に正しいのか? が当のプログラムを作った本人達以外が理解できなかったこと。
故に、それを以て本当に「証明」あるいは「解決」と言えるのか? という論争を巻き起こした。
現在では、そのプログラムも詳しく検証され、改良され、四色問題の解決が否定されることはなく四色定理となった。
■QED 神器封殺
袋とじの中についてはノーコメント。
その他についてもいくつか「知らなかったなぁ」とか「全然気がつかなかった」とか思ったことはメモを取っておいたけど、別にここに書き出すほどのものはないなぁ。
中盤は非常にワクワクしながら読んだ、とだけ書いておこう。
あ、そうだ。
ビタミンB1を世界で初めて発見したのは日本人だった。が、その発見者鈴木梅太郎さんは医学博士ではなかったという理由で医学界から無視され、結局その1年後にイギリスの研究所で同一の物質を発見して「ビタミン」と名付けた。この「ビタミン」は"その後に"ようやく売られるようになってやっとのことで脚気(かっけ)で死亡する人数が減少しはじめた……。
という話が載っていた。
攻殻機動隊SACの地上波放送分を撮っておいたのを観ていた(というかBGVにしていた)のが、つい昨日の話だったのでこのタイミングの良さにビックリした。
■買ってきた
遅まきながら。
目次をながめてみたら「高速道路」論の章があるみたいだったので買うことにした。
本屋で見かけてしまった。
葛生千夏に出会ったことで気にいっていたこともあって、対訳なら、と思って買った。
あのぉ、"The Raven"中の非常に重要な韻でもある"Nevermore"が、対訳の方で日本語に訳されていない("Nevermore"とそのまま書いてある)んですけど……。
いや……でも、しょうがないのかなぁ。
の「もはやない」はちょっと味気ないし、
の「またとない」は――私は非常に好きだけど――現代の言葉遣いとしては違和感があるし。(追記:2007年10月に改版されました。訳は変わっていないものの漢字の字形、仮名遣いは改められています)
でもその違和感がまた雰囲気があっていいと思うんだけどなぁ。
大鴉はいらえた、「またとない。」
あぁ、でも英語詩を日本語に訳してしまうという行為自体が不毛なのか?
(追記)
これを書いた後も、時々読んでいるけど、対訳版は英語詩を英語で楽しむためのものであって、訳はそのための手助けだということなのね。
なので、上に書いたことは完全に的外れで、英語詩の韻を意識させるという意味では "Nevermore"のままでも正解。
英語詩に親しんでおくと、
の聴き方もちょっと変わるね!
■バッドノウハウって
葉があります。"><
http://q.hatena.ne.jp/1142543835
ソフトウェアの世界で「バッドノウハウ」という言葉があります。システムに欠点があるとき、それを直すのではなく、その欠点を回避するために磨き上げられた手段、というようなものを表す言葉です。
ひさしぶりのhatenaカテゴリの様な。
ともかく。
バッドノウハウって……違うよね?
確かに「システムに欠点があるとき、それを直すのではなく、その欠点を回避するために磨き上げられた手段」はバッドノウハウが醸成される原因(の一つ)ではあるだろうけど、バッドノウハウという言葉が指す概念はそうではないハズ。
自分の言葉で書いてみるか。
"問題を解決するための手段"であるはずのソフトウェアが――もしくはそのソフトウェアを使うために――その問題およびその周辺のソフトウェアとは全然関係がない知識を必要とすること。もしくはその知識そのもの。
あるいは、
あるソフトウェアが、それを使う上で周辺のソフトウェア――もしくは同種のソフトウエア――と著しく異なる様な特徴を持ち、目的を果たすために周辺ソフトウェア――もしくは同種のソフトウエア――とは異なる知識を必要とすること。
てな感じか。
自信がないので、他人任せで良回答を期待。
■無限大という数は存在しない
の姉妹編。
「『無限大』は『数』ではない」という話。
「無限大」が「数」だとしよう。
その言葉の感覚から「無限大」は「他のどんな数よりも大きい数」ということになるだろう。
しかしながらこれは「自然数が無限にある」ことに反する。
なぜなら「無限大」が「他のどんな数よりも大きい数」であるなら「自然数の集合」は「無限大という数」という上界が存在することになってしまうから。
したがって「無限大」なる「数」は存在しない。
終わり。
これは数学の話ではなくてただの言葉遊びなのであしからず。
■極限で使われる=は等号ではないのではないか?
つらつらと考えてみたこと。
Wikipediaの"極限"の項目の引用から。
これによれば、数列\(\{a_n\}\) がある値αに収束するとは、次のようなことを言う。
\(\normalsize\displaystyle~\forall~\varepsilon>0~\;\exists~n_0\;~\textrm{~s.t~}\;~\bigg[n>n_0\Rightarrow~|a_n~-~\alpha|<\epsilon\bigg]\)
これが極限であり、この事実をこう表現する。
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~=~\alpha\)
さて。この = は等号なのだろうか?
なにやら難しい理屈から数列\(\{a_n\}\)
の極限なるものを考えたときの表現であってこの = は「左辺と右辺が同じ値ですよ」という意味での等号では無い気がする。
数列\(\{a_n\}\)
が正の無限大に発散する時、どう書いただろう?
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~=~\infty\)
だった。
で、一つ前のエントリの話になる。\(\normalsize\displaystyle~\infty\)
って、「数」じゃないのだ。だから、この = は普段使っている"等号"とは意味が違うんじゃないか? と思った。
さて、数列\(\{a_n\}\)
,\(\{b_n\}\)
が共に収束し
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~=~\alpha\)
かつ \(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~b_n~=~\beta\)
である時、
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~\pm~b_n~=~\alpha~\pm~\beta\)
であり、また、
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~~b_n~=~\alpha~\beta\)
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~\frac{a_n}{b_n}~=~\frac{\alpha}{\beta}\)
でもある、極限の最初の方で教わる規則だ。
……よく見て欲しい。
\(\normalsize\displaystyle~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~\pm~b_n~=~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~a_n~\pm~\lim_{x~\rightarrow~\infty}~b_n~=~\alpha~\pm~\beta\)
と最初に書かれることはない。一つ前の段落に書いたそれぞれの式の = は、普段目にしている"等号"とは似て非なるアナロジーとしての記号のはずなのだ(それは、普通の計算式の = と、方程式の = が似て非なるものであることに近い様な気もする)。
ところが、いつのまにか上の様な書き方が、それと意識しないうちに忍び込んでくる。
最初はアナロジーとしての記号だったものが、いつの間にか普通の計算式での = と同じ様に機能してくる。
で、思ったのだ。
まるで、プログラミング言語における演算子のオーバーロードみたいだなぁ、と。
終わり。
これもまた、数学の話ではなくてただのお遊びなので、あしからず。
2006-03-18
■LOOX
debianを入れていた LOOX の PCMCIAカード部分が逝ってしまったみたいだ……。
追記
ただの自分の勘違いだったらしい。
2006-03-19
■無限大という数は存在しない、のだけど……
の続き。
これは数学の話ではなくてただの言葉遊びなのであしからず。
と結んだのはなぜか?
数学の話でなら、ちょいと事情が違うからだ。
実は「無限に大きい数」や「0に限りなく小さい数」というのを考えることはできる。
それとも、その様な概念を公理として取り入れ、新たな公理系を作ることができる、と言うべきか。
まぁ、もっとも、そこでは「無限に大きい数」や「0に限りなく小さい数」は無限に存在することになるのだけど。
そんな、「超現実数」のお話。
わお! Knuth 先生だ!
2006-03-20
■コメント
旧はてなダイアリーから一部のコメントをコピーしてきました。
(内部情報では)今日の日付で大量のコピーがされたことになっています。
おしらせ、というよりは備忘録みたいなものということで。
2006-03-21
■ダウンロード可能性
確かに、公表すると検索,ダウンロードをする人が増える→ダウンロード可能性が高くなる、ということになるなぁ。
日立は2005年9月の段階で、すでにこの事実を把握していたが、「Winnyの特性上、被害の拡大を防止するため、公表を控えていた」
ジャスダック、Winny介してシステム情報流出 - nikkeibp.jp - IT
2006-03-22
■回答したけど間違えた
シフト演算で3分の1の様な奇数を実現する方法がわかりません。
人力検索はてな - シフト演算で...
\(\normalsize\displaystyle~\sum_{n~=~0}^{n}\) と書くべきところを、
\(\normalsize\displaystyle~\sum_{n~=~1}^{n}\)
と書いてしまったような気がする。まだ回答は開かれてないけど、メモ。あとでフォロー。
■サマータイムマシン・ブルース
いやいや、楽しかった & 可笑しかった。
SFを研究していないSF研の部室に突如現れるタイムマシン。昨日壊してしまったクーラーのリモコンを、昨日から持ってこよう! として……というコメディ。
タイムマシンがどっからきたの? っていうのは藤子・F・不二雄の「あいつのタイムマシン」と同じで、"それはいいっこなし"。
タイムパラドックスが起きない――予定調和になっている――作りなので話はさほど複雑ではない。
のだろうけど……、細かいネタは色々落っこちていそう。
初見で「あー、なるほど!」と思わされたのは一箇所。
舞台版も面白そうだ。
2006-03-23
■linux Pentium-M
の組み合わせの消費電力制御ってどうなってるのかなぁ、と思ったので検索してみたメモ。
ただ、Debian標準のカーネルでは、Speedstep-centrinoモジュールがACPIを参照する設定になっているので、
Matzにっき(2004-09-09)
■サマータイムマシン・ブルース 再見!
実はどっかに欺瞞がしかけてあるんじゃないか? とか疑っていたので図を書きながら観た。
OK! おもしれー!
まぁ、いずれ2回観ないと面白い所が判らない映画だしね。
■比喩の持つゆらぎがスパイウェアというモノを曖昧にしているのでは
しかし、スパイウェア検出ソフトを使って自分のコンピュータをスキャンしてみたときに、たくさん検出されてびっくりしてみたら、大半がcookie*1で(あとはせいぜいJWordとAlexaが検出されるという程度で)拍子抜けしたという人も多いだろう。スパイウェア検出ソフト売り業者たちは、製品を実行しても何も検出されないという事態を避けるため、わざとcookieをスパイウェアに含めることにしている。
高木浩光@自宅の日記 - ブログからFUDへ? 眞鍋かをりは30個の「スパイウェア」のうちcookieの数を明らかにせよ
ふと思ったこと。
スパイに対する比喩としてのスパイウェアという言葉が、「スパイウェアというモノ」を曖昧にし、ゆらぎを作っているのではないか。
ウィルスは比較的早くから使われ始めたこともあって、一時期必要以上に恐れられた期間は確かにあったかもしれないが、比喩としてうまく機能しているのだろうか*1。
スパイウェアという比喩をもっと分化するというのはどうだろう。
ストーカ(stalker 跡を追う者),スティーラ(stealer 覗き見る者)とか。
*1 とはいっても、ウィルスと細菌の区別がつかない人に対して比喩が効果的に働くとは思えないケド。
2006-03-24
■パラケルススの娘 3 を読んだ
さまよえるユダヤ人。
その彼の友人。
彼の、無力ゆえに美しい、おだやかな言葉が、弟子たちやさまざまな者たちの意図によって勝手に歪められていくのを、私はもう見ていられなくなったのだ。
彼が慎重に落とした、ひとしずくのルビー色の液体。
セイクリッド・ブラッド、。
そう呼ばれる、彼女の名前。それはクリスティーナ。
そして、彼女のメイド、レギーネが使う印形(シジル)。彼女が呼ぶ、その言葉。
2006-03-25
■卒園式
上の子の卒園式だった。それなりのいでたちで家族写真も撮った*1。
あとは小学校への入学を待つのみ。
……さて、問題は、だ。入学する学校のサイトが、
許可なく転載・転用・複製・リンクすることをお断りします。
なことなんだな。
さてさて、1手打ってはいるけどそれがどう効いてくるか、効いてこないか。効いてこなかったら次はどうしようか。
■Cthulhuの正体 その果ての狂気
「クトゥルフ神話って、近代唯物科学そのものの世界観なのよ。ここ250年、科学がものすごい力を発揮したんで、われわれ、それに沿って研究してきたわけだが、『これどうも俺たちって何の究極的目的も持たずにできあがっているてきとうな産物なんじゃね?』って」
「うはは」
「研究していけばいくほど、知識を得れば得るほど、それがあからさまになっていってしまうのが、薄々わかっていながら、学ばざるを得ない。それにそれを知りたくもある。でも理解したくない嫌な予感もする。だから『クトゥルフ神話』技能は『唯物科学』技能でもいいんだ」
指輪世界の第二日記 - Aの魔法陣とクトゥルフと近代唯物科学とオカルト
クトゥルフ神話と近代唯物科学の世界観の類似という指摘には唸らされた。
むう。科学が何かを解き明かしていけばいくほど、全体は曖昧模糊になっていく。
cthulhu mythos では――私が捉えている感覚としては――核心に近づけば近づくほど主人公の"それまでの世界観"が破壊されていく、といのが恐怖の骨格。
この、「薄々判っていながらも学ばざるを得ない」科学の行く末って、
でも引用した、エリアルコミック収録のやまむらはじめ作品「熾天使 来臨る街」の世界観、
栄華の頂 恣(ほしいまま)にするには とある文明社会
理論・科学 そして――それらを操る技術……
"永遠"だった筈の 加速度
―ある一点でだ―
突如 人外神技の領域へ 相―転―移……
ヒトは 完全に見失ってしまった
ヒトたちの行動 および思考の基盤 としてきた"世界観"を
それ というのも
ヒトの意識を 人の思うすべを
世界構造――物質レベル――に関与させる手段を 発見したから
結果――ヒトは 自らの立脚点を失う
世界は 現実と虚構の混沌……
――曖昧! ――曖昧! ――曖昧、曖昧、曖昧!!
………………
ヒト 愚かなるかな 悲しき実在――(非実在?)
この いたたまれぬ状態から 脱出すべく
新たなる 世界観を 確立すべく
影なき遍塞 あいまみむべく
試行錯誤 繰り返しの試行錯誤……
――精神の、永い"離散の旅(ディアスボラ)"の始まりである
ここは、そんな人々がおこなった、ひとつの試みの世界
世界構造を言語に置き換えた街……
(引用註:先頭行"ほしいまま"は原文では"恣"のルビ。他、強調表示部分は原文では傍点。)
を彷彿とさせる。
*1 こういう発想は私の方には無い。むしろカミさんの価値観からの行動である
2006-03-26
2006-03-27
■ライアー・ゲーム ≠ 嘘つきのゲーム
題名のインパクトはあるけど、「嘘つきのゲーム」とはちょっと違うような。
「うまく嘘をついた者が勝つ」というよりは「嘘を見抜いた者が勝つ」ゲーム。見抜いた上でそれを上回る嘘(=勝つ手段)をつく必要はあるけれども、絶対的に必要なのは「嘘を見抜く」能力の方だと思った。
2巻の最後、小数決ゲーム*1で残り4人の状態で、最初に1票入れてしまうという手段。囚人のジレンマの変奏曲だな、と思った。
だけど、勝利に至る手段はあらかじめ仕掛けられた、「嘘」。
追記
「囚人のジレンマの変奏曲」と表現したけど、本質は全く違う。
囚人のジレンマは「系に属する全員が『系の最善』を目指して行動すれば『個の最善』を得られる、という論理的な状況にあるにも関わらず、人間の心理が必ずしもその論理的な最善の行動をとるとは限らない」と言い換えられる(あってるかな?*2)。
ライアー・ゲームはそもそも、全員が「個の最善」を目指すゲームなので、「系の最善」なんて要素を持ち出すこと自体無意味。
追記
ところがところが3巻になって「系の最善」が出てきたよ……。
↑の追記での論議は半端だったものの方向としては間違ってなかったな。とあとになって思う。
■鋼の錬金術師 13
あ、特典のトランプ、まだ見てないや。
本編は……もうちょっとテンポよく進んでも良さそうなのに? と思った。前巻が結構進展あったからちょっと緩めたか、それともシャオメイをもう少ししっかりと描きたかったか。
2006-03-28
■リヴィエラ が意外に面白い
意外に面白い、というか「こんなシステムありか!」みたいな新鮮さがある。
はちょっと私が期待していたシステムとは違うみたい。
面白い/面白くないの判断は全然できないが、予想と違っていたので凍結。というかリヴィエラをプレイしているからなのだけど。
2006-03-29
■ジャーゴン 秘密通信 通過儀式
2ちゃん語を使わないとか
理由垂れてたサイトだかブログは
そんな事言っていること自体がまた他の痛みである訳で
昼サイブログ2.0 - 2ちゃん語を使わないとか
どんな理由が書いてあったのか判らないのでどういう"傷み"なのかも判らないけど。
2ちゃん語と俗に呼ばれるようなもの――つまりジャーゴン(jargon)の機能は、秘密通信であり、また通過儀式《イニシエイション》の一部なのだな。
秘密通信というのは"トラトラトラ!"とか"Xday"あたりと同じ。あらかじめ意味を共有していないと通じない、という効果を持つもの。
あるいは、
「ドリップは終わったか?」
「ああ。だがフィルターが汚れてしまった。新しいのを用意してくれ」
なんて感じのもそうだ。
もっともネットではあらかじめ取り決められた秘密通信文なんてのはなくて、自然に醸成されるものだ。
それを称して「文化」と書いたりする人もいるようだが……。
通過儀式というのは、なんだこりゃ? となる最初に読む時の障壁を超えられるか? という話。それが読める様にするか? しないか? という選択を迫られる。読む! と決めたら努力をしないといけない。
通過儀式というのは秘密結社で使われる言葉だけど。ちなみに秘密結社というのはショッカーに想像するようなものとは違って、存在自体は公になっているものが多い(フリーメーソン*1とかね。)。"秘密"なのは、結社に入るための条件や、その結社に属しているかどうかを確認するための符牒とかの方。
昔で言うと「やおい」とか、最近で言うと「ツンデレ」とかいうジャーゴンも、オタク*2であるかを確認するための符牒なんだよね。
実際ツンデレってげんしけんで最初見たときに全然判らなかったし。
あ、つまり「2ちゃん語を使わないという理由垂れていたサイト」に見られる「痛み」ってのは、扱っている内容から想像できる"書き手"像と一致しない、っていう、そういうことなのかな?
……なんかつまんない話になっちゃったな。
おしまい。
追記
前にも書いたんだっけっか。書いていてつまらないのも道理。
追記の2
時間を遡ってパソコン通信時代には、通信量を1バイトでも減らしたいという涙ぐましい理由により、ジャーゴンが形成されていった、というのもあったんだなぁ。
追記の3
これはクイズ。
昔会社の先輩宛で香港から来たメールに、
BTW, ……
という書き出しの文があってこれはなんだ? と悩んだそうだ。後になってクイズとして私も見せられたけど、正解に気がつくまでに数分かかった。
■referer
"プロメテウスコンプレックス"や"フランケンシュタインコンプレックス"で検索してくる人がちらほら。
なんの影響だろうか。
そのエントリはこちら↓。だけど、私自身は何も書いてないぞ〜。
2006-03-30
■秘密通信
最近の戦争のニュースや、ガンダムSEED なんかを見ていても秘密通信の傍受、暗号の突破、なんて出てこないな。まぁ前者については、「相手の秘密通信での暗号の突破」というニュースは「自軍の秘密通信」以上の機密度になる*1から、話題に上らない方が自然なのだけど。
ガンダムSEED の時代だと暗号化方式は「充分に頑健」になっていて、かつ「鍵の秘匿」も高いレベルで行えるのだろう。宇宙空間に入ればレーザー通信も使えるし。レーザー通信は指向性が高くて傍受しにくいし、なおかつ傍受されてもそれと判るわけで。
あぁ、これは銀英伝を見ていたときにも思ったんだったな。
■彼自体
うーん。「彼自体」、「あの人自体」という表現をしている時は、本当に「彼自身」を、「あの人自身」を指しているのだろうか?
「あの人自体、もともと××だから」というのは、「関連者から観察され認識の一致がある」という前提を含んでいる様な気がする。
「彼自体はOKだそうです」は、「彼が主体的に動いた」のではなくて「受動的な立場にある」という認識を含んでいる様な気がする。
面と向かって訊かれた時のことを想像してみる。
「君自身はどう考えているんだ」と訊かれると"意志の表明"を求められているのだろう。
「君自体はどう考えているんだ」と訊かれると"どう認識しているのかね?"というニュアンスの様な気がする。
果たして……?
「彼自体はOKだそうです」とか「あの人自体、もともと××だから」という言い回し、増えていませんか?
ものも人もまとめて「自体」で面倒を見るのは楽だけれど、「社長自体はどうお考えですか」とか言ってしまわないようにしたいもの。
まんぷく::日記 - ものは「自体」、人は「自身」
■DS Lite入手
えっ? GBAのカートリッジがはみ出るの? 知らなかった。
まぁ、GBAミクロがあるからいいんだけど……。
■ハチミツとクローバー 8
森田さんがあゆに怒るシーン、よかった。
追記
あと3話? かな。野宮さんが鳥取にいっちゃったということは、青春スーツ再装着完了! は見られるのだろうか?
今回は(も)森田さんがいい味出てるなぁ。
2006-03-31
■「その他」というカテゴリを付けること≠カテゴリをつけないこと
etcというカテゴリはここでは「なんでもあり」だ。
ならカテゴリを作らなくても良さそうなものだが、そうでもない。
本当にどうでもいいエントリには"カテゴリを付けない"から。
もひとつ。
etcというカテゴリの中でも2種類の区別がありそうだなぁ、と考えた。
自分の身に起こったことと、自分で考えたこと。
このエントリなんかは後者。
この2つは区別してカテゴライズしたほうがいいのかしらん。
■永・久・保・存・版!
あぁ、やっぱりTungsten C か TX を今の内に入手しておくべきか?
今のTG50の外装がボロボロなのをみるにつけ心の中をよぎるそんな思い。
「プロジェクト・パーム」は電子出版の運びとなるらしい。よかったよかった。
■会社員としてやっていけるのも才能
あ、私、会社員として楽しく仕事をやっていけるのは立派な才能だなと最近気がついて。会社にぶら下がる、って意味じゃなくてね。
日経ビジネス EXPRESS X : 【ボトムズを作ってしまった男、語る:PART2】1人でやれば、どうやってでも食っていける
他にも面白いところがいっぱいあった。
例えば「新しいサイトをやりたいので、これこれの予算と人をください」というと、「いくら儲かるんだ」という話がたちまち始まるんですけれど、「今の仕事をやります、今まで通り数字も上げます、その代わりこれも、自分だけちょっと余計に働くからやらせてもらえませんか」というと、「うーん、まあ、やってみれば」みたいな感じに、意外となっちゃう…のではないかと。
日経ビジネス EXPRESS X : 【ボトムズを作ってしまった男、語る:PART3】自分が動けば、人も動く
こういう発想はしたことがなかった。
――実際にこの家建てた人が言うと説得力あるね。
倉田 このドームハウスは300万円の予算で、10カ月間の自分の労働で建てたんですが、お金に換算したら、外注で建てた場合は1000万円とか、1500万円とかにはなっているかも。
――なっているかもしれない。
倉田 ということは、僕がその年に1000万円以上の収入があったのと同じじゃないですか、本来は。でもお金持ちな感じはしないんですよね、自分でやると。
日経ビジネス EXPRESS X : 【ボトムズを作ってしまった男、語る:PART3】自分が動けば、人も動く
要は「やっぱり、収入は多ければ多いほどいいよね」という、かつての“常識”が作ったレッテルという気がするんですよ。
日経ビジネス EXPRESS X : 【ボトムズを作ってしまった男、語る:PART3】自分が動けば、人も動く
自分の言葉を書いている時間がないので引用だけにて失礼。
最後に、リンク。
さて、子供を風呂にいれないと……。