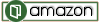2008-04-01
■ぽわそん・だぶりる
今日の日記に書かれたことはすべて嘘であるか間違いである。
■怪獣ソフビ大全
"あえてカタログ形式ではなく"ってあたりが気になる。
(BK1内容説明より)
ウルトラQからウルトラマンレオまでのウルトラシリーズと、同時期のゴジラシリーズの希少怪獣ソフビを一挙614体収録。単なるカタログ形式ではなく、「美しい怪獣の本」をコンセプトに美麗な写真を掲載。
■tDiary2.2.x 問題なさそう
正確には「問題ない」のは tDiary2.2.x ではなくて、私が自分で変更したソースの部分なのだけど。
結局、Subversion を使って、
- tDiay2.1.3 をこのサイトが使っている plugin に合わせて配置
- ブランチ
- 一方を 2.2.1 に、一方のこのサイトのソースで上書きしてコミット
- 2.2.1 の系に私の変更分をマージ(捨てた部分も多いけど)
という手順を踏んでやっとまともに動く様になったという。
自分で書いたソースはちゃんとリビジョン管理できるシステムに入れておかないとなぁ、と改めて思った。
あと、"リビジョン管理する"ことを考えてソース書かないとね。
(追記)
自分の Feed を Google Reader で見てみるとタイトルが、".."が付いてしまって途中までしかでていない。
タイトル部分を途中で切り取らないで全文出すように変更していたんだったかなぁ。
2.1.x で自分が手を入れた部分が捕捉不可能というエンジニアにあるまじき失態。
おかけで 2.2.x への更新がこんなに遅れたわけだし。
あと、自分の Feed は自分のリーダで確認することはわりと大切。
■"Availability" UI
なるほど! という UI をいくつか紹介している。
[Screens Around Town] TripIt, Theocacao, Gmail, and a look at "Availability" UI - (37signals)
以下気になったものを項目箇条書きとかなり怪しい訳を付けておく
■創造的「図解」の技術
Amazonのカスタマレビューでは惨憺たる評価。
いわれのない中傷ではないと思う。
図解について「文」で説明しようとすれば、無理がでるのも道理。
章立ても良くないし、なぜここにこの図が挿入されているのか、という唐突な例示が多すぎる(説明がない)。
でも読む価値がないとまでは思わなかった。
「説明文」はざっと読み流して雰囲気だけ感じ取って、あとは図解の豊富な例を眺めればよいんじゃないか。
そのぐらいの心持ちで読めばいいと思う。
理論立てて「図解はこうやるんだ」ときっちりと説明しているような本は(あるのか?)別に読めばいいんだ。
まあ、上で書いたような読み方をするには高くつく感もあるけど、紙質という面で考えれば妥当でもある。
*1 travel を訳したが、go でも意味は変わらないと思うので、ここでは"遠地への移動"というニュアンスの方が妥当なのだろう。
2008-04-02
■Rubyスクリプティングテクニック テスト駆動による日常業務処理術
結構楽しめた。存外に良書だ。借りて読んだのだけど、自分でも買おうか迷っていたりする(家に置いておくために)。
基本は、「ソフトウェア開発プロジェクトに参加していて、日々手作業による雑用におわれている人」を対象にしているので、「プログラミングなんて初めての人」ぱある程度切り捨ててしまっていると言っていい。
「いまさら"Hello World"から始まる本なんて読みたくない」けど、「他の言語を使っているけど Ruby も気になる人」や「なんとなくスクリプトを書いているけど Ruby についてもっと深く理解したい」人にはよいかと。
第1章はインストールや環境の話なので置いておくとして、
第2章 はじめてのスクリプト : ファイルインベントリを比較する
第3章 Rubyの事実 : 配列
で始まる。ちなみに"Rubyの事実"とついた章は要するにリファレンス。他に"等価テスト、そしてUnless","ブール値","正規表現","クラス(シンボルについて)", "ハッシュ","引数リスト","モジュール" などの章がある。
これらも意外に秀逸。
例えばモジュールの章、
19.1 入れ子のモジュール
19.2 モジュールをインクルードする
19.2.1 名前の衝突
19.2.2 入れ子とインクルードは異なる
19.3 クラスはモジュール
である。19.1 の前にリード文があって"普通の説明"はここに収められている。そこで終わらないのがこの本のいいところ。
目次を引用しておく
1章 さあ、Rubyをはじめよう
I部 基本
2章 はじめてのスクリプト : ファイルインベントリを比較する
3章 Rubyの事実 : 配列
4章 3つの改良と1つのバグ修正
5章 Rubyの事実 : 等価テスト、そしてUnless
II部 スクリプトを拡張する
6章 チャーン (churn) : 落ち着いてプロジェクトを記述する
7章 Rubyの事実 : ブール値
8章 我がよき友、正規表現
9章 Rubyの事実 : 正規表現
10章 クラスのデータとメソッド
11章 クラス(シンボルについて)
III部 Webの世界に飛び込む
12章 正規表現によるWebページのスクレーピング
13章 Webアプリケーションとの別の形での連携
14章 カンマ区切り値を利用する
15章 Rubyの事実 : ハッシュ
16章 Rubyの事実 : 引数リスト
17章 ヘルパースクリプトとアプリケーションをダウンロードする
18章 スクリプトの仕上げ
19章 Rubyの事実 : モジュール
20章 スクリプトの実行中に問題に遭遇したら
IV部 完ぺきなスクリプタを目指して
21章 フレームワーク : ブランクを埋めてスクリプトを記述する
22章 発見は作成より安全である
23章 最終的な考察
V部 付録
(略)
■申請があってから許可するんじゃなくて、まず許可してしまえ(ついでに"無断リンク禁止"なんてやめちゃえば?)
Forgiveness も Permission も辞書を見ちゃうとあまり違いがなくて、でもニュアンスは違うはずだし、と気にかかっていてずっとInstapaperに入ったままだったこの記事。
Twitter を使い始めて、ようやく意味が判った(ような気がした)。
Enterprise 2.0 Executive Forum | Blog | Forgiveness, not Permission
Tweitter で誰かを forrow するのは簡単。
相手の設定がそうなっていればボタン一つでOK。
でも、そうすると相手に通知がいく。相手がこちらを見て「何だこいつ?」と思ったら、相手は block することができる。
相手に許可を与える時に、まず申請をもらってそれに対してOKを出す。それが従来のやり方だった、と。相手は申請してから許可がおりるまで待たされることになる。
そうではなく、まず許可を与える。誰に対しても。誰かが申し出てきたら判るようにしておく。許可を与えたくなければ、拒否する。その方がずっとよい。
というような考え方を説明しているらしい。
金を払うまで使えないパッケージソフトよりも、一定期間使える試用版の方がいいよ、というメタファを持ち出すと当たり前の話なんだけど。
でも、ここではコミュニティとかコラボレーションとか、人と人との繋がりをどのように形成するか? という文脈で読むべきか。
Twitter で誰かが自分を forrow したよ、というメッセージが来る。
ちょっと見に行って、いかにも無差別的な forrow でなければそのままにしておいちゃえ、って思うもの。
もちろん誰もがそう思うわけではないだろう。最初にまずプロテクトしてしまう人はいる。
知らない人からforrowされるなんて気持ち悪い、という人は間違いなくいる。
それは"無断リンク禁止"の件をとってみれば分かることだけど。
でも"これからのネットワーク"は、そういう形には進んでいないんだな、と。
2008-04-03
■絶版のYA文庫は入手しにくい
なぜかという"卒業"してしまうので、実家に置きっぱなしになったりして、新古書店や古書店の流通にも乗らずに破棄されることが多いから。
ということで、
にはがんばっていただきたい。
などと口で言っているだけではいけないので、ちゃんと購読者になることにしようと思う。
■間違った手法で失敗すると、正しい手法で失敗することを怖れるようになる
といういい見本かも。
非正規形のDBを使っている技術者はJOINが遅くなることを体験しており、「正規化するともっと遅くなる」と誤解している。
DOA+コンソーシアム(ディー・オー・エー・プラス コンソーシアム)
なんとなく説得力がある。
「正規化するとJOINが多くなるから遅くなるんじゃない?」って考えがちなようだという観察があって、その根拠が「非正規形のDBを使っていてJOINが遅いことを体験しているから」ではないかという仮説を立てた。
でもその仮説が偽ならば、つまり「JOINが遅いのは非正規形のDBだからだ」が真だと言えるなら、「正規化するとJOINが多くなるから遅くなる」の根拠にはならなくなる。
それを実証してみました、と。
(なんとなく関係がありそうなこと
p118
人の脳はストレスを感じると、すでに知っている方法によってそこから逃れようとする、という話をしました。うまくいかないことが起こると、同じ個とを、"より一生懸命"繰り返す。それで解決することもあるでしょうが、まったく違うアプローチが必要なことも少なくない。
p64
仕事でも生活でも、私たちはみな、失敗するのではないかとか、うまくできないのではないかと思っていると、無意識に新しいものや良いものを遠ざけてしまう。
2008-04-04
■tDiary と plugin と referer
単純なメソッドだけを持つプラグインを書いて、その中で @cgi.referer としても nil が返ってくるだけっぽい。(日記表示で呼ぶ時)
TDiaryView に、
unless referer_filter( @cgi.referer )
def @cgi.referer; nil; end
end
と書いてある。
referer_filter の実装と、今自分の環境で登録している filter を全部見るか。別の道をいくか。
というところまで書きかけていたのでとりあえずアップ。
■ヘルマフロディテの体温
(BK1内容説明より)
背徳と情熱の町ナポリ。海辺の田舎町からやってきた青年シルビオは、謎めいた真性半陰陽の大学教授と出会う。男でもない女でもない教授が出す、奇妙な課題の数々。だがシルビオは、次第にその課題の虜となってゆく−。
「奇妙な課題」の中身次第では読んでもいいなぁ。
2008-04-05
■ダスキン からモップレンタルした
契約とかないんだ!
形態こそレンタルだけど、ニコニコ現金払いだからか。
2008-04-06
■まんがサイエンス 11
ロケットです。筆者の好きなモノです。
私の好きなネタです。
それだけに難しいのです。取れるアプローチが少なくなってきているのです。
墜落した
ロケットなんて古い技術のことは記録されていない。
ということで人間(もちろん子どもだ!)の出番。
宇宙って?
宇宙に行くって?
大砲? ロケット?
などなどのお題でお話が進む。
作者の十八番。
(関連)
2008-04-07
■Continuous Integration がうまくいく1つの条件
「Continuous Integrationを成功させる6つの方法」という感じの記事を紹介しているのだけど、最後の、
なによりこの6項目,それなりに感ずることができるチーム(個人じゃダメよ)だったら,よほどの事が無い限り困る事は無いと思うぞ。
2008-04-06 - marsのメモ
にやられた。
もっともすぎて返す言葉がない。
チーム全員がこの6つに関して価値観が共有できていれば、確かに、さほど心配要らないなぁ。
ネタ元はこっち。
MirosナBw Jedynak - .NET blog: 6 steps to successful Continuous Integration
■デザインバーコード
サントリーの「カテキン式」のバーコード、

などのデザイナーらしい。
BARCODE のリンクを辿ると、
このページ。センスいいなぁ。
"本棚"と"トイレ"がデザインバーコードを見られるリンク。
via
こっちのページは下の方に、バーコードをモティーフにしたポスターやデザイン作品も紹介されている。面白い。
■ "以前の日記へのリンク元"が変?
今気がついたけど、"以前の日記へのリンク元"が"今日のアクセス数"よりも多い気がする。
2.2.x の仕様変更をまた読まないと。
■ Prism 面白い
Proxy の設定
C:\Program Files\Prism\xulrunner\greprefs\all.js
に追記。
//proxy
pref("network.proxy.type", 1);
pref("network.proxy.http", "proxy.example.com");
pref("network.proxy.http_port", 8080);
pref("network.proxy.ssl", "proxy.example.com");
pref("network.proxy.ssl_port", 8080);
pref("network.proxy.no_proxies_on", "localhost, 127.0.0.1");
てな感じで。
自動設定は、
pref("network.proxy.type", 2);
pref("network.proxy.autoconfig_url", "http://proxy.example.com/proxy.pacs");
こうみたい。(via http://d.hatena.ne.jp/caffeine/20071028 )
便利なのは、2つのアカウントの iGoogle を同時にデスクトップに表示できるあたり。ということは Gmail もできるハズだ。
Prism
http://labs.mozilla.com/2008/03/major-update-to-prism-first-prototype-of-browser-integration/
2008-04-08
■WoW
あぁ懐かしい。
Windows NT 3.5でWOW(Windows on Windows)というサブシステムを使って、ユーザーがNT上でWindows 95アプリケーションを実行できるようにしたのだ。
Vistaに見切りをつけたMicrosoft (2/2) - ITmedia エンタープライズ
Windows3.1 アプリケーションだよな?
■ Collective と Collaborative についてちゃんと知ろう
読み応え充分。(追記 collective はここでは"集団で"というような意)
Getting to Know Collective and Collaborative :: Personal InfoCloud
collaborative と collective はあまり区別されないで使われてきた。辞書上ではあまり違いがないように書かれている。しかし私はこの2つには、social software 上では(when it comes to value in social software)、大きな違いがあると感じていた。
folksonomy が、collaborative tagging の類似語であるかのように使われている。それでは folksonomy は、マナーに基づいたタグ付け(tagging done in a collective manner)と区別するだけの新語のように思えてならなかった。そのことは私をひどく悩ませた。
というわけでこのチュートリアルを書くことにした、と。
面白かったのである程度、訳を書きたいところだけど今は勘弁!
■ blogger のように書く
最後の3つは簡単なこと。これを後ろに持っていくあたりがこの人のセンスか。
7. リスト*1にすることを怖れるな。人はリストが好きだ。
8. まず見せよう。"書かない"ままでは考えを明確にするのに役立たない*2。完ぺきになるまで待つことは、最低の戦略だ。
9. 話そう。隠さなくていい。装飾しなくていい。
というあたりはいいね。
■有能性の罠(Competency Trap)
いつか、これを受けて自分なりに考えたことを書きたい
prima materia - diary : 能力の罠(Competency Trap)
とか言って放っておいたのだった。
「能力の罠」よりは「有能性の罠」「有能ゆえの罠」の方がしっくりくるな、と今は思っている。
The concept is deceptively simple. Organizations try things. If what they do succeeds, they "learn" that what they have done breeds success. So they persist, becoming ever more focused in what they do, and ever more specialized in the skills they acquire.
How successful companies can avoid 'competency trap' - February 1, 2007
コンセプトはシンプルだ。組織が何かにチャレンジする。成功したとすると、その成功が"いかにして成されたか"を学習してしまう。
それ(手段/手法)は習慣化し、固定化し、永続する。
そしてそれ以外のことを学ばなくなる、学ぼうとしなくなる。学ぶ必要がないと思いこむ。
これは私が最初に目にした、
これは、「正しいプロセスを省いて誤った学習を積み重ねるうちに、能力が頭打ちになる」という内容のこと。
プログラマの思索: 能力の罠(Competency Trap)
とはちょっとニュアンス違うなぁ、と思った。
続きはまた書くかもしれない。
2008-04-09
■再販? 再版?
ちくまがやっているようなことを、各出版社が積極的にやるようになっくれればいいのに、とは思います。
電子書籍だけでなく、古本の取り扱いも出版社がするようになったら面白いのかもなんてことも思いました。絶版本も電子書籍や古本で販売しながら、場合によっては再販もするとか。自動車会社が中古車の販売も手がけることもあるし、まったくありえない話でもないとは思うけど難しそうです。
2008-04-08 - Log of ROYGB
出版社にとって怖いのは"再版しても売れない"って事態なわけで、それよりは"よりたくさんの種類の本を出したい"っていうのが出版社の――大小に関わらない――願いだと思うんですよ。
この点で本の買い手*1の願いと、出版社の願いが食い違う。
「六の宮の姫君 (創元推理文庫)(北村 薫)」か「朝霧 (創元推理文庫)(北村 薫)」のどちらかだったと思うのですけど、
出版社というものは本が売れたら"儲かった"とは思わない。"また次の本が出せる"と思うものなんだ。
という趣旨のことが書いてあったかと。
そこで話題にしたいのは、ちくま学芸文庫の復刊投票と、復刊ドットコムなのです。
ちくま学芸文庫 復刊投票2007 このページはいずれ消えるでしょうが……
あからじめ、復刊 or 再販 or 再刷 したらどれだけ売れるか? の予想が立ちさえすれば、ちゃんとそうしてくれる可能性は増すはずなので。(権利関係でそれができないってこともあるわけですが)
とりあえず復刊ドットコムはチェックして欲しい本は投票、と。
■単行本にならない原稿たち
それはそれとして、単行本に入らない原稿たちをどうしてくれようか、というのもあって。
小説じゃなくて漫画の方が多いはずで、私の場合はやまむらはじめさんの漫画が筆頭なわけだ。
なにがネックかというといわゆる版権モノというやつで、アニメやらゲームやらのちゃんと許諾を得たコミックアンソロジーに収録されたものたち。
これらが単行本に収録されたりすることは絶望的で、雑誌(雑紙)で保存することを余儀なくされている。
とりあえず個人用にということでスキャナは用意して、いずれデジタル化するだろうけど、それはあくまで個人的な複製。
これらを公に救出する方法って……ないよなぁ。
著作権者が作者だけじゃないから、っていうのが壁になるから。
■理系のためのフリーソフト ただしWindows版
(BK1内容説明より)
レポート・論文の執筆から研究発表まで、あなたの理系ライフをしっかりサポートしてくれる優れものフリーソフトを特選5本+定番16本ピックアップ。CD−ROM付きでインストールも簡単! Windows版。
……Windows版。そうなんだ。
■暗号化されていることと消去とは関係がないと思う
「消去できる」ではなくて「事実上読み出し不可能な状態にできる」ではなかろうか?
また同社のFDE製品に標準で搭載されているKey-Erase技術により、HDDを転用したり、修理に出したり、廃棄する際、迅速かつ安全にデータを消去できる。
Seagate、「自分で暗号化する」HDDを開発 - ITmedia News
詳しく技術情報を見ないと精確なところはわからんが。
*1 消費者とは呼びたくないなぁ。
2008-04-10
■これでもうタスクに漏れは無い?
という(仮想の)上司の台詞。
現実にはリスク(=不確定性)が存在するという事実に目を背け、真実ではないことを「真実である」と仮定することで、不確定な要素が現実化したときに「予測できなかった事態が発生した」という言い訳を可能にする機能を持つ魔法の言葉。
■タスクには優先度などない
あるのは依存関係。
優先度があるのは「タスクの目的」の方。つまり「タスクを完了することで実現できるようになること」には大抵優先度がある。
後者は多分に主観的な尺度であろう。
前者は客観的な事実であるはずである。
2008-04-11
■経験有り
TomcatのバグDBにある問題点と全く同じ現象がでていて、Webを探せばソースパッチもあるのに、「注意点としてマニュアルに載っている」の一言で修正してもらえなかったり。
バグがあると分かっているのに、直せない。
プログラマの思索: SIerの俺様フレームワークは最悪に激しく同意
その理由は契約上だったり、ソースそのものが公開されてないことだったりする。
あの時ほどソースが手許にないプロダクトを嫌だと思ったことはないなぁ。
あ、冒頭の話はフレームワークではないけどね。
元記事、元々記事には全面的に賛同できる。
困ったことがあった時に Twitter で呟くだけでレスポンスがくる、とかそんなことほぼ絶望的だな。
■誰の左手?
時々紹介している"Photoshopの災厄"。
PSD: Photoshop Disasters: Cuisinart: M.C. Escher Strikes Again
自分的にウケたのでリンク。
これもなかなか。
本家Sonyのページを見てみると……。
Sony Bravia E4000 | KDL-26E4000, KDL-32E4000, KDL-40E4000 - HDTV Lounge
ホントだ。床に映りこんでいるのが修正前の部屋なのね〜。
■またの名を○○という
紹介のみ。外国人、特にオカルト関係とか詩人なんかも怖いかも。
日本人だと、明治時代以前の人名は要注意。一人の人物が使う名がたくさんあって(幼名とか本名とか通称とか号とか…)同じ人の別名だとは気づきにくいのです。
記述形その2:法然、またの名は… (TRC データ部ログ)
2008-04-12
■"クラスメソッド"は実は"クラスオブジェクトの特異メソッド"
クラスオブジェクトはもちろん Class クラスのインスタンスという意味だろう。
(Ruby1.7.3 のソースの解説書なので注意)
p76
特異メソッドはどんなときに使うか。まず Java や C++ で言うスタティックメソッドのようなものを定義するときだ。つまりインスタンスを生成しなくても使えるメソッドである。こういうメソッドはRubyではクラスオブジェクトの特異メソッドとして表現されるのだ。
とある。
後の章で、
p129
Ruby ではクラスに定義された特異メソッドのことをクラスメソッドと呼ぶのだが、そのクラスメソッドにはちょっと不思議な仕様がある。クラスメソッドは、なぜか継承するのだ。
(サンプルのソース 略)
こんなことはクラス以外のオブジェクトの特異メソッドでは絶対に起こらない。つまりクラスだけが特別扱いされているのである。この説ではクラスメソッドが継承する仕組みを追っていこう。
と続く。
うーん。
意外だ。
「Rails勉強会@東北 第10回」で、クラスにモジュールをextendできるという話題から。
……いやいや。
元の話題は、モジュール使ってクラスメソッドを追加できないのか? という話で、Rails では小難しい手順でそれを実行しているのに対して、もっとシンプルに exrtend メソッドで可能だという話題。
つまり。
class Hoge
end
module Foo
def a
p "a"
end
end
Hoge.extend Foo
Hoge.a #=> "a" が出力
となること。
"クラスに対してモジュールからクラスメソッドを追加する"ことが、実は"extendメソッドを使って特異メソッドを定義してやることで見た目上可能"なんだ! となったのだけど……。
真実はその逆だったのね。
追記
http://www.slideshare.net/xibbar/rubyactive-support-for-expert-2
セッションとスライドがアップされました。
2008-04-13
■聖なる花嫁の反乱 2
紫堂恭子の本領発揮。
久々のファンタジー。成り立ちや世界観がちゃんと仕込んであるファンタジー。
でもストーリーはキャラクタ主導の、紫堂恭子流の面白さ。
先が楽しみ。
なんで表紙がエリセじゃないの? と読む前は思ったけど、読んでみると何やら世界の設定と関係ありそう。次の表示は今巻登場の彼女かザディアスか?
2008-04-14
■やってくれるぜ Willcom
つい最近 nine+ に機種変したばかりだといのに。
と思ったら、
新製品はWILLCOM D4、立て188mm、幅84mm、新書本と同じサイズ。470g。
むー。
私が欲しいのとはセグメントが違うか。
■維納
む。ちょっと値が張るな。写真いっぱいなんだろうか。欲しい……。
(蛇足)
タイトルの漢字をだすのに太田忠司さんの「うぃーんおるごーるのなぞ」を検索したら、
文庫では漢字にしたんだ! (新書版はこちら)
装丁は BK1 のリンクを見た方がよい。
■日本で2番目に面積が広い湖を…
Wii の投票チャンネルの質問で、県別の結果を見たときのあまりに予想通りっぷりに一人笑っていた。
■虎よ! 虎よ!
読むのに時間がかかってしまった。
しかし、紛れもなく傑作で時が移ろうとも色褪せない作品というものはあるものだ。
ものすごい量の要素をこれでもかとつっこんでいて、破綻しそうでいてそうならない緊張っぷり。
再販されて本当によかったなぁ、としみじみ。
藤原京の「狼たちの〜」シリーズを読んだ時から気にかかっていた作品なわけで、実に15年越しということになるのか。
(追記)
これを読んでいる途中で、
を再読したくなった。
あぁ、再刷されたおかげでマーケットプレイスが安くなってるなぁ。
2008-04-15
■スイス・インターフェース・症候群
って何のこと?
長いし読み切れないところだけど、
its symptoms extend to the apparently randomly distributed presence of Max Miedinger and Eduard Hoffmann’s 1957 typeface ― Helvetica ― in the graphical user interface. Helvetica is, without a doubt, the most used and abused typeface in existence.
It’s also obvious why Helvetica and Lucida Grande are so different; one has been designed before any computers existed, and the other was designed in 2000, with pixels in mind.
あたりから察するに。
Helvetica は濫用されている。それはコンピュータが存在する前に作られた typeface である。Lucida Grande は2000年にデザインされたもので、ピクセルで表現されることを考慮されたもので、そちらの方がより GUI を構成するのに(特に小さいポイントで使う場合には)相応しいのではないか。
ということの様。
で、Mac OS X の UI を検証している記事なのではないかと。
スイス・インターフェースは、Helvetica の制作者に由来する、と。
"Lucida Grande" メモ。
via
■セムラーみたいにスマートに働こう
Tips on how to work smarter from Ricardo Semler - (37signals)
書評(というか引用?)なのだな。
ミーティングの仕方、のところぐらい訳しておこう。
- Begin on time.
- Don’t start a meeting without first setting a time to stop.
- Go over the agenda in front of everyone.
- Delegate to one or more people any item that might take more time than is allotted for it.
- Don’t have meetings that last longer than 2 hours.
- Be a bear about interruptions. The only excuse for breaking into a meeting is a customer with a problem.
- Transform as many meetings as possible into telephone calls or quick conversations in the hall.
時間通りに始めろ。
"first setting"抜きに始めるな*1(追記 コメントを参照ください)
アジェンダを全員の見えるところに出せ
(ここはピンとこないのでスルー)*2
2時間以内に終えろ
割り込みを許すな。唯一の例外はお客さまに問題が起きた時だけだ
可能な限りミーティングなどしないで、電話をして、問題についてすぐに直接会話して解決しろ
■上司からのメール
時間厳守で進めてください。
よろしくお願いします。
じゃ駄目でしょう?
時間厳守で進められるような工夫を考え実践してください
その工夫が有効だったかどうか話し合ってください
ぐらい具体的でいいよね。
だって何の手段も講じないで「時間厳守でやりましょう」って冒頭に誰かが言うだけで終わっちゃうもの。
(おっと。期せずして一つ上のエントリと関係があるな)
■PPL2008の論文が公開
via http://www.kmonos.net/wlog/84.html#_1726080410
これ地味に凄く便利じゃないですか。コンパイルエラーになったら、当然そこでエラー表示はするのだけれども それはそれとして、エラー箇所を実行時例外を投げるコードに置き換えることで、コンパイルは 続行して、とにかく実行可能な出力を生成するという。
d.y.d.
アドレス空間広ければ「この型はこの辺りのアドレス」 みたいに型ごとにアドレスを分けちゃえばアドレス値に型情報埋め込めたことになるじゃん!っていうの。
d.y.d.
ごめんなさい。ただのメモです。
del.icio.us のコメントに入りきらなかったので……。
論文はこちら。
2008-04-16
■highlight.rb を入れた
JavaScript部分に手を加える必要があってほったらかしだったけど、やっと入れた。
アンカー付きのURL(#p01とか)が入れられた時はそこをハイライトして、title 要素も変更するというプラグインです。
不具合とかあったらコメントくださいませ。
修正の理屈が分かったから section_footer.rb も変えようか……?
■これ以上夫で儲ける気か!
(BK1 タイトルデータ)
「夫育て」魔法のルール
どんな男も必ず輝く! 無職、バツイチ、借金アリの夫を、「そうじ力」のカリスマ、200万部突破ベストセラー作家に育てた「妻の力」
■ウラン兵器なき世界
(過去エントリ)
prima materia - diary : すでに、唯一にして最後の被曝地ではない
prima materia - diary : 日本はすでに"唯一の被爆国"ではない
■天神・大名WiFi化プロジェクトお疲れ様でしたっと
のイベントが先日ありました。
仕掛け人の1人、杉山さんのblogの、
先立つものが出来てからやりましょう、ってテンポ感では、これからの時代、おいてかれるなぁ、というのがこのプロジェクトをやった実感。
Fly to the...: 天神・大名WiFi化プロジェクト イベント終了〜
が、胸に刺さりますね。
「それは(会社に)余裕があるときじゃないとできないよ」という言葉を聞くとがっくりくるもんなぁ。
■両端
超整理法な話として、使ったものを必ず最右に返す、とすると、よく使うものが右に寄ってくる、というのがある。
それとは関係なく、ブックマークツールバーを整理する時によく使うものを上に持ってくるわけだけど、「頻繁には使わないが一日一回は必ず使う」ようなものは「最下に置いておいても使いやすい」ことに気がついた。
それだけ。
■IE と Firefox のフォント選択
おっと。回答できないや。
ウェブサイトで、「〜」の記号って、文字化けしませんか?
(略)
同じWindowsでもIEとFirefoxでも表示が異なります。
http://q.hatena.ne.jp/1208319323
原因はすでについている回答でいいとして。
- Shift-JIS や EUC、JIS で書かれたページに、そのコードで"〜"を書いた時
- Shift-JIS や EUC、JIS で書かれたページに、〜 ~ みたいに数値文字参照で記述した場合
- UTF-8 や UTF-16 で普通にエンコードした場合
- UTF-8 や UTF-16 で数値文字参照で記述した場合
1番目はさほど問題じゃないのはいいとして。
Firefox は設定で選択しているフォントに、表示したい文字の code point が入っていない場合、インストールされているフォントからその code point を表示できるものをできる限り探し出してきて表示しようとするらしい。
そこだけ浮いて見えるかもしれないけれど、とりあえず表示される可能性が高い。
IEだとバージョン/OS/設定しているフォントで挙動が違う。観察しているだけではよく分からない。
Unicode で追加になった文字を使う必要性があまりないなら、実は UTF-8 を使わない方がハッピーだったりして。
使いたい時には、𪚲 という記法を使えば 𪚲 と表示されて、Firefox を使っている人に対しては特に問題がなかったり(Firefox を使っているけど見えない人は、この code point を表示できるフォントが入っていないってことでしょう、きっと)。
……なんだ、読み返してみたら回答になってないや。
2008-04-17
■魔法使いとランデブー ロケットガール4
重いもの(「虎よ! 虎よ!」のこと)の後なので軽いものでも……と思ったら。
あっさり1日足らずで読了。あっさりしすぎだよ。
表題作が中編。これの大気圏突入シークエンスが新鮮だった。
というか理解できてないぞ。
宇宙ものからちょっと離れて。
パラシュートを使うとなんで安全に降りられるのか? という疑問にちゃんと答えられるか?
自由落下では位置エネルギー(ポテンシャル)が運動エネルギーに変換されるけど、パラシュートを使うとそれがどう変わるんだろう。
空気抵抗で速度が落ちる……のは分かるけど、ポテンシャルが熱に変わったわけでもないしな。
あー、空気の方の運動エネルギーに変換されるということなのか?
とか考えてみたりするけどよくわからない。
■選択したテキストが notes に入る様に del.icio.us の bookmarklet を拡張する
これは良いなあと思ったのは、Description の記入なのだが、事前にウェブページ内のテキストをコピーしておけば、それがこのDescription 内に記入されているのだ。
pukka で del.cio.us (感じ通信)
を見て。
Mac じゃないので pukka が何者なのかはまだよく分からないけど(del.icio.us専用クライアントらしい)、ウェブページ内のテキストを選択しておいて del.cio.us の notes に入れたいのなら。
ブックマークレット
javascript:location.href='http://del.icio.us/post?v=4;url='+encodeURIComponent(location.href)+';title='+encodeURIComponent(document.title)
を、
javascript:location.href='http://del.icio.us/post?v=4;url='+encodeURIComponent(location.href)+';title='+encodeURIComponent(document.title)+'¬es=' + encodeURIComponent( window.getSelection ? window.getSelection() : (document.getSelection) ? document.getSelection() : (document.selection ? document.selection.createRange().text : 0))
にする。
で、"post to del.icio.us"をクリックすると、
こうなる。
この選択テキストを取得する部分のソースは、
のブックマークレットを参考にした。
■数学を使ってコンピュータでできるようになること
じゃないかと。狭くしすぎてるか?
確率・統計→予測、パターン認識
2008-04-17 - きしだのはてな
次の形態素を予測して生成しているとみなせば、人口無脳は予測とパターン認識を同時にやることになるなぁ、と思った。
追記
グラフ理論→ネットワーク(と可視化)・デッドロック/無限ループの検出・ガベージコレクト
とかも?
2008-04-18
■Who can kill a child? 30周年特別版
なんとか入手できた〜。
いくつかのホラー紹介本で、隠れた名作と誉れ高いスペインホラーの珠玉。
封切りからソフト化まで実に24年経っている。 → asin:B00005MFQL *1
そして、30年経ってからの再ソフト化で、テレビ放映の日本語吹き替えが収録(テレビ放映していたんだ……)。
なにより一番の収穫は、当時の桜多吾作による漫画の収録!
これはよく描けている。本編内容をしっかりカバーしているので、読むのは映画観た後でないとね。漫画ゆえの描写の違いはあるけど、怖さをうまく抽出できてるなぁ。
しっかり前のパッケージも持ってるので、いつ観ることになるかは分からないけど。
↓初見の時のエントリ。
パンフを読んでみた。
マスターにしたフィルムが違うのか。そしてフィルムのキズなどもしっかりデジタル修復しているらしい。映像的には期待大だが、内容が重いのでさていつ観たものか……。
ジャケットに使われているスチールも、色彩感が旧ソフトとは全然違う。そしてパッケージ写真が封切り当時のパンフレットと同じなのも価値高し*2。
(追記)
画(え)は、色鮮やかで「真夏!」という感じがよくでている。
ただ、肌がすごく赤みがかっていて日焼けしているみたいにしかみえない。現実、その土地の日差しの強さで日焼けしている、という表現なのか、画作り上の問題(というか背景の色味を重視するために目を瞑ったということ)なのかは分からない
前の版よりもクッキリしているという感じでよい。
■図書館のなかの人が「図書館戦争」を見る
はい、今週も図書館退屈男が本筋とはまったく関係なく図書館の描写だけを綴ります。
図書館退屈男: 図書館退屈男が「図書館戦争」状況〇二を見る
(略)
いつまで続けようかこのシリーズ。
とても面白いのです。是非続けてください。
といことで紹介がてら応援 & 要望トラックバック。
出納が遅すぎて利用者に差し戻された本。
図書館退屈男: 図書館退屈男が「図書館戦争」状況〇二を見る
この本のタイトルは「金箔芸術の世界 (日本のxxシリーズ)」?「金箔」の字が微妙で読めないけれど、表紙には金の壷。ちなみにNDCで756は「金工芸」。おお、分類が合っているぞ。ついでに背ラベル。三段目にシリーズの通番のような数字が。
とか。
ある作品に対して、自分の知らない面からディティールを説明してもらうというのは、貴重な体験です。
普通は、自分の得ている暗黙知だけで作品を解釈するしかないのです。
そうではないアプローチを、しかも形式知化された形で得るというのは――あとになって自分から探そうとしたとしても――なかなかないのではと思います。
■鳥居を自分の庭に建てる
って、そこをくぐったら"あっちの世界"ですから!
ま、
It is the division between the physical and spiritual worlds. Shinto is a native religion of Japan and was once its state religion.
Construct a Japanese Torii Gate for Your Garden - Instructables - DIY, How To, home
わざわざ説明しているけどね。
2008-04-19
■「平均」の罠と幻想
待ち行列理論の"平均3時間"が、日常的な"平均3時間"の感覚と食い違っているイメージを書いてみたつもりですが
などと書いてみたが実は言葉の綾で"日常的な平均"なんてものがそもそも幻想なのだ。
相談室の待ち行列理論の問題です。
http://q.hatena.ne.jp/1208181379
例えば6人がテストを受けて、
- 6人全員50点
- 3人が0点で、3人が100点
- 2人が80点、2人が50点、2人が20点
どれもみな平均50点である。
"当たり前だ"とか"そりゃそうだな"と思った素直な人よりも、"テストでそんな極端な結果でないだろ"とツッコミたくなった人の方が、どちらかといえばより正しい。
ある程度の人数でテストをした時に、結果がどのように分布するか。それは経験的に分かっている。
だから平均点が、指標として使えるのだ。
だから偏差値が、異なるテストの結果を見比べるのに役立つのだ。
分布がどうなっているのか分からないうちに、Excelでささっと選択して平均を取ったりしてはいけない。*1
平均を出す前に、分布がどうなるのかを見える様にした方がいい。
そうでないと「感覚的に違和感が」出てきてしまうんだ。
p190 ミルカさんの台詞から
「ひとこと言っておくよ。グラフを描かないのが、きみの弱点だ。数式をいじることだけが数学じゃない」
■東京マーブルチョコレート
下記の順番での観賞をお奨めします(個人的には)。
「ちゃんと愛されたことないんじゃない?」と友達に言われてしまうような女の子、チヅルちゃん。
臆病で、好きだって口に出すことができなかったんだ――でもとても優しい男の子、悠大君。
悠大君が用意したプレゼントの箱の中になぜか入っていた謎の生物、ミニロバのおかけで振り回されるふたり。
すれ違いと、大切なものを見つけるまでのストーリー。
というのがアニメの方。
コミックの方は完璧に谷川史子節。
テンポも場面もキャラクターも、全部彼女自身の作品。アニメーションへのグラウンドストーリーなんてことに気を遣わずに、肩肘張らずに描いた感じが素敵。
アニメーションのあの尺では掘り下げられないキャラクターが、コミックのおかげでしっかりと深くなっている感じがいい。
すごくゆったりと過ごせた〜。
■そんなことは全然ありません
quintiaさんは三度の飯よりプロジェクトが好きだと思うんです。ココロの思い過ごしですか?
prima materia-ココロのココロ: 04月19日のココロ日記(BlogPet)
*1 上司に「ついでにここに平均を入れといて」なんて言われたらどうする? と問われると頭が痛い。
2008-04-20
■.hack//G.U. TRILOGY
カミさんと上の子と観た。(私は2度目)
うーん。ハイクオリティ。
AIDAに取り憑かれたアトリや、パロディモードを見ると、アトリ(ヒロインね)には上手な人を持ってきたかっただなぁ、とわかる。
昨日見た東京マーブルチョコレートの主人公の声、どっかで聴いたことがあるなぁ、と思っていたら、なるほどハセヲ君の声だったのか、と一人納得。
2008-04-21
■Amazon 予約 届かない
という検索語でのアクセスがあった。
私が出会った事例を一つ書いておこうか。
- 予約した時点で発売日がちゃんと入っていなくて、月までしか入っていない。
- 予約すると、発送予定日が次の月の1日になっている。
- そのまま放っておいた。
- 発売日が来ても、データ上発売日が月までしか入っていなかった。
- 本屋には既に並んでいるのに発想されない。
- Amazon に連絡(というか一方的な申告だが)。カタログデータの不備を指摘。
- その後届く。
という事例。これは遅れてもいっこうに構わない本だったからよかったけど。
ここからは記憶は曖昧なので話半分で。
予約時点で日が入っていなくて発送予定日が次の月の1日になってしまうところまでは、まだいい。
問題になるのは、途中でカタログデータが整備されて発売日が入れられた時に、予約データに反映されなくて発想予定日が変更されなかったとしたら?
そんなことが起こって予約を解除して改めて予約しなおした記憶があるんだけど……。
記憶違いだろうか?
今は問題が修正されていることを祈る。
(発売日が月までしか入っていないデータには予約しないようになったので、その辺、判らないのだ)
2008-04-22
■「面白い」と「面白くない」の二項対立
私的には、
「完全に予想の範囲内」と「完全に予想の範囲外」の中間
が「面白い」の(やや広めの)定義かなぁ……。
「完全に予想の範囲外」は、さらに「面白くない」と「感動」の二分になるかな。後者はめったにない。
それと、「面白い」と「面白くない」の
■"逆説"要らない
"順接の暗号"なんて必要ないじゃないか。暗号にする必要があったなら、順接ではないでしょ。
"順接の暗号"を仮に認めたとして、それがどんなのか? と考えてみようか。
主張を強める暗号を忍ばせて、解題できる能力がある人にだけ追加のメッセージを残す、ってのもあるかもしれないけど……、それって手間多くして労なしなんじゃないかと。
■CSSを使って何かすごいことをやっている例とチュートリアル
Using CSS to Do Anything: 50+ Creative Examples and Tutorials - Noupe
Blockquotes は最近やたら目にするような……。
2008-04-23
■MySQL Server Monitor だって
0.1b1 だけどね。
MySQL Server Monitor | Free System Administration software downloads at SourceForge.net
メモ。
■押して欲しいのか欲しくないのか判らない怪しい広告
いかにも怪しげな上に、この赤いバッテンマークはなんなんだろう?
単なるイメージなので("View Image" で確認した)、別にセキュリティソフトの類が出しているわけではない。
……この表示を"消す"ためのボタンだと思ってクリックする人を狙っているのか?
だとしたら頭がいい! と言いたいところだけどデザインのセンスがなさすぎ!!
うん。
Close と書いてある"ボタンに見えるリンク"には気をつけないといけない、とこれを見て思った。
色々な意味で"失敗作"だね。これは。
■ccTiddlyWiki
TiddlyWikiからの派生で、サーバサイドで動くものないかな〜と思って探そうとしたら、wikipedia がまとめになっていてさすがと思った。
ccTiddlyがよさげ。
でも、WikiName を無効にするオプションが見あたらない。
TiddlyWiki.js 中の
config.textPrimitives.wikiLink = "(?:(?:" + config.textPrimitives.upperLetter + "+" + ...
になっているのを、
config.textPrimitives.wikiLink = "(?:(?:wiki:" + config.textPrimitives.upperLetter + "+" + ...
と書き換えてみる。
何にもヒットしない正規表現にしちゃうと、WikiName のキャンセル記法(~WikiName らしい)まで変になってしまうのでこんなもんでいいんじゃないかと。
■Twitter 日本語化
と、Tech Crunch が報じているのだけど、
there's no need to bother making it stable before embarking on a glorious expansion crusdade
Twitter! Japan! Ads!
"十字軍に乗り出す前に、安定化を心配する必要はない"……?
stable はシステムの安定性のことを言っているわけじゃないのかな。
ま、そのうち日本語版に訳が出るでしょ。
■怠慢な SSL/TLS 実装がゲームなどに使い回されたらどうしよ?
日本のWebブラウザ実装者の怠慢
高木浩光@自宅の日記 - 新型myloのオレオレ証明書を検出しない脆弱性がどれだけ危険か
が今回あったわけだけど、これがブラウザ(HTMLユーザエージェント)だったから高木さんの様な人が目を光らせていてちゃんとチェックされた。
でも、こういったプロトコルスタック実装が使い回されて、ブラウザじゃないようなアプリケーションと結びついた時、どうやって確認したらいいんだろう。
とか考えたら怖くなった。
2008-04-24
■IE6 標準準拠モードの div 要素の大きさって?
このサイトの右上の操作メニューを模したhtml。
IE6 の標準準拠モードになっているのだけど、
上下のボーダーが消えてる……。外側の div要素(adminbar)の高さってどうやって決められてるんだろう?
単純に height:100px; とかすると下のボーダーは表示される様になるけど、上のボーダーは消えたまま*1。
判らない……。
今まで IE 無視! だったツケを払っている気分。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="ja-JP">
<head>
<title>DIVの高さって?</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<style type="text/css">
<!--
.adminbar {
font-size: 90%;
/*height: 100px;*/
}
.adminbutton {
background-color: #999999;
background-color: #f5f5dc;
border-style: solid;
border-color: #eeeeff #999999 #999999 #eeeeee;
border-width: 1px;
padding: 2px;
}
div.main {
float:right;
width: 78%;
}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div class="adminbar"><span class="adminbutton"><a href="./test">追記</a></span></div>
</body>
</html>
■SHA1ハッシュ値をキーにした連想配列を作ればいいよ
もちろん連想配列はハッシュ表で実装するのだ!
ハッシュ関数SHA1を使ってハッシュテーブルを作成したいです。SHA1は160ビットのハッシュ値を生成するため、単純に考えると縦の列が2^160の巨大なテーブルが必要になるため、どう作成したらよいのか分かりません。ハッシュテーブルは衝突が起きたときにはポインタでハッシュ値をつなげるような形にしたいと思っています。
http://q.hatena.ne.jp/1209004002
*1 このサイトを IE6 で見てる人は、この、上のボーダーが消えている状態をずっと目にしていたんだろうな。
2008-04-25
■Googleでフレッシュな情報を検索する
by simply adding “&as_qdr=d” to the end of any query
Filtering Google Searches By Freshness
(略)
simply change the =d to d5 for 5 days, or w5 for five weeks, or y5 for 5 years
クエリの後ろに、(Advanced Search が付加するパラメータでもある) &as_qdr=d5 と付けると過去5日分という指定ができる、というtips。
面倒くさい?
prima materia - diary : Firefox OpenSearchFox add-on で 検索結果の言語を制御する
あたりを合わせて読むとよいかも。
■類書は多いけど最新版ということで
実はこういう本を持っていないなぁ、と思ったのでなんとなくメモ。
(BK1内容説明より)
UMLを使い、ユーザー要求をどのようにモデルに落とし込んでいけばよいのか、その手順とポイントを基本から丁寧に解説。より良いモデルへ導いていくための道筋を伝授する。
■見えない視覚
気になる……。
(BK1内容説明より)
【イギリス心理学会優秀図書賞】われわれには、意識されない「もうひとつの視覚」があった。事故で「視力」を失った患者の不思議な能力からもたらされた、脳のしくみの新しい理解。ひとつの脳のなかに2つの視覚システムがあることを証明する。
■翻訳デスクトップアプリケーション translateclient
.Net で動く。GUI に日本語はまだ用意されていない。
translateclient | Free software downloads at SourceForge.net
Any Language → 日本語 とか 日本語 → Any Language ができることが秀逸(というほどのことでもないか。でも今まで、出来そうでいて出来なかった機能のような気が)。
未知の単語を調べるのによいかと。
GUI の使い勝手は十分。結構ちゃんと考えてあるな、という印象。
自動起動とホットキーは邪魔だから外したけど、.Net アプリケーション だから起動遅いしなぁ。
常駐させるかどうかは微妙。
■赤きティンクトゥラ
鋼の錬金術師に出てくる"賢者の石"の別名。
赤チンキのことか!
同じく"第五実体"は"quinta essentia"で、これは私のIDにつながるのだけど、サイト名は謙虚に"第一質料"である"prima materia"。
2008-04-26
■SILVER SPOON
こんなの出ていたんだなぁ。
田村直美のセルフカバーアルバム。
……一番大好きな"SILVER SPOON"が収録されているじゃないですか?
買った。
やっぱりいいなぁ。しかも今の自分の環境で聴くと歌詞が重い……。
■仮面ライダー SPIRITS 14
出る度にそろそろ買うのをやめようかな、とか思うんだけど読んだ後にはそんなこときれいさっぱり無くなってるんだよなぁ。
俺たちのフィールドあたりから分かっていたけれど、「細かいエピソードを重ねつつも全体にうねりと統一感を作る」っていうのがすごく上手い。
「最初から計算された大きな物語」とは違ったストーリーテリングなわけで*1、でも統一感があるってのは驚愕だなぁ。
でもなんで表紙が1号2号なの?
■ヘブンズゲイト GREEN
白門井亜矢。
普通のコママンガでショートショートって好き。
小説のショートショートも好きだけど。
そう。
最後のコマ/ページで落とすというショートショートの面白さが、ここにある。
■Windows の Ever Note クライアント
期待してますよ〜。
Evernote started out as a Windows app, but in version 3.0, currently in private beta, it has become a web service along with a sharp looking native Mac OS X client app.
AppleInsider | Evernote for Mac, iPhone to make managing information overload easy
*1 事実かは知らない。"そう見える"ということでしかない。
2008-04-27
■MySQLがUTF-8になった
ので、http://materia.jp/shelf/も、UTF-8にした。
中身で検索できない問題を抱えてしまったけど、元々できないことを無理矢理実現してたことなので仕方がないといえば仕方がない。
WordPress 3.5.x 系にアップするときまでの宿題。
2008-04-28
2008-04-29
■ FathomFive
lucene を使った pure Java のスパイダリングとインデクシングのユーティリティっぽい。メモ
FathomFive is a classification aware lucene powered spidering and indexing solution, written in pure Java.
SourceForge.net: FathomFive
■シュレディンガーの《世界》
「シュレディンガーの猫」からの発想で、「シュレディンガーの世界」というフレーズをメモしていた(私が、だよ。)んだけど、まさにそのもののお話だった。 > シュレディンガーのチョコパフェ
2008-04-30
■MISAO を英語でググる
επι的にはMISAO大歓迎です。
僕は楽しいのが好きだから
MISAO って何? と思って(まぁ、オンラインでプレゼンテーションにツッコミできる掲示板みたいなものっぽいけど)検索してみると。
るろうに剣心ですか……。
URLはこれ。(日本語のFirefoxだと違う結果が表示されるのかな?)
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=MISAO&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
■3次元スライドショー
という表現が正しいかどうか。
Displays images on an engaging interactive 3D wall using the Papervision3D engine.
Flash 3D Wall - Flashloaded
3次元空間の壁状にスライドショーを表示するためのエンジン。有償ライブラリらしい。
スクリーンショットを撮ってみた。
これをマウスで動かせるのだ。
via