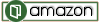2012-05-01
■4月の読書
4月の読書メーター
読んだ本の数:14冊
読んだページ数:3911ページ
ナイス数:19ナイス
 ビブリア古書堂の事件手帖―栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス文庫)
ビブリア古書堂の事件手帖―栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス文庫)
本屋大賞ノミネートは、主人公に対しての「本のことについて熱く語っても引かないで付きあってくれるこんな人がいたらなぁ」という願望が理由だったのでは、とか邪推。一気読みしてしまう程度には面白かった。
読了日:04月30日 著者:三上 延 カンナ 天草の神兵 (講談社ノベルス)
カンナ 天草の神兵 (講談社ノベルス)
読了日:04月28日 著者:高田 崇史 カンナ 飛鳥の光臨 (講談社ノベルス)
カンナ 飛鳥の光臨 (講談社ノベルス)
読了日:04月24日 著者:高田 崇史 The Indifference Engine (ハヤカワ文庫JA)
The Indifference Engine (ハヤカワ文庫JA)
スナッチャーとMGSを下敷きにした作品を読んだら、小島秀夫さんがMGS4のノベライズを任せたのも納得できた。すごかった。いつものように既読のものは今回読んでない。
読了日:04月19日 著者:伊藤 計劃 せどり男爵数奇譚 (ちくま文庫)
せどり男爵数奇譚 (ちくま文庫)
一本だけ妙にグロかった。知ってはいたけど見かけたことがない本だったので、新刊書店に普通に並んでいる状況はうれしい。
読了日:04月19日 著者:梶山 季之 All You Need Is Kill (集英社スーパーダッシュ文庫)
All You Need Is Kill (集英社スーパーダッシュ文庫)
面立てにして4冊ぐらいは置けるはずのスペースに、ポツンと1冊置いてあった。なんとなく手にとってパラパラと。オビを読む。奥付を見る。2010年11月30日第6刷。買うか。それが、今日の昼の出来事。今これを書いていることから、面白さは推して知るべし。ところで、この設定だとループは1回しかできなくて、改変も無理なような感じがするのだが気のせい?
読了日:04月16日 著者:桜坂 洋 心のおくりびと 東日本大震災 復元納棺師 ~思い出が動きだす日~ (ノンフィクション 知られざる世界)
心のおくりびと 東日本大震災 復元納棺師 ~思い出が動きだす日~ (ノンフィクション 知られざる世界)
前半は読んでいて涙が止まらない。復元の様子、そしてその前後の家族の様子を細かく描写する。その文章に"泣かされている"面もあるかもしれない。が、事実はそれ以上に過酷だ。後半、細かな描写はなりをひそめ、残された者が死を受け入れるということ、その上で自分の生と向かいあうということに比重を移していく。緩和ケア医への協力の声がけも、その必然として書かれている。前半に描かれる「死」と、後半に描かれる「生」。この構成そのものが、この本への「思い」を反映していると感じた。
読了日:04月15日 著者:今西 乃子 偉大な記憶力の物語――ある記憶術者の精神生活 (岩波現代文庫)
偉大な記憶力の物語――ある記憶術者の精神生活 (岩波現代文庫)
フィクションでよくみる直感像記憶とは全く違う。文字、数字、言葉などが情景や音や色を伴って感覚される(つまり共感覚)。その情景を長期に渡って記憶が可能な人の「記録」。しかし「記録」に過ぎないはずのものが「物語」となって読者の前に立ち現れるというところがすごい。
読了日:04月14日 著者:A.R.ルリヤ NOVA 7---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫)
NOVA 7---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫)
「ヒツギとイオリ」素直に良い。フリンジ3rdシーズンでこの話とは逆の、"読み取ってしまう"能力者の回の浅さが認識できた。「リンナチューン」圧巻。「サムライ・ポテト」ホラーに振ると草上仁のサージャリ・マシンなんだけど、これは切ない話だった。「コズミックロマンス(略)」馬鹿馬鹿しいようだけど極めて示唆的な一本。「土星人襲来」がなんで東北大学/国分町なのか不思議。北大/ススキノじゃ駄目だったのは、キャンパスが固まってるからか?
読了日:04月12日 著者:扇 智史,小川 一水,片瀬 二郎,壁井 ユカコ,北野 勇作,谷 甲州,西崎 憲,藤田 雅矢,増田 俊也,宮内 悠介 NOVA 1---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫 お 20-1 書き下ろし日本SFコレクション)
NOVA 1---書き下ろし日本SFコレクション (河出文庫 お 20-1 書き下ろし日本SFコレクション)
「黎明コンビニ血祭り実話SP」が好み。既読のものは読み飛ばしてる。
読了日:04月09日 著者:伊藤 計劃,円城 塔,北野 勇作,小林 泰三,斉藤 直子,田中 哲弥,田中 啓文,飛 浩隆,藤田 雅矢,牧野 修,山本 弘 サイバーテロ 漂流少女
サイバーテロ 漂流少女
「最後に現れた首謀者」だけがなんか無理矢理っぽい感じ。その手前まではとても楽しめた。犯罪の現場がネットワーク中継&拡散されることで犯人および被害者の個人情報が暴露されてしまう、っていう事態は今後起こりうるかもなぁ。
読了日:04月05日 著者:一田和樹 嘆きの美女
嘆きの美女
「ご都合主義的な展開」と「テンポの速さ」の境界線スレスレのところをいっていると思う。そのギリギリのバランスが楽しい。プロットやあらすじでは、この話の面白さをうまく伝えられないかと。
読了日:04月05日 著者:柚木麻子 パラドックスの悪魔
パラドックスの悪魔
「便利になれば多忙になるというパラドックス」はみんな実感しているだろうな。
読了日:04月03日 著者:池内 了,ワタナベ ケンイチ われ敗れたり―コンピュータ棋戦のすべてを語る
われ敗れたり―コンピュータ棋戦のすべてを語る
「格闘家にとっても異種格闘技戦のようなもの」という例えに得心が行く内容。将棋は全くの素人なので棋譜・解説部分は読まず。自身も、相手(=コンピュータ)も、双方が最大限の力を発揮できるようにするためのレギュレーション策定部分はとても興味深く読めた。
読了日:04月01日 著者:米長 邦雄
2012年4月の読書メーターまとめ詳細
読書メーター
2012-05-11
■スケルトン・キー
なにこれ、すっごい面白い。
軽い気持ちで見始めたんだけど、めちゃくちゃ引き込まれた。
ホラーの棚に入れていいのかと思うぐらいまったく怖くはないが、優れたオカルトホラーだった。
ラストまで丁寧にこつこつと積み上げていくタイプの作り方なので、オチはもうこれ以外にないでしょ、というものでそこに意外性はなかった。
意外性がなくとも、そのオチだよねとあたりをつけてからの色々な発見は楽しい。
……いや。楽しいというのはメタな感想であって、「ん? ということは、あのシーンのあれはどういうこと?」とか思いいたってひどく居心地が悪い思いをしたり。
2012-05-16
■海が呑む
この連作の存在を私は以前から知っていた。
とあるアンソロジーに1編が収録されていたからだ。もちろん読了している。
この連作を思い出したのは、東日本大震災後に本屋で平置きされている文庫を見かけたときだった。
「そうだ、この人はずっと前から津波の話を採集していたんだった」と思い出した。が、その時点では"この話"を読む気にはなれなかった。
(と記憶しているが、残念ながら記録していない。勘違いかもしれない。)
時間が経ち、何かの折りに冒頭の本が出版されていることを知った。
読もうと思った。
最初に困惑したのは、収録作の「海が呑む(I)」は確かに読んでいるはずのなのに、文章を読んでも全く記憶がないことだった。
読んだ本を取り出してきてみると、果たして全然違う文章であった。
初出を照らし合わせて分かったのは、いつの間にか改題されているという事実。
初出「物いわぬ海」が「海が呑む(I)」に、「海が呑む(I)」が「海が呑む(II)」に、「海が呑む(II)」が「海が呑む(III)」になっていた。
紛らわしい!!
せめて数字の表記が変わっていればもう少し分かりやすかったのに、と思ったのだが。とにかく改題を尊重して最新の書籍のタイトルに寄せて書くことにする。
「海が呑む(I)」は初出1982年(昭和57年)。三陸地方を襲った大津波に関するもの。
明治29年と昭和8年の三陸沖地震(それぞれ明治三陸地震、昭和三陸地震と呼ばれる)と、昭和35年のチリ地震による津波である。
読んで驚くのは、口伝や文献で伝わったり筆者自身によって取材された"津波の描写"を読むと、去年の3月13日以降にテレビやネットで見た映像群が容易に想起されること。
あるいは、直截に言うと「あの映像をそのまま文にしたらこうなるだろうな」と感じてしまう。
もちろんこれは順序が逆で、あの映像を見た後に読んでいるからこそなのだけどそれでもなお、"津波の描写"がここまで生々しく伝えられているということが驚きだった。
一般の人にも映像を記録する手段が行き渡っていたおかげで、今回の災害では多くの状況が映像として残った。
それらはずっと残していかなければならないだろう。
「海が呑む(II)」は初出1984年(昭和59年)。
日本海中部地震の津波が主な内容。
他に国語の教科書に載っていた、安政東海地震、安政南海地震の際の出来事にまつわる話(昭和12年の国語の教科書からの転載あり)。
そして、筆者がなぜ津波の話に関わるのか? ということに関する物語。この部分が「物語(を書く者)の物語」となっているためアンソロジー「物語の魔の物語」に収録された。
以前に読んだ時の記憶を探ってみると、アンソロジーの主眼である「物語の物語」の部分ではなくて、日本海中部地震に関する記録・取材に関する部分の方がはるかに印象が強い。
「海が呑む(III)」は初出1985年(昭和60年)。
安政東海地震、安政南海地震の話と、筆者が現地に赴いた際の話。
「奥尻島悲歌」は初出2000年。
タイトルの通り北海道南西沖地震の際の奥尻島での話と、やはり筆者が現地に赴いた際の話。
「3・11巨大地震津波体験記」は寄稿による。
大船渡市在住の医師の手によるもの。気仙沼方言の研究もしていらっしゃるとのことで、方言の採録が生々しい雰囲気を出している。
そして、やはりこれもまた「物語の物語」、"三陸沿岸という土地に刻まれた津波の記憶"という物語だった。
p92〜93
やがて各新聞社・雑誌社から、私のところに取材が押しかけるようになった。その判で押したように一様な質問は、予想もしなかったものだった。
「被災者の皆さんは、きっと『どうして自分たちはこんなひどい目に遭わなければならないのか(略)』という疑問を持っているに違いない。(略)どうして善良な人々がひどい目に遭わなければならないのか。(略)」
(略)
実は気づいていたことがある。生死も知れぬ大災害のなか、「なぜ俺たちはこんな目に遭うのか」という恨み言を、実は一度も聞いたことがない。
(略)
そこで考えた。なぜ都会から来る人々は口を揃えて、こんな質問をするのだろう。われわれが夢にも思っていないことを、なぜこうもしつこく尋ねるのだろう。
このあと「かくも厳しい三陸という土地でなぜ我々は生活しているのか?」という問いへの考察へと続いてゆく。
ここに至って、この文章は単純な体験記から遠く離れていく。
その部分が花輪莞爾の手による前の4編と通底する。
この寄稿は確かにこの本に収められるべきだと、そう思った。
以上収録作のうち前の4編は、
にも収録されていた。
加筆修正や改題が、その時点で行われたものかどうかは不明。
追記
大阪府立図書館のWeb検索で「悪夢百一夜」の内容細目が確認できた。
13番目(第十三夜)が「物いわぬ海」ではなくて「海が呑む」になっている。
「悪夢五十一夜」には「物いわぬ海」として収録されているので、「悪夢百一夜」刊行時に改題したんだろうなぁ。
2012-05-20
■入力するふりがなは平仮名がいいなと思う
ひらがなだとそのままEnterで確定して学習されない。
カタカナだと変換が必要なので学習されてしまう。
あらかじめ入力をカタカナにすればいいんだけど面倒くさい(キーボード的な意味で)。
……ひらがなかカタカナなんてチェックする必要なくて、DBにいれるときにどっちかに寄せたいっていう都合なら勝手に置き換えてくれていいのに。
2012-05-21
■皆既日食だと暗くなるのです
皆既日食だともっともっと暗くなるのかー、というつぶやきがTwitterのTLに見えたので。
2009年の皆既日食の時、奄美大島で撮られたPVがあったっけ、と思い出した。
2012-05-25
■モンティ・ホール問題、その祖先と子孫
まずは一般によく知られている形式をWikipediaから。
「プレイヤーの前に3つのドアがあって、1つのドアの後ろには景品の新車が、2つのドアの後ろにはヤギ(はずれを意味する)がいる。プレイヤーは新車のドアを当てると新車がもらえる。プレイヤーが1つのドアを選択した後、モンティが残りのドアの内ヤギがいるドアを開けてヤギを見せる。
ここでプレイヤーは最初に選んだドアを、残っている開けられていないドアに変更しても良いと言われる。プレイヤーはドアを変更すべきだろうか?」
モンティ・ホール問題 - Wikipedia
この形式の設問には、司会の振る舞いについての前提が曖昧だという問題があって、↓の漫画でも確認できる。
この解答は書かない。
あたりをどうぞ。
以降モンティ・ホール問題については十分理解しているかどうかが問われる問題と、十分理解していても難しい問題を「数学セミナー」連載の「確率パズルの迷宮」、2012年7月号掲載記事「逆確率の罠」から引用する。
に掲載されているらしいので読みたいところだけど、マーケットプレイスのプレミア価格……。
まずは曖昧さを無くした、同種の問題。
A,B,Cの3人の死刑囚が独房に入れられている.ときの為政者のはからいにより,3人のうち1人は(等確率で無作為に選ばれて)釈放されることになり,残り2人は処刑されることになった.囚人たちもこのことを知らされているが,誰が釈放されるかまでは知らされていない.
処刑の数日前,Aは独房を見回りに来た看守に対して,誰が釈放されるか教えてほしいと頼んだが,拒否された.しかし諦めず,
「だったら,BとCのうち処刑される者の名前を1人だけ教えてくれ.3人のうち2人が処刑されるから,BとCのうち少なくとも1人が処刑されるのは確実だ.それなら,そのうちの1人の名前を聞いたところで俺が処刑されるかどうかとは無関係だから,教えてくれてもいいじゃないか.なぁ,こうしよう.Bが釈放されるならCだといってくれ.Cが釈放されるならBだといってくれ.俺が釈放されるなら,BというかCというかはコインを投げて決めてくれればいい.もちろん,いまコインを投げたら俺が釈放だとわかってしまうから,答えは明日教えてくれればいい.お願いだ.頼む.」
といってまんまと看守を説得した.生真面目な看守は翌日,Aのいった通りのやり方で答えを決め,Cが処刑されることをAに教えてくれた.
看守の誤算だったのは,実はAとBの間では密かに情報を伝達しあう方法ができあがっていて,Aは,上で述べた看守とのやりとりの一部始終をBに教えてしまったことであった.
さて,Cが処刑されるという情報を得て,AもBも,自分が釈放される確率が1/3から1/2に上がったと喜んだ.釈放される確率に関するAとBの結論は正しいであろうか.
下記のような抽選会が行われた.その中の(1)から(7)の各時点において,あなた(中村さん)のクジが「あたり」である確率を,それまでの司会者の発言(もちろん,100%信じるものとする)をもとに計算すると,それぞれいくらとなるか。
部屋の中には,司会者を除き100人の人がいて,あなた(中村さん)もその1人である.クジは101本あって,その中の1本だけがあたりである.また,あなただけは目隠しをさせられる.
司会者「今日は渡辺さんだけが2本,ほかの人は1本ずつ引いてもらいます」(1)
司会者「みんながクジを引きましたが,まだだれも中を見ていません」(2)
司会者「さて,みんなが自分のクジを開いて見ましょう.中村さんだけは目隠しをしているので見えませんね」(3)
司会者「さて,はずれた人は1人ずつ部屋から出てもらいます.中村さんはこのままお待ちください」
司会者「さて,はずれた人は1人ずつ部屋から出てもらいます.中村さんはこのままお待ちください」
98人出て行ったところで,
司会者「ここでストップします.いま,まったくランダムな順番で98人が出たところです」(4)
司会者「ところで,ここに残った人は,クジを2本引いた渡辺さんと目隠しをした中村さんだけでした」(5)
司会者「渡辺さんの持っている2本のクジのうち,はずれのクジを私がいただきましょう」(6)
司会者「ては,中村さん,目隠しをとってください.ご覧のとおり,結局,中村さんは外れで,渡辺さんがあたりでした」(7)
・
・
・
・
・
1つ目の問題。
モンティ・ホール問題と同じ。
看守の話を聞く前はA,B,Cの釈放される確率は同じ1/3。
看守の話を聞いても、Aが釈放される確率は1/3のままで変わりない。
一方、Cが釈放される可能性が0になったため、Bが釈放される確率は、1-1/3=2/3となる。
したがってA,B両者とも結論は間違い。
つまり、Aが自分で言った「そのうちの1人の名前を聞いたところで俺が処刑されるかどうかとは無関係だから,教えてくれてもいいじゃないか」が正しい。Bの名前がでてきても、Cの名前がでてきても、Aにとっては何の情報にもならない。Aが釈放される確率は1/3のまま。
いっぽうBから見ると、Cの名前が出たことで「AとBが処刑でCが助かる」目が無くなったことでその分の1/3が「Bが釈放される確率」に加算されたことになる。
といったところか。
2つ目の問題。
(1)〜(3)は1/101。
(4)はモンティ・ホール問題と同じ。1/101で変わりない。
(5)が難しい。1/199。
(6)もモンティ・ホール問題と同じ。1/199と変化しない。
(7)の段階で0。
(5)……難しい。ベイズ定理に因らない計算でこの答えを導き出せない(解答はベイズ定理を使っている)。もうしばらく考えてみたい。
渡辺さんが「当たり」であるパターン。
自分が「当たり」で、残ったのが渡辺さんであるパターン。
の2とおりで考えるといいと思うのだけど……。
(追記)
続きあり。
2012-05-29
■CSS3の傍点どうなった?
どうなったっていうかどのブラウザもサポートしないことは分かってるけど。
UnicodeのCombining Diacritical Marksで表̇示̇可̇能̇に̇なりそうだからだろうか。
……Firefoxではちゃんと見えないのが残念。(Safariもだったか)
表̇示̇可̇能̇に̇
と書いてます。